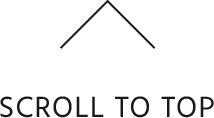COLUMNS コラム一覧

正直MATSURI日記番外編:アメリカにおけるバイオ燃料最新情報
こんにちは。正直MATSURI新人担当者のサリーです。サリーは生物のことは得意なのですが、環境負荷の評価や関連する活動についてはまだまだ素人です。 今回は日記の番外編として、2024年7月3日に開催したMATSURIパートナー限定のオンライン情報共有会「アメリカにおけるバイオ燃料最新情報」の開催報告をしたいと思います。 「バイオ × 環境 × ビジネス」の最新動向に関する有益な情報を提供するオンライン情報共有会には120名もの方々にご参加いただきました。 今回の情報共有会はサリーが「2023年9月 米国のエタノール団体はトウモロコシエタノールSAFについて、CORSIAモデルではなく、最新のGREETモデルの数値を使うことを米国政府に求めた。」(”Ethanol Industry Associations Ask Treasury Secretary To Use GREET Model For Scientific Accuracy”September 14,2023)というニュースを目にしたことから始まりました。 このニュースは正直MATSURI日記2でも取り上げました。MATSURI会員専用ページではモデルの違いについて詳しく解説しています。 情報共有会では「藻類産業を発展させるために、微細藻類の価値をどのようにして定量的に発信していくか?」という観点からこのニュースを掘り下げて議論しました。このニュースを起点に、近年の米国におけるSAF動向をまとめ、それを藻類産業の視点から考察しました。 前半はサリーから「アメリカにおけるバイオ燃料最新情報」に関して、最新の政策や、可食バイオマスの多くが燃料になっている現状等について解説し、藻類産業の視点からの考察を共有しました。 後半はサリーとエネルギーアナリストの大場 紀章氏と日本微細藻類技術協会事務局長の 野村 純平も交え、藻類産業構築に向けて私たちは何をすべきか、将来の展望についての議論と参加者を交えた質疑応答が行われました。 質疑応答では、「藻類で航空燃料を作る場合のLCAがどのようになるか」、「可食バイオマスを燃料にすることについてアメリカはどう考えているか」など多くの質問が寄せられ、パートナー企業の皆さまのエネルギー事情への関心の高さが伺えました。 ちょっと緊張しているサリー(左)...

正直MATSURI日記番外編:グリーンウォッシュ批判の時代の中で何を発信するか
こんにちは。正直MATSURI新人担当者のサリーです。サリーは生物のことは得意なのですが、環境負荷の評価や関連する活動については、まだまだ素人です。 今回は日記の番外編として、2024年11月21日に開催したMATSURIパートナー限定のオンライン情報共有会「グリーンウォッシュ批判の時代の中で何を発信するか」の開催報告をしたいと思います。 情報共有会の報告記事はこちら「グリーンウォッシュ批判の時代の中で何を発信するか」と題し、MATSURIパートナー限定情報共有会を開催いたしました 近年、「グリーンウォッシュ」と呼ばれる、環境や気候への影響について虚偽または誤解を招く主張に対する監視が強まっています。こうした行為に対する世間の批判が高まるだけでなく、環境への取り組みを紹介するCMでの不適切な環境表現を禁止するガイドラインが策定されて実際にそのようなCMに禁止命令が出されるなど、規制当局による具体的な措置も増えています。 このような状況の中で、我々はどのような環境発信ができるのでしょうか?そのヒントを得るために、すでに市場にある各企業による環境発信や、それに対する世間や行政の反応についての有名な事例をいくつか紹介しました。 紹介した事例のひとつが、LEGO社のサステナブル素材への取組みです。現在、LEGOブロックは石油由来のABS樹脂から作られています。LEGO社は2030年までにすべてのパーツを持続可能な資源由来のプラスチックに切り替えるという目標を掲げ、2015年には10億デンマーククローネ(約210億円)を投じて、デンマーク本社に「サステナブル・マテリアル・センター」を設立しました。そして2021年には、ペットボトルを再利用したブロックの試作品の作成に成功したと発表しています。しかし、2023年にLEGO社は、再生ペット(PET)を使ったブロックの生産を行わないことを正式に発表しました。同社はこの決定について、「試作品を発表したときは、可能性について楽観的だった。しかし、2年間の試験を経て、CO2排出量の削減に寄与しないことがわかったため、これ以上の開発を行わないことにした」と説明しています。(参照:https://www.sustainablebrands.jp/news/us/detail/1218450_1532.html) この発表に対して、世間から「なんで再生プラスチックをやめるんだ?」とか、「何も進んでいないのでは?」とか、「ABS樹脂を使い続けるための言い訳では?」といった非難の声は、ほとんど見受けられませんでした。それどころか、LEGO社がきちんと検証し、正直に淡々と結果を公表した姿勢が評価されているように感じます。この評価は、LEGO社が人と資金をしっかり投入し、本気でサステナビリティに取り組んでいるからこそ得られたものなのでしょう。まさに「正直MATSURI」だな、と私は感じました。 最後に、サリーとエネルギーアナリストの大場 紀章さん、日本微細藻類技術協会事務局長の 野村 純平さんも交えディスカッションが行われました。 まだまだ緊張しているサリー(右)と エネルギーアナリストの大場 紀章氏(左) 正直MATSURIのサリーとしては、藻類を将来価値のある取り組みとしてどのようにアピールしていくかを、もっとじっくり考えていく必要があると感じています。 情報共有会の詳しい内容についてはMATSURIパートナー専用ページにて!

MATSURI参画企業32社のC4視察イベント
MATSURI参画企業32社、100名近くの参加者が集まる※C4視察会イベントが2024年5月末に開催されました。※C4・・「Chitose Carbon Central Capture」 藻類産業構築の基点となるC4はマレーシアのクチンに世界最大規模5 haのスケールとなり、藻類由来の製品開発・産業構築を共に目指す多くの企業に参加いただきました。藻類バイオマス活用と聞くと化学メーカーや特定の業界をイメージされる方が多いのですが、我々が目指す藻類産業構築は日常生活に欠かせすことが出来ない石油由来の製品を藻類由来に生まれ変わらせることが出来るため、視察イベントには大手銀行をはじめ化粧品メーカー、食品メーカーや建設業界、燃料業界など幅広い企業・機関の皆様にご参加いただくことになりました。 ご参加いただいた皆様にはマレーシアの炎天下にもかかわらず、微細藻類の生産状況や今後の研究開発、そして世界課題となっているカーボンニュートラルな世界実現にむけて、あらゆる業界をまたぎ熱く議論されただけでなく、各社の中長期的計画に微細藻類をどう活用していくのか?どのような目的で藻類産業構築を目指すプロジェクトMATSURIに参画されたのかを熱い想いのつまった生産現場にて語っていただけましたのでご紹介させていただきます! ■株式会社みずほ銀行 足立 龍生様 常務執行役員 写真で見るより想像をはるかに超えてます。今5haが完成して直近のマイルストンは2000ha。ものすごいインパクトになるんじゃないかな。輸送や設備の課題を解決してどう実現化していくかが重要ですね。是非サポートさせてください。 ■出光興産株式会社 鈴木 基弘様 次世代技術研究所 所長(執行役員) 藻類はポスト石油に継ぐ一つの答え。微細藻類だけではなく様々なピースをはめていくことも含めて色んなものでソリューションしていく。おそらく一つだけでは成し得ない。様々な企業が集まって色んなソリューションを考えるように作られたのがMATSURI(コンソーシアム)だと思う。 ■池田糖化工業株式会社 水ノ上 伸二様 専務取締役 藻類由来の食品市場展開はまだ未知数です。食品としての展開は味でいくのか、栄養面や健康面か美容か、食品として消費者が何に価値を感じるのかが課題と思います。 ■株式会社資生堂 池田 智子様 チーフブランド&プロダクトイノベーションオフィサー 藻類由来の原料は消費者イメージは良いと思うが、それが購買動機に繋がるかは難しいのストーリーが必要。藻類に対する期待度は「これからあるべきもの」。まずは出来るところから絶対に開発する!と考えています。藻類も種類によって実行しやすい・しにくいがあるようなので、まずは入手し早速開発に着手していきたいと思います。 ■郵船商事株式会社 櫻 俊彦様 取締役執行役員 培養への期待度はすごく高いです。そして栽培についても技術的にいろんなことを工夫されているし、栽培場所についても十分に考えられた結果がここにあると感じました。郵船グループとしてもゼロカーボンで船を動かすと2050年までにと言ってるから、なんとか成し遂げないといけないと言ってるので、グループ会社の我々もそれに対しする燃料供給など役割を果たしていきたい。船舶燃料だけでなく、潤滑油なと油関係で藻から出る油分を使った製品でカーボンゼロを達成できればなおいいですね。 ■株式会社レゾナック 藤森...
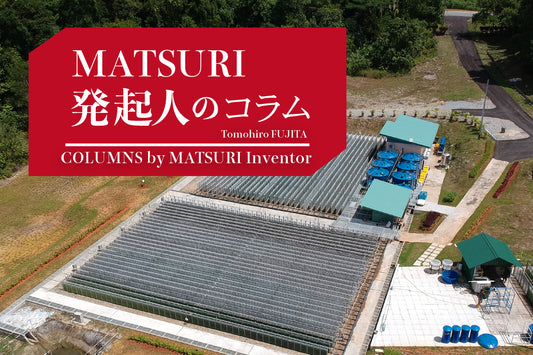
意志や価値観を広げるということ「Decision Making to Expand #5」
前回と前々回は、物事を整理しすぎると意志や価値観が広がらない。整理することこそが正義だという社会にしてしまったことが、世の中に意志や価値観が広げられない社会になってしまった原因だと思うということが書きたかったのですが、何が言いたいのかわからない文章にしてしまいました。今回も引き続き、意志や価値観を広げるということについて書きます。 少し前に、ある漫画の原作のドラマ化で原作者と脚本家の間に価値観や考え方の齟齬があり、大変残念な結末になってしまったニュースがありました。私は、件(くだん)の漫画もドラマも見ていないのですが、でも、まず世の中に伝えたい「意志」や「価値観」があって、それを伝えるために心血を注いで描いた漫画だからこそドラマ化が検討されるほどのファンが居たのだろうという事実が、あまりにも軽視されているような報道が目立っていたと私は感じます。自分の子どものように、いや、自分自身のように大事にしている作品が、自分が伝えたい「意志」や「価値観」とは全く異なる仕上がりのドラマになって自分の名前で世間に広がっていくことが、人生の全てを投げ出したくなるほど辛い状況であるという気持ちを、私は嫌になるほど理解できます。 今の日本の世の中には、このゼロからイチを作った人間の「意志」や「価値観」を踏みにじられる時の辛い気持ちを理解できない人が本当に多いということを、さらに、そんな気持ちが理解できない人の方が出世し易い社会の構造になっていることを、私は経験上知っています。もちろん、マスコミや広告代理店、コンサルや商社のような、業界と業界の間に立つ仕事をしていたらゼロからイチを作った面倒くさめな性格の人間の「意志」や「価値観」なんかを、いちいち丁寧に大事にしていたら仕事にならないし、何よりイチを十・千と広げることなんかできないという状況になるのもとても良くわかります。 しかし、だからこそ誰か面倒くさい人が作った「意志」と、その「意志」に一定の同調者が存在するという事実を大事にしないと、漫画からドラマや映画とメディアを変えて万・億の人の心には届かないはずなのです。たとえそれが大衆に広げるプロの目から見て、メッセージが難し過ぎて大衆には広がらないと判断したとしても、それでも尚、その難しさ・分かりにくさを内包した作品でないと、十・千になることはできても、万・億と広げることはできないと思うのです。一定のファンが居るアイドルやタレントを主演にして、彼らのファンに伝わり易いように「意志」や「価値観」を改変して小さな商業上の利益を確保したいだけなら、難解な価値観の原作なんか使わなければ良いのです。 この「意志」や「価値観」の伝播を、価値観が異なる大勢の人の間で調整しながら繋ぐという複雑でストレスフルな役割を担っているからこそ、マスコミや広告代理店、コンサルや商社のような仕事は付加価値が高く給料も高いのだと私は思います。しかし、この数十年の日本社会は、価値観と価値観の間に立っている職業の人間が過剰に偉くなってしまい、この複雑でストレスフルな役割を担わずに、表面的な仕事を進めてなんとなく繋がっていれば正解という価値観になっているように感じます。難解なテーマを伴う「意志」や「価値観」だからこそ、ドラマ化や映画化の議論の俎上に乗るほどのファンが居るのだという当たり前の事実を、この数十年の日本の社会はあまりにも軽視して来たのではないでしょうか。 一方で、Netflixのシティーハンターのように主演の俳優はじめ作品制作に関わった全ての人が、数十年前の原作に込められた「意志」や「価値観」をリスペクトして現代の視聴者に届けようとしている作品は、たとえそのモチーフが数十年前の古く難解なものであっても、ちゃんと世界で大ヒットするのです。Netflixにはできることなのに、日本企業には「原作者の意志や価値観をリスペクトする」ことができなくなってしまったことが、世界中で日本だけ30年も経済成長しなかった根本的な大きな理由の一つであると私は感じています。 私が新規事業を生み出すときにいつも一番大事にしているのは、この「最初にやろうと言い出した人間の意志や価値観が、どこにあるのかを大事にしながら、更に多くの人の意志や価値観をどんどん載せていくような器を作ること」なのですが、この「意志」と「価値観」を伝播させることが大事だという仕事の仕方が日本ではどんどん失われてしまっているので、この概念を伝えるのがなかなか難しいです。 藤田がたまに地獄のような顔をして悩み込んでいるときは、ほぼ間違いなく、私が仕事をするうえで最も大事にしているこのポイントを、社内外の誰にどう説明しても理解してもらえず、自分の説明力不足に打ちひしがれて困っているときだということだけでも知ってもらえれば、とりあえず眉間の皺も少しは減るし、髪の毛の減り具合も遅くなります(笑)。 written by: Tomohiro FUJITA ◾️本連載の記事一覧 #1:「広がる意思決定」と「縮まる意思決定」#2:整理と混沌のバランス#3:バランスを均一にしてはいけません#4:積み上げたものぶっ壊して、遮るものはぶっ飛ばして #5:意志や価値観を広げるということ
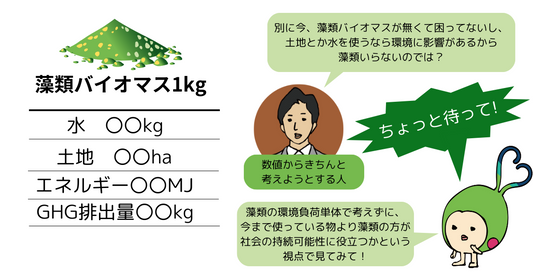
正直MATSURI日記3:藻のLCAの目的ってなんだろう?
こんにちは。正直MATSURIの新人担当者のサリーです。サリーは生物のことは得意なのですが、環境負荷の評価や関連する活動についてはまだ素人です。 ~前回のあらすじ~ 学ぶとは、「マネをする」ところからということで、社内にある環境負荷に関する報告にあったGREETというソフトを触ってみることにしました。環境負荷の計算をするためのソフトは世界に様々ありますが、「燃料」用途の環境負荷計算ではGREETがよく使われている印象です。四苦八苦しつつ、関連するニュースを読みながらGREETソフトを眺めることができるようになりました。そんな中で温室効果ガスの排出量を計算する方法というのは複数あり、変化し続けているものであることを理解していきました。どんな方法を使ったかも併せて情報発信する温室効果ガスの情報について発信するのが正直MATSURIな姿勢だと考えたところです。 ~あらすじ終わり~ ということでMATSURIの藻の製品をGREETソフトで分析するぞ!GREETソフトで計算をするにはまず計算の前提となる情報を整理する必要があります。藻の製品のゆりかごから墓場までにどんなステップがあるのか、そのステップで使うエネルギーや原料等のインプット、そのステップで出てくる産物や廃棄物等のアウトプットを整理していきます。このような製品のゆりかごから墓場まで考えて環境負荷を計算することをライフサイクルアセスメント(LCA :Life Cycle Assessment)[1] といいます。LCAの実施手順はISO14040で国際規格化されています。 藻の製品のライフサイクルに対するサリーの初期の認識はこうです。 藻を育てる。藻は縦型のフラットパネル型の藻類生産設備(PBR)で太陽光をいっぱい浴びて、どんどん育つ!育つのが早すぎて光合成に使う水中の二酸化炭素が足りなくなって育ちが悪くなるのを防ぐために二酸化炭素をブクブク(エアレーション)する。 藻ツリーの幹となる藻類バイオマスを収穫する。 バイオマスからいろんな製品ができる!その時に電気や熱や他のいろんな原料も使って作る。 燃料として使われる場合はエネルギーを得る。その際に燃やすことで二酸化炭素が出るけど光合成によって還元した二酸化炭素由来の二酸化炭素なのでその分はカーボンニュートラル。 物として使う場合は、その製品をある程度の期間製品として使われた後、埋立したり焼却処分される。分解したり、焼却する時に二酸化炭素が出るけどその分はカーボンニュートラル。 食品として食べる場合は人間が口に入れるまでについて考える? さて、これをどうやってGREETで扱えばよいのでしょう? LCAの実施方法はISO14040で国際規格化されているのでそれに沿って考えましょう。LCAを行う際は「目的や調査範囲の設定」(ISO14040)を行います。MATSURIが藻類のLCAをする理由とはなんでしょうか? 理由は2つあります。 理由1「藻類製品の環境負荷をより低いものにするための活動をするために現状把握をし、改善効果の予想をしたい!」 理由2「藻類が環境に優しいということを定量的に示したい!」 1つずつ整理して考えてみましょう。 理由1「藻類製品の環境負荷をより低いものにするための活動をするために現状把握、改善効果の予想をしたい!」 藻を育てて収穫するのに水などの資源やポンプを動かすなどの電気エネルギーを使ったり、藻類バイオマスから製品を作るのに加工に様々な原料やエネルギーを使用します。原料調達から廃棄されるまでのどの工程がGHG排出が多いのか、エネルギー消費が多いのか、水の消費が多いのかを把握することができれば、改善すべき工程・方向性がわかります。例えば、育てるときのブクブク(エアレーション)を24時間から12時間に減らすことができるとするとどの程度のGHG削減効果が見込めるのかが数値化できます。どのような改善をするとどの程度の効果が見込めるのかが数値化できるので、やるべき改善の優先度を決めるのにとても役に立ちます。 理由2「藻類が環境に優しいということを定量的に示したい!」 MATSURIは今の石油基盤社会から藻類を基盤にする社会になることで持続可能な社会の実現をします。MATSURIが幅広い賛同を得るには、藻類が環境に優しいということを定量的に示す必要があると考えています。これを示すためにはいったいどのような計算をすればよいのでしょうか? 「藻類バイオマス1kgの生産に水〇〇kgと土地〇〇haとエネルギー〇〇MJを使い、バイオマスに〇〇kgの二酸化炭素が固定され、GHG排出量は〇〇kgでした。」ということが計算されたとします。その結果を見て「藻類は環境に優しい!」と思うでしょうか?シンプルに考えると、「別に今、藻類バイオマスが無くて困ってないし、土地とか水を使うなら環境に影響があるから藻類いらないよ」と思うのではないでしょうか?しかし、この考え方には罠があります。あらゆる既存品を代替する新しいものが真のポテンシャルを評価されることなしに「いらない」という考えに結び付けられてしまうのです。...

積み上げたものぶっ壊して、遮るものはぶっ飛ばして「Decision Making to Expand #4」
※年度末だったことや担当の体調不良など色々なことが重なり、第四回のコラムの更新が遅くなってしまいました。 前回は、拡大するためには整理と混沌のバランスを意識するのが大事だという話を書きました。 「仕事を進めること=整理を進めること」が一般常識とされている中で、藤田がそこそこの頻度で混沌が進むような意見を言ったり、わざわざ混沌が増すような指示をしたりすることに、新たにちとせに加わったメンバーが困っているのを見ると大変申し訳無い気持ちになります。 だからといって整理と混沌のバランスの取り方こそが、組織の拡大のための鍵であると私が信じている以上、現在の日本の常識である何事も整理が進むほど良いのだという考え方に自分を合わせるわけにもいきません。藤田がこのタイミングで混沌させるようなことを言う理由を何度も何度も説明するのですが「まーた藤田さんがわけわからないことを言っている」「せっかく一生懸命やってるのに認めてくれない」と余計困惑させてしまうことが多いので、そんな状態が少しでも和らぐと良いなと思い、前回の記事を書きました。 こうしてどんなに私なりに言葉と時間を尽くして説明しても、整理と混沌のバランスが大事なのだから整理ばかりしていても事業が広がっていかないのだということをなかなか理解してもらうことができません。その理由は、現代日本の価値観と異なるから以外にもいくつかあるのですが、そのうちの一つに、そもそも何を拡大したいのかが擦り合っていないという理由があるような気がしています。 私が広げたいのは個人の「意志」や「価値観」です。なにも藤田の「意志」や「価値観」だけを広げたいのではなく、そこには釘宮や笠原や堀内や星野だけでなく、今井や野本のような裏方の仕事をしているメンバーの「意志」や「価値観」も加わりますし、さらにそこには今や四〇〇人近いちとせグループに所属する一人一人の「意志」や「価値観」が加わります。さらにさらに、ちとせと資本提携したり業務提携していただく企業に所属する一人一人の「意志」もそこに加えて、世界に広げて千年先まで残したいと思っているのです。 関わった人たちの「意志」や「価値観」が広がれば広がるほど、様々な立場でそこに関わった個人に対して経済的にも恩返しができると私は信じています。資本主義って本質的にはそういうことでしょ?と思うのです。私は会社のCEOを名乗っている責任とプライドとして、ちとせに出資や業務委託をするという決断をしたり、自分の人生を賭してちとせに入社するという決断をした一人一人に「経済的にも得をした」と思って頂く方法を常に考えています。私が個人の「意志」や「価値観」を広げたいと何度も言っている理由は経済的な観点で考えてもその方が良いからと思っているからなのです。 今の日本は極めて高度に整理された社会です。その中にあるちとせのような小さな会社でも、皆が一生懸命働くほどその結果としてどんどん整理が進みます。しかし、私が広げたいのは個人の「意志」や「価値観」なのだから、整理と混沌のバランスが、過剰に整理に傾くのは、「意志」や「価値観」が広がらなく状態になっている匂いがするぞ感じるのです。 せっかく積み上がった整理をぶっ壊すのは、いつも気が引けるし申し訳ない持ちになるのですが、それでも創業者兼CEOにしか壊せないバランスってあるよなと感じて、「また、藤田さんがわけわからんこと言ってるぞ。」ということを言うのです。 某ヒット曲の様に、♫積み上げたものぶっ壊してー♫遮るものはぶっ飛ばしてー♫と楽しげに勢いよくできれば良いのですが、生憎そういう楽しげな性格に人間ができていないので、毎回なんだか申し訳ないなぁと感じているんです。役割なのでやりますけどね。 written by: Tomohiro FUJITA ◾️本連載の記事一覧 #1:「広がる意思決定」と「縮まる意思決定」#2:整理と混沌のバランス#3:バランスを均一にしてはいけません#4:積み上げたものぶっ壊して、遮るものはぶっ飛ばして #5:意志や価値観を広げるということ
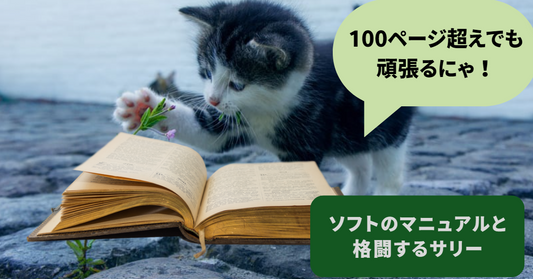
正直MATSURI日記2:燃料として使う場合の温室効果ガスどうやって計算するんだ?
こんにちは。正直MATSURI新人担当者のサリーです。サリーは生物のことは得意なのですが、環境負荷の評価や関連する活動についてはまだまだ素人です。~前回のあらすじ~学ぶとは、「マネをする」ところからということで、社内にある環境負荷に関する報告に記載があったGREETというソフトを触ってみることにしました。インストールするだけでも大苦戦でしたが、無事にインストールを完了し、ソフトを動かせるようになりました!~あらすじ終わり~GREET起動! このGREETというソフトですが、起動するとすでに様々な製品・原料の数値・フローが入っています。例えば、トウモロコシから作られたエタノールをジェット燃料にするトウモロコシエタノールSAF(Sustainable Aviation Fuel:持続可能な航空燃料)を見てみましょう。ソフトのProductsからSustainable Aviation Fuel(SAF)を選択し、さらにEthanol- To Jet: Satandalone from Cornを選びます。 なるほど。なんかカッコいい図が出てきました。でもよくわからない。( ノД`)シクシク…。わからないときはおとなしくマニュアル[1]を読みます。100ページを超えていますが、張り切って読みます💪。 GREETは、アメリカ政府のエネルギー省の研究機関であるアルゴンヌ研究所が作成・管理しているソフトウェアです[2]。エネルギー省の所管ということで、燃料やエネルギーを生産し、消費(燃焼)するまでに出る温室効果ガス(GHG:二酸化炭素だけでなく、メタン、代替フロンなども含むめる)や、酸性雨の原因となる物質、使用される水の量を計算できるようになっています。環境への影響を計算をするためのソフトは世界中に様々ありますが、燃料を対象とした場合はGREETが広く使われていて、逆に燃料以外ではあまりGREETは使われていない印象です。MATSURIプロジェクトでは燃料だけでなく生活用品や食品まで様々なものを作ります。つまり、サリーは他のソフトやデータベースの使い方や仕組みも勉強しないとってこと?これは大変だ…😅。 燃料のライフサイクルを考えてみます。まず、燃料として使える状態に生産するまでと、どんな乗り物の何の燃料として使うかの大きく2つに分けられます。これを専門用語でWTP(Well -to Pump:油田からポンプまで)とWTW(油田からホイールまで(つまり走行段階まで))と言います。WTWにさらに乗り物の製造に関連する排出量を足したものをC2G (Cradle -to -Grave ゆりかごから墓場まで)と言います。 これらは、GREETの「WTP Results」タブと「WTW and C2G Results」タブに対応しています。そして「WTP Results」タブで右下に出てくるカッコいい図がこういうフローで燃料をつくるよ、ということになります[3]。そして各工程で原料の量や電気の使用量が数値として入っています。原料・エネルギーを作る際に排出されるGHG量がデータセットとしてソフトに入っており(多くの原料・エネルギーに対応しているが、ないものもある)、それらの数値を使うことで計算ができるようになっています。そして左下にある「Emissions」で二酸化炭素排出量や酸性雨の原因となるSOxの量等が表示されます。なるほど、ちょっと分かった! フローをクリックすると表示されるウィンドウ。使う原料やエネルギーの値が入っている。 さて、2023年9月にこのGREETに関する話題がありました。アメリカのエタノール団体がトウモロコシエタノールSAFについて、最新のGREETモデルの数値を使うことをアメリカ政府に求めたのです[4]。まず、サリーはこの話を聞いて「???もともとGREETの数値使ってるんじゃないの~?いまGREETを使っていてGREETを使ってほしいってどういうこと~?」と混乱しました。 何に混乱しているか現状を整理します。アメリカのエタノール団体の要求は「トウモロコシベースのエタノール...

百人組手の一人相撲 vol.4 「藻類産業に足りていないもの」
MATSURI関連企画「百人組手」のチャレンジを続ける中で感じたことを綴る「百人組手の一人相撲」。連載の第4回目は、藻類産業に足りていないもの。 前回は「地図を眺めること」についてお話ししました。今回は私が藻類の産業利用における課題について書きたいと思います。もちろん、課題は至る所に山積しているのですが(だからこそ、MATSURIという活動の意義があります)、その中でも藻類の文化的アプローチにとって最も根本的な問題、すなわち「藻類とは何者なのか」というポイントについてです。 そもそも「藻類」という言葉の生物学的意味もそれほど明確ではありません。それは光合成する生き物のうち、いわゆる陸上植物(コケ、シダ、裸子植物、被子植物など)を除いた生物たちの総称です。つまり、系統的なことを言えば必ずしも近縁な生物のまとまりではなく、極めて多様な特性を持った種からなる、かなり強引な単語です。私たちがイメージするような緑藻(アオサなど)や紅藻(ノリなど)、褐藻(ワカメやコンブ)の仲間は食卓にのぼる種も多く、比較的イメージしやすいかと思います。ただし、多くの場合比較的大型の藻類をイメージされる方が多く、MATSURIがメインとして取り組んでいるような小さな藻類(微細藻類)は理科の教科書でわずかに触れる程度の接点しか持って来なかった方も多いのではないかと思います。 微細藻類の世界は、私たちの肉眼で捉えられないもう一つの植物の世界です。そして目で見える世界は、その表層にすぎないのだと感じることでしょう(実際のところ陸上植物とは乾燥を克服し地球の薄皮にへばりつく生き方を選んだ生命です)。微小の世界に蠢いている藻類には、もちろん緑藻や紅藻の仲間もいます。生物学に少し関心のある方なら珪藻を知っているかもしれません。そのほかにはアルベオラータやリザリア、エクスカバータといった呪文めいたグループ名が並びます。ちなみにエクスカバータにはミドリムシがいますし、緑藻や紅藻は(実は地上植物も)アーケプラスチダのサブグループです。ですが、人間にとってイメージしやすいような種類がそれぞれのグループの代表という訳でもありません。微細藻類は生態系のダークマター(暗黒物質)のような存在だと感じます。 私の感じる課題とは、つまりダークマターに関していかにコミュニケーションできるのか、ということです。私たちの社会は、いまだ微細藻類というグループに対して「有望な産業の道具」以上のイメージを持てていません。もちろん、そうした側面があること自体は問題にならないどころか、インセンティブとしてとても重要です。しかし、身近な動植物に対して私たちの社会が様々な考えを抱きうるように、人間の文化(culture)に根付いた成熟した関係を涵養(Cultivate)し、複雑な思考を巡らせられるようにならねば、微細藻類との関係は一面的で薄っぺらなものになってしまうでしょう。 食卓に並ぶ穀物や野菜、牛や鶏や羊やペットの犬も、はじめからその姿で人間の生活に組み入れられていた訳ではありません。それは多くの努力と長い時間をかけて織り成されてきたテキスタイルなのです。そして私たちはわずかな時間の中でテキスタイル作りを成し遂げようと努力しています。この驚くほど小さく、多様で、謎に満ちた存在について、合理的で豊かな関係を取り結べるようにすることこそ、「藻類産業構築」の終わりなきオープンゴールなのではと思います。 written by:Aoi Nakamura

バランスを均一にしてはいけません「Decision Making to Expand #3」
先週6日間ほどインドに行ってきました。整理と混沌のバランスをいつも意識していると第二回で書いた藤田にとって、インドという国は想像以上にとても興味深い国でした。一般的に日本人がイメージしているほど過剰に混沌側に偏った国ではないし、むしろ日本人よりも整理と混沌のバランスとそのあり方についてとても深く考え続けているのがインド人なのだというのが、たった6日間の滞在ですがよくわかりました。 インド人とは対照的に、現在の日本人は混沌を少しでも減らしてとことんまで整理し続けることがあるべき正解だと思っている人が多い気がします。そういう価値観の方に整理と混沌のバランスが大事なのでは?と意見すると必ず「世間知らず。」「MBAに行け。」などと頭ごなしに怒られて否定されます。いくつになっても、整理だけが正義だよ教の人に「バランスが大事なのでは?」と言っても怒られるだけなのがわかっているのに、それでも言っちゃう性格なのは直せません(笑) 整理と混沌のバランスが大事と言っても、何も私は組織の全ての部分のバランスを均一にするのが正しいとは思ってはいません。20年近く前に私がコンサルタントの仕事をしていた頃に発電所の目標設定や人事評価指標を作る仕事をしたことがあるのですが、発電所に混沌を持ち込んではいけません。発電所のような業務の場合、個人の意志や個人の判断は極力排除して、仕事の全てが綺麗に整えられたマニュアル通りに遂行することを良しとする組織で当たらないと危険だからです。(とはいえ、そういう価値観で作られた組織が、マニュアルを作ったときに全く想定していなかった事象に対峙しないといけないようなことが起こると・・・) 発電所は世の中でも極端な例にはなりますが、やり方がある程度確立している業務を行う組織においては、可能な限り業務をマニュアル化し、誰がやっても同じ品質を提供できる組織構造を作ること、つまり「整理すること」がビジネスを「広げる」ことに繋がります。マクドナルドやスターバックスが世界を制したのも、その業務を世界の多くの人でも対応できるようなマニュアルに整理するのが極めて上手だったことが大きな理由であることは言うまでもありません。また、マニュアル化して整理することにより従業員や顧客の安全が確保される確率も跳ね上がります。お金を稼ぐ大前提として、顧客の従業員の安全を守ることが会社経営にとっては何よりも大事であり、そのためにも業務を整理をすることは何よりも大事ということになります。(もっとも、整理が進んだ組織には全く想定外のことが起きた時の対処が遅れがちになってしまうという側面もあります。) 語り尽くされた議論ですが、今の日本で成功している企業には、欧米で作られてある程度やり方が確立している業務を日本人のセンスで整理し直して世界に広げた例は枚挙に暇がないくらい多いです。また、バブル期の過剰にアグレッシブな経営を収集するためになんとか事業を整理したことで高利益体質になり無事に今も日本経済の中心にいる企業もとても多いです。どちらの場合も、今それぞれの企業でトップに居る方の多くが「業務を上手に整理をしたこと」を評価されてそのポジションについていることになります。このことが、整理と混沌のバランスが他の国と比べて日本だけ大きく整理側に偏ってしまっている大きな理由の一つであるように私は感じます。 確認したいのですが、藤田は日本の大企業が過剰に整理側に寄っているから悪いということを言いたいのではありません。そもそも整理をすることが悪いことだとも思っていません。実際、ちとせという企業が大きくなるにつれて、我々が更に成長するためにも、顧客と従業員の安全を守るためにもより整理を進めなければならない業務・部署はどんどん増えています。 個人的な告白をすると、私自身は物事を整理するほうが楽だし、好きだったりします。しかし、スタートアップのCEOという役割をここまでの人生で選んでいることもあり、日々必死に自分の組織における混沌側の割合を増やそうと骨を折っているので、私自身が混沌を起こしたい人・混沌が好きな人だと思われている気がしていますが、決してそうではありません。そもそもシンガポールでの生活が好きって言ってる人間ですしね。 私はただ、他の国と比べて日本だけが、世の中の全てを整理側に寄せることだけが仕事の進歩であり社会の進捗であると多くの人が疑わない社会・カルチャーになってしまっているのはなぜなのか?という論点について議論したいだけなのです。その理由のうちの一つが、今の日本の経済界で実権を握る人のほとんどが「混沌の状況を上手に整理したこと」で評価された人だからというのは、多分ピントの外れた指摘ではないのではないかと思っています。 ちとせのような小さな会社を経営する上では、チームづくりという仕事の重要さが経営者が果たす仕事の割合で大きいと考えています。ちとせに「人事部」がまだ存在しないのもそれが理由です(そろそろ人事部ができることになるとは思いますが)。会社の中に無数にあるチームのそれぞれにとってあるべき整理と混沌のバランスは、それぞれのチームが対峙している業務の種類によって異なります。そして、それぞれのチームの整理と混沌のバランスは、チームにアサインする人間の嗜好と志向と思考によって調整するのが経営者の役割だと思うのです。 ちとせの中で最も混沌寄りのチームを作らなければいけない業務は、世の中でまだ誰もチャレンジしたことのない研究開発・事業開発を行うチームです。こういったミッションに対峙するチームを作る場合には、その分野について全くの素人を集めたチームでは上手く行かないのは言うまでもないのですが、だからと言ってその分野のエキスパートばかりを集めても上手くいきません。 この『チーム内の人材のバランスで整理の混沌のバランスを保つことこそが研究開発・事業開発の肝だ』という説明をすると、事業会社の方々には「なるほど面白いことを言うね。」とか「以前からそう思っていたのだけど言語化してもらってスッキリした。」というお言葉をいただくことが多いです。一方、コンサル業のような、外部から事業を支援するという生業に従事しており、尚且つその道で経済的に成功したキャリアの人は、「専門性は深ければ深いほど良い。」「専門家の割合が増えれば増えるほどよい。」と考えるために、藤田の「素人と専門家のバランスによって、整理と混沌のバランスをとるのが大事なんです。」という意見に対しては、お前は相変わらず「世間知らずだ。」とか「MBAに行け。」とお小言をいただくことが多いです。 その人が辿ってきたキャリアによってここまで綺麗に意見が分かれるのを見るたびに、好奇心旺盛な藤田はついつい楽しくなってしまって、ついついニヤニヤしながら真剣なお説教を聞いてしまうので、更に怒られます(笑) このあたりの「素人と専門家のバランス」が、新しい事業を興すときになぜ大事なのかという具体例がよく分かるので、先日公開されたアフリカを自転車で縦断したことがある片岡の記事(ちとせのひと Vol.6 片岡陽介 ~エボリューションの中で生きている~)を是非読んでみて下さい。 私自身は自転車で50kmも移動したことないのに、自転車でアフリカ縦断の片岡の話が面白くて何度も聞いているせいで、たまに面接で日本をバイクで縦断したとか、九州から東京まで自転車で旅をした話を熱心にしてくれる若人の話の反応が、ついつい薄い反応になってしまって申し訳なく感じています。 written by: Tomohiro FUJITA ◾️本連載の記事一覧 #1:「広がる意思決定」と「縮まる意思決定」#2:整理と混沌のバランス#3:バランスを均一にしてはいけません#4:積み上げたものぶっ壊して、遮るものはぶっ飛ばして #5:意志や価値観を広げるということ
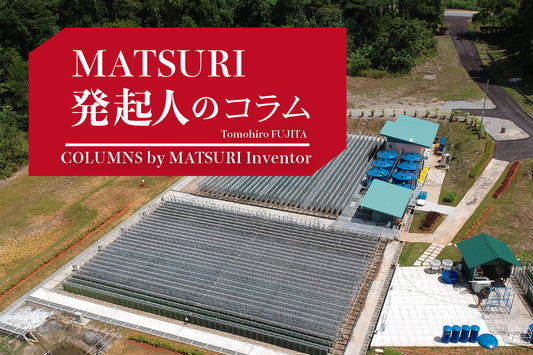
整理と混沌のバランス「Decision Making to Expand #2」
「なんか社会の誰からも求められていない気がするけど、50歳にもなってしまったし久しぶりに連載でも始めるか。」という動機で、大海原に向かって小石を投げ続けてみようという気持ちで始めた連載ですが、第一回からボチボチ反響をいただきまして嬉しく思っています。 前回は、私が言いたい「広がる意思決定」とは、ポジティブやネガティブという軸とは全く関係がないのですということを言いたかったのですが、今世界にはびこるポジティブ信仰がなかなか根強いせいか、「私もポジティブ信仰にはしっくりこないと感じていた!」という点での反応が多かったような気がします。 第一回で私が言いたかったことは以下の図のようになります。 ポジティブと「広がる」が一致する第一象限は特に問題ないのですが、私が言いたいことを伝えるためには、ポジティブなのだけれど縮まる意思決定である第四象限について例を挙げて説明すれば良いのだということがわかりました。しかしながら、私がこの連載で対峙したいラスボスのうちの一人である「日本に蔓延るポジティブ信仰」は、どうやら現在のヒノキの棒とメラだけの装備では倒せそうもないことがわかったので、このラスボスを倒すのは連載の後回しにして他の論点の話をしたいと思います。 ポジティブと「広がる」の関係の説明を後回しにしてでも、まず先に触れなければいけないのは「整理や混沌」と「広がる」の関係です。 私が経営判断を迫られ、これは「広がる意思決定」なのかどうかを自問自答するときに、かなり重要視しているのが「整理と混沌のバランスを維持する」ことです。なぜなら、物事は整理しすぎても広がらず、混沌としすぎても広がらず、物事や組織が自発的に広がっていくには、最適な整理度合いというか、最適な混沌度合いがあると考えているからです。論理的な表現に言い換えれば、ポジティブやネガティブと「広がる」は独立事象でしたが、整理と混沌と「広がる」は独立事象ではないということになります。 ここで、私が「整理と混沌」のバランスを如何に大事にして意思決定しているかの例としてちとせのロゴマークの事例をご紹介します。デザイナーのIzuさんと何度もやり取りを重ねて最終的に出来上がったロゴマークは、文字間が広いものと狭いものの2通りでした。 デザインの完成度で言えば文字間が狭いものの方が正解だと思いつつも、私は文字間が広い方の案の採用を関係者で一人だけ強く主張しました。わざわざ不正解を選ぶ社長の意見は関係者全員からだいぶ反対されたのですが、ここは年に一回の社長のわがままカードを使わせてくれと強く主張したのを覚えています。 ちなみに、私はIzuの案よりももう少しだけ文字間を広げて欲しかったのですが、上記のような経緯だったので、デザインの完成度をさらに下げる方向の社長の願いは当社の広報部門に受け入れて貰えず今のデザインに落ち着いています。 では、なぜデザインとしての完成度を落としてでもロゴマークの文字間をもっと広げてほしかったのでしょうか。それは、「整理と混沌」のバランスが経営の意思決定をする上で大事だと思っている私の価値観を、ロゴマークからも表現したかったからです。 改めて言われれば誰でもそりゃそうだと言ってくれるのですが、古今東西、ありとあらゆるものが、混沌や隙間、つまり不完全さがないと広がらないわけです。完璧を目指すことは、完璧を実現したその瞬間から衰退が始まることを認めることになります。なんだか説教めいた難しいことを言っているようですが、カニだって食べられるリスクを背負って脱皮するし、我々の文化だっていつも人間的には不完全な人間ばかりが、新しい時代の文化の扉を開き続けて来ました。完璧を目指すことのつまらなさこそ、日本人が大事にし、世界に発信し続けるべき価値観の一つなのではないかと私は思っています。欧州や中華の価値観では最上とされてきた完璧な造形と幾何学模様の食器よりも、どこか曲がった造形で、ある意味運任せで描かれた模様の食器にこそ高い価値を置く日本人の価値観は、人類全体が大事にすべき宝だと私は思うのです。 だからといって、完全なる混沌の中では成長も発展の可能性も生まれません。「整理と混沌のバランスを取り続けること」こそが、組織やビジネス、文化や価値観が広がっていくためにとても重要なポイントだというのは、これくらい謎の熱量で説明すれば、何を言っているのかよくわからないけど、まぁなんか正しいことを言っていそうだし、めんどくさいから頷いておこうという気持ちで(笑)多くの人が同意してくれます。 こうして「整理しすぎてはいけない。」「完璧を目指したら広がらない。」という総論では(まーた藤田がめんどくさいことを言い始めたよとしぶしぶ)納得してくれるのですが、いざ個別に具体的な事例での意思決定の場面になると、藤田が物事を「混沌寄り」にバランスを動かそうとするたびに、「常識を知らない。」「センスがない。」「なんでわざわざ壊すんだ。」と文句を言われ、藤田が目指したいバランスに物事を調整することを許してもらえません。 この整理と混沌のバランスを調整することは、自分が最終決定者にならないとやらせてもらえないと30歳前後で感じたことがサラリーマンを辞めて自分で会社を作るしか無いと思った理由の一つです。その後20年近く経ち、株主だろうが社長だろうが、所詮社会の中の駒の一つでしかない以上は、私が「ここだ!」と思うバランスでの意思決定を続けさせてもらうことはなかなか難しいのだなぁとつくづく感じています。 written by: Tomohiro FUJITA ◾️本連載の記事一覧 #1:「広がる意思決定」と「縮まる意思決定」#2:整理と混沌のバランス#3:バランスを均一にしてはいけません#4:積み上げたものぶっ壊して、遮るものはぶっ飛ばして #5:意志や価値観を広げるということ

「広がる意思決定」と「縮まる意思決定」「Decision Making to Expand #1」
もう半年前の出来事なのですが、50歳になりました。半世紀です。ヤバいです。 この50年間、とくにちとせを始めてからの15年間、大変多くの方との縁と支援に恵まれて、日本だけでなく色々な国の方と仕事をするような人生になりました。欧米のビジネスマンだけでなく、東南アジアや中東の王族の皆様、一代で大財閥を築き上げたオーナーや二世三世のオーナー、選挙で選ばれた政治家や官僚のトップ、国立研究所や大学の研究者の皆様、また一方で、現場の労働者の人達や森の中に住む原住民の皆さん、途上国から出稼ぎで来ている皆さんのそれぞれと、長い時間を掛けて色々な話をさせてもらい色々な価値観と接することができました。 そもそも私の根源的な仕事の動機は、ただひたすら「新しい世界を知り好奇心を満たすこと」にあります。多様な価値観の皆さんの考え方・行動原理と接し新しい価値観と触れることそのものが、私にとっては仕事の動機なのです。そんな動機で仕事をしてきた結果、世界中で日本だけが、なぜ失われた30年と呼ばれる時代を過ごしてしまったのかの本質的な理由がなんとなく見えてきたような気がしています。 その理由とは、意思決定において「広がる意思決定」か「縮まる意思決定」かという視点・軸が、日本人(特にエリートの日本人)の考え方、物事の決定のプロセスに含まれていないからだという仮説を持っています。また、少なくともちとせにおいては、意思決定者である私が可能な限り「広がる意思決定」を選び続けてきたことが、なんとか15年間会社が倒産せずに少しづつ拡大してきた大きな理由の一つだと思うのです。 日本がこの30年徐々に縮んでいる間に、東南アジアの各国も、中東の各国も大発展を遂げています。欧米も日本のような経済的停滞は起こしていません。 私は経済発展だけが正義であるとは思いませんし、かなり強く母国を愛しているタイプの人間です。ですが、日本の外に出て暮らしがドンドン発展する中に身をおいていると、世界中で自分の母国だけがドンドン縮んでいくことを実感します。日本を愛しているからこそ、この状況を目の当たりにし続けるのは気持ちの良いものではありません。 日本だけが世界と異なる状況であることの肝は、「広がる意思決定」という概念にあるのだと私は感じています。今までこのことについて説明する機会がなかったのですが、今回連載記事を書くことになったのであの手この手で皆さんに「広がる意思決定」とはどういうことを言おうとしているのかを説明し続ける努力をしてみようと考えています。 一体、藤田は「広がる意思決定」という言葉で何を説明したいのかさっぱり伝わっていないと思いますが、「広がる意思決定」と似て非なる概念に「ポジティブな意思決定」があると思っています。私は、この「ポジティブ」と「広がる」は違うものだと言いたいのですが、この違いをどうもうまく説明できないままでいます。 なぜ、うまく説明できないかと言うと、とにかくポジティブで居続けることが良いことだという価値観が強く蔓延っているからだと思うのです。藤田がなにか小難しいことを言っている時点で、こいつもどうせ「ポジティブでいろ」と、近頃よく聞くお説教を始めたいのだと思われてしまうのです。違うのに。 このポジティブで居続けろという社会からの圧力は年々その強度が増しているような気がしています。おそらくこのポジティブ信仰は、元来は米国で強かったものであり、私が若い頃の日本は今ほどの圧力ではなかったように思うのです。今や日本では、公の場で少しでもネガティブな意見を言おうものなら人間性ごと否定され、社会から抹殺されるような非難を浴びるので、根っからやたらシニカルに人間できている藤田は、近年は何も思ったことも言えないような窮屈さを感じながら生きています。私のようにこの世界に蔓延る「ポジティブ教」になんとなく窮屈な思いをしている人は少なくないのではないでしょうか。 正直に告白しますが、私は社交性や爽やかさがだいぶ足りない人間です。許されるのであれば、週の半分は誰とも話さずに部屋の隅っこでじっと座っていたいと日々思って生きている人間です。 仕事で知り合う方に、自分のことをこのように「根っから根暗なんですよ。」と言っても、あまり信じてもらえないどころか、「そんなことはない。あの時の藤田さんだって。」という話になることが多いです。 この認識のギャップの理由を考えると、それは根っからシニカルな私自身は、ポジティブな人間で居続けることは諦めている一方で、何かの意思決定をする時にそれが「広がる選択」なのか「縮む選択」なのかについては強く意識し、無理をしてでも常に「広がる選択肢」の方を選ぶようにしていることが理由のような気がしています。可能な限り「広がる選択肢」を選ぼうとするので、なんとなく藤田は前向きなことを言うポジティブな人間だという印象を多くの方に持っていただけているのだと思います。しかし当人的には、それはポジティブなのではなくて、「広がる選択肢」を選んだだけという意識なのです。 初回は、結局藤田の言いたい「広がる意思決定」というのはポジティブであることとは違うらしいということしか書けませんでしたが、今後あの手この手で整理を続けてみたいと思っています。私がこんなゆるい連載を書くことで、日本が再び世界の中で大きな存在感を発揮できる国に戻ることに、ほんの少しでも貢献ができれば良いなと考えて、現時点で誰からも求められてないことを始めている気もしていますがとりあえず一年は書き続けてみたいと思います。 written by: Tomohiro FUJITA ◾️本連載の記事一覧 #1:「広がる意思決定」と「縮まる意思決定」#2:整理と混沌のバランス#3:バランスを均一にしてはいけません#4:積み上げたものぶっ壊して、遮るものはぶっ飛ばして #5:意志や価値観を広げるということ

百人組手の一人相撲 vol.3 「最初の一歩」
MATSURI関連企画「百人組手」のチャレンジを続ける中で感じたことを綴る「百人組手の一人相撲」。連載の第3回目は、最初の一歩について。 日々進化している百人組手の「地図」(2023年夏版) 今回の「百人組手の一人相撲」では、プロジェクトを始めるにあたって考えたことをお話ししてみたいと思います。前回、私たちは状況の分析から入ったと述べました。すなわち自分たちの現在地と、「とりあえず」の目標地点を定め、予期される障害物をある程度詳らかにするというプロセスです。それは冒険に出る人が地図を読むことにも似ているかもしれません。 今回のケースで言えば、その目的地は「藻類産業の興りを具体的なアイテムのコレクションとして表現し、産業界の関係者だけでなく広く様々な属性の人々にその世界観を伝える」ことが目的となります。しかし、ここですでに「広く様々な人々」とは誰か?という問いが生じます。一方で、これは問いの立て方が不十分、ということでは必ずしもないと私たちは捉えました。問題を構造化するということはそれ以外の要素を方法的に忘れ去る、ということです。問いを限定することは、同時に矮小化でもあります。私たちが目指すものは「なるべく多くの人に藻類産業のポテンシャルと具体性を問うこと」ですから、むやみに問題を小さくすべきではありません。ここに、二律背反が生じました。 地図をつくる様子 私たちの得た回答はこうでした。「広く様々」をそれ以上に限定せずに、かつ具体的なアプローチが可能な定式に落とし込むには、その世界観を表現する力と志向を持った人々に私たちの理念を託し、その表現する人々の関心に応じながら、藻類の世界を広めていけばよいのではないか。つまり、クリエイターとのコラボレーションにより藻類を用いたマテリアルやアイテムを制作し、それぞれの領域へと拡散していくことで最大限の多様性を担保できるのではないかと考えました。すると実質的な目的地は次のように姿を変えます:「クリエイターと共に藻類産業の興りを具体的なアイテムのコレクションとして表現し、それらのアイテムを受け止めてくれる人びとには誰にでも、その世界を覗く窓を拓く」。 もちろん、この変形にはそれなりの代償があります。例えば、プロジェクトの大前提として偶然性や思いがけなさへの対処を「やってみる」という即興性への覚悟が必要になります。多くのコラボレータと共に創り上げていくからには、先々の展開をちとせの予想通りにコントロールすることは難しいでしょう。そこでは舗装された道の快適さはもはや期待できません。しかし、同時にそれは非ヒト種を扱うときの通例、生物学の常道でもあります。彼らは人間の都合は必ずしも関係なく、直接の制御を受け付けません。彼らと仕事をするには、彼らのやり方に流れを沿わせ、うまく付き合っていく必要があります。そしてこれはちとせの基本方針をなす要素でもあります。私たちはこのやり方でまずは目的地に「向かってみる」ことにしました。 written by:Aoi Nakamura
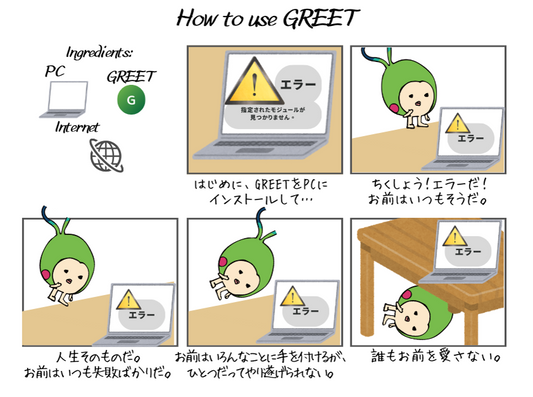
正直MATSURI日記1:まずはGREETってやつを使ってみようと思います。
こんにちは。正直MATSURI新人担当者のサリーです。サリーは生物のことは得意なのですが、環境負荷の評価や関連する活動についてはまだまだ素人です。ですので、学ぶためにも、まず最初に社内にある環境負荷に関する報告を自分で手に取り、動かしてみようと思います。学ぶとは、「まねる」または「マネをする」ところから始まるものですよね! 2022年2月24日の「GREET MODELを用いたCO2排出量試算について」というMATSURI検討会[1]の資料を読みました。その中で、GREET[2]っていうソフトを使って藻類生産の温室効果ガス(GHG)の排出を評価していました。おそらくこのソフトを使えば「この作業でGHG排出が多く発生しているよ。」といったGHG排出の現状や「この作業の電力を50%削減するとこんなに効果が!」といったアクション対効果をソフトの数値設定を変更してみることで理解できるようになるのではないでしょうか?ですので、まずはこのソフトを実際に動かしてみることにします! ということで、まずはサリーのPCにインストールだ! な、なんということでしょう。マニュアルの手順通りにやっているはずなのにエラーが発生します。 思い返せば、私の人生はいつも失敗ばかりです。「とりあえずやってみよう!」といって手を付けてはうまくいかない。ソフト一つ動かせない私なんて… その後、ソフトの付属ファイルの保存先を試行錯誤するなどして無事にGREETソフトを動かすことができるようになりました。よし!ここから実際にソフトを動かしながら学んでいこう! 次回もお楽しみに! [1]MATSURI検討会とは2022年年度まで月1で行われていたMATSURIパートナー向けのクローズドな検討会です。2023年度からは分野ごとの事前検討会(分科会)に変更となりました。 [2]GREETはアメリカのエネルギー省のアルゴンヌ国立研究所(ANL)が取りまとめる燃料のGHG排出量の算定を行うためのモデルです。Greenhouse gases, Regulated Emissions, and Energy use in Transportation model で略してGREETモデル。以下のサイトからソフトをダウンロードできます。https://greet.anl.gov/index.php?content=greetdotnet written by : サリー ◾️本連載の記事一覧 #1:まずはGREETってやつを使ってみようと思います。#2:燃料として使う場合の温室効果ガスどうやって計算するんだ?#3:藻のLCAの目的ってなんだろう?
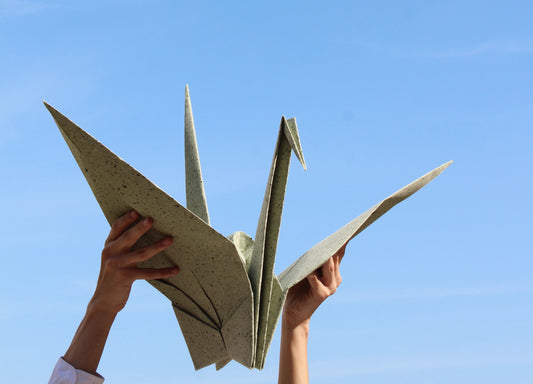
百人組手の一人相撲 vol.2 「きっかけ」
MATSURI関連企画「百人組手」のチャレンジを続ける中で感じたことを綴る「百人組手の一人相撲」。連載の第2回目は、百人組手のきっかけについて。 百人組手の記念すべき第一弾「千社札」。折り鶴と同じく越前和紙で作られている。 今回の「百人組手の一人相撲」では、そもそも100個のアイテムを作るというアイディアはどこから来たのか、そしてそれらをどのようにかたちにしようとしているのか話をしようと思います。とはいえ気の張った所信表明などではなく、今の段階での「とりあえず」の考えです。百人組手は過程を見せるプロジェクトですから、それも許されるでしょう。 さて、この百人組手のきっかけは既に2年前となったちとせグループの10周年記念に遡ります(ちとせグループ10周年記念特設サイト)。このイベントにおいて、ちとせのロゴである「折り鶴」を記念品として制作することになりました。もちろん、この特別な節目にただ折り鶴を折るだけでは魂がこもらないというものです。私たちはちとせのストーリーを表現し、これからの1000年に向けての誓いを込めて、「越前和紙」とのコラボレーションを企画しました。越前和紙には一説には1500年もの歴史があると言い伝えられており、その歴史と品質はまさに「千年先まで豊かに暮らすためのテクノロジー」です。その歴史へのリスペクトを込め、ちとせの思い描くバイオエコノミー産業の礎となる「藻類」を漉き込んで染めた特製和紙を作製し、鶴を折り上げました。 10周年記念で制作された折り鶴。(出典:ちとせグループ10周年記念特設サイト) 特製折り鶴の制作を通じて、このプロジェクトには記念以上の意味があったと感じるようになりました。世界観やコンセプトを発信する上でモノを作ることの重要性が、この折り鶴制作をきっかけにちとせの中で次第に強く認識されるようになったのです。モノの制作を通じた豊かなコミュニケーションの可能性が開かれたことにより、私たちは、ちとせそしてMATSURIの世界観を作り上げる新しいアプローチを手にしたのです。せっかく新しいアプローチに気づいたのですから、それを試し、さらに理解を深めたくなるのが人情です。 とはいえ、MATSURIは広大な可能性に開かれており、単発のアイディアではその射程を捉え切ることはできません。ですからここも「とりあえず」の気持ちで、単一のアイテムではなく、数多くのアイテムのコレクションにより、その世界の輪郭を朧げながらも描き出すことができないか、と考えました。最終的には10周年の「10」とちとせ(千年)の「1000」の間をとって「100」のアイテムコレクションを作るプロジェクトの構想から、「MATSURI 百人組手」をスタートさせることとなりました。 さて、いざ何かを作るとして、何から始めるべきでしょうか。私たちは分析から入りました。いまMATSURIに足りていない要素は何か?そもそも藻類とは?これを文化に取り入れるとはどういうことか?この分析の過程は今後もう少しだけ掘り下げることになるかもしれません。とりあえず、ここでは「染める」というキーワードが浮かび上がってきたという結論を述べるに留めておきたいと思います。 それでは皆様良いお年を。 written by:Aoi Nakamura

百人組手の一人相撲 vol.1
MATSURI関連企画「百人組手」のチャレンジを続ける中で感じたことを綴る「百人組手の一人相撲」。連載の第1回目として、まずは担当者よりご挨拶。 「百人組手」。それは文字通り百度の挑戦を潜り抜ける荒行。ちとせはMATSURIプロジェクトの一環として、100種類のプロダクト(のプロトタイプ)を制作し、その過程をレポートする難題に挑戦しています。現在は、最初の取り掛かりとして「染めるーー藻類産業における工芸の可能性」をテーマに、主に視覚的な表現の観点からユニークなモノづくりをしている作家や熟練の技術を持つ技術者とコラボレーションを進めています。これから藻類という魅力的な生物とより多くの人が接点を見つけられるよう、テーマ探しも精力的に進めていますのでよろしくお願い申し上げます。 さて、今では少しずつ社内での認知も上がり、「こんなリクエストがきてますよ」とか、「ここと何かできないですかね?」と声をかけていただくことも増えてきたこのプロジェクトですが、最初のきっかけはいわば個人発案の持ち込み企画でした。周囲の応援があるとはいえプロジェクトの方向性が自分に委ねられており、始めはさしずめ「一人相撲」の様相でした。最近では、いろいろな人の力を集めていくうちに「百人組手」というプロジェクトそれ自体が一つの生き物のように自律的に立ち上がっていくのを感じており、時々「おっ」と呟かされます。 とはいえ、百人組手はまだ始まったばかり。会社という狭い埒を超えてオープンワールドをどんどん探索し、どんどん強い生き物に成長して欲しいです。思えば、プロジェクトの行きたがる方向が次第に見えてきて、「百人組手」に対するガッチリとした手応え、いわばぶつかり稽古感が芽生えてきたように感じます。 何かを思い描きながらその輪郭が描けない人、自分の先入観を超えて何かを作りたい人、その「一人相撲」、私たちと一緒にとりませんか?たかが一人相撲、されど一人相撲。どこまで行っても一人相撲かもしれませんが、集まってみれば一人相撲以上の意味が生まれ出てくるかもしれません。しかしそれは、みんなで集まって「つながる」「力を合わせる」ことを呼びかけることとも少し違うのだろうと思います。それぞれが一人相撲をやりおおせるために、つかの間だけ、近くにいると感じることが何か意味を持つのではないかと思います。 written by: Aoi Nakamura

マレーシア サラワク州において、CHITOSE Carbon Capture Central(C4)の開所披露会を執り行いました
2023年5月10日、マレーシア サラワク州において、CHITOSE Carbon Capture Central(C4)の開所披露会をちとせグループ、Sarawak Biodiversity Centre、Sarawak Energy Berhad社と共同で執り行いました。 開所披露会には、在マレーシア日本国大使館 狩俣公使や経済産業省の皆様をはじめ、MATSURIにご参画いただいているパートナー企業様、金融機関様にお越しいただきました。マレーシアからもサラワク州のトップであるアバン・ジョハリ首相ほか、政府関係者等の来賓にお越しいただき、あわせて約250名の盛況な会となりました。 世界最大規模の藻類生産設備であるC4の開所は現地でも高い関心と注目を集め、テレビ番組でも報じられるほか、新聞各社の一面を飾りました。C4で生産された藻類がSAF(持続可能な航空燃料)等への応用に期待される点や、熱帯気候下における次なる藻類工業規模生産に向け、C4がマイルストーンになったとの見解も報じられています。※関連記事一覧はこちらから。 今後ちとせグループは藻類産業構築のためさらに活動を加速させ、サラワク州から世界を変えていきます。生き物たちの力と共に千年先の未来をもっと豊かにするという大きな目標に向かって挑戦し続けてまいります。 中央:ちとせグループ代表 藤田 右:アバン・ジョハリ首相

世界最大規模の藻類生産設備が開所式開催
2023年4月4日(火曜日)9時現地時間MRT/マレーシア:クチン 世界最大規模の「藻」生産設備5ヘクタールの開所式が催されました。 式には在マレーシアの日本大使をはじめNEDO理事、経済産業省の方々やMATSURIプロジェクトに参画している多くの企業の代表や役員の方々にご列席いただき開催する事ができました。ここから藻類の産業構築が本格始動しています。※本プロジェクトはNEDOから委託され藻から燃料にするための研究開発をしております。 晴天の中で迎えた開所式は、多くのメディアも参加し日本からはNHKも取材に来られ当日のNHKワールドやNHK WEB、おはよう日本などでも放映されております。開所宣言を発したCHITOSEグループ代表の藤田は、これまでの熱い想いや、ここから加速する藻類産業への想いを語られ参列者を感動させるスピーチとなり、きっと誰もが忘れられない日となったと思います。 ※完成に先立ち、ここから加速する藻類産業への熱い想いをスピーチをするCHITOSEグループ藤田代表 委託先であるNEDOからもリリースと情報発信がされました! https://twitter.com/nedo_info/status/1648589497527939074https://www.nedo.go.jp/ugoki/ZZ_101191.html?from=TW


未来の生活を支える”藻類”プラスチック
「1人 1日 約200g」 この数字は、日本人1人が1日に捨てるプラスチックの量である。プラスチックは石油を精製したエチレンやプロピレンなどからできているが、石油はこのまま使い続けると後50年ほどで枯渇するだろうと言われている。そのため、石油を原料としない「バイオプラスチック」が世界中で注目されている。 未来の私たちの生活を支えるバイオプラスチック バイオプラスチックの原料となるのは、トウモロコシ等の穀物資源、サトウキビ等から取り出される糖類が主体である。バイオプラスチックの一種であるポリ乳酸(PLA)は、デンプンの発酵によってできた乳酸が化学反応することで精製される。一方で、トウモロコシやサトウキビを原料とすることは、有限な農場において人々への食糧の供給を減らすことにも繋がるため、農作物以外の原料を探索する研究も進んでいる。例えば、微生物による発酵やセルロース(食物繊維)を用いたバイオプラスチックの生産が試みられているが、中には、藻類を原料とした生産に着手した企業もある。米企業ALGIXは、藻類からプラスチック素材を製造することに成功し、同社の製品は包装材、園芸用資材、電子機器等に活用されている。 藻類を用いたバイオプラスチックへの注目 このようにバイオプラスチックに注目が集まる中、藻類を原料としたユニークなプラスチック製品を発見したので紹介したい。「Ooho」と名付けられたその製品は、ロンドンの学生達がペットボトルの廃棄量削減を目指して発明した、”食べられる”ボトルだ。この製品は、植物や海藻(褐藻)から抽出した天然素材で作られていて、4~6週間で分解される。そのため、従来のペットボトルと異なり、このまま土や海に捨てたとしても自然に分解される。また、ジェル状の膜で水を覆ってあるため、清潔な水を持ち運ぶことができ、且つOohoを割って中の水を飲むこと、そのままOohoを食べることも可能である。さらに環境に優しいことに、同じ量のプラスチックを作るのに対し、Oohoの製造に必要な二酸化炭素量は5分の1であり、エネルギーも9分の1で済む。是非とも下の動画でこのユニークな製品をご覧いただきたい。 Oohoを製造しているSkipping Rocks Labのホームページによると、現時点では残念ながらイベント等での小規模な販売のみで、一般流通はしていないようだ。今後、量産化が進み、日本でも気軽に手に入る日が来ることを待ち遠しく思う。

バイオ燃料で注目が集まる、「藻」という生き物の魅力とは?
約30億年前に「光合成」という反応を世に生み出し、大気を生み、多くの生物を絶滅させ、そしてまた生み出してきた藻。技術の進歩がめまぐるしい現代においても、結局ヒトは、藻が作り上げてきた地球の生態系の中の一コマに過ぎず、その事実はこれからも変わることはありません。 生活が豊かになり、様々な価値観が生まれたことで何が正解かが見えにくい時代になっていますが、そんな現代だからこそ、この「藻」という原点となる生物と向き合うことに価値があるのではないかと思います。 このページでは藻という生き物の魅力を、歴史を紐解きながらお伝えしたいと思います。直近で話題になっているバイオ燃料(SAF/燃料)の基点となっている藻類とは・・・。 藻類とは何か? 「藻」はどんな生き物かご存知でしょうか? 身近なところで言えば、池や水田でよく見かける緑色の水を思い浮かべてください。あの緑の水の中には、肉眼では見えない多種多様な小さな緑色の生物が存在しています。水中にいる、体長1ミリにも満たない主に緑の生物、これを本サイトでは『藻類(※)』と呼んでいます。 商業利用されている代表的な藻類©2017 ちとせ研究所 ※生物学的に厳密に言えば、『藻類』のカテゴリーにはワカメや昆布などの海藻や、光合成もしない原生動物も入ってくるのですが、それらを指す際は別の言葉で言い分けて記載しています。本コラムでの『藻類』という単語は、特に断りがない限り『微細藻類』のことを指しています。 藻類と人類の関わり 藻類は、植物と同様に光合成をするため「小さな植物」と呼ばれることもありますが、実は進化の過程においては藻類こそが植物の祖先にあたります。 食料も化石燃料も、元を辿れば藻類から 藻類の起源は約35億年前までにさかのぼります。地球が誕生したのが46億年前で、現在の人類(ホモ・サピエンス)が誕生したのが20万年前と言われていますから、藻類の起源がいかに古いものかお分かりいただけるかと思います。 藻類は水中での進化を重ね、約5億年前に上陸。コケ植物、シダ植物を経て、今の我々の身の回りにある植物へと進化しました。この藻類から植物への進化の過程において、大量に繁茂したバイオマス(※)の残骸が地中に堆積し、長い年月をかけて石油、石炭、天然ガスなどの化石資源へと変換されたといわれています。つまり、現代人は藻類から植物への進化の蓄積を掘り起こし、エネルギー源や化成品原料として利用しながら生活しているわけです。 また、現代の植物は藻類の子孫になりますが、人類はその植物を農作物として直接的・間接的に食することによって日々生きています。 ©2017 ちとせ研究所 このように、藻類が存在したことによって今の人類の生活は成り立っており、藻類は人類の生活の基盤を支えている原点といっても過言ではありません。 ※バイオマスとは:動植物そのもの、または副産物などで資源として利用できるものの総称 藻類の産業ポテンシャル 人類と藻類の関わりについて理解していただいたところで、次は産業としての藻類の可能性について説明していきたいと思います。 藻類は様々な産業分野で利用可能 藻類は植物と同様に、『光合成』で増えます。光合成は文字通り、光のエネルギーを利用して二酸化炭素(CO2)と水から炭素化合物を合成する反応です。藻類は光合成により合成された炭素化合物の他に窒素、リン、カリウム、ミネラルといった無機物を取り込みながら複雑な化合物を合成していきます。 合成された種々の化合物は、藻類バイオマスとして各産業の原料として利用することができるため、藻類は様々な産業分野に展開することが可能になります。 ©2017 ちとせ研究所 藻類が合成できる化合物の利用用途は様々です。よく説明される例として利用用途の分野をバイオ業界では色に例えて以下のような表現がなされます。 ●『レッドバイオ』:医薬品原料や機能性素材をメインとした医薬・健康に関連する分野 ●『グリーンバイオ』:食品や飼料といった食に関連する分野 ●『ホワイトバイオ』:燃料や化成品原料といったエネルギー・化学に関連する分野...

宇宙藻類の時代到来・・
『宇宙兄弟』という漫画をご存知だろうか。宇宙を目指す兄弟の物語なのだが、綿密な取材を元に構成されているストーリーはもとより、ちょい役の登場人物一人一人にさえ人生を感じる丁寧な作り込みに圧倒される名作である。まだ読まれたことの無い方は機会があれば是非手にとってみていただきたい。 さて、そんな宇宙兄弟になぞらえて今回は『宇宙藻類』と題し、宇宙開発に関する藻類研究をいくつかご紹介したい。 そもそも宇宙と藻類に接点があるの?と思われる方も多いかと思うが、実はかなり古くから注目され、研究が行われている分野である。それというのも宇宙空間に長期間滞在するためには空気(酸素)と食料の自給が求められることになるが、その自給システムに藻類を利用しようというアイデアがあるためである。 藻類は宇宙飛行士が吐き出す二酸化炭素を吸収して酸素を供給することができ、増えた藻体は栄養食として食べることができる一石二鳥の材料となる。しかも植物と比べて栽培のためのスペースや資源が少なくすみ、育つまでの時間も短いという利点も持っているので、宇宙との相性が抜群に良いのだ。 このような宇宙空間での藻類利用を念頭に、2017年12月15日にESA(European Space Agency)のプロジェクトの一環として、生きたスピルリナが初めて宇宙ステーション(ISS)へと打ち上げられた。円筒形のフォトバイオリアクターに入れられたスピルリナは約1ヶ月間ISS内で培養されて、地球上と同じ速度で育って酸素も生成することが確認された。この1ヵ月間の培養期間に4回サンプリングが行われ、それと合わせて培地も4回入れ替えて試験が行われた模様だ。 無重力空間下における液体培養の場合は、液体中への二酸化炭素の供給および発生した酸素の除去が課題になるが、資料をみている限りは気体と液体をガス透過膜のようなもので仕切り、圧力をかけて強制的にガス交換を行う仕組みとなっているようだ。この辺の詳細情報は論文として公開された際にも確かめたい。 Green smoothies in space この記事をesa.intで読む > この試験の装置作成、宇宙ステーションでの実験計画、戻ってきてからのサンプル測定などの様子が資料としてまとめられて公表されていたので、興味のある方は以下の資料にも目を通してみていただければと思う。写真も多く、研究者達の楽しそうな雰囲気が伝わってくる。自分達が作った実験装置が宇宙船(SpaceX)で打ち上げられて、宇宙で実験されて、そのサンプルを分析できる、なんていうシチュエーションを与えられたら研究者だったら誰でも盛り上がるだろう。 また、2018年9月にはNASAでも宇宙ステーションにスピルリナを打ち上げ、微小重力下での増殖能を確認するための試験が行われている。こちらはNASAが企画する『皆のためISS科学(ISS Science for Everyone)』というプログラムの一環として、高校生のチームから応募されたアイデアを元にして行われたようだ。 SFみたいなテーマを高校生のチームが提案して、それを宇宙で実際に試験しちゃうなんて、私が高校生だった時には想像すらできなかった世界である。20年でここまで時代が変わるのであれば、20年後には月に人が住み、火星へ到着した人類がいてもおかしくはない。人が想像できる範囲というのは、いずれ実現できるものなのだなぁとシミジミ感じる。 NASA NASA – NanoRacks-Modesto Christian School-Comparing the Growth of Spirulina...
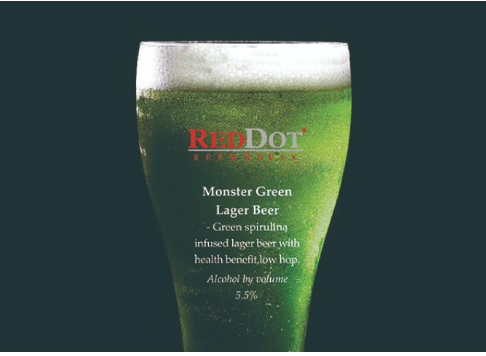
【スピルリナStyle】鮮やかなグリーンビール@シンガポール
MATSURIプロジェクト編集局としては見逃せない、シンガポール生まれの、スピルリナを使ったグリーンビールに関するコラムです。 これはReddot Brewhouseが製造している、RED DOT Monster Green Lager Beer (モンスターグリーン ラガービール)です。 なんといっても、この色鮮やかなスパークリンググリーンの色が特徴です。スピルリナビールの色は、青色のフィコシアニン、緑色のクロロフィル、橙色のβカロテンと抗酸化作用をもつ天然色素であり、健康に良い色です。※RED DOT Monster Green Lager Beerの栄養成分は分からないため、正確な事は言えません。 Reddot Brewhouseの方にお聞きしたところ、「着色料は使用していません。brewing(醸造)の段階でスピルリナを入れています。」とのことでした。 スピルリナはたんぱく質が70%と豊富で、ビタミン、ミネラルをバランスよく含むため、スピルリナを摂取することで得られるヒトへの良い機能は数多く報告されています。ビールの発酵に欠かせないビール酵母にとっても、スピルリナは良いエサになりそうです。 RED DOT Monster Green Lager Beerは、苦味は控え目、アルコールは5%です。スピルリナビールは麦芽比率からビールの定義をクリアしていますが、ビールの副原料の定義にスピルリナは認められていないので、正確には発泡酒の分類になります。 Reddot Brewhouseはシンガポール植物園(Singapore Botanic Garden)近く, Dempsey hillにある醸造所です。7種類の自家製クラフトビールとお食事が楽しめる、緑に囲まれたビアレストランが併設されています。 REDDOT BREWHOUSE Dempsey Road...

一生に一度は見てみたい! -藻が作り出す絶景7選-
昨今、藻といえばタンパク質等の栄養面や燃料利用に注目が集まりがちだが、藻の持つ色素も同様に重要な特性だ。昨今、藻といえばタンパク質等の栄養面や燃料利用に注目が集まりがちだが、藻の持つ色素も同様に重要な特性だ。 1.クリミア半島の赤く染まる海(ウクライナ) まず紹介したいのは、ジブリ作品「風の谷のナウシカ」に登場する「腐海」のモデルとなった、ウクライナのアゾフ海の西岸に広がる干潟だ。これは、微細藻類ドナリエラ(Dunaliella)が増殖することによって、海が赤く染まって見えるのだそうだ。 2.ナクル湖のフラミンゴ (ケニア) Kenya Connection: Lake Nakuru, Flamingos, A New Friend – TravelUpdate Shadrack and I made an instant Kenya connection after I brazenly asked if I could...

藻は世界のサンゴを救う?
藻は世界のサンゴを救う? サンゴ礁は、最も多様な海洋生息地と言われており、実に様々な生き物が住んでいる。その生き物を餌にして育つ魚を、あなたは昨日食べたかもしれない。また、美しいサンゴ礁が広がる海で、シュノーケルやダイビングなど楽しんだ経験がある方もいることだろう。サンゴ礁は、漁業や観光業など世界で年間300億ドルの経済効果をもたらし、5億人の生活に直接関与しているのだ。 しかし、サンゴ礁の保全対策を直ちに行わなければ、全世界のサンゴ礁の99%が今世紀中に絶滅する、と気候変動影響モデルの研究は予測している。 サンゴは褐虫藻に頼って生きている 動物であるサンゴは、褐虫藻と呼ばれる単細胞藻類(Symbiodinium属の渦鞭毛藻)と共生関係を結ぶことで生存を維持している。褐虫藻はサンゴの成長やサンゴ礁の形成に必要な物質(酸素や栄養分などの光合成産物)をサンゴへ供給し、その代わりに光合成に必要な窒素、リンなどをサンゴからもらっている。 褐虫藻から栄養をもらう以外にも、触手で動物プランクトンを捕食するそうだが、そこから得られる栄養だけでは健全な生育が難しいと言われている。 褐虫藻と離れ離れになったサンゴの結末 近年、温暖化に伴う水温上昇により褐虫藻の光合成系が損傷され、またサンゴから放出されることでサンゴ骨格が透けて見える状態になるという、サンゴの白化現象が世界中の海に広がっている。栄養供給を褐虫藻に依存しているサンゴは、長時間にわたり褐虫藻との共生関係を失うと最終的に死んでしまう。 褐虫藻が共生しているサンゴ(左)と褐虫藻がいなくなり白化したサンゴ(右)引用元:https://oceanservice.noaa.gov/education/kits/corals/media/supp_coral02d.html サンゴの白化を防ぐには、ストレス耐性をもつ褐虫藻が鍵? 褐虫藻の種間遺伝的多様性がサンゴの白化耐性に大きく関与することが知られている。オーストラリアのニュー・サウス・ウェールズ大学(University of New South Wales)に所属するレイチェル・レビン(Rachel Levin)博士の研究チームは、褐虫藻のシークエンシングデータを用いて、ストレス耐性の増加を図る褐虫藻の遺伝子組換え戦略を立てた。その研究結果は2017年6月30日、ジャーナルFront. Microbiol.に公開された。https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5492045/ 「褐虫藻についてはほとんど知られていないため、サンゴ礁保全行動を改善するための情報が得られない。」「褐虫藻は生物学的に非常に独特であり、今まで確立された遺伝工学の手法は適用しない。必要とされる研究を進展するため、我々は褐虫藻の新たな遺伝子解析を行い、その障害(遺伝子組み換え技術の確立)を克服することを目指していた。」とレイチェル・レビン氏が褐虫藻研究の困難性について説明している。 研究者らは、サンゴの白化を防ぐ可能性のある遺伝子(抗酸化遺伝子など)を特定した。「水温が徐々に上昇している海洋環境下でサンゴとの共生が維持できるように、遺伝子工学手法により強化された褐虫藻は、世界的なサンゴの白化現象を減らす可能性を示唆する」と彼らは語った。 しかし、遺伝子工学手法により開発した褐虫藻を環境中へ放出することに関しては、「フィールドベースの試験が始まる前に、潜在的なマイナスのリスクについて広く厳密に研究することが必ず必要だ」と強調した。 また、最近、米・ペンシルベニア州立大学(The Pennsylvania State University)の研究者たちはストレス耐性をもつ新種の褐虫藻(Symbiodinium glynnii)を同定した。この種類の褐虫藻と共生するサンゴが頑強であり、他の褐虫藻種と共生するサンゴにとって酷な環境にも耐えられることが分かった。 どうやら、ストレスに強い褐虫藻が、サンゴを救う鍵となっていくであろう。 参考資料:A super-algae to...

宇宙開発とスピルリナ -NASAもJAXAも注目の藻類食糧-
栄養価とタンパク質含量の多さから、宇宙開発においても食用藻類スピルリナの有用性が注目されています。米国航空宇宙局(NASA)や欧州宇宙機関(ESA)では研究が進んでいます。 日本でもスピルリナの宇宙に向けた研究が進んでいます。宇宙航空研究開発機構(JAXA)と、ちとせグループとの宇宙開発研究について、ここでご紹介いたします。 JAXAとのスピルリナ宇宙開発研究 ちとせグループでは、2018年から2019年にわたりJAXAらと一緒に「食用藻類スピルリナを用いた省資源かつコンパクトなタンパク質生産システムの開発」を行いました(ちとせグループの参画企業;(株)ちとせ研究所・(株)タベルモ)。先の研究開発を受けて、2020年にはJAXAとシダックスグループと「月面農場における食用藻類スピルリナの循環型培養システムの改良と生スピルリナ入りメニュー開発」の共同研究を行っています(ちとせグループの参画企業;(株)タベルモ)。 2019年までの研究では、宇宙利用を想定したスピルリナ生産システムの開発に成功しました。2020年はJAXAの協力を受け、実用化に向けさらなるスピルリナ生産システムの改良を行う予定です。さらに、長期滞在する宇宙飛行士が月面農場でスピルリナを培養することを想定し、シダックスグループと共同で栄養価の高い生スピルリナを取り入れた月面滞在食メニューの開発を行っています。 また、2021年度は『国際宇宙ステーション(ISS)の「きぼう」日本実験棟の船内環境を利用する実験テーマ(フィジビリティスタディテーマ)』に採択されました。テーマ名「効率的なタンパク質生産とCO2処理を目指したスピルリナの担持体培養実証」を行います。ここでは、宇宙飛行士の健康に重要なISSで育てたスピルリナの生物学的安定性の解析と、スピルリナ培養によるISS内の空気再生可能とする先進的な培養システムの構築を目的に、地上での実験を開始します(ちとせグループの参画企業;(株)ちとせ研究所・(株)タベルモ)。 宇宙で藻類、スピルリナが食べられる日が着実に近づいているのを感じます。 宇宙開発に”生”スピルリナを使用しなければいけない理由 現在、地上で流通している一般的なスピルリナは、加熱滅菌をすることで長期保存を可能としているため乾燥粉末になっています。 しかし宇宙環境では、培養して、すぐに食べる(食材として利用する)ことが想定されるので、非加熱の生スピルリナを使ったメニューを開発する必要がでてきます。生スピルリナは加熱乾燥スピルリナに比べ味や臭いがなく、熱で壊れやすい栄養成分も損なわれずに摂取できるなど、食品として加熱乾燥スピルリナとは性質が大きく異なります。 宇宙開発の研究に必要な「生スピルリナ」を生産、販売している企業は世界でも僅かです。ちとせグループの(株)タベルモは、国内唯一の生スピルリナメーカーであり、また世界的にも唯一大規模に生スピルリナを製品化できているメーカーです。 ちとせグループは、本研究を通して、生スピルリナの認知拡大と研究を推し進め、地球環境にも宇宙環境にも良いタンパク質源を提供していきたいと考えております。
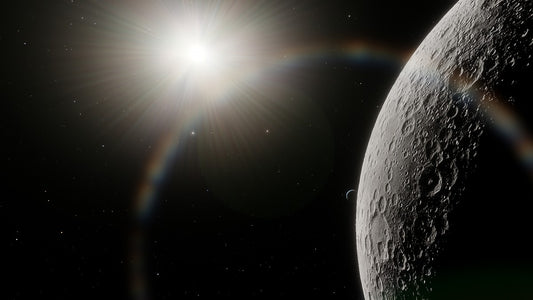
宇宙開発とスピルリナ -NASAもJAXAも注目の藻類食糧-
栄養価とタンパク質含量の多さから、宇宙開発においても食用藻類スピルリナの有用性が注目されています。米国航空宇宙局(NASA)や欧州宇宙機関(ESA)では研究が進んでいます。 日本でもスピルリナの宇宙に向けた研究が進んでいます。宇宙航空研究開発機構(JAXA)と、Modiaを運営しているちとせグループとの宇宙開発研究について、ここでご紹介いたします。 JAXAとのスピルリナ宇宙開発研究 ちとせグループでは、2018年から2019年にわたりJAXAらと一緒に「食用藻類スピルリナを用いた省資源かつコンパクトなタンパク質生産システムの開発」を行いました(ちとせグループの参画企業;(株)ちとせ研究所・(株)タベルモ)。 先の研究開発を受けて、2020年にはJAXAとシダックスグループと「月面農場における食用藻類スピルリナの循環型培養システムの改良と生スピルリナ入りメニュー開発」の共同研究を行っています(ちとせグループの参画企業;(株)タベルモ)。 2019年までの研究では、宇宙利用を想定したスピルリナ生産システムの開発に成功しました。2020年はJAXAの協力を受け、実用化に向けさらなるスピルリナ生産システムの改良を行う予定です。さらに、長期滞在する宇宙飛行士が月面農場でスピルリナを培養することを想定し、シダックスグループと共同で栄養価の高い生スピルリナを取り入れた月面滞在食メニューの開発を行っています。 また、2021年度は『国際宇宙ステーション(ISS)の「きぼう」日本実験棟の船内環境を利用する実験テーマ(フィジビリティスタディテーマ)』に採択されました。テーマ名「効率的なタンパク質生産とCO2処理を目指したスピルリナの担持体培養実証」を行います。ここでは、宇宙飛行士の健康に重要なISSで育てたスピルリナの生物学的安定性の解析と、スピルリナ培養によるISS内の空気再生可能とする先進的な培養システムの構築を目的に、地上での実験を開始します(ちとせグループの参画企業;(株)ちとせ研究所・(株)タベルモ)。 宇宙で藻類、スピルリナが食べられる日が着実に近づいているのを感じます。 宇宙開発に”生”スピルリナを使用しなければいけない理由 現在、地上で流通している一般的なスピルリナは、加熱滅菌をすることで長期保存を可能としているため乾燥粉末になっています。 しかし宇宙環境では、培養して、すぐに食べる(食材として利用する)ことが想定されるので、非加熱の生スピルリナを使ったメニューを開発する必要がでてきます。生スピルリナは加熱乾燥スピルリナに比べ味や臭いがなく、熱で壊れやすい栄養成分も損なわれずに摂取できるなど、食品として加熱乾燥スピルリナとは性質が大きく異なります。 宇宙開発の研究に必要な「生スピルリナ」を生産、販売している企業は世界でも僅かです。ちとせグループの(株)タベルモは、国内唯一の生スピルリナメーカーであり、また世界的にも唯一大規模に生スピルリナを製品化できているメーカーです。 ちとせグループは、本研究を通して、生スピルリナの認知拡大と研究を推し進め、地球環境にも宇宙環境にも良いタンパク質源を提供していきたいと考えております。

休耕田は藻類燃料生産の救世主になるのか?-農地の潜在能力と課題-
農閑期の農地の活用、休耕田の活用は各地で行われています。Modiaにも、休耕期間中の農地で藻類生産をすることへのご質問をいただきました。 昨今の温暖化問題の深刻化を懸念しており、ネットを読んでいて藻ディアに行きつきました。 まずは身近なところか、藻類のエネルギー利用を普及できないか、と考え、質問させていただきたく、メールいたします。 藻類からオイルを抽出するステップを踏まずに、乾燥させただけの段階で燃料として使用することは、現実的でしょうか?世の中には、自家発電の規模では、薪ストーブで発電するケースもあるようです。 【イメージ】 ・農家が休耕期間中に水田で藻を育成 ・農閑期に納屋等で藻を乾燥させる ・小規模な発電装置で自家発電して利用 今回は、回答を皆さまにもご紹介します。 藻類燃料の特徴 薪と藻類(微細藻類)のと燃焼用材料としての特徴を比較をします。どちらもCO2を吸収して蓄えるので、これを燃やせばカーボンニュートラルなエネルギーになります。 薪は水分量が10%で、得られるエネルギーは4780kcal/kgです。また燃焼後の灰分は1%と非常に少ないです。薪はもともと乾燥していて、主成分がセルロースをはじめとする炭水化物が約99%なので、燃焼に良い材料です。平均樹齢40年の直径20cmの杉1本は約400kgなので、木を一本倒せば400㎏の薪が入手できることになります。 一方で水中で生育する藻類は収穫時に水分量は90%以上です。水分含量10%まで乾燥させた藻類のエネルギーは3000-3500kcal/kg、燃焼後の灰分は5-20%となります。一般的な藻類は炭水化物が10%前後、タンパク質が50%以上と高く、燃焼するとエネルギーは得られますが、異臭がする、灰分も多くなることが予想されます。そこで、藻類の燃料利用には、エネルギー効率の高い脂質の割合が高い藻類種を選択し、藻体から脂質を抽出する事が必要です。また、乾燥した藻類を手軽に入手することは非常に難しいです。 田圃の藻類生産の潜在能力と問題点 文献を基に、5月の水田(富栄養の水質、イネが成長していないので水面に光が届く期間)で微細藻類のバイオマス量を計算したところ、乾燥重量2g /m²/dayでした。一般的な水田1区画50a(5000m²)で取れる藻類は乾燥重量10kg/dayになります。水田の藻類バイオマス量の潜在能力は軽視できない大きさになることが予想されます。 しかし、現実問題として、水田からの藻類の回収手段がありません。基本的に藻類は何かしらに付着して増殖、もしくは土底付近で増殖をするため、土との分離は今の技術的に不可能だと考えられます。また、乾燥手段も問題です。簡単な微細藻類回収手段が確立されたとしても、先の例なら50aの水田の1回の収穫時には水分を含んでいるので100kg以上になります。100㎏の水分を含んだ藻類を自然乾燥させるには薄く伸ばす必要がありますが、厚さ0.5cmと分厚くても20m²の広げる面積が必要になります。乾燥器を使う場合、エネルギーをかけてエネルギー源を確保するという矛盾が生じかねません。 休耕期間中の田圃の藻類生産 これを踏まえて、農閑期に藻類を培養して納屋で乾燥させる案が現実的なのかというご質問にお答えします。 まず水田の休耕期間は冬です。この気温が低い期間は、藻類の増殖は見込めないです。実際に冬にたまたま水がはってあった水田を観察したことはありますが、そこの土ばかりが目立ち、顕微鏡でみても藻類はほとんどいない状況でした。仮に、低温下で高増殖する藻類がいたとしても、前述の通り水田から藻類だけを回収するのは非常に困難です。技術的に回収方法が確立しても、乾燥方法も前述の通り問題になってくると思います。したがって、日本において、また技術的に現在のところは現実的ではないと考えます。 藻類技術は成長期 藻類技術は農業や林業に比べると研究の歴史は浅く発展途上にあり、培養生産、収穫、乾燥、抽出など規模も含めて既存の手法には技術的に、価格的に敵わないです。しかし、樹齢40年の木1本のエネルギー量は、培養面積50aの水田だけで約40日培養した藻類のエネルギー量と同じです。藻類専用の培養装置を使えばもっとエネルギー生産量は効率よくなります。この藻類エネルギー量を活用できる技術を開発することが、ちとせグループや世界中の研究者・技術者の役割だと思います。 温暖化の原因の一つが化石燃料によるCO2大量放出と言われていますが、エネルギー枯渇の問題の抜本的な解決には、エネルギー生産量を増やすことが望まれます。藻類をエネルギーとして活用できるまでには藻類の技術開発とともに、藻類の魅力を伝え(代替エネルギーの他、代替タンパク質としても注目を集めています)、藻類の認知度を向上させる事が欠かせません。 藻類の活用を広めていくためにも、現在藻類産業の中心である藻類食品に目を留めていただき、藻類技術開発を応援していただければ幸いです(ちとせグループの宣伝になってしまい恐縮ですが、グループ会社のタベルモでは、タンパク質危機を解決を目標に、藻類スピルリナの大量培養技術開発、販売を行っております。)。 <参考文献>The Asian Biomass Handbook(The Japan...
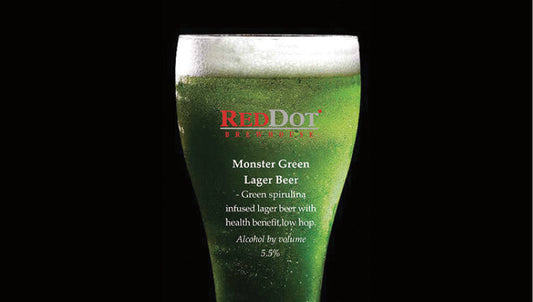
【スピルリナStyle】鮮やかなグリーンビール@シンガポール
世界各地で藻類フードが注目されています。その中でも栄養価が群を抜いて高く、スーパーフードの王様ともいわれる「スピルリナ」の人気は絶大です。そこでModiaでは、スピルリナ商品のトレンドを【スピルリナStyle】としてどんどんご紹介していきたいと思います! 日本もだんだん暑くなってきましたね。ビールが美味しい季節になってきました。第2回目は、シンガポール生まれの、スピルリナを使ったグリーンビールです。 これはReddot Brewhouseが製造している、RED DOT Monster Green Lager Beer (モンスターグリーン ラガービール)です。 なんといっても、この色鮮やかなスパークリンググリーンの色が特徴です。スピルリナビールの色は、青色のフィコシアニン、緑色のクロロフィル、橙色のβカロテンと抗酸化作用をもつ天然色素であり、健康に良い色です。※RED DOT Monster Green Lager Beerの栄養成分は分からないため、正確な事は言えません。 Reddot Brewhouseの方にお聞きしたところ、「着色料は使用していません。brewing(醸造)の段階でスピルリナを入れています。」とのことでした。 スピルリナはたんぱく質が70%と豊富で、ビタミン、ミネラルをバランスよく含むため、スピルリナを摂取することで得られるヒトへの良い機能は数多く報告されています。ビールの発酵に欠かせないビール酵母にとっても、スピルリナは良いエサになりそうです。 RED DOT Monster Green Lager Beerは、苦味は控え目、アルコールは5%です。スピルリナビールは麦芽比率からビールの定義をクリアしていますが、ビールの副原料の定義にスピルリナは認められていないので、正確には発泡酒の分類になります。 Reddot Brewhouseはシンガポール植物園(Singapore Botanic Garden)近く, Dempsey hillにある醸造所です。7種類の自家製クラフトビールとお食事が楽しめる、緑に囲まれたビアレストランが併設されています。 Dempsey Road "...
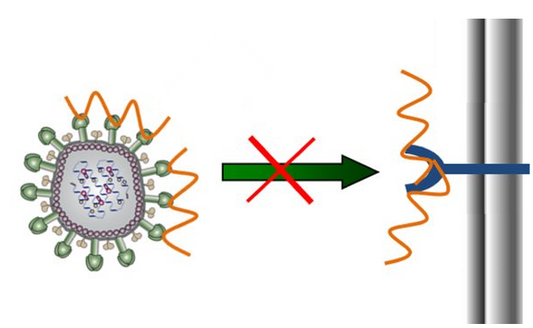
抗ウイルスが報告されている藻類由来物質スピルラン-スピルリナの効能-
新型コロナウイルスの流行から、ウイルスとの共存をしていく「新しい生活様式」が求められています。ウイルスの感染予防を体の内側から実行することも必要になってくるでしょう。スピルリナといった抗ウイルス活性をもつ食材を常日頃から摂りいれることは私たちの免疫力向上に大いに貢献します。 今回は、スピルリナ特有のラムナン硫酸「スピルラン」の性質と抗ウイルスの仕組みについて説明します。 スピルリナ特有のラムナン硫酸「スピルラン」 スピルリナから抽出された抗ウイルス物質「スピルラン(Spirulan)」は、ラムノース(Rhamnose)が主で、他にアコフリオース(Acofriose, 3-O-メチルラムノース)、ウロン酸(Uronic acid, 具体的にはグルクロン酸とガラクツロン酸)が結合している多糖が骨格であり、ラムノース部分には硫酸基(-SO3-)が結合しているラムラン硫酸と言われる硫酸化多糖の一種です。 スピルランは親水性の硫酸基、疎水性のメチル基が存在することから、両親媒的性質をもっていると推測され、この特徴的構造が生物活性の発現に関与していると考えられます。今までに、抗ウィルス・抗真菌・抗菌・コラーゲン形成・細胞再生・紫外線防御といった特性を持つことが報告されています。 スピルランの構造(林2008より改変) スピルランの抗ウイルス活性メカニズム 今回取り上げるスピルランの抗ウイルス活性の理由として、硫酸化多糖類が負の電荷をもつ性質が関係していると考えられています。 ウイルスの宿主細胞への感染は、ポリアニオン(全体として負(マイナス)電荷をもつ物質)のウイルス表面タンパク質が、細胞表面の正(プラス)電荷の糖タンパク質(スパイクタンパク質やヘマグルチニンタンパク質)に吸着し、ウイルスが侵入して始まります。感染メカニズムについて詳しくはこちらをご覧ください。 負の電荷をもつ硫酸化多糖は、細胞表面の正の電荷をもつ糖タンパク質に対してマスキングの役割を果たし、ウイルスの宿主細胞への吸着・侵入を防ぐ役割があると言われています。また、正の電荷をもつウイルス表面タンパク質に負の電荷をもつ硫酸化多糖が直接結合して宿主細胞への感染を阻害する抗ウイルス活性のメカニズムも報告されています。 硫酸化多糖の抗ウイルス活性メカニズムA.ウイルスの侵入メカニズムB.硫酸化多糖による抗ウイルス活性メカニズム(Mathieu et al. 2015より改変) スピルランの抗ウイルス活性の研究例 スピルランの抗ウイルス活性については、ヘルペスウイルス(HSV)を対象に研究がなされています。HSVは医学的にも重要ですが、様々な解析手法が確立されており、最先端かつ多面的な研究が可能であることからウイルス学において多く研究されています。ウイルスにも分類がありますが、HSVの構造はコロナウイルス、インフルエンザウイルスと同じくカプシドがエンベロープに包まれたエンベロープウイルスの分類に入り特徴が似ています。 エンベロープウイルスの構造(「【バイオのプロが解説】ウイルスとは?-似た症状でも治療方法が違うウイルス、細菌、真菌の違い-」参照) 1)エンベロープウイルスに対して抗ウイルス活性が示されたスピルランはヘルペスウイルス(HSV)、サイトメガロウイルス(HCMV)、はしかウイルス(Measelesvirus)、ムンプスウイルス(Mumsvirus)、インフルエンザウイルス(IFV)、HIVウイルスの6種類のエンベロープウイルスに対して、ウイルス増殖抑制作用が示された。一方、ポリオウイルス(Poliovirus)、コクサッキーウイルス(Coxackievirus)の2種のノンエンベロープウイルスにはウイルス増殖抑制作用は示されなかった。 2)宿主細胞への吸着・侵入時に抗ウイルス活性がみられたスピルランはHSV感染前から培養液に存在した場合の方が、抗ウイルス活性が強かった。このことから、スピルランの標的段階は宿主細胞への吸着・侵入段階と推測された。 3)感染後も抗ウイルス活性がみられたHSV感染前から培養液に存在した場合よりは弱いが、感染2時間後にスピルランを培養液に添加した場合でも抗ウイルス活性がみられた。また、スピルランは宿主細胞内に選択的に取り込まれ、抗ウイルス活性を保持していた。このことから、スピルランはウイルス感染後のウイルス複製段階も標的にすると推測された。 4)糖鎖分子の立体構造が活性発現に重要な役割をするスピルランから金属イオンを除去した場合や、脱硫酸化したところ、HSVに対する抗ウイルス活性は失われた。このことから、金属イオンと硫酸基との結合により形成される糖鎖分子の立体構造が活性発現に重要な役割を果たしていると示唆された。 5)スピルランは経口投与でも抗ウイルス活性を示したマウスにHSVを感染させ、スピルランを経口投与したところ、用量依存的に病変の進行が抑制された。 今回はウイルスが体内に侵入するのを防いでくれる「抗ウイルス活性」についてのスピルリナの機能を紹介しました。海外では、スピルランに着目した商品も発売されています。 Modia[藻ディア] 藻の口紅 https://modia.chitose-bio.com/articles/10...
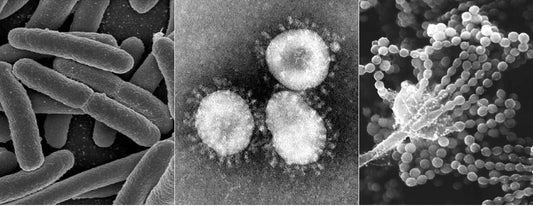
【バイオのプロが解説】ウイルスとは?-似た症状でも治療方法が違うウイルス、細菌、真菌の違い-
Modia(藻ディア)を運営している私たち「ちとせグループ」は、”ちとせ研究所”を中核とするバイオベンチャー企業群です。生き物(主に微生物、藻類、動物細胞)の研究開発から事業の展開までを通貫して行えるバイオのプロフェッショナル集団です。 ちとせグループが社会に貢献できる1つとして、専門的な正しい知識を、わかりやすい言葉に変えて、みなさまにお伝えすることだと考えています。 Modia(藻ディア)の場をお借りして、みなさまに知ってもらいたい知識をお届けします! ウイルスとは?-新型コロナウイルスも、生き物ではないから治療が難しい- 先のModiaの記事で、ウイルスとは何かを、生物学的な視点からお話をしました。結論は、ウイルスは生物ではないということでした。 Modia[藻ディア] 【バイオのプロが解説】ウイルスとは?-生き物との違いとコロナウイルスの増殖機構- https://modia.chitose-bio.com/articles/virus_01 Modia(藻ディア)を運営している私たち「ちとせグループ」は、”ちとせ研究所”を中核とするバイオベンチャー企業群です。生き物(主に微生物、藻類、動物細胞)の研究開発から事業の展開までを通貫して行えるバイオのプロフェッショナル集団です。ちとせグループが社会に貢献できる1つとして、専門的な正しい知識を、わかりやすい言葉に変えて、みなさまにお伝えすることだと考えています。Modia(藻ディア)の場をお借りして、みなさまに知ってもらいたい知識をお届けします!ウイルスって何でしょうか?今回の記事で1番知ってもらい... 今回の記事で1番知ってもらいたいことは、ウイルスは生き物ではないため、増殖を止めることが難しいということです。 病気の原因として、みなさまが混同している可能性があるのは、「ウイルス」「細菌」「真菌」だと思います。人に感染して、増殖して、似た症状が表れるため、この3種類はどれも同じだと思っている方が多いように感じられます。 比較のため、今回は「ウイルス」「細菌」「真菌」の性質や構造、治療の違いと、病原体や病名の種類をまとめました。 ウイルスは生物ではないので、細菌や真菌との治療方法とは根本的に違うことがわかります。細菌と真菌は分裂、増殖するときに、細胞の構成成分(細胞膜、細胞壁、タンパク質など)を合成します。治療薬には、細菌や真菌が細胞構成成分を合成する過程を阻止できる薬が使われます。ヒトも同じ生き物ですが、細菌や真菌にはあって、ヒトにはない細胞構成成分を治療薬はターゲットにしているので、治療薬はヒトには効きません。一方で、ウイルスの増殖は宿主の細胞成分合成機構を利用します。例えば、ヒトに感染するウイルスの場合、宿主はヒトです。ウイルスの増殖を阻害しようとすると、宿主の正常な細胞の増殖も阻されてしまいます。したがって、新型コロナウイルスはもちろん、大多数のウイルスの感染による病状に対しては基本的に対処療法をすることしかできません。ウイルスの予防的観点からの有効な治療薬は、個々のウイルスに対してワクチンを開発し接種することです。ワクチンを接種すると、そのウイルスに対しての免疫力がつきます。自分自身がもつ免疫の力でウイルスを排除するので、日常生活の中でウイルスに対処できるよう免疫力を高めておかなければいけません。 スピルリナをはじめとする藻類に免疫力を高める効果があることは昔から知られています。また、スピルリナでワクチンを作る研究も進んでいます。詳しくは以下の記事をご覧ください。 Modia[藻ディア] 食品分野における藻類の利用 -栄養組成から免疫効果まで- https://modia.chitose-bio.com/articles/algae_and_food 今年に入って特定の藻類に注目した記事を書く機会が多かったのですが(Modiaが発行しているニュースレターでも、毎月一種の藻類を特集しています!)、今回は対象を広げて、藻類全体が食品分野で注目される理由と直面している課題についてまとめていきます。そもそも藻類は、光合成によって光エネルギーを取り込み、それを細胞が利用できる形に変換してエネルギーを蓄えます。窒素、リン、カリウム、ミネラルといった無機物を取り込み、タンパク質等を生成しながら成長し、分裂して、増殖していきます。取り込み過ぎたエネルギーは脂質... Modia[藻ディア] スピルリナの持つ7つの効能 https://modia.chitose-bio.com/articles/efficacy_of_spirulina 2010年から現在に至るまで、私の所属する(株)ちとせ研究所ではスピルリナの研究開発を継続し、国内唯一の生食タイプのスピルリナを生産してきた。私自身も静岡県の掛川市でスピルリナの培養に携わり、生スピルリナの生産に向けて注力してきた。今では、掛川でのスピルリナ生産が学生時代のバドミントンに次いで私の第二の青春になっている。真夏の強い紫外線を物ともせず、たくましく増え続けるスピルリナ。その強さのもととなるのは、高い抗酸化力や生理活性物質などスピルリナ自身が産生する有効成分である、と私は考えている。これ... Modia[藻ディア] スピルリナワクチンの可能性 https://modia.chitose-bio.com/articles/63 大人も子供も関係なく、予防接種と聞くと鋭い注射針を思い出し、嫌がる人も多いのではないだろうか。園芸学科出身の私は、バナナなどを食べるだけで免疫を獲得できるようになることを大学時代からずっと期待してきた。こうした夢のような期待に応えてくれるかもしれない研究が、健康食品でお馴染みの藻類「スピルリナ」で行われていることをご存知だろうか?ワクチンによる予防接種ワクチンは感染症の原因となる細菌やウイルスを弱毒化させたもの、あるいは病原性を無毒化させ抗原性だけを残した特殊な薬液である。この薬液に含まれる... ウイルス・細菌・真菌の比較 ウイルス 細菌(真正細菌)...
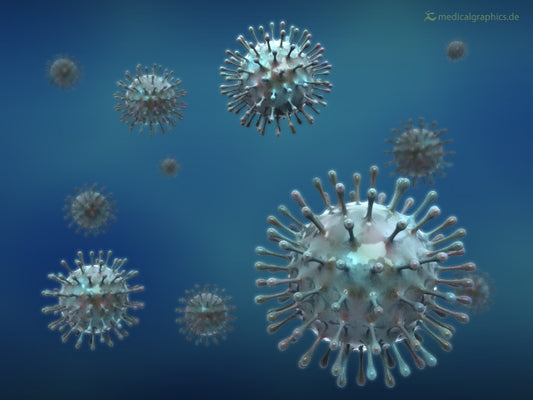
【バイオのプロが解説】ウイルスとは?-生き物との違いとコロナウイルスの増殖機構-
Modia(藻ディア)を運営している私たち「ちとせグループ」は、”ちとせ研究所”を中核とするバイオベンチャー企業群です。生き物(主に微生物、藻類、動物細胞)の研究開発から事業の展開までを通貫して行えるバイオのプロフェッショナル集団です。 ちとせグループが社会に貢献できる1つとして、専門的な正しい知識を、わかりやすい言葉に変えて、みなさまにお伝えすることだと考えています。 Modia(藻ディア)の場をお借りして、みなさまに知ってもらいたい知識をお届けします! ウイルスって何でしょうか? 今回の記事で1番知ってもらいたいことは、「ウイルスは生き物ではない」ことです。そもそも、生き物とは何なのか?この問いは、生物学者の究極のテーマともいえるくらい大変定義が難しい問題です。今回は生き物とは何かをみることで、ウイルスとは何かをご説明します。 生き物とは 「生き物」の共通点はいくつも見出せます。そこから選りすぐって「生き物」の定義を強いてするなら、「細胞を基本構造として、自己複製ができるもの」と言われています。 「細胞を基本構造とする」というのは、以下の特徴を共通点にもつ「細胞」が最小単位となっているということです。・リン脂質二重層の細胞膜で囲まれている。・核酸(DNA・RNA)を有する。・核酸の遺伝情報から自らリボソームというタンパク質合成装置を作り、タンパク質を合成できる。・そのタンパク質や取り込んだ物質を反応させて自分に必要な物質を生み出す様々な反応系(=代謝系)をもつ。 「自己複製ができる」というのは、自分自身で内容物を増やし(細胞小器官の複製)、切り分ける(分裂)一連の仕組みをもっているということです。 ウイルスとは-ウイルスあっての生き物の定義- ウイルスとは、「核酸(RNAまたはDNA)それを包むタンパク質の外被からなる粒子。(細胞の分子生物学より)」とされます。これだとよくわからないと思いますが、生き物の定義を通してウイルスをみると、わかりやすくなります。 実は、生き物を定義するとき、反例として挙げられる代表例がウイルスです。ウイルスは増殖するので一見生き物のように見えますが、「自己複製ができない」ため生き物とはみなされません。ウイルスを通して、初めて生き物の定義が確実になるのです。生き物とウイルスの関係は、まるでニワトリが先かタマゴが先か問題のようにもみえます。 ウイルスの特徴の「自己複製できない」ということは、どういうことでしょうか?ウイルスの増殖方法は、細胞に感染して細胞内に入り込み、細胞のエネルギーを使い、細胞の代謝系を利用してウイルスの構成成分を複製します。ウイルスは細胞の感染なしには何もできません。これが「自己複製できない」ということです。ウイルスの増殖メカニズムは、次項で詳しく説明します。 細胞とウイルスでは基本構造が違うので、この2つの比較だけなら基本構造だけで明瞭な区別はできます。しかし、細菌性や真菌性といった生き物が原因となる病気にかかった時と、ウイルス性の病気にかかった時とでは、治療法が基本的に異なります。その理由が「自己複製できるか」「自己複製できない」に関わってきます。ウイルス、細菌、真菌の病気と治療の観点からの比較について、詳しくはこちらをご覧ください。 Modia[藻ディア] 【バイオのプロが解説】ウイルスとは?-似た症状でも治療方法が違うウイルス、細菌... https://modia.chitose-bio.com/articles/virus_02 Modia(藻ディア)を運営している私たち「ちとせグループ」は、”ちとせ研究所”を中核とするバイオベンチャー企業群です。生き物(主に微生物、藻類、動物細胞)の研究開発から事業の展開までを通貫して行えるバイオのプロフェッショナル集団です。ちとせグループが社会に貢献できる1つとして、専門的な正しい知識を、わかりやすい言葉に変えて、みなさまにお伝えすることだと考えています。Modia(藻ディア)の場をお借りして、みなさまに知ってもらいたい知識をお届けします!ウイルスとは?-新型コロナウイルスも、生き物ではないか... ウイルスの定義に自己複製できないことは書かれませんが、「ウイルスは生き物ではない」=自己増殖できないということをわかった上で、細菌性、真菌性の似た症状の病気と根本的に違うことを皆様には理解してもらいたいと思います。 ウイルスの増殖メカニズム-宿主細胞に依存する複製過程- 細菌や真菌の増殖過程は、宿主細胞(感染される側の細胞)に取り込まれて、もしくは宿主細胞の表面で、自分の力で細胞構成成分を合成し、2分裂で増殖します。そのため、徐々に細菌や真菌の数は増えていきます。 ウイルスは生き物ではないですが増殖します。これは、宿主細胞の力を借りて、宿主細胞にウイルスの合成してもらうのです。ウイルスは生物にくらべて非常に簡単な構造をしているので、合成時間も短いです。生物のように分裂で増殖するのではなく、ウイルス構成成分を作って、パッケージングすれば完成です。1個のウイルスが宿主細胞に感染すると1,000個もの子ウイルスが生産されます。増殖が早いインフルエンザウイルスでは、24時間で1万個に達すると言われています。ウイルスの増殖機構を、風邪の原因の一つでもあるコロナウイルスを例に示します。 ※肺炎を引き起こす新型コロナウイルスは、主に咽頭や肺の細胞を宿主細胞にして、図で示す複製過程で増殖すると考えられます。※新型コロナウイルスの宿主細胞側の受容体はACE2(アンジオテンシン転換酵素2;angiotensin-converting enzyme 2)であることがわかっています。 ウイルス表面のスパイクタンパク質(S)とヘマグルチニンタンパク質(HE)が宿主細胞のN-アセチルノイラミン酸と受容体をそれぞれ認識し、結合する。 ウイルスが宿主細胞に取り込まれる。その機構がウイルス膜と宿主細胞膜との膜融合によるか、エンドサイトーシスによるかは不明である。 ウイルスから持ち込まれたRNAの一部は宿主細胞リボソームに結合し、RNA合成酵素を作る。 作られたRNA合成酵素は持ち込まれたウイルスRNAを鋳型にRNAを複製する。これは子ウイルスの核酸RNAとタンパク質合成用mRNAとして用いられる。...

2020年注目のスーパーフード『スーパー藻類』!-スピルリナの4つのトレンドポイント-
日本スーパーフード協会が、『2020年上半期スーパーフードランキングTOP10』を発表しました。ここに、スピルリナを含む『スーパー藻類』が第6位にランクインしています。 このランキングが示すトレンド予測とは何でしょうか?そして、『スーパー藻類』がランキングに入った理由を、スーパーフードの代表藻類・スピルリナを例に解説します。また終わりに、『スーパー藻類』として注目されている今の社会的背景と、昔から続く藻類の食経験についてご紹介いたします。 ★2020 年上半期トレンド予測 スーパーフードランキング TOP10★第1位 青パパイヤ第2位 菊芋第3位 マルベリー第4位 サジー第5位 ノニ第6位 スーパー藻類第7位 国産スーパーキノコ第8位 進化系シード第9位 スーパーフラワー第 10 位 スーパー天然甘味料 ランキングが示すトレンド予測 このトップ10は、一般社団法人日本スーパーフード協会が、海外(主に米国)のリサーチをもとに、日本市場の現況の流れとの擦り合わせを 行った上で、2020年の上半期に日本でブームとなる可能性が高いスーパーフードを10品目予測し、 ランキング形式で発表したものです。 ランクインしたスーパーフードの共通点として、以下の4つの傾向がみられるとのことでした。 ①漢方・伝承民間薬としての歴史がある②古代種 (在来種)・ワイルド(野生)など植物の原点への回帰③サプリメントは化学合成的なものから、より 自然食品に近いものに④カラダに良いものを「+ たす」だけでなく、カラダに悪いものを「- ひく」 (排出) 食材に対して伝統的な歴史があり、農作物(ほとんどが人為的に品種改良されています)の祖先となる野生種が見直されてきたということになります。また、機能性物質にしても、化学合成品由来から自然食材からの抽出や食材を丸ごと体内に取り入れることが好まれるようです。そして、今まで機能性物質を追加することでより健康を維持しようという考え方が主流となっていましたが、体の老廃物を排出する「デトックス効果」の観点が食材選びのポイントの一つになってきたということです。...

【スピルリナStyle】青いタピオカミルクティー@シンガポール
世界各地で藻類フードが注目されています。その中でも栄養価が群を抜いて高く、スーパーフードの王様ともいわれる「スピルリナ」の人気は絶大です。そこでModiaでは、スピルリナ商品のトレンドを【スピルリナStyle】としてどんどんご紹介していきたいと思います! 第1回目は、シンガポールでスピルリナを使ったタピオカドリンクです。 シンガポールにあるタピオカドリンクショップ「Playmade by 丸作」。そこにあるのは、3種類の「BLUE ALGAE」メニューでした(BLUE ALGAE=青い藻)。 Playmade by 丸作 Pair your favourite pearls with Orange Pulp Green Tea for a Vitamin ... C boost! Did you know that the...

藻ガール尾張の藻類コレクション vol. 16 ボルボックス
みんな大好きなボルボックス。暗い背景にキラキラと緑に輝くボルボックスは、大人も子供もうっとりする美しさです。テレビや図鑑で皆さまもご覧になったことがあるのではないでしょうか? ●学名:Volvox carteri 和名:オオヒゲマワリ●分類:真核生物>アーケプラスチダ>緑藻類>ボルボックス目>ボルボックス科●生息:日本を含め世界中に生息。●体長/形態:約2,000個の細胞が球の側面に1層配置している。各細胞は2本の等長鞭毛をもち、寒天質に包まれている。細胞は鞭毛が球の外側に向くように並び、それら鞭毛が協調して球全体を回転させながら遊泳する。球の内部の空洞には、ゴニディアと言われる生殖細胞と形成中の娘群体が入っている。●レア度:★☆☆☆☆ Volvox aureus Volvox aureus - Aufnahmen im Dunkel- und Hellfeld Mikroskop: Motic BA310LED Objektive: EF-N Plan 4X/10X/40X Kamera: per Motic C-Mount Adapter 1X adaptierte N... ボルボックスは、もちろん研究者も魅了してやみません。2019年には、日本で『ボルボックス国際会議』が開催されました。なにそのマニアックな学会、と笑われる方。ボルボックスを侮ってはいけません!今回は学会プログラムを通して、ボルボックスの魅力をご紹介いたします。...

米国の藻類研究 -最新版-
2019年10月1日に、米国エネルギー省(DOE)のバイオエネルギー技術事務局(BETO)が、バイオエネルギーの研究開発支援として35のプロジェクトに総額$73,000,000(80億円:$1=\110として計算)を投下することを発表した。内訳を見てみると、森林資源(リグノセルロース)からのバイオ燃料生産(急速熱分解を含む)や、サーキュラーエコノミーを見据えた炭素・プラスチック関連、都市排水処理といったプロジェクトが目立っていた。 35のプロジェクトのうち5つは藻類プロジェクトであり、そこに$20,000,000(22億円)が投下される。藻類生産においては、従来の生産性向上やプロセス最適化などの手法に加え、オミックス手法を用いた研究が取り入れられている点が真新しい。それぞれ3億円から5億円の規模となる5つのプロジェクトについてご紹介したいと思う。 2019年度採択の補助金プロジェクト 51)Optimizing Selection Pressures and Pest Management to Maximize Algal Biomass Yield(OSPREY)(藻類バイオマスの生産性最大化に向けた選択圧の最適化と防除管理) 【概要】屋外での藻類大量培養のために、品種株選択と培養環境の最適化を通じて50%の収穫量増加と20%の燃料変換効率を目指す。既存の屋外培養設備に大きな変更を加えることはしない。藻類培養における障害となる害虫や病原体の感染機構を明らかにするためにメタゲノム解析を行い、これらのデータは米国内の研究拠点にオンラインで共有される。遺伝子組み換え手法を用いない外部環境による選択圧を用いて屋外培養に適した株を選抜する。また同時に、リアルタイムで藻類の生育を追尾できるようなシステムも構築する。さらに得られた株を屋外培養で試験し、改善状況を評価する。【委託先】(中核機関)ニューメキシコ・コンソーシアム (参加機関)コロラド州立大学、ニューメキシコ州立大学、カリフォルニア大学サンディエゴ校、Qualitas Health社、Cyanotech社、Phase Genomics社【期間】2019年~【費用】総額:$4,999,475(5億5千万円)URL:https://www.energy.gov/sites/prod/files/2019/09/f67/2029-1657_New_Mexico_Consortium_Summary.pdf 52)Innovations in Algae Cultivation(藻類培養のイノベーション) 【概要】Global Aglae Innovation社は、経済的合理性を有する藻類由来のバイオ燃料と高たんぱく質ミール生産の技術開発を行っている。本プロジェクトでは生産に係るすべてのプロセスを見直し、12項目の培養技術、および3項目のモニタリングツールを開発する。ライフサイクルアセスメント(LCA;Life Cycle Assessment)の目標値と限られた生産コストの範囲内で、藻類の大規模培養に向けた50%の生産性向上、50%の強靭性向上、そして20%の変換効率の向上をめざす。第一フェーズでは、上記15項目の開発技術を評価し、2ないし3項目への絞り込みを行う。同時に、ラボスケールの結果を円滑に大量培養に結びつけるために、研究室レベルで生産量数kgが達成可能なスケールアップ技術開発を行う。第二フェーズでは、選定された新技術について、商業化のための大量培養に向けた最適化を行う。【委託先】(中核機関)Global Aglae Innovation社 (参加機関)国立再生エネルギー研究所【期間】2019年~【費用】総額:$4,500,000(5億円)URL:https://www.energy.gov/sites/prod/files/2019/09/f67/2029-1769_Global_Algae_Innovations_Summary.pdf 53)Algal Productivity...

水産分野における藻類の利用 -現状と将来性-
水中に生息している藻類は、水圏における食物連鎖のなかで太陽エネルギーを吸収できる生産者の立ち位置として重要です。水産分野でもその役割は変わりません。今回は、水産分野における藻類の利用についてご紹介していきます。 ※なお、本記事に用いる「藻類」は微細藻類を指します。海藻は含みません。 世界の水産業界の流れ 上図は、最新の世界の漁獲量と養殖生産量の変遷の図です。天然の魚介類の漁獲量は1990年代より最大持続生産量(資源量を減少させず持続的に達成できる最大の漁獲量)に達しているため、既に漁獲制限がかかっています。その影響もあり、世界の魚介類の養殖生産量は年々増加しています。この養殖業界において、現在藻類は注目を集めています。 Modiaでも以前より水産業界についての記事を紹介してきました。 Modia[藻ディア] 牡蠣の養殖業界に吹く新しい風 https://modia.chitose-bio.com/articles/26 老若男女問わず、日本人に大人気の牡蠣。1999年に全国初のオイスターバーが誕生して以来、オイスターバーは増加を辿り、牡蠣を楽しめる場所が広がっている。今回はそんな牡蠣と藻にまつわる話を紹介したい。Belgian algae producer on the verge of oyster industry debut in Asia, USベルギーのTomAlgae社がアジアの牡蠣養殖業者に向けた藻類生産を間もなく開始するようだ。当社のCEOであるWilliam van der Riet氏は、今はアジアのどの国かは明言できないが、9月には明らかになるだろう、と述べている。TomAlgae社は2013年に設立され... Modia[藻ディア] 遺伝子組み換え藻類を使った、次世代の水産餌料 https://modia.chitose-bio.com/articles/34 今年はサンマが不漁のようで、サンマの水揚げ量が全国3位の気仙沼市では、サンマ祭り用の量が確保できず延期になったと、ニュースになっていた。毎年の漁獲状況は我々日本人の生活にも大きく関わり、新聞やニュースでも頻繁に取り上げられる。今回は、こうした漁業大国である日本が見習うべき事例について見ていきたい。Windfall for...

米国の藻類研究 -2018年度版-
今回は、アメリカで2018年に開始もしくは採択された、補助金のついている藻類プロジェクトをまとめた。具体的には、①アメリカ連邦エネルギー省(DOE)によって2018年以降に採択されたプロジェクトのうち、予算額が1億円を超える藻類プロジェクトと、②DOEのバイオエネルギー技術局(BETO)による2018年補助金プログラムに採択された藻類プロジェクトである。 ※2017年度以前の補助金プロジェクトは、米国の藻類燃料研究の変遷 part. 1 (2009~2014年度)、米国の藻類燃料研究の変遷 part. 2 (2015-2017年度)をご覧ください。 2018年度採択の補助金プロジェクト 42)Novel Algae Technology for CO2 Utilization(DE-SC0017077、二酸化炭素利用に向けた革新的な藻類技術) 【概要】発電所における石炭燃焼においてCO2を減少させる必要性は喫緊であるが、現在のCO2捕捉技術は経済的合理性にかけている。本プロジェクトでは藻類を用いて90%以上のCO2を回収し、燃料もしくは高付加価値商品に変換させることで、CO2捕捉の費用を商品利益と相殺する。その結果1トン当たり10ドル以下のCO2回収費用に抑えることを目指す。フェーズ1ではそれぞれの技術要素に焦点を当て、80%以上のCO2捕捉技術と、脱水技術と膜技術の向上を目指す。フェーズ2では研究室レベルでそれぞれの技術要素を併せて、将来の適応環境に合わせた試験を行う。脱水技術と膜技術は継続して研究を続ける。TEA分析(Techno-Economic Assessment;技術経済評価)も精査する。将来の可能性としては発電設備と組み合わせて液体燃料と食品、栄養補助剤の生産を目指す。また、使われた水のおよそ99%のリサイクルによって水の消費を抑える。以上の技術は新しい産業と雇用機会を生み出す。【委託先】Helios-NRG社【期間】2018年8月27日〜2020年8月26日【費用】$ 1,009,588($1=110円とすると約1億1100万円) 43)Development of a High Throughput Algal Dewatering System Using Magnetic Particles(DE-SC0013837、磁性粒子を用いた高収率の藻類脱水技術) 【概要】収穫後の藻類の脱水は藻類利用技術における乗り越えなければならない課題の一つであるが、現在はまだ安価な商用化技術は実現できていない。Manta Biofuel社の開発した磁性体を用いた脱水技術は、従来の技術コストを大幅に下げることのできる可能性がある。技術開発と実地試験を通じてプロジェクトの最終段階では96%ものコスト削減を目指し、将来の藻類の大量培養のきっかけにつなげる。【委託先】Manta Biofuel社【期間】2018年8月27日〜2020年8月26日【費用】$...

藻ガール尾張の藻類コレクション vol.15 クレブソルミディウム
暑くなってきましたね。涼しい木陰で休むとき、ちょっと木の幹をご覧ください。一息付きながら、藻ガール(藻ボーイ)気分を味わえます!木の幹に付着している藻類クレブソルミディウムを見つけに、皆さまも「藻探し」してみませんか? ●学名:Klebsormidium sp.●分類:真核生物>アーケプラスチダ>緑藻類・車軸藻綱>クレブソルミディウム>クレブソルミディウム科●生息:日本を含めアジア、ヨーロッパ、アメリカなど世界中に生息。●体長/形態:多細胞で付着部(仮根)のない非分枝糸状体を形成する。細胞壁に沿った帯状葉緑体をもち、不完全な筒状に細胞を取り巻く。一個のピレノイドをもつ。細胞中央には大きな液胞がある。●レア度:★☆☆☆☆ クレブソルミディウムは糸状体の藻類です。水中でも見られますが、乾燥に強いため樹木の表面やコンクリート塀でも生育することができます。他の緑藻(Elliptochloris subsphaerica)と一緒に生育して、やや濃い緑色の毛羽立った付着物の様相をしています。 クレブソルミディウムが木の幹に生えている様子(Holzinger & Karsten (2013)) 乾燥している陸上で生育する藻類は、様々な生存戦略をとります。例えば地衣類は、菌類と共生することで生きています。クレブソルミディウムは他の生物の手を借りることなく、空気中の水分で生きています。このように、陸上で湿り気のない場所に成育する藻類を「気生藻類」と総称します。 水中で生活をしている藻類に比べて気生藻類の生態はあまり明らかにされていませんでしたが、1989年、すなわち平成元年に、気生藻類の中でも生育環境により特徴が異なることがわかってきたのです(Hoffmann 1989)。ここで、イシクラゲなどの土壌藻類、岩生藻類、洞窟藻類、氷雪藻、動物着生藻類、そしてクレブソルミディウムなどの植物着生藻へと分類がなされ、それぞれの研究が進めやすくなったのです。 気生藻類にかかわらず、新しい時代、令和の藻類研究がどのように発展していくのか楽しみです。応用面での藻類研究では、我々ちとせグループが大いに貢献できると考えています。 皆さま、藻類業界を盛り上げていきましょう!! 藻藻子(藻ガールの子供の愛称)の初藻探し 参考資料Hoffmann, L. (1989). Algae of terrestrial habitats. The botanical review, 55(2), 77-105.Holzinger, A., & Karsten, U. (2013). Desiccation...

欧州の藻類研究 -最新版-
Modia執筆者にニューメンバー川原田が加わりました。欧州でバイオエコノミーを学んだ熱気あふれる人物です。今回は川原田が最新の欧州藻類研究について紹介します。今後の記事にもご期待ください! 欧州の藻類研究は、欧州委員会によって管理される研究開発用の枠組みプログラム『HORIZON2020』の基で2014年から2020年までを一つの区切りとして各プロジェクトが進んでいる。2017年までの欧州の藻類研究については以下をご覧いただきたい。 Modia[藻ディア] 欧州の藻類燃料研究の変遷 https://modia.chitose-bio.com/articles/73 今回は欧州の微細藻類燃料開発の動向についてまとめてみる。2010年あたりの藻類燃料ブームの際に米国の盛り上がりに引っ張られる形で、大型予算がついたプロジェクトが複数走っていたが、現在はトーンダウンしている。欧州も米国同様に戦略的にプロジェクトを走らせて、その結果を踏まえて次の戦略を立てているのが特徴的である。EUの微細藻類燃料研究の動向2016年11月に発表された欧州員会の戦略的エネルギー技術計画(Strategic Energy Technology Plan:SET-plan)によると、微細藻類燃料で設定されている目標値は、2020年時点で『70... Modia[藻ディア] 欧州の藻類燃料以外の研究の変遷 part. 1 https://modia.chitose-bio.com/articles/78 これまで二回にわたり、欧州における藻類研究についての動向、藻類燃料研究の変遷についてご紹介してきた。前回の記事でご紹介した通り、EUは燃料研究に傾斜していた時期から、燃料用途以外も見据えた総合的な微細藻類研究にシフトしてきている。今回は、微細藻類燃料関連以外で日本円換算にして1億円以上の予算がついているプロジェクトを紹介していく。なお、これらのプロジェクトはFP7, HORIZON2020と呼ばれる枠組みプログラムに含まれている。燃料以外の取り組みを赤字で示した一覧表が以下となる。これまでに燃料以外で1億円以上... Modia[藻ディア] 欧州の藻類燃料以外の研究の変遷 part. 2 https://modia.chitose-bio.com/articles/83 これまで三回にわたり、欧州における藻類研究についてご紹介してきた。今回は前回に引き続き、1億円以上の予算がついている37プロジェクトのうち、残りの18 プロジェクトについて紹介する。EUにおける燃料以外の微細藻類研究プロジェクト微細藻類研究(燃料以外含む)に関するEU国内グラント一覧表/筆者作成33)SALTGAE : Demonstration project to prove the techno-economic...
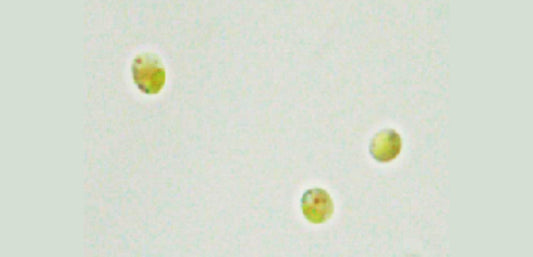
ナンノクロロプシスとは -EPAを生産する藻類-
「ナンノクロロプシス」と一般的にいわれる藻類は、真正眼点藻綱のナンノクロロプシス属(Nannochloropsis)に所属する一群です。ナンノクロロプシスはω3不飽和脂肪酸のEPAを細胞内に蓄積することで注目を集めています。 1.ナンノクロロプシスとは 左図:ナンノクロロプシスの顕微鏡写真、右図:系統樹ナンノクロロプシス/尾張作成 ナンノクロロプシスは、真正眼点藻綱、ユースティグマトス目、ユースティグマトス科、ナンノクロロプシス属に所属する一群です。非常に小さい球形の単細胞藻類で、体長は2〜5μmです。葉緑体は緑色をしていて、細胞の形態は緑藻綱のクロレラと似ていますが、「真正‘眼点‘藻綱」とその名が示す通り、細胞内に赤い眼点があるのが特徴です。また、「海産クロレラ」ということもあります。細胞の重さの50%を超える油脂を蓄積することから、油脂生産藻類とし活用されています。Nannochloropsis oculata、Nannochloropsis gaditanaが主に利用されています。 2.ナンノクロロプシスが生産する「EPA」 EPAの構造式 EPA(エイコサペンタ塩酸)は5つのシス型二重結合をもつ20炭素のカルボン酸です。構造式のω3位(脂肪酸のメチル末端から3番目の結合の意味)に二重結合をもつ脂肪酸であるため、ω3不飽和脂肪酸といわれます。 同じω3不飽和脂肪酸のDHA(ドコサヘキサエン酸)に比べるとEPAの認知度は低いです。しかしDHA同様に人に対する生理活性については世界的にエビデンスが整ってきていて、現在は主に医薬品及び機能性食品として利用されています。一般的にEPAは魚介類に豊富に含まれるというイメージがありますが、これはEPAを含む藻類等をエサとして魚介類が摂取して蓄積するからです。 2.油脂業界の利用 様々な藻類の脂質(脂肪酸)組成(%)/尾張作成 ナンノクロロプシスはEPAの他にも様々な脂肪酸を作ります。油脂業界で利用される場合は、ナンノクロロプシスからEPAを抽出して、精製します。ナンノクロロプシス由来EPAは医療用原体として利用することが進められていますが、現在は医療用原体よりも精製度が低い健康食品原料として販売されています。 DHAが脳や神経への影響を訴えるのに対し、EPAは血液に働きかける効果を持ちます。「血液をサラサラにする」「中性脂肪値を下げる」「血管年齢を若く保つ」「心臓病・脳梗塞を防ぐ」「動脈硬化を防ぐ」といった文句が謳われています。 【市場動向】 市場規模:世界のω3生産量が年間約8.6万トン(2014年時点)。このうち2 %(1,725トン)が医療用原体として利用される。売上ベースでは全体の30 %(600億円程度)と予測されている。 平均原料価格:魚油由来で食品グレードのEPAは、18-28 %でのkgあたりの原料単価は、2,000〜6,000円ほどである。DHAの例を取ると魚油由来の3倍ぐらいの値段になると推測される。 ナンノクロロプシスは有機溶媒で抽出、脱色、精製され、最終的に25-30%の濃度のEPAを含有するオイルまたは粉末として販売されている。 現在の医療用原体用途のEPA原料は魚油由来であり、微細藻類由来のものはまだない。医薬用原体として利用するためには96.5%以上の純度が必要となるため、高度に精製されている。 3.食品業界の利用 食用として利用されている、または研究開発が進行中の藻類の栄養素組成 / 尾張作成 ナンノクロロプシスはタンパク質、炭水化物、脂質のバランスのとれた食品といえます。加えてEPAや様々な油脂を含有し、ビタミンB12を含むため、抽出や精製をしなくてもナンノクロロプシスそのものが健康補助食品として利用できます。 【市場動向】 海外勢数社がサプリとして魚油の代わりに微細藻類由来のEPAを進めている。 Qualitas...
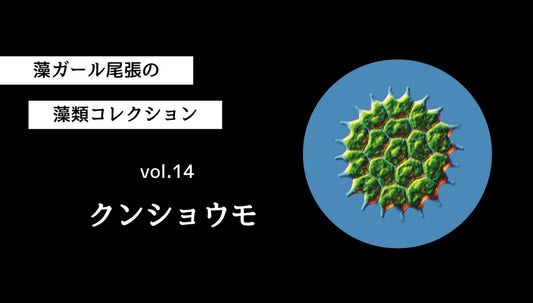
藻ガール尾張の藻類コレクション vol.14「クンショウモ」
学校の教科書でもお馴染みの藻類ですね。規則正しく細胞が並んでいますが、どうやって配置されていくのか想像できますか?クンショウモは水中で緑色の花を咲かせるように増えていきます。 ●学名:Pseudopediastrum boryanum(和名:クンショウモ)●分類:真核生物>アーケプラスチダ>緑藻綱>ヨコワミドロ目>アミミドロ科●生息:日本を含めアジア、ヨーロッパ、アメリカなど世界中に生息。●体長/形態:16個または32個の扁平な細胞が側辺で相互に接着し、放射状に並んだ定数群体をつくる。群体内に細胞間隙はない。群体の周縁部の細胞には2本の角状突起がある。葉緑体は1個、中央に1個のピレノイドがある。●レア度:★☆☆☆☆ クンショウモは平たい多角形の細胞が規則正しく集合してできています(定数群体)。鞭毛がないため細胞1個1個は動くことができないはずなのに、どういうわけか周囲との間隔を測っているかのようにきれいに敷き詰められています。パズルのようにぴったりはまったクンショウモは、とてもユニークな増殖をします。 まず1個の細胞が、1つのクンショウモができるだけの細胞数になるまで繰り返し分裂をします。 分裂してできた細胞は遊走子といい、この時には鞭毛が生えているため自由に動き回ることができます。遊走子は一つの袋(嚢状体)に入っていて、その中でクンショウモの形になるように他の遊泳子と接着します。配置が決まると、細胞の鞭毛は消失し、突起など細胞の位置に合わせて変形していきます。そして、小さなクンショウモができあがるのです(図;Park et al. 2014)。 動画もご覧いただけます!(再生開始3分から分裂過程が始まります) 遊泳子が泳ぎ回ってから小さなクンショウモができるまでにかかる時間はたった10分程度。とても不思議な現象です。緑のクンショウモが形作られ、咲く瞬間に出会えたら幸せですね! 参考資料Park, J. B. K., Craggs, R. J., & Shilton, A. N. (2014). Investigating the life-cycle and growth rate...

シアノバクテリアと好塩菌から醸しだすバイオプラスチック
藻類からのプラスチックに関連する取り組みを引き続き紹介したい。前回はケイ藻を利用した取り組みだったが、今回はシアノバクテリアを利用した取り組みである(かなり研究寄りの専門的な報告になってしまうがご勘弁を)。 前回の記事はこちらよりご覧いただきたい。 Modia[藻ディア] 藻類プラスチックから作るカーニバルのメインアイテム、マルディグラビーズ https://modia.chitose-bio.com/articles/91 近年、海洋投棄問題に端を発して環境課題として注目されやすいプラスチック。藻類からのプラスチックに関連する取り組みを今回から2回に渡り紹介したい。今回はルイジアナ州立大学で発明された藻類からの生分解性マルディグラビーズ(Mardi Gras beads)製造の話である。マルディグラビーズをご存知であろうか。マルディグラとはフランス語で「Mardi=火曜日」「Gras=太った」という意味で、英語では「Fat Tuesday=ファット・チューズデー」とも言われる。2月や3月に位置する謝肉祭の最終日を意味して、西方キリスト教では祝賀が行わ... アリゾナ州立大学(ASU)のTaylor Weiss助教のチームは、シアノバクテリアとバクテリアの共存システムによって日光からバイオプラスチックを作らせる研究を進めている。 ASU developing biodegradable plastics made from bacteria The world is awash in discarded plastics. A recent estimate of...

藻類プラスチックから作るカーニバルのメインアイテム、マルディグラビーズ
近年、海洋投棄問題に端を発して環境課題として注目されやすいプラスチック。藻類からのプラスチックに関連する取り組みを今回から2回に渡り紹介したい。 今回はルイジアナ州立大学で発明された藻類からの生分解性マルディグラビーズ(Mardi Gras beads)製造の話である。マルディグラビーズをご存知であろうか。 www.lsu.edu Biodegradable Mardi Gras Beads Update https://www.lsu.edu/mediacenter/news/2019/01/28bio_kato_beads2019.php LSU Department of Biological Sciences Professor Naohiro Kato is refining the process to make biodegradable Mardi Gras beads. マルディグラとはフランス語で「Mardi=火曜日」「Gras=太った」という意味で、英語では「Fat...
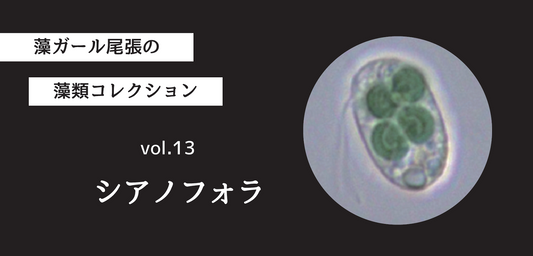
藻ガール尾張の藻類コレクション vol.13「シアノフォラ」
シアノフォラが所属する灰色藻は、皆さんには馴染みが薄いかと思います。現在知られている灰色藻は6属16種と小さな藻類グループですが、葉緑体の進化を研究する上で面白い藻類です。 ●学名:Cyanophora paradoxa●分類:真核生物>アーケプラスチダ>灰色藻綱>灰色植物目シアノフォラ属●生息:日本を含めアジア、ヨーロッパ、アメリカなど世界中の淡水環境に生息●体長/形態:遊泳性の単細胞藻類。腹部から等長の2本の鞭毛が生える。青緑色の2個の葉緑体(シアネレ)が細胞の大部分を占める。葉緑体中央部にはピレノイドと葉緑体核を有する区画がある。デンプン粒が多く存在している。●レア度:★★★☆☆ 灰色藻はシアノバクテリア(藍藻)を細胞内共生により葉緑体化した(一次共生)藻類のなかで、一番最初に分化した藻類と言われいます。光合成色素に青色のフィコシアニンが含まれているなど、シアノバクテリアの特徴を色濃く残しているため、灰色藻の葉緑体は「シアネレ」という特別な名称がついています。 シアネレの分裂様式は他の真核生物の藻類の分裂様式とは異なり、シアノバクテリアの体細胞分裂に近い様式で分裂します。シアノフォラでは、球状のシアネレがまず片側がくびれるハート型になり、そこからくびれが分裂面全周に広がるダンベル型へと変化していき分裂します。ダンベル型に広がった溝は、時間をかけて深くなっていくため、通常は先の顕微鏡写真のようなダンベル型のシアネレが観察されます。 上のハートが3つ並んでいる写真は、分裂中のシアノフォラ細胞からシアネレを単離し、電子顕微鏡(FE- SEM)で表面の微細構造を撮影したものです(Sato et al. 2009)。分裂中のシアネレは、葉緑体外部にできる分裂リングがないため、表面はなめらかです。そして分裂は片側から進行するので、ハート型になるのです。 一般的な藻類、陸上植物の葉緑体の分裂は、まず葉緑体の外側全周に分裂リングが付着して、分裂リングが同心円状に収縮することで進行していきます。そのため、残念ながら決してハート型にはならないのです。 藻ガールより愛をこめて、シアノフォラの超ミクロなハートをご紹介させていただきました。 参考資料Sato, M., Mogi, Y., Nishikawa, T., Miyamura, S., Nagumo, T., & Kawano, S. (2009). The dynamic surface of...
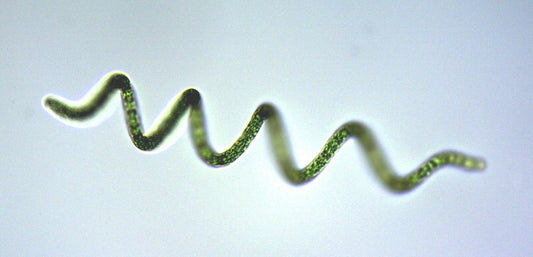
スピルリナ2.0
2018年11月にLumen Bioscience社(ワシントン州シアトル)のスピルリナの遺伝子組み換え技術の特許が成立したことが発表された。 US Patent & Trademark Office Grants Broad Foundational Patent to Lumen Broad composition-of-matter claims cover all products currently in development スピルリナは、その高い栄養成分、安全性、そして栽培の容易さから、現在世界で最も生産されている藻類である。人の健康食品だけでなく、青色着色料、水産養殖用の色揚げ材、家畜の濃厚飼料などといった幅広い分野で利用されており、最近では宇宙食としての研究も盛んだ。 分類学的な視点から見ると、スピルリナは藍藻(シアノバクテリア)と呼ばれる種にカテゴライズされる。もっとも単純な藻類ではあるが、複数細胞が連なった集合体として成長していくため、これまで遺伝子組み換えができない種として有名であった。 今回、そんなスピルリナの遺伝子組み換え系ができたということは画期的なことだと言える。特許を読む限り、エレクトロポレーションで細胞内に遺伝子を導入し、相同遺伝子組み換えを起こさせているようだ。この仕組み自体は特別なものではないが、相同遺伝子組み換えにかかる配列の長さが上流、下流それぞれ2,000塩基ずつと他の生物の場合と比べて相当長い。ここがポイントになっていそうだ。これ以外にも特許には書かれていないようなノウハウもきっとあることだろう。 Lumen社はスピルリナの遺伝子組み換え技術をコアとして、2017年末にシリーズとして1,300万ドル(約14億円)の資金調達に成功している。その後は本技術の用途開発先を生物製剤分野に絞り、立て続けに大型プロジェクトで採択されている。 2018年1月にはビル&メリンダゲイツ財団から、発展途上国の乳児を腸内病原体から守るための抗体治療薬開発の支援先として選ばれ、同年6月にはその支援金額が3倍に増額された。この増額は、1月に発表されたプログラムの初期段階の概念実証段階からポジティブな結果が出たことによるものである。遺伝子組み換えスピルリナ内で抗体を生産させることにより超低コストな抗体治療薬が作れる、というところが売りだ。 同年5月には国立衛生研究所(NIH)からも遺伝子組み換え経口マラリアワクチンの開発資金提供先として採択されている。マラリアワクチンを経口摂取でも効果を持つように修飾し、それをスピルリナ内で発現させるというものだ。薬が買えなかったり、届かないような貧困地域(=マラリア感染が多い地域)の現地でも生産でき、そのまま予防薬として供給することができる、というのが特徴となる。 同じく同年5月には米国農務省(USDA)から、養殖サケ魚(サーモンとニジマス)の感染性造血壊死症ウイルス(IHNV)に対する経口ワクチンの開発資金先としても選ばれている。現在養殖サーモンへのワクチン接種は一匹一匹に針注射をして行なっているが、Lumen社の遺伝子組み換えスピルリナベースのワクチンは経口投与用に設計されており、通常の食物供給と混ぜ合わせることができる。このため、流通と投与が非常に簡単になる。...

医療現場における藻類の応用
2019年1月31日、英国のヘルスケア企業であるAdvanced Medical Solutions Group(AMS)が、2007年に設立したハイファを拠点とするイスラエルのスタートアップ企業であるSealantis社を2500万ドルで買収したことを発表した。Sealantis社では、様々な用途に対応する医療用の接着剤を開発している。 従来、外科手術において切開部の閉鎖には縫合糸やステープラーが使用される。しかし、縫合糸がアレルギーや感染の原因となるリスクがあるため、近年これらの代わりに外科手術用接着剤が開発された。縫合系で処置した場合と比較して処置時間が短くなり、組織に与える損傷も少ない。また、手術の痕が目立ちにくいという利点もある。さらに、縫合部からの出血や体液の漏出、肺部の手術における切断面からの空気漏れを防止する目的でも止血材やシーラント材として医療用接着剤が使用されている。 生体組織には接着阻害因子となる水分が常に多量に存在するため、医療用接着剤は強力な粘着力を持つことが必要不可欠であるが、既存製品にはまだ大きな課題が残されている。そこでSealantis社は、藻類が水中で岩石などに付着するメカニズムを技術に応用することで湿った生体組織でも付着性に優れた接着剤の開発に着手した。 Sealantis社は接着剤の成分に動物由来のタンパク質素材を使用せず、藻類由来のアルギン酸を使用している。生体適合性に優れ、かつ生体内での分解吸収が可能な材料であり、動物由来と比較して感染及びアレルギーのリスクを大幅に低減させることができる。さらに、製品は低温輸送・保存や使用前の解凍、加温、及び予備混合が不要で、すぐに使える状態に整えている。 Sealantis社は独自の技術プラットフォームをベースにして、様々な臨床ニーズに応じた外科手術用シーラント、組織接着剤、部位特異的ドラッグデリバリー製品の開発を行い、術後感染の発症予防や術後の早期回復につなげることを目指している。 Sealantis社が開発した製品の第一号は、血管吻合部からの出血に対して高い止血効果を持つ外科用シーラント「Seal-V」であり、2007年10月、EUの安全基準条件を満たすことを表示するCEマークを取得したことを発表した。Seal-Vの他にも、消化管手術での縫合不全による消化管内容物の腹腔内流出を防ぐのに有効な「Seal-G」という製品も出している。縫合不全は世界中で年間600万件以上も行われている消化管手術に発生頻度が高い合併症の一つであり、術後感染率及び死亡率の増加と高く関連している。発症すると入院期間が長期化し、患者1人当たり平均28,000ドルの追加費用が発生するというデータも報告されている。 このように医療現場で必要とされる外科手術用シーラントの世界市場は、年間10億ドルを超えている。 今回の買収により、AMSは製品開発能力を充実することとともに、医療製品(主に外科手術用)市場における事業の拡大を目指し、神経外科、整形外科、及び心臓血管外科への適応拡大を図っている。 参考資料http://www.sealantis.co.il/https://www.jpost.com/HEALTH-SCIENCE/Algae-based-medical-adhesive-start-up-Sealantis-acquired-for-25m-579326http://nocamels.com/2013/11/israeli-company-imitates-algae-to-close-internal-incisions-efficiently/

本物の肉に近づく植物肉市場に藻類が波乱を起こす?
最近、インポッシブル・フーズ(Impossible Foods)社の植物肉がシンガポールに上陸したことが社内で話題になった。食べたことのある人からの感想を聞くと、「何も言われなかったら肉だと思う」、「思っていたよりずっと旨い」など、概ね好評であった。 ほぼ肉と同じ見た目、味、食感、香りを生み出すことに成功した秘密は、レグヘモグロビン(Leghemoglobin)という天然では大豆などのマメ科植物の根粒に存在する色素たんぱく質が使用されたからだ。レグヘモグロビンはヘム(heme)という色素部分とグロビンというたんぱく質部分から構成され、肉に豊富にあるミオグロビン(myoglobin)及び血液中に酸素を運搬し全身の組織に届けるヘモグロビン(hemoglobin)と構造が類似している。そのヘムこそ、肉独特の風味を生み出す要素である。 今のところ、米国において植物肉を扱う企業としてインポッシブル・フーズ社とともに二大巨頭となっているビヨンド・ミート(Beyond Meat)社は、植物肉を血の滴るような肉にみせるためにビートジュースを使用しているそうだが、ヘムがもたらす効果とは全然比べものにならないという。 インポッシブル・フーズでは、大豆レグヘモグロビンの生成に必要な遺伝子を組み込んだ酵母を発酵技術で大量に培養することで、レグヘモグロビンを生産・精製している。 インポッシブル・フーズが米国内で製品を展開する際に、特に米国食品医薬品局(Food and Drug Administration ;FDA)の承認は必要としなかったが、彼らは食の安全性・透明性に対する消費者の信頼性を高めるため、2014年に自ら、レグヘモグロビンについて一般的に安全な食品であると認められるGRAS(Generally Recognized As Safe)物質としての申請を行い、FDAによる安全評価を求めた。FDAは当初、遺伝子組み換え酵母を用いて生産したレグヘモグロビンの安全性に対して懸念していたが、約4年間に渡る評価の後、2018年7月23日にレグヘモグロビンをGRAS物質として認定した。 確かに安全性についてはFDAからのお墨付きが得られた。しかし、この方法により生産したレグヘモグロビンを原材料として使用した植物肉は、遺伝子組み換え酵母は含まれていないものの、非遺伝子組み換え食品とは認められない。「非遺伝子組み換え」は食品ジャンルでは大きなセールスポイントになるのである。 持続性、植物性、非遺伝子組み換えと、この三つのキーワードを満たし、まるで本物の肉のような風味と食感が楽しめる肉の代替品は作れないのだろうか? 藻類由来の植物性ヘム 以前、藻ディアの記事でも取り上げたTriton社(2013年設立の米・カリフォルニア大学サンディエゴ校発のベンチャー企業)は、藻類由来のヘムの開発に積極的に取り組んでいる。Triton社はクラミドモナス(Chlamydomonas reinhardtii)と呼ばれる藻類を食品原料として展開しようとしている。 緑藻のクラミドモナスは、紫外線の照射により赤色に変化し、ヘムの生成が誘導される。赤色を呈するヘムと緑色を呈するクロロフィルは構造が類似していて、生合成は途中の段階までは同じ経路である。紫外線を照射することで生合成経路の流れが効率的にヘムの生成に働く。紫外線の照射により藻類が本来もっている遺伝子が変異する可能性はあるが、本来もっている遺伝子の変異は従来の植物品種改良にも同様に起こっている広く受け入れられている現象である。この技術は外来遺伝子は導入していないため、遺伝子組み換え生物には該当しない。また、従来の品種改良に加えて高生産株を選別・取得している。 今後、Triton社はインポッシブル・フーズと同じステップを踏み、FDAの認可を取得する方針である。ちなみに、このTriton社のクラミドモナス由来のヘムについては既に植物肉メーカー何社かが興味を示しているそうだ。 藻類原料は、近年の急成長から今後競争が激化していくと予想される植物性たんぱく質市場に、間違いなく波乱を呼ぶだろう。 参考資料https://impossiblefoods.com/https://www.foodnavigator-usa.com/Article/2019/03/13/Triton-woos-plant-based-meat-makers-with-Non-GMO-source-of-heme-the-secret-sauce-in-the-Impossible-Burgerhttps://www.forbes.com/sites/jennysplitter/2018/11/30/algae-next-plant-based-protein/#359c54b65510https://this.kiji.is/476434498977727585?c=39546741839462401https://www.engadget.com/2018/07/25/fda-impossible-burgers-safe-to-eat/http://fortune.com/2018/07/24/impossible-foods-burger-fda-approval/https://www.tritonai.com/
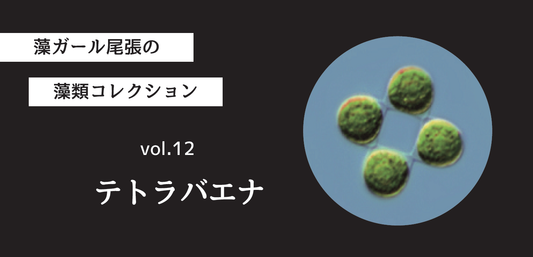
藻ガール尾張の藻類コレクション vol.12「テトラバエナ」
藻ガール尾張の藻類コレクションは、めでたく1周年を迎えました。これからも、どうぞお付き合いの程をよろしくお願いします。 藻ガールは、こうして藻をアピールする機会をいただけることが幸せです!皆さまにも、大きな「幸せも」、小さな「幸せも」、いっぱいの幸せがありますよう願っております。ということで、今回は、『幸せ藻』についてお話しします。 ●学名:Tetrabaena socialis(和名:シアワセモ)●分類:真核生物>アーケプラスチダ>緑藻綱>クラミドモナス目>テトラバエナ科●生息:日本を含め世界中に生息。●体長/形態:4個の細胞が平面で正方形型に配置している。細胞同士は細胞壁の側部で部分的に接着している。各細胞は直径約10µmで2本の等長鞭毛が伸びている。●レア度:★☆☆☆☆ シアワセモ(幸せ藻)は4個の細胞がきれいに正方形型に並んでおり、その姿はまるで幸運を呼ぶ「四つ葉のクローバー」。しかも水中では列を乱さずに泳ぐため、まさに四つ葉のクローバーが舞っているように見えます。 テトラバエナが和名に「シアワセモ」と名づけられた理由は2つあり、1つは形態が幸せの象徴である四つ葉のクローバーに似ていたことです。そしてもう1つの理由は、幸運にも、進化的に初期に多細胞化を成し遂げた藻類だと考えられていることです。 今までシアワセモは単に4細胞が規則正しく配置されただけの「集合体」とみなされていました。しかし、Arakakiら(2013)の研究で、シアワセモが4細胞を正方形に配置するために、発生の初期に細胞同士が連絡していることが明らかにされました。また細胞の鞭毛の配置が単細胞性緑藻よりも群体性緑藻に近いこともわかり、シアワセモは4細胞の集合体ではなく、統合が取れた「多細胞」とするのが妥当であると結論付けられたのです。 群体性緑藻の面々というのが、実はパンドリナでも紹介したヒゲマワリシリーズです。今までヒゲマワリシリーズの最小構成細胞数は8細胞のヒラタヒゲマワリでした。構成細胞数4細胞のシアワセモの登場で、「多細胞化への進化」の研究が一層進むことが期待されます。 シアワセモをヒゲマワリシリーズに当てはめるなら、皆さんはどのような名前をつけますか?シカクヒゲマワリ?ヨツカドヒゲマワリ?こんなことを思うと、藻ガールはわくわくしてしまいます。 参考資料Arakaki, Y., Kawai-Toyooka, H., Hamamura, Y., Higashiyama, T., Noga, A., Hirono, M., … & Nozaki, H. (2013). The simplest integrated...
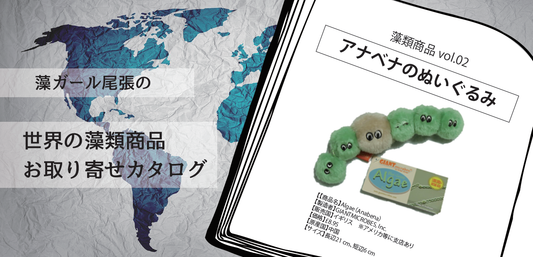
世界の藻類商品 お取り寄せカタログ vol.02『アナベナのぬいぐるみ』
藻類商品vol.02『アナベナのぬいぐるみ』 【商品名】Algae(Anabaena)【製造者】GIANTMICROBES, Inc.【販売国】イギリス ※アメリカ等に支店あり。【価格】£8.95【原産国】中国【サイズ】長辺21 cm、短辺6 cm【URL】https://www.giantmicrobes.com/uk/products/algae.html この商品の藻類は? この商品のモデルとなった藻類は、藍藻(シアノバクテリア)のアナベナ(Anabena)です。世界中の淡水環境に見られるアナベナは、アオコの代表種の一つです。●学名:Sphaerospermopsis sp.(Basionym: Anabeana sp.)●分類:原核生物>真正細菌>藍藻綱>ネンジュモ目>アファニゾメノン科>スファエロスペルモプシス属※近年の系統分類学では、アナベナは改変されています。詳細は後半に解説します。 この商品のポイントはここ! (1)青緑色の細胞が並ぶ形状、トリコーム 藍藻や緑藻には、緑色の細胞が一列に並んだ糸状体の藻類が存在します。構成している主たる丸くて小さな細胞のことを栄養細胞といいます。しかしこのぬいぐるみでは、丸く小さな緑色の栄養細胞の他に、丸く大きな灰色の細胞の2種類の細胞が連続的に連なっています。緑色も、例えばユーグレナのぬいぐるみような緑色ではなく、青みがかった青緑色をしています。これは、青色色素フィコシアニンを光合成色素にもつ藍藻の、ネンジュモ目の特徴です。藍藻の糸状体の形態を特にトリコームといいます。 (2)灰色で大きな細胞、アキネート トリコームの構成細胞の丸くて大きな灰色の細胞は、アナベナの耐久胞子でアキネートと呼ばれています。栄養細胞が大型化したもので、貯蔵物質を蓄積する役割を担います。光合成を行わないため光合成色素が薄いのが特徴です。 (3)一つだけ目をつぶっている小さな細胞、ヘテロサイト 小さくて丸い緑色の細胞には、よく見ると目を開いている細胞に混じり、目をつぶっている異質な細胞が1つあります。これはヘテロサイト(heterocyte、異質細胞)と個人的に判断しました。ヘテロサイトは栄養細胞から分化した、窒素固定に特化した細胞です。アキネートと同じく光合成を行わないため光合成色素が薄いのが特徴ですが、このぬいぐるみでは栄養細胞と同じ緑色なのが残念です。 (4)広義のアナベナ、本当はスファエロスペルモプシス属 古くからアナベナ属としてまとめられてきた藻類は、現在アナベナ属(Anabaena)、トリコルムス属(Trichormus)、ドリコスペルマム属(Dolichospermum)、スファエロスペルモプシス属(Sphaerospermopsis)の4属に分けられています。これからも、4属とも合わせて広義的にアナベナという名称が使用されていくと思いますが、このぬいぐるみの属はどうでしょうか?新しい分類は、トリコームの中でアキネートが異質細胞に対してどのような位置に発達するか、トリコームの形状、アキネートの形状、加えて遺伝子情報などから4つの属に分けられています。 1.アナベナ属(Anabaena).2.トリコルムス属(Trichormus).3.ドリコスペルマム属(Dolichospermum)4.スファエロスペルモプシス属(Sphaerospermopsis) このぬいぐるみは、アキートが球状である点、アキネートが栄養細胞とヘテロサイトよりも大きい点、アキネートとヘテロサイトが隣接している点から、スファエロスペルモプシス属で間違いないでしょう。 今回のぬいぐるみも、属の同定ができるくらい再現性の高いぬいぐるみでした。 アナベナのぬいぐるみはアメリカおよびヨーロッパの安全基準を満たされている商品です。しかし、本当のアナベナの一部には、神経毒素アナトキシン、肝臓毒素ミクロキスチンが含まれていますので、お子さんには正しい知識を教えてあげてください。 参考資料新山優子, & 辻彰洋. (2012). 藍藻ネンジュモ目の浮遊性種の分類学的変更と類似種の比較. 陸水学雑誌, 74(3), 153-164.https://www.kahaku.go.jp/research/db/botany/aoko/aokocontents/nosto.html 顕微鏡写真Werner, V....

日米欧の戦略と日本が目指すべき方向
日米欧の戦略比較 日米欧の予算分布から見る戦略イメージについて図にまとめてみた。横軸に微細藻類のアプリケーションの両極としてEnergy(燃料)とNon-Energy(燃料以外)をとり、縦軸はIndustry(産業)とAcademic(基礎)とした。この時に日米欧の予算戦略のポジションをマッピングしている。米国は燃料研究を柱として、学術的な基礎研究から産業的な応用研究まで幅広く予算をつけて進めている。また、EUは燃料以外として食料・飼料、化粧品原料といった高付加価値物質の研究、かつ産業化を主眼に置いた応用研究に舵をきっている。米国とEUは研究方針こそ異なるが、ともに国家としての方針を決め、それぞれ体系立って研究開発を進めているのが特徴である。一方、日本は燃料関連の研究のもと、食料・飼料に関連する研究が混在している。内容としては全般的に基礎研究寄りのものが多く、産業化を目指している取り組みは欧米に比べて少ない。 日米欧の微細藻類研究戦略のマッピングイメージ/筆者作成 日本が目指すべき方向 日米欧3極の藻類研究において、予算規模については3極の中で日本が最も少ないが、米国、EUと比べて2倍弱であり、そこまで大差のない範囲であろう。課題があるとすれば米国、EUが方向性を明確にして、国の主導のもとで体系だった進め方をしているのに対して、日本はプロジェクト単位で進めているところだろう。 藻類研究はまだ始まったばかりの分野であり、業界を発達させていくためには研究者同士の交流、研究開発で得られた知見の共有化を通して、業界を支えていくための人材を育成し、業界全体を底上げしていくことが大事である。そのような視点から見たときに、欧米のような目標設定を明確にした上で、大きなコンソーシアムを組んで体系だった攻め方は効率的であり、日本のような個別プロジェクト単位で孤軍奮闘する攻め方は現段階では非効率だと思われるからだ。 ただ、日本の場合は欧米と異なり縦割り行政であるため、国としてまとまった方針が立てにくいのは制度上仕方がない。このため、藻類研究を行っている大学、公的機関、企業らでつくる業界団体が分野を横断して集結し、日本が国としてサポートすべき研究方針を決めていくことが必要であろう。 現に米国もEUも国が強い指導力を発揮しているものの、その陰には米国のABO(Algae Biomass Organisation)や、EUのEABA(European Algae Biomass Association)といった各国の業界団体がロビー活動を通して常に最新動向をインプットしながら国への提言を行っている。日本も藻類業界団体を介して研究方針を提言することが大事になっていくだろう。 以下はあくまでも私個人の考えではあるが、日本オリジナルなモデルとして、『ツリーモデル』というものを考えてみた。これは藻類研究のポイントなる部分を点で抑えながら、基礎研究から事業化までの流れを作るモデルだ。各省庁下のグラントで重点的に蓄積してきた技術を結びつけて体系化させるというアイデアだ。 重点技術分野の明確化/筆者作成 重点技術として日本は各省庁で蓄積してきた『大量培養』『評価基準』『藻類バイオロジー』の3点を取ってみた。『大量培養』は藻類を大量かつ安定的に培養する技術である。大量培養確立して初めて事業化に繋がっていくため、技術は産業界の方が持っている場合が多い。現在は主に経産省がリードして、技術を蓄積している。 『評価基準』は、統一した藻類の評価基準法を策定することで様々な技術シーズが出てきた際の比較を容易にさせるためのものだ。これにより技術の選別が可能となり、有用なシーズを早期に事業化することが可能となる。 『藻類バイオロジー』というのは藻類の基礎知識を含むものだ。主に大学を中心としたアカデミックな機関で行われきた藻類研究がメインとなる。事業化に繋がるシーズの発見が期待される。 現在はこれら重点分野の連携は部分的であり、それぞれが独立して技術を蓄積している状態であるが、これらの縦の交流の場を作ることによって、シーズから事業が生まれるまでの動きを作るのが『ツリーモデル』の元となる考え方だ。シーズから事業化までの流れが活性化することで産業としての魅力が高まり、結果として優秀な人材が集まる、という正のスパイラルを作っていけると理想的だ。 ツリーモデルの概念図/筆者作成 現実的には各プレイヤーの思惑もあるので、こんな夢のようなモデルが成り立つことはないわけだが、縦割り型の構造の中で進めてきた成果をうまく利用して、こういった進め方ができたらいいなぁ、、という個人的な希望を込めて描いてみた。日本全体としての藻類研究の進め方を考える際の参考になれば幸いだ。ここまで長きにわたって日米欧の研究動向を紹介してきたが、本稿を持って一旦まとめとしたい。

‘’藻類×卵 ‘’待望の第二弾!
皆さんはInstagramにおける、最も「いいね!」の数が多い投稿をご存知だろうか?それは今年の1月4日にWorld Record Eggというアカウントがアップロードした、ある一枚の、ごく普通の卵の写真である。史上最多の「いいね!」獲得を目指し、“一緒に世界記録をつくろう!カイリー・ジェンナーが持つ記録を打ち破ろう!”とのメッセージが添えられており、投稿後わずか9日で目標を達成した。現在までになんと5200万以上もの「いいね!」を獲得し、堂々と王位についた。こうして、今も記録を更新し続けている「謎の卵」に世界中から注目が集まっている。 なぜ卵を選んだのか?「卵には性別、人種、宗教はない。卵は卵で、どこにでもある。」だからだそうだ。一見ただふざけているように見えて実はこんなに深い意味を持つとは、感心した。 さらにWorld Record Eggは「いいね!」獲得の目標を達成して終わりではなく、アメリカで毎年恒例のスーパーボウルのタイミングに合わせ、みんなに愛される「謎の卵」を動画広告に活用した。その動画は、2月3日に開催されたスーパーボウルの後にHuluで放映された。 動画は殻にヒビの入った卵の自己紹介から始まり、その後、ソーシャルメディアからのプレッシャーやストレスを理由に割れてしまう。続けて、あなたも同じように苦しんでいるなら、誰かに話しかけてくださいと言った後、卵は殻にヒビの入ってない姿を取り戻した。広告の最後には、非営利団体のメンタルヘルスアメリカのウェブサイトが掲載された。※World Record EggのInstagramアカウントに投稿された動画はこちら 「謎の卵」のクリエイターによると、ユージーンと名つけられた卵は今後も他の問題に対して何らかの社会的メッセージを広げていくだろうとしている。ユージーンからの次のメッセージをとても楽しみしている。 前置きが長くなったが、個人的にも謎の卵を応援したいという気持ちもあり、今回も卵の記事を書くことにした。 卵はどれでも同じだと思われるかもしれないが、実は見た目が同じであってもニワトリに与える餌によって、低コレステロール卵や栄養強化卵など通常の卵とは成分が異なるデザイナーエッグ(designer egg)を作ることができる。近年、消費者の健康志向が高まるにつれ、このようなプレミアム卵が商品化されている。 ここで、藻が大きく活躍するのである。ニワトリの飼料に色々な種類の藻類を配合することで、付加価値の高い栄養強化卵を作ることができるのだ。今回はそれらのうちのいくつかをご紹介したいと思う。 ■アスタキサンチンプラス卵 ビタミンEの550倍、ビタミンCの6000倍も高い抗酸化作用が特徴のアスタキサンチンという赤色色素は、以前藻ディアでも取り上げているヘマトコッカスという藻類に多く蓄えられている。ヘマトコッカスを含んだ飼料で育てたニワトリは、アスタキサンチンを豊富に含んだ卵を産卵する。マレーシアのAlgaetech International Sdn Bhd社は、アスタキサンチンプラス卵を2019年はじめまでに、一日50万個販売することを目標としている。 ■DHA・EPAプラス卵 海産魚類の油には、健康に良い様々な効果があるとされるDHAやEPAが多量に含まれていることが知られている。そのため、魚油や魚粉を飼料に配合することでDHAやEPAの含んだ卵を生産することができる。しかし、実はほとんどの海産魚類は自らDHAを生合成する機能を持っておらず、EPAの変換が可能な種類も一部に限られている。EPAやDHAは微細藻類によって合成され、その後、動物プランクトンや小動物と言った一連の食物連鎖の過程を経て最終的に魚の体内に蓄積されているのだ。現在は、DHAやEPAなどのオメガ3脂肪酸を生産するラビリンチュラ類(Schizochytrium)が新たな供給源として、魚油や魚粉の代わりに使用されている。オルテック社からはAll-G-RichというSchizochytrium limacinumパウダーが製品化されており、中国に供給先が何社もある。また、中国のENNグループはナンノクロロプシスを飼料に使用することによって、EPAを含有した卵を開発した。 ■カロチンプラス卵 高い抗酸化作用をもつβカロテンは、体内でビタミンAに変換されて夜間視力低下の予防や維持、皮膚や粘膜の健康維持など様々な働きをする。 (有)宮崎養鶏場の天然カロチンの卵は、赤色色素のβカロチンを豊富に含んだドナリエラ入りの飼料で生産された卵であり、普通の卵と比べて30倍ものβカロチンを含有している。 ■ルテインプラス卵 ルテインと呼ばれる黄色色素は、加齢黄斑変性の進行を抑えたり、発症を予防するなど目の健康を守る働きをする。通常ルテイン強化卵はマリーゴールドを飼料に配合することで生産するが、ルテインを豊富に含んだクロレラの使用も可能であることが報告されている。 これら以外にも、現在、栄養強化や飼育法を工夫した高付加価値の特殊卵が数多く世に出回っており、国内で販売されているものは1,000種類以上もあるといわれている。皆さんの身近なところでも栄養強化と表示された卵を多く目にするようになっているのではないだろうか?その中に、藻類を餌として飼育されたニワトリが生んだ卵があるかもしれない。...
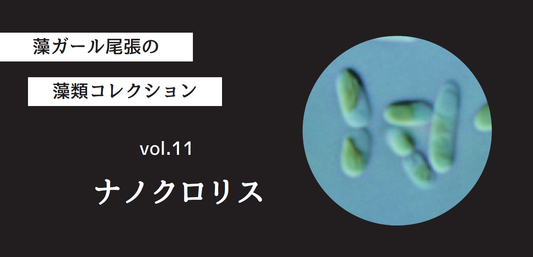
藻ガール尾張の藻類コレクション vol.11「ナノクロリス」
「植物以外の真核生物に存在する」とWikipediaにも記載されている『セプチン』が、植物で初めて、緑色植物の緑藻ナノクロリスで存在することが発見されました!セプチンは動物や菌類で分裂に必須のタンパク質で、植物には存在しないといわれています。 ナノクロリスはクロレラにとても近しい親戚で、大学院時代に同じく珍しい分裂様式をするマルバニアとともに研究していました。藻ガール尾張が苦楽を共にした藻類の1種であり、とてもマニアックな藻類です。 ●学名:Nannochloris bacillaris●分類:真核生物>アーケプラスチダ>緑藻>トレボキシア藻綱>クロレラ目>クロレラ科●生息:マニアック過ぎて不明●体長/形態:約1 µlの単細胞藻類。細胞内には葉緑体と核が1個ずつ存在し、細胞内の容積の多くを占める。この特徴から細胞分裂の研究に適している。●レア度:マニアック過ぎて不明 植物の細胞分裂では細胞内部から細胞板が形成されることによって仕切りができ、2細胞に分裂します(細胞板形成型)。一方で、動物や菌類の細胞分裂は環状にくびれこんでちぎれるようにして2細胞に分裂します(環状収縮型)。高校の生物の授業で習った方も多いのではないでしょうか? ナノクロリス(※)の細胞分裂は、始め1つの細胞が細長く伸張し、真ん中で環状にくびれこみ2つの細胞に分裂する環状収縮型分裂をします。このような分裂様式を二分裂型といい、分裂酵母の細胞分裂に似ています。ナノクロリスのように二分裂型に分裂する藻類はあまりいません。※本記事では、Nannochloris bacillarisをナノクロリスと呼称します。Nannochloris bacillaris以外のナノクロリス属の種の細胞分裂は内生胞子形成型です。 植物であるはずのナノクロリスが、分裂酵母のような分裂をするのはどうしてなのでしょうか? 実は、植物の中でも、緑藻のなかで環状収縮型細胞分裂から細胞板形成型細胞分裂への分岐点があるのです。クロレラやヘマトコッカスは環状収縮型細胞分裂をしますが、アオミドロや車軸藻は細胞板形成型細胞分裂をします。陸上植物は全て細胞板形成型細胞分裂をします。 セプチンは、マイクロフィラメント(アクチン)、中間径フィラメント、微小管と並ぶ第4の骨格と言われており、動物や菌類では、細胞分裂の他にも樹状突起・軸索・鞭毛の形成など様々な生命現象に関与しています。植物にはないと公言されてるタンパク質なので、ナノクロリスにセプチンが存在すると知った時はとても驚きました。 現在の生物学は次世代シークエンサーの登場により、自分が研究している種がもつ遺伝子ライブラリーを容易に作成することができます。また、その他に多くの種の遺伝子ライブラリーも公開されています。どのような種がセプチン遺伝子をもっているのか、様々な生物グループでライブラリーを横断検索してみると、緑藻以外の藻類もセプチン遺伝子をもつことがわかりました。「植物以外の真核生物に存在する」と言われ、動物や菌類などオピストコンタ界の生物種ばかりで研究されてきたセプチンは、藻類を含めた原生生物に広く分布して、何らかの機能を有する可能性があります。 系統樹の青色の枝の生物グループがセプチン遺伝子をもっている(Yamazaki et al. 2013) 藻類では、今回ご紹介したような細胞分裂機構や、それ以外の機構についても、高等植物に比べると研究が進んでいません。だからこそ、藻類には未知の可能性があるのです! 参考資料Yamazaki, T.*, Owari, S.*, Ota, S.*, Sumiya, N., Yamamoto, M., Watanabe, K.,...
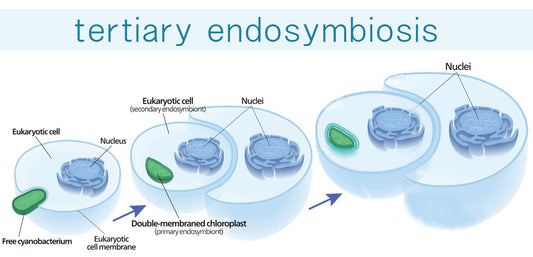
三次共生とは?ー渦鞭毛藻の多様性ー
今回取り上げる三次共生(tertiary endosymbiosis)という言葉を理解するために、始めに一次共生と二次共生、そして光合成色素の進化について説明をします。記事を読み終わる頃には、皆さん渦鞭毛藻の虜になること、間違いなしです!! 一次共生と光合成色素 シアノバクテリアを真核生物が取り込み、葉緑体化した現象を「一次共生」と言います。この一次共生により生まれたのが、灰色藻、紅藻、緑藻になります。この3種類の藻類は光合成色素の構成が異なっており、それぞれの色素が藻類の色を特徴づけます。灰色藻は青色のフィコシアニンをもつため青緑色、紅藻は赤色のフィコエリスリンをもつため紅色、緑藻はクロロフィルの色が強いため緑色です。 二次共生と光合成色素 一次共生により獲得した葉緑体をもつ藻類を真核生物が取り込み、葉緑体化した現象を「二次共生」と言います。二次共生により生まれた藻類は2系統あります。1系統は緑藻を取り込んで生まれたクロララクニオン藻とユーグレナ藻です。2つの藻類とも葉緑体はクロロフィルの色が強く、緑色をしています。もう1系統は、紅藻を取り込んで生まれたクリプト藻、ハプト藻、ケイ藻を含む不等毛藻と渦鞭毛藻です。紅藻を取り込んだ藻類は光合成色素の構成を紅藻から進化させ、それぞれの藻類の色を特徴づけます。クリプト藻はフィコビリンもしくはフィコエリスリンをもち紅色や青緑色です。ハプト藻は特有の19’-ヘキサノイロキシフコキサンチンをもち黄色みがかった茶色です。不等毛藻には6種類以上の異なる藻類が含まれていますが、代表的な微細藻類はケイ藻です。ケイ藻はフコキサンチンをもち茶色です。渦鞭毛藻は特有のペリニディンもち赤色がかった茶色です。※ユーグレナ藻については、緑藻を取り込む前に、ケイ藻に近い紅藻由来の藻類を二次共生で獲得したという報告もあります(Maruyama et al. 2009)。 葉緑体の進化(Keeling 2004をもとに作図) 三次共生とは? 一次共生、二次共生により藻類が多様化していっていることがわかります。類推して『二次共生により獲得した葉緑体をもつ藻類を真核生物が取り込み、葉緑体化した現象を「三次共生」と言います。三次共生により生まれたのが○○藻類です。』といきたいところですが、まだ三次共生により生まれた藻類はいません。 しかしながら!三次共生をした種が渦鞭毛藻の一部で発見されています!しかも、「連続的二次共生」という方法で葉緑体を獲得した種も発見されています!渦鞭毛藻の様々な葉緑体は、葉緑体化の初期段階の種から終了段階の種まで存在しているので、細胞内共生関係の成立過程を研究する良い材料なのです。 1.二次共生により葉緑体を獲得した渦鞭毛藻 前提として、二次共生によりうまれた元祖の渦鞭毛藻を記します。 (1)通常の渦鞭毛藻・二次共生(一次共生により獲得した紅藻を、渦鞭毛藻の祖先が取り込んだ)・葉緑体として成立・葉緑体包膜は3枚・渦鞭毛藻特有の光合成色素ペリディニンを有する 通常のペリディニンタイプの渦鞭毛藻の顕微鏡写真(左)と模式図(右)(Waller & Koreny 2017) 2.三次共生により葉緑体を獲得した渦鞭毛藻 以下は、通常のペリディニンタイプの葉緑体を消失後、各藻類を取り込みました。 (2)クリプト藻由来の葉緑体をもつ渦鞭毛藻・三次共生(二次共生により獲得したクリプト藻を、渦鞭毛藻が新たに取り込んだ)・葉緑体として成立していないため、数日経つと細胞内で消化してしまう「盗葉緑体(クレプトクロロプラスト;kleptochloroplast)」である・葉緑体包膜は2枚・葉緑体の特徴(フィコビリソームを伴わないフィコビリン(フィコシアニンやフィコエリスリン等の総称))がクリプト藻に似ている・この渦鞭毛藻は特異的にクリプト藻を取り込んでいる※Dinophysisのクリプト藻の取り込みについては、繊毛虫が媒介しているという報告がある。 クリプト藻由来の渦鞭毛藻の顕微鏡写真(左、Waller & Koreny 2017)と模式図(右、Gagat...

日米欧の予算比較
米国、日本、EUの微細藻類研究に関して、国の予算動向面からまとめてきた。微細藻類研究に本格的な予算が投下され始めた2009年から2017年までに各国の微細藻類研究に投下された予算総額について以下の図に示す。米国が約370億円、日本が約180億円、EUが約290億円となっている。内訳として、燃料関連の研究費が、米国約370億円、日本約140億円、EU約90億円、燃料以外の研究予算は、米国は無し、日本約40億円、EU約200億円となっている。 日米欧の微細藻類研究予算の総額の比較(2009年〜2017年)/筆者作成微細藻類研究に予算が投下され始めた2009年から2017年までの間に、国から予算がついた藻類研究費の比較。予算規模としては米国、EU、日本の順番で、米国は日本の約2倍、EUは日本の約1.5倍となっている。米国は燃料関連に予算を集中させている一方、EUは燃料から燃料以外への研究に軸足を移している。日本は燃料研究を中心にしつつ、近年は燃料以外の研究も出てきている。 日米欧の中では米国が最も予算投下額が大きく、日本の約2倍である。その次はEUで、日本の約1.5倍となっている。動向としては、米国は燃料関連の研究費に集約させている一方で、EUは燃料関連よりも燃料以外の研究費の割合が多い。日本は燃料の方が多いが、燃料以外の研究費についても予算がついている。 【燃料関連の藻類研究予算の動き】 燃料関連研究の予算投下の移り変わりを見ていくと、2009年に米国で170億円を超える大規模な予算投下が行われているのが目立つ。これは米国がこれまで投下してきた予算総額の約半分に該当する。日本、EUは米国の積極的な予算投下を後追いする形で2010年、2011年にそれぞれまとまった額の予算をつけている。 米国は初期に巨額な研究費を投下して全体像と課題を把握し、その後は把握された課題を解決する技術へピンポイントな予算投下を継続している。 EUは方向性の異なる戦略をもった複数のプロジェクトに集中的に初期の予算を投下し、その中から可能性のある方向を伸ばす、という進め方をしている。この結果、EUは2014年以降は燃料研究への予算投下を止め、燃料以外の研究開発に予算を集中させている。 日本は企業や大学が先行して行っていた研究シーズに対して、国が予算をつけて補助する、という形をとっている。サポートした中で有望そうなものを絞り込み、そこに対するサポートを厚くして継続する、という選抜型の仕組みとなっている。 【燃料以外の藻類研究予算の動き】 燃料以外の研究への予算投下について見ると、米国は燃料研究に集中して進めているのに対し、EUは燃料関連研究への予算を止め、燃料以外の研究に対して予算を投下する傾向が見られる。EUも初期の頃(2010年頃)は燃料関連研究にまとまった予算をつけていたが、燃料研究の事業化は遠いと判断し、より事業化の近い分野での産業化を最初に狙うことに切り替えたためと推測される。 一方、日本は燃料関連を中心としつつ、並行して少しずつ燃料以外の研究にも予算が投下され始めた状態である。EUが国として戦略を切り替えたのに対して、日本の場合は大学や企業からの研究提案を国がサポート形式であるため、国が主導して方向性を定めているわけではない。世界の動向をみながら動き出すことになるため、トレンドから少し遅れて、かつ世界のトレンドを平均化したような取り組みが反映されてくる構図になっている。 藻類の研究だけを見てても各国のカラーというのが浮き上がってくるものだなと感じる。どのスタイルも一長一短あるので、それぞれの強みを生かした戦略を立てていくことが大事だ。日本はボトムアップ型のスタイルであるため、各テーマは小ぶりだが、研究内容に幅広いバラエティーがあるところが強みになるだろう。この幅の広さが共有できるような場を整え、研究者の交流を活発化させ、有望な研究については大きく育てていける体制を作っていくことがポイントだ。
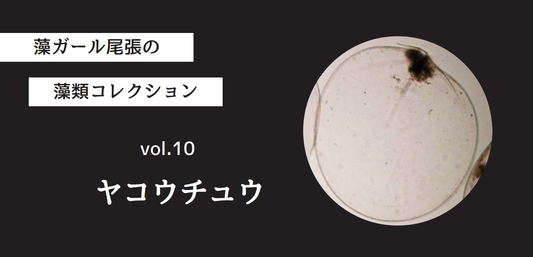
藻ガール尾張の藻類コレクション vol.10「ヤコウチュウ」
これまでもModiaで度々取り上げている夜光虫。青白く光る仕組みは蛍と同じ酵素反応によるものです。光合成を行わないことや、細胞のサイズが0.1 mmから2 mmと藻類の中では群を抜いて大きいことなど、変わり者の藻類です。また、身近な赤潮生物の一種でもあります。 ●学名:Noctiluca scintillans(和名:ヤコウチュウ)●分類:真核生物>SAR>アルベオラータ●生息:日本を含め、世界中に分布。●体長/形態:100 – 2000 µmの巨大な海産性単細胞藻類。扁平型をしている。細胞の大部分は透明な液胞が占めている。細胞質がくぼんだ箇所(写真上部)に密に集中しているため不透明にみえる。ここから触手が1本伸びており、他の藻類や原生生物を捕食する。ヤコウチュウは赤潮生物の一つである。物理的刺激により青白く光るルシフェリンールシフェラーゼ発光が見られる。●レア度:★☆☆☆☆ ヤコウチュウは葉緑体をもっておらず、光合成を行うことができないため、藻類の中でも従属栄養生物(詳しくはこちら)に入ります。触手でエサを捕らえて栄養にするのですが、なんと他の藻類も捕食します。 写真は、渦鞭毛藻のヤコウチュウが同じく渦鞭毛藻のPeridiniumを捕らえている写真です(Almeda er al. 2014より)。ヤコウチュウにとっては、同じ仲間でもエサはエサなのです。 赤潮を形成する藻類は、黄褐色や茶色の葉緑体をもつ珪藻や渦鞭毛藻など数多く存在しています。それらが大量発生すると、茶色を帯びた赤潮になります。 しかし、ヤコウチュウの赤潮は赤からピンク色になります。これはカロテノイド色素によるものです。前述した通り、ヤコウチュウ葉緑体を持っていないため、それこそ珪藻や渦鞭毛藻などもエサにして養分を補っています。ヤコウチュウの体内でそれらの藻が持つ葉緑体が分解されると、カロテノイドが蓄積してピンク色の赤潮になるというわけです。 皆さんも、海で粒状の物体とともに発生しているピンク色の赤潮に遭遇したら、「ヤコウチュウ!」と思い出してください。空のペットボトルに入れて持ち帰り、暗い所で振ってみると、きれいな青白い光が楽しめるかもしれませんよ!(ヤコウチュウの発生時期は春から夏にかけてです。) 赤潮ヤコウチュウを採取した時の筆者 参考資料Almeda, R., Connelly, T. L., & Buskey, E. J. (2014)....

欧州の藻類燃料以外の研究の変遷 part. 2
導入文と結びの文の要約をお願いします。 ———微細藻類研究(燃料以外含む)に関するEU国内グラント一覧表/筆者作成 33)SALTGAE : Demonstration project to prove the techno-economic feasibility of using algae to treat saline wastewater from the food industry. 【概要】食品業界から出てくる、既存の排水処理技術が使えない高塩濃度の排水を微細藻類を用いて処理する。具体的には耐塩性微細藻類/細菌コンソーシアムを用いて高塩濃度排水から栄養素を回収し、生産された微細藻類バイオマスから副産物を取り出す。排水に関連する様々な分野のステークホルダーの動員とネットワーキングのためのプラットフォームを開発し、普及のための共通ロードマップの開発を目指す。排水に関するイノベーションの横断的障壁に取り組む法律、規制および価格設定方法の整備、金融投資の促進、を伴いながら排水の「処理」から「資源化」へのパラダイムシフトを促進する。【委託先】<公的機関>パダノテクノロジーパーク財団(イタリア)、NOVA ID FCT(ポルトガル)、炭水化物/天然物評価センター(フランス)、INSTMコンソーシアム(イタリア)、INSTITUTO DE BIOLOGIA EXPERIMENTAL E...
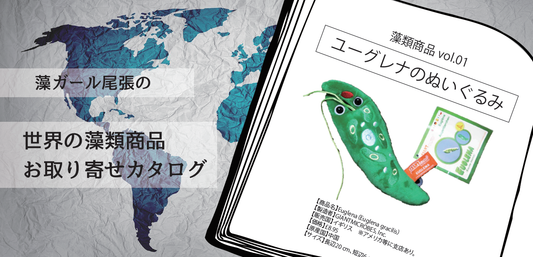
世界の藻類商品 お取り寄せカタログ vol.01『ユーグレナのぬいぐるみ』
藻ガール尾張は、仕事はもちろんですが趣味としても世界の藻類商品を調べて、願わくば実際の商品をお取り寄せしたいと思っています。 藻類商品のポピュラーなものとして、海苔といった海藻類やスピルリナといった微細藻類など「藻類食品」が世界中で食べられています。また、専門家向けから子供向けまで、「藻類図鑑」などの書籍も各国で出版されています。さらになんと、藻類アクセサリー、藻類ぬいぐるみなども販売されています。こうした商品のジャンルの幅広さを見ていると、藻類に魅了された人が世界中にいることがわかります! その中で見つけてきた世界中のマニアックな藻類商品を、藻ガール尾張がマニアックにご紹介する、題して『世界の藻類商品お取り寄せカタログ』。今回から連載をスタートさせていただきます! 第1回は『ユーグレナのぬいぐるみ』です。本物の特徴が良く再現されています! 藻類商品vol.01『ユーグレナのぬいぐるみ』 【商品名】Euglena(Euglena gracilis)【製造者】GIANTMICROBES, Inc.【販売国】イギリス ※アメリカ等に支店あり。【価格】£8.95【原産国】中国【サイズ】長辺20 cm、短辺6 cm【URL】https://www.giantmicrobes.com/uk/products/euglena.html この商品の藻類は? この商品のモデルとなった藻類は、健康食品としても知られているユーグレナ(Euglena gracilis)です。世界中の淡水環境に観られるユーグレナは、多くの人々に知られています。緑色で光合成をするところは「植物」的であり、独特の激しい動きをするところは「動物」的であるため、「ユーグレナは植物か?動物か?」という疑問をもつ人も、世界中にいるそうです。●学名:Euglena gracilis●分類:真核生物>エクスカバータ>ユーグレナ藻綱>ユーグレナ目>ユーグレナ属※ユーグレナの詳しい説明&トリビアは、藻類コレクションvol.5ユーグレナをご覧ください。 この商品のポイントはここ! (1)紐のついている位置 写真で見ていただくとわかる通り、ぬいぐるみ頭部の凹みから紐が出ています。ユーグレナ藻綱の特徴として、細胞の先端部(頭部)は深く陥入しています。陥入部は「貯胞」と呼ばれ、貯胞の底部からは鞭毛が生えています。このぬいぐるみはユーグレナを縦切りにした状態で、頭部の凹み部分から鞭毛が生えている様子を表しているのです。 (2)紐の本数、長さ 鞭毛を表している紐ですが、長い紐と短い紐の2本伸びています。これはユーグレナ目の特徴です。鞭毛の数と長さは、ユーグレナ藻綱の目を分類する上で重要です。「鞭毛の数が1本もしくは2本」、「遊泳時に鞭毛全体が動く」、「貯胞から長い鞭毛が1本外に伸びている」という項目が、ユーグレナ目の特徴です。このぬいぐるみは「2本」の「自由自在に曲げられる紐」がついていて、「1本はぬいぐるみの丈ほど長い」です。ユーグレナ目を的確に表しています。本来、短い鞭毛は貯胞内に留まる長さなので、このぬいぐるみの短い紐はもう少し短いほうがよりユーグレナに近いですが、電子顕微鏡を使わないと観察できない細かな特徴を表現しているのはあっぱれです。 (3)全体に散っている緑色の丸い刺繍 緑色の刺繍は、葉緑体を表しています。ユーグレナ属の葉緑体は種によって特徴があります。小さな丸状葉緑体が多数個存在しているものもあれば、1個の葉緑体が花びら状に細胞全体を包んでいたりと様々です。Euglena gracilisの場合は、皿状の薄い葉緑体が10個程存在します。各葉緑体の中央部には「パラミロン鞘」に包まれた「ピレノイド」が存在しています。ぬいぐるみについている緑色の刺繍には、中央部に黄色いドーナツ状の刺繍があり、ドーナツの内側はまた緑色です。これはパラミロン鞘に包まれたピレノイドを表しています。 (4)全体に散っている白い米粒型の刺繍 白い米粒型の刺繍は「パラミロン」を表しています。パラミロンとは細胞内原形質に漂う白い結晶で、細胞の中でキラキラしています。ユーグレナ属のパラミロンも種によって特徴があります。形は粒状・棒状・円盤状等、大きさも様々です。Euglena gracilisの場合は、小さな球状や卵型のパラミロンが多数存在しています。このぬいぐるみの、光沢のある白い糸で縫われた刺繍は一目でパラミロンだとわかります。 (5)頭部に1個ある丸い赤い刺繍 丸い赤い刺繍は「眼点」を表しています。眼点とは光受容体で、赤いカロテノイド顆粒が並んでいます。ユーグレナ藻綱の眼点は頭部の貯胞上部に位置します。まさに、このぬいぐるみの赤い刺繍の位置です。 (6)真ん中に1個ある丸い水色の刺繍 丸い水色の刺繍は「核」を表しています。核は遺伝子等がコードされているDNAをしまっている袋です。細胞が成長時など活発に活動しているとき核内でrRNAの転写等が行われますが、それが行われる場所が「核小体」です。核に色はありませんが、葉緑体が前面に広がっている藻類においては無色透明な核は明瞭にわかりますし、とりわけユーグレナ藻綱は核が大きいことも特徴です。このぬいぐるみでは薄い水色の刺繍を核、濃い水色を核小体で表しています。...

宇宙藻類
『宇宙兄弟』という漫画をご存知だろうか。宇宙を目指す兄弟の物語なのだが、綿密な取材を元に構成されているストーリーはもとより、ちょい役の登場人物一人一人にさえ人生を感じる丁寧な作り込みに圧倒される名作である。まだ読まれたことの無い方は機会があれば是非手にとってみていただきたい。 さて、そんな宇宙兄弟になぞらえて今回は『宇宙藻類』と題し、宇宙開発に関する藻類研究をいくつかご紹介したい。 そもそも宇宙と藻類に接点があるの?と思われる方も多いかと思うが、実はかなり古くから注目され、研究が行われている分野である。それというのも宇宙空間に長期間滞在するためには空気(酸素)と食料の自給が求められることになるが、その自給システムに藻類を利用しようというアイデアがあるためである。 藻類は宇宙飛行士が吐き出す二酸化炭素を吸収して酸素を供給することができ、増えた藻体は栄養食として食べることができる一石二鳥の材料となる。しかも植物と比べて栽培のためのスペースや資源が少なくすみ、育つまでの時間も短いという利点も持っているので、宇宙との相性が抜群に良いのだ。 このような宇宙空間での藻類利用を念頭に、2017年12月15日にESA(European Space Agency)のプロジェクトの一環として、生きたスピルリナが初めて宇宙ステーション(ISS)へと打ち上げられた。円筒形のフォトバイオリアクターに入れられたスピルリナは約1ヶ月間ISS内で培養されて、地球上と同じ速度で育って酸素も生成することが確認された。この1ヵ月間の培養期間に4回サンプリングが行われ、それと合わせて培地も4回入れ替えて試験が行われた模様だ。 無重力空間下における液体培養の場合は、液体中への二酸化炭素の供給および発生した酸素の除去が課題になるが、資料をみている限りは気体と液体をガス透過膜のようなもので仕切り、圧力をかけて強制的にガス交換を行う仕組みとなっているようだ。この辺の詳細情報は論文として公開された際にも確かめたい。 Green smoothies in space この試験の装置作成、宇宙ステーションでの実験計画、戻ってきてからのサンプル測定などの様子が資料としてまとめられて公表されていたので、興味のある方は以下の資料にも目を通してみていただければと思う。写真も多く、研究者達の楽しそうな雰囲気が伝わってくる。自分達が作った実験装置が宇宙船(SpaceX)で打ち上げられて、宇宙で実験されて、そのサンプルを分析できる、なんていうシチュエーションを与えられたら研究者だったら誰でも盛り上がるだろう。 また、2018年9月にはNASAでも宇宙ステーションにスピルリナを打ち上げ、微小重力下での増殖能を確認するための試験が行われている。こちらはNASAが企画する『皆のためISS科学(ISS Science for Everyone)』というプログラムの一環として、高校生のチームから応募されたアイデアを元にして行われたようだ。これについては以前藻ディアでも取り上げているので、興味ある方はこちらの記事もご覧いただければと思う。 SFみたいなテーマを高校生のチームが提案して、それを宇宙で実際に試験しちゃうなんて、私が高校生だった時には想像すらできなかった世界である。20年でここまで時代が変わるのであれば、20年後には月に人が住み、火星へ到着した人類がいてもおかしくはない。人が想像できる範囲というのは、いずれ実現できるものなのだなぁとシミジミ感じる。 NASA - NanoRacks-Modesto Christian School-Comparing the Growth of Spirulina on Earth...

卵代替品市場に藻類が参入
旅行の計画を立てる際、私はいつも「どこで、何を食べるか」を考えることから始める。その土地ならではの料理を楽しむことは、私にとって旅行で一番の楽しみといっても過言ではない。なぜかというと、景色については事前に写真などを見れば大体イメージすることができるが、料理についてはどんな味なのかをビジュアルから想像することが難しく、期待と喜びでワクワクする一方で不安も感じたりと、複雑な気持ちにさせてくれるからである。そうは言っても、海外旅行の場合、滞在時間が長くなると米が恋しくなる。あつあつのご飯の上に生卵をかける、あの至福の瞬間がたまらない。 ところで、世界で一番卵を食べている国は日本だということをご存知だろうか。日本人一人当たりの卵の年間消費量は平均320個であり、ほぼ1日1個食べている計算になる。海外では珍しい、生卵を食べるという日本特有の文化もその原因の一つかもしれない。しかし、そんな身近な存在である卵が、今後もしかすると簡単に手に入らなくなるかもしれないのである。 卵は完全栄養食品ともいわれるくらい、人間にとって健康を維持するために必要な栄養素を豊富に含んだ手軽に摂れる良質なタンパク質源である。そのため、今後世界中でのタンパク質の需要拡大に伴い、供給が間に合わなくなる可能性がある。また他にも、鳥インフルエンザによる卵不足の危機や卵の生産コストの上昇、動物由来製品の摂取に反対する消費者の増加などが原因で、今後は植物由来で作られる、卵の代替品の需要が急拡大していく見込みである。2017年11月23日に発表された市場調査報告によると、世界の卵代替品市場は、2017年から2022年にかけて5.7%の年平均成長率で増加し、2022年には11億1500万ドルに達すると予測されている。 実は、そんな卵代替品市場に藻類も参入しているのである。 2015年末に世界初の藻類を原料とした植物性卵ヴィーガンエッグ(VeganEgg)が発売された。開発したのは、1970年に南カリフォルニア州にあるレストランとして始まったヴィーガン食品メーカー「フォロー・ユア・ハート(Follow Your Heart)社」である。同社は1977年に卵や乳製品を一切使用しないマヨネーズの代用品、ヴィーガネーズ(Vegenaise)の発売以来、ヴィーガンチーズやサラダドレッシングなど様々なヴィーガン食品を開発してきた。 New & Improved VeganEgg What happens when one of your key ingredients is no longer available? You pivot and find a way to...

欧州の藻類燃料以外の研究の変遷 part. 1
これまで二回にわたり、欧州における藻類研究についての動向、藻類燃料研究の変遷についてご紹介してきた。 Modia[藻ディア] 欧州における藻類研究の動向 https://modia.chitose-bio.com/articles/72 前回までに日本、米国での微細藻類研究の動向を国の予算面から見てまとめてきた。今回から数回に渡ってEUの微細藻類研究の動向を同様な視点から見ていきたいと思う。米国の動向はなんとなくチェックしているけどEUまではなかなか、という方々も多いと思うので参考にしていただければと思う。私も自分で調べながら日本や米国とは異なる戦略で進めているEUの開発動向を知ることができて勉強になった(調べるの大変だったけど、、)。今回はEUでの微細藻類研究の歴史と研究政策の枠組みといったところについて記す。EUにおける微細藻類研... Modia[藻ディア] 欧州の藻類燃料研究の変遷 https://modia.chitose-bio.com/articles/73 今回は欧州の微細藻類燃料開発の動向についてまとめてみる。2010年あたりの藻類燃料ブームの際に米国の盛り上がりに引っ張られる形で、大型予算がついたプロジェクトが複数走っていたが、現在はトーンダウンしている。欧州も米国同様に戦略的にプロジェクトを走らせて、その結果を踏まえて次の戦略を立てているのが特徴的である。EUの微細藻類燃料研究の動向2016年11月に発表された欧州員会の戦略的エネルギー技術計画(Strategic Energy Technology Plan:SET-plan)によると、微細藻類燃料で設定されている目標値は、2020年時点で『70... 前回の記事でご紹介した通り、EUは燃料研究に傾斜していた時期から、燃料用途以外も見据えた総合的な微細藻類研究にシフトしてきている。今回は、微細藻類燃料関連以外で日本円換算にして1億円以上の予算がついているプロジェクトを紹介していく。なお、これらのプロジェクトはFP7, HORIZON2020と呼ばれる枠組みプログラムに含まれている。燃料以外の取り組みを赤字で示した一覧表が以下となる。これまでに燃料以外で1億円以上の予算がついているものが37プロジェクトがあり、今回はそのうちの19プロジェクトについて紹介する。 EUにおける燃料以外の微細藻類研究プロジェクト 微細藻類研究(燃料以外含む)に関するEU国内グラント一覧表/筆者作成 14)HARVEST : Control of Light Use Efficiency in Plants and Algae –...

氷雪藻とは?-北極も南極もつながる藻たち-
上のサムネイル写真のように白い雪の上が赤色に染まったり、他にも緑色に染まったりする現象をご存知ですか?この現象は「彩雪現象」や「雪の華」と呼ばれています。特に赤色に染まっている雪は、日本語では「赤雪」や「紅雪」と、英語では「Watermelon Snow(スイカ雪)」と呼ばれます。この真っ白い雪のキャンパスに描かれている、赤色や緑色の絵の具の正体は、実は藻類なのです。 氷雪藻とは? 雪の上に育つ藻類を「氷雪藻」や「雪上藻」といいます。一般的に、高山帯や極圏の夏季において雪や氷上に生育する低温耐性の藻類の仲間を指し、100種以上の藻類が含まれます。 多様な氷雪藻 ・シアノバクテリア(藍藻) クロオコッカス属、ユレモ属、Calothrix属(ネンジュモ目)・緑藻綱 クラミドモナス属、クロロモナス属・車軸藻綱 メソテニウム属、アンキロネマ属・黄金色藻綱 オクロモナス属・シヌラ藻綱 マロモナス属そのほか、多数知られています。 多様な氷雪藻(a) Oscillatoriaceae cyanobacteria, (b) Calothrix parietina, (c)Chlamydomonas nivalis, (d) Ancylonema nordensholdii.(Takeuchi et al. 2014) 氷雪藻は世界中で発見されていますが、ほとんどの種が10℃を超える環境では生育できないため、年間を通して低い気温が維持され、標高がある程度高く、積雪が良く残る場所に限定されます。日本でも山岳地帯や高原の融雪時期に見られることがあります。 最も多くみられる氷雪藻は、緑藻綱Chlamydomonas nivalisです(図(c))。通常は緑色の藻類ですが、雪の上では低温、強い紫外線、ほとんど栄養がないという非常に厳しい環境に置かれるため、赤色のアスタキサンチンを蓄積して環境に耐えます。厳しい条件になるとアスタキサンチンを蓄積するという点は、同じく緑藻綱ヘマトコッカスと同様です。 氷雪藻はどこからくるのか? 氷雪藻は極地や高山帯に生育しているので、採取しに現場にいくことが難しく、分類や生態の研究では未だに不明な点が多く残されています。 そもそも氷雪藻がどこからやってくるのか、という疑問もその一つです。考えられているのは、地表から這い上がってくる説と、空中から舞い降りてくるという二つの説です。 多くの藻類は鞭毛が生えているため、水中で自由に動き回ることができます。融雪時には、雪の表面と地表が水でつながれるため、光を求めて氷雪藻が地表から雪表面に上っていき、大量増殖することで赤や緑に染め上げられる。これが地表からか這い上がってくる説です。この説では、数メートルの積雪でも這い上がれるのか、という疑問が残ります。また、北極海など地表がないところでの氷雪藻の増殖については説明がつきません。 一方の、空中から舞い降りてくる説では、大気中を飛散している藻類の胞子が、雪の上に降下、沈着し、雪解けとともに繁殖をはじめるというものです。この説が正しければ、地球上のどの地域でも同じ氷雪藻が見つかることになります。 北極と南極で同じ氷雪藻が存在した! 2018年、氷雪藻がどこからくるのかを考える上で、興味深い論文が発表されました。 Bipolar dispersal of...

【速報】2018年農業法に藻類が追加!(米国)
年末にホットなニュースが飛び込んできた。米国の次の農業法の中に『藻類』が正式に組み込まれることとなったのだ。この新しい農業法は12月11日に上院、12日に下院でそれぞれ可決され、20日にトランプ大統領の承認と署名を経て成立した。今後5年間の農業支出の後ろ盾となる農業法だが、2019年から2023年までの5年間の予算総額は428ビリオンドル(≒48兆円)と、インパクトは大きい。 Trump Signs 2018 Farm Bill As USDA Aims To Increase SNAP Work Requirements President Trump signed the farm bill today at 4 p.m. without SNAP work requirement changes...
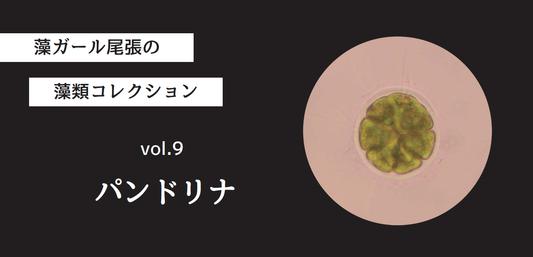
藻ガール尾張の藻類コレクション vol.9「パンドリナ」
今回ご紹介する藻は、淡水環境であればどこにでもいる藻類です。みなさんが毎日通り過ぎている公園の池の水でも、きっと発見できると思います! ●学名:Pandorina sp.(和名:カタマリヒゲマワリ、クワノミモ)●分類:真核生物>アーケプラスチダ>緑藻綱>ボルボックス目>ボルボックス科●生息:日本を含めアジア、ヨーロッパ、アメリカなど世界中に生息。●体長/形態:8個、ないし16個の細胞が密着して、長径約100 -250 µmの長楕円体の群体を形成する。群体は寒天質に包まれている。各細胞からは2本の等長鞭毛が寒天質を突き抜けて伸びていて、回転しながら遊泳する。●レア度:★☆☆☆☆ 藻ガール尾張は日々藻のサンプリングをしてくれる人を募集しており、「サンプリングしてきてもらえませんか?」がお決まりのセリフです。大抵は忘れ去られてしまうのですが、ある時、社内の某人が弊社オフィスビル(かながわサイエンスパーク)に併設されている公園の池でサンプリングをしてきてくれました。このサンプルの中にパンドリナがいました。 パンドリナは池や田圃といった水が滞留する環境はもちろん、公園の池などの水が循環する人工環境でも、どこにでも生息している藻類です。今回観察したサンプルもそうですが、最盛期には水を濃縮しなくとも高頻度で出会えるくらい、水中に沢山いる藻類です。 パンドリナには「カタマリヒゲマワリ」という和名があります。「ヒゲマワリ」を和名の一部にもつ藻類は、ヒラタヒゲマワリ、ニセヒゲマワリ、カタマリヒゲマワリ、タマヒゲマワリ、ヒゲマワリ、オオヒゲマワリと多数存在しています。共通した特徴として、定数群体を形成しており、髭の様な鞭毛を各細胞に2本もち、回転しながら遊泳します。’ヒゲマワリ’シリーズは、ヒラタヒゲマワリからオオヒゲマワリに向かって進化していると考えられていて、細胞学的に興味深い藻類たちです。こちらについては、また別の機会にご紹介できたらと思います。 パンドリナである「カタマリヒゲマワリ」は、‘塊の髭廻り’の意味です。‘ヒゲマワリ’シリーズの中でも、細胞同士が規則正しく密に接着して塊様になっている藻類はパンドリナだけです。この接着した様子は藻類界でも稀で、桑の実に例えて「クワノミモ」とも呼ばれています。 皆さんも、お近くにある公園の池を通りかかった際には、ぜひ足を止めて沢山の藻類がいることを思い出してみてくださいね。 プレゼントの野外水サンプルをわくわく観察している筆者 参考資料Arakaki, Y., Kawai-Toyooka, H., Hamamura, Y., Higashiyama, T., Noga, A., Hirono, M., … & Nozaki, H. (2013). The...

欧州の藻類燃料以外の研究の変遷 part. 2
これまで三回にわたり、欧州における藻類研究についてご紹介してきた。 Modia[藻ディア] 欧州における藻類研究の動向 https://modia.chitose-bio.com/articles/72 前回までに日本、米国での微細藻類研究の動向を国の予算面から見てまとめてきた。今回から数回に渡ってEUの微細藻類研究の動向を同様な視点から見ていきたいと思う。米国の動向はなんとなくチェックしているけどEUまではなかなか、という方々も多いと思うので参考にしていただければと思う。私も自分で調べながら日本や米国とは異なる戦略で進めているEUの開発動向を知ることができて勉強になった(調べるの大変だったけど、、)。今回はEUでの微細藻類研究の歴史と研究政策の枠組みといったところについて記す。EUにおける微細藻類研... Modia[藻ディア] 欧州の藻類燃料研究の変遷 https://modia.chitose-bio.com/articles/73 今回は欧州の微細藻類燃料開発の動向についてまとめてみる。2010年あたりの藻類燃料ブームの際に米国の盛り上がりに引っ張られる形で、大型予算がついたプロジェクトが複数走っていたが、現在はトーンダウンしている。欧州も米国同様に戦略的にプロジェクトを走らせて、その結果を踏まえて次の戦略を立てているのが特徴的である。EUの微細藻類燃料研究の動向2016年11月に発表された欧州員会の戦略的エネルギー技術計画(Strategic Energy Technology Plan:SET-plan)によると、微細藻類燃料で設定されている目標値は、2020年時点で『70... Modia[藻ディア] 欧州の藻類燃料以外の研究の変遷 part. 1 https://modia.chitose-bio.com/articles/78 これまで二回にわたり、欧州における藻類研究についての動向、藻類燃料研究の変遷についてご紹介してきた。前回の記事でご紹介した通り、EUは燃料研究に傾斜していた時期から、燃料用途以外も見据えた総合的な微細藻類研究にシフトしてきている。今回は、微細藻類燃料関連以外で日本円換算にして1億円以上の予算がついているプロジェクトを紹介していく。なお、これらのプロジェクトはFP7, HORIZON2020と呼ばれる枠組みプログラムに含まれている。燃料以外の取り組みを赤字で示した一覧表が以下となる。これまでに燃料以外で1億円以上... 今回は前回に引き続き、1億円以上の予算がついている37プロジェクトのうち、残りの18 プロジェクトについて紹介する。 EUにおける燃料以外の微細藻類研究プロジェクト 微細藻類研究(燃料以外含む)に関するEU国内グラント一覧表/筆者作成 33)SALTGAE : Demonstration project...

藻類タンパク質関連の最近の動向
先日、Forbesで『藻類タンパク質が植物タンパク質マーケットを破壊するかも』という刺激的なタイトルの記事が出ていた。 Algae Might Be About To Disrupt The Plant-Based Protein Market Triton is a company poised for disruption. The small San Diego based algae start-up is hitting all the right...

教育と産業
先日、米国で藻類に特化したカリキュラムが作成されたコミュニティーカレッジで、初めての卒業者が誕生した、とのニュースを見かけた。アメリカのエネルギー省DOE(United States Department of Energy)のサポートによって設立されたATEC(Algae Technology Educational Consortium) によって作成されたプログラムを修了すると準学士(Associate Applied Science Degree in Controlled Environment Agriculture with a certificate in Algae Cultivation)がもらえる仕組みとなっている。 ATECは大学教授、藻類企業のリーダー、NREL(National Renewable Energy Lab)などのメンバーから構成されている。カリキュラムの中には藻類企業からの知見も取り入れられており、卒業生達が会社でも即戦力として働けるような知識の提供とトレーニングとが行われているそうだ。スポンサーであるDOEの立場からみると、せっかく藻類関連の補助金を出しても研究者が藻類を扱えるようになるまでの時間で大半が溶けてしまっている部分の改善に期待しているようだ。補助金の費用対効果を考えると理にかなった取り組みだなと感じる。 A First-of-a-Kind Algal-based College...
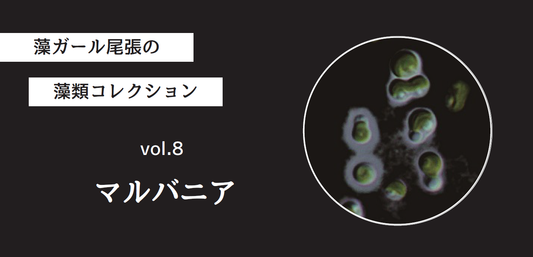
藻ガール尾張の藻類コレクション vol.8「マルバニア」
今回紹介する藻類はとてもマニアックな藻類です。クロレラにとても近しい親戚で、藻類では非常に珍しい出芽をすることで分裂増殖します。藻ガール尾張が大学院時代に細胞分裂の研究をしている時に偶然みつけた奇跡の写真をご紹介します! ●学名:Marvania geminata●分類:真核生物>アーケプラスチダ>緑藻>トレボキシア藻綱>クロレラ目>クロレラ科●生息:マニアック過ぎて不明●体長/形態:直径約1 µlの単細胞球状藻類。細胞内には葉緑体と核が1個ずつ存在し、細胞内の多くを占める。この特徴から細胞分裂の研究に適している。細胞外には多糖質をまとっている(写真は多糖層をわかりやすくするため培養液に墨汁を溶かしたサンプル)。●レア度:マニアック過ぎて不明 マルバニアの分裂様式は藻類では珍しい出芽型です。 M. geminataのFE-SEM写真、尾張2008 写真左a-eは正常なマルバニアの分裂の様子です。1つの細胞の、写真の向かって左側の領域から、右側にぷっくりと成長していることがわかります(写真左a-d)。やがて完全に切れ目が入り2つの細胞に分裂します(写真左e)。写真の向かって左側の領域は「母細胞」、右側の出芽してくる領域は「娘細胞」といいます。 この写真で観察している細胞表面のざらざらしたものは細胞壁です。マルバニアの出芽型分裂ではその都度細胞壁が作られますが、新たに成長する際に自然と母細胞壁ははがれるのが一般的です。そんな中、成長や分裂中に母細胞壁がはがれなかった細胞を発見しました!それも母細胞壁の周りにも2枚の細胞壁があります。生物学の専門用語としてはないですが、祖母細胞壁、曾祖母細胞壁が残存していた、ということです。この細胞の写真から娘細胞は同じ側に出芽することがわかります。 母細胞壁が開裂しない異常な分裂細胞の写真ですが、非常に珍しいショットだったので論文や植物細胞形態学の写真集に掲載されました! 大学院時代(修士課程)の筆者 @研究室の培養庫 参考資料 Yamazaki, T.*, Owari, S.*, Ota, S.*, Sumiya, N., Yamamoto, M., Watanabe, K., Nagumo, T., Miyamura, S., &...

欧州の藻類燃料研究の変遷
今回は欧州の微細藻類燃料開発の動向についてまとめてみる。2010年あたりの藻類燃料ブームの際に米国の盛り上がりに引っ張られる形で、大型予算がついたプロジェクトが複数走っていたが、現在はトーンダウンしている。欧州も米国同様に戦略的にプロジェクトを走らせて、その結果を踏まえて次の戦略を立てているのが特徴的である。 EUの微細藻類燃料研究の動向 2016年11月に発表された欧州員会の戦略的エネルギー技術計画(Strategic Energy Technology Plan:SET-plan)によると、微細藻類燃料で設定されている目標値は、2020年時点で『70ユーロ以下/M Wh』となっている。1M Wh = 0.086 toe(IEA基準)とすると、原油換算で1M Wh = 101.1リットルということとなり、日本円換算だと約90円/リットルとなる(1ユーロ= 130円とする)。2030年には2020年の半分を目指すということで、45円/リットルということとなる。 この設定値は『2030年までに年間50億ガロン(1ガロン= 3.785リットル)の微細藻類由来燃料を1ガロンあたり3ドル(日本円換算で約84円/リットル、1ドル= 106円とする)で生産する』という米国の目標値よりかなり高い値で設定されている。ただし、EUの場合は生産量については言及していない。 EUの微細藻類研究は2007〜2013年の枠組みプログラムであったFP7内で採択され、本格的に始まった。米国での盛り上がりを受けて、2010年あたりから微細藻類燃料関連のプロジェクトが採択され、現在までに全10のプロジェクトが行われている(現在進行中も含む)。この中でも中核となるプロジェクトが2011年から始まった「BIOFAT」, 「All-Gas」, 「InteSusAl」と呼ばれる3つの大型の微細藻類燃料研究プロジェクトで、これら3つのプロジェクトは『ALGAE CLUSTER』と総称されている。ALGAE CLUSTERへの予算投下総額は約 30.4百万ユーロ (日本円換算3,956百万円相当、1ユーロ= 130円とする)であった。以下にALGAE CLUSTERを含めた、EUでの燃料関連プロジェクトについて説明していく。 微細藻類燃料に関するEUグラント一覧表/筆者作成 1)SOLARH2:European Solar-Fuel...

欧州における藻類研究の動向
前回までに日本、米国での微細藻類研究の動向を国の予算面から見てまとめてきた。今回から数回に渡ってEUの微細藻類研究の動向を同様な視点から見ていきたいと思う。米国の動向はなんとなくチェックしているけどEUまではなかなか、という方々も多いと思うので参考にしていただければと思う。私も自分で調べながら日本や米国とは異なる戦略で進めているEUの開発動向を知ることができて勉強になった(調べるの大変だったけど、、)。今回はEUでの微細藻類研究の歴史と研究政策の枠組みといったところについて記す。 EUにおける微細藻類研究の歴史 EUの微細藻類研究に対する歴史は長い。1890年にオランダの微生物学者であるバイエリング博士によってクロレラが発見され、その後ドイツが第一次世界大戦時にタンパク質源としてクロレラの培養研究を行っていた。その後、一旦落ち着きを見せたが、第二次世界大戦後の1940年代終わりから世界人口が飛躍的に伸び、1950年代に25億人に届いた際には、小麦や米不足への懸念から食糧源としての微細藻類研究(特にクロレラ)に再び注目が集まった。結局、この食糧危機への不安は「緑の革命」によって落ち着きを見せ、それに伴う形で微細藻類研究に対する注目もトーンダウンしていった。 このようにEUの微細藻類研究の歴史は長いが、食糧危機からくるトリガーが強く、米国のように燃料生産を大々的にうたった研究開発は特に行われてこなかった。しかし、2008年からの米国での微細藻類燃料開発の盛り上がりを受けて、EUでも微細藻類燃料開発に大規模な予算が投入され、それにともなって再び微細藻類研究が活発になってきている。 微細藻類燃料研究から見るEUの研究政策 EUの微細藻類燃料研究は、欧州委員会によって管理される研究開発用の枠組みプログラムによって進められている。枠組みプログラムとは、複数年の研究開発・イノベーションプログラムの方向性を示し、それに基づいて資金配分を行う仕組みである。現在進行中の枠組みプログラムは、2014年から2020年までをカバーする『HORIZON2020』となる。 微細藻類研究から見るEU研究予算の流れEUの場合は、欧州委員会主導で枠組みプログラムが作られ、その中から微細藻類関連の予算が出される仕組みとなっている。このため、省庁間の枠組みによる住み分けはなく、プロジェクト単位で研究費が投下される。 EUでは温暖化対策としてバイオ燃料の使用を促進するため2009年に「再生可能エネルギー指令(RED:Renewable Energy Directive)」を定め、輸送用燃料に混合するバイオ燃料の割合を2020年までに10%以上にする義務的目標を設定している。微細藻類燃料は先進型(第二次世代)の非食用作物由来の輸送バイオ燃料としてカテゴリーされているため、微細藻類燃料研究に関しては、再生エネルギー指令の目標に準ずるように進められている。 REDは頻繁に改正されているが、最近ではパリ協定に基づくGHG(Green House Gas)排出削減目標を踏まえて2016年11月に改正提案が行われている。バイオ燃料に関する変更部分は以下の通り。 再生可能エネルギー指令の現行指令と改正案との比較 参考:平成28年度石油産業体制等調査研究 (バイオ燃料を中心とした我が国の燃料政策のあり方に関する調査)(バイオジェット燃料関連) 報告書/ 2017年3月 三菱総合研究所 輸送バイオ燃料の例 参考:EUにおけるバイオ燃料政策 農水省 本改正案によると食用作物由来の第一次世代のバイオ燃料の割合を下げていき、微細藻類燃料も含まれる先進型(第二次世代)のバイオ燃料は導入率を引き上げていく方針が見てとれる。
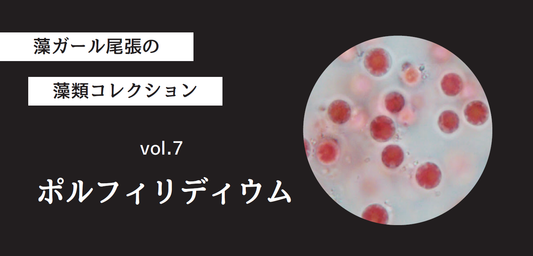
藻ガール尾張の藻類コレクション vol.7「ポルフィリディウム」
日本ではまだ知名度は低いですが、世界的には硫酸化多糖や不飽和脂肪酸を生産する藻類として注目されている藻類です。 ●学名:porphyridium purpureum 和名チノリモ●分類:真核生物>アーケプラスチダ>紅藻●生息:日本を含め、世界中に分布。●体長/形態:直径約10 µlの単細胞球状藻類。細胞中央部に鮮赤色のフィコエリスリンを主成分とする星状葉緑体をもつ。細胞外に寒天質をまとっているため細胞同士が接着して大きな群体を形成することがある。●レア度:★★★☆☆ 『ポルフィリディウム』という海産藻類は、和名が「チノリモ」、漢字では「血糊藻」と書きます。なんとも生々しいグロテスクな名前をもちますが、顕微鏡で観察すると赤くてかわいらしい色の丸い藻類です。 ポルフィリディウムは野外でも肉眼で観察できます。赤色〜赤褐色で、ぬるぬるのっぺりとしたマットを形成するその様子は、和名「チノリモ」のとおり、まさしく「血糊」です。 自生しているポルフィリディウムの様子:Gaikwad et al. 2009 ポルフィリディウムの細胞が赤系の色をしているのは、光合成色素にフィコビリン系色素のピンク色のフィコエリスリンが含まれているからです。同じ赤系でも、アスタキサンチンなどのカロテノイド系色素とは全く異なる色素です。細胞の増殖時には盛んに葉緑体で光合成するためフィコエリスリンが多く、細胞はきれいな鮮赤色です。しかし増殖を止めると葉緑体が収縮してフィコエリスリンも少なくなり、細胞は赤褐色になってしまいます。代わりに、細胞内に健康食品用途で利用される不飽和脂肪酸のDHAやEPAを蓄積し始めることが知られています。(ポルフィリディウムの脂質に関しては、記事『【藻の基礎知識】脂質分野における藻類の利用』もご参照ください。) また、ポルフィリディウムのぬるぬるの正体は多糖質です。寒天(=アガロースという多糖が主成分)の原料で知られるテングサと同じ紅藻の一種であり、細胞外に大量の多糖を分泌します。この多糖により細胞同士が接着し、地面や岩にのっぺりと広がります。乾燥や直射日光からこの多糖が保護してくれるおかげでポルフィリディウムは増殖できるのです。ポルフィリディウムの生成する多糖はこの性質から化粧品に利用されています。 ポルフィリディウム’porphyridium’ の語源は、ギリシャ語で紫’porphyra’に似ている’idion’という意味で、この言葉からは赤紫の藻類かな?ということしかわかりません。一方で和名チノリモ’血糊藻’は、赤色と多糖の性質をよく表した名前です。よくぞこんな大胆な和名をつけてくれたと、昔の日本の藻類学者を誇らしく思います! 海でのサンプリング中、ボートで休憩している筆者 参考資料Gaikwad, M. S., Meshram, B. G., & Chaugule, B. B. (2009). On occurrence of the...

日本の藻類燃料以外の研究の変遷
先日、日本国内における藻類研究の動向(2018年3月現在)についてご紹介した。 Modia[藻ディア] 国内における藻類研究の動向(2018年3月現在) https://modia.chitose-bio.com/articles/56 最近は藻ガール尾張のマニアックな紀行記事に押され気味で、私の記事の存在感低下が著しい。それはそれでいいことなのだが、そもそも私の記事と藻ガールの記事の何が違うのだろうか、ってところを色々な角度から考えた結果、『藻に対する愛の差』ってことに行き着いた。よっしゃ、じゃあ俺も負けずに藻への愛に溢れる記事を書いたろうじゃないの!ということで、緊急企画『現時点で国からの研究予算の交付を受けて進めらている藻類関連の研究についてのまとめ』をお届けしたい。すいません、やっぱ愛より金っすわ。国内の藻類研究予算... また、3回にわたるシリーズで日本の藻類燃料研究の変遷についてもご紹介した。 Modia[藻ディア] 日本の藻類燃料研究の変遷 part.1 (2009~2010年度) https://modia.chitose-bio.com/articles/58 先日、2018年3月時点で国の予算を受けて進行中の藻類研究を記事にまとめた。この記事では、2018年3月時点で走っている藻類研究を大小全て並べてみたが、今回は過去も含めて「藻類燃料」に関連する予算で動いているプロジェクトに焦点を当てて調べてみた。 米国での藻類研究への注目が集まった2008年前後から、国内の主だったプロジェクトを調べてみたところ、燃料関連ではこれまでに60以上のプロジェクトが行われていることがわかった(現在進行中も含む)。 今回から3回に渡り、2009年度から現在までの『日本の藻類燃料研究の変遷』... Modia[藻ディア] 日本の藻類燃料研究の変遷 part.2 (2011年度) https://modia.chitose-bio.com/articles/60 前回 part. 1では、日本の藻類燃料研究の流れと、2009~2010年度に開始されたプロジェクトを紹介した。今回 part. 2では2011年度に開始されたプロジェクトNo.23〜39の詳細を記す。なお、一覧表および次項にある各プロジェクトの説明に記載した金額は、各事業の募集時点の予算規模(最大額)を記している。微細藻類燃料に関する国内助成金一覧表/筆者作成2011年度当時は、藻類が急速に注目を集める中、最終目標に燃料を設定しながら、多様な研究が行われていた。多様な藻類脂質原料の燃料化研究、バイオ燃料化プロセスの中の特定プロセ... Modia[藻ディア] 日本の藻類燃料研究の変遷 part.3 (2012~2017年度) https://modia.chitose-bio.com/articles/61 part.1、 part.2では、2009~2011年度採択の藻類燃料研究分野助成金プロジェクトを紹介した。最終回...

藻類ファサードで覆われた夢の塔
米中貿易摩擦が激化する一方で、フランスと中国は両国関係の一層の強化を図り幅広い協力関係を構築している。例えば環境問題において両国は、気候変動対策、持続可能な都市開発、水の安全保障の3つの目標を設定し、国際協力と革新により経済基盤の確立に取り組んでいる。 その戦略的パートナーシップの一環として、先月中国の杭州で文化・自然、および最先端のブロックチェーン技術が融合する「フレンチドリームタワー(FrenchDreamTowers)」と名づけられたスマートビルの建築プロジェクトが開始された。 中国六大古都の一つである杭州市に位置する西湖は、「杭州西湖の文化的景観」として世界遺産に登録されており、中国では「上に天堂天国があり、下に蘇州杭州がある(上有天堂,下有蘇杭)」ということわざがあるほど最も有名な観光地の一つとして知られている。広々とした湖畔およびその周辺に点在している石橋、寺院、庭園、遊歩道などは「人間と自然の理想的な融合」を表し、自然環境に恵まれた美しく魅力的なその景色は、昔から多くの文人や芸術家にも好まれている。 現在、フランス・パリに事務所を置くXTU Architects建築設計事務所とフランスÎle-de地域の支援を受けているビジネスクラスターのSystematic、および中国の開発業者は、西湖の湖畔に自然景観との調和がとれた、省エネで環境に優しい「夢の塔」を立てる建築計画を進めている。 高さの異なる4基のタワーが相互に繋がって構成されるフレンチドリームタワーは、中国とフランス両国の歴史や文化をデザイン要素に取り入れている。 China And France Build On Relations With New Eco-Tower As the United States engages in a with China, French-Chinese relations are proving more and...
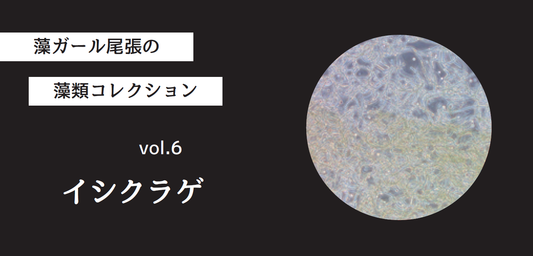
藻ガール尾張の藻類コレクション vol.6「イシクラゲ」
先日、乾燥耐性と料理方法を紹介したイシクラゲ(詳しくはModia記事の『藻ガール尾張のわくわく藻探し -道端で発見!つかめる微細藻類「イシクラゲ」』をご覧ください)。今回の記事では宇宙との意外な関係をお伝えします。 ●学名:Nostoc sp.(Nostoc commune)●分類:原核生物>真正細菌>シアノバクテリア●生息:日本を含め、世界中に分布。●体長/形態:トリコームといわれる球状の細胞が数珠状に繋がっている細胞群を形成する。多量の細胞外多糖によりトリコーム同士が付着して塊となる。野外では、雨水等で膨潤すると握りこぶしほどの黒褐色の柔らかい塊になる。乾燥すると黒色で平な海苔のような板状になる。●レア度:★☆☆☆☆ イシクラゲが分泌する細胞外多糖には、保水能力、強光阻害から細胞を守る抗酸化機能、日焼け止め機能があることが明らかにされています。加えて、極度に過酷な環境、例えばガンマ線、紫外線、重粒子線、高温(100℃)環境への耐性があることも示されています。 現在、NASAやJAXAなどの世界14機関で構成される国際宇宙探査共同グループが作成する国際宇宙探索ロードマップでは、火星の宇宙農業構想が提唱されています。そのなかで、火星の栄養のない無機物土・レゴリスを野菜が育てられる有機土壌にするために、保水力が高く、強光に強く、酸素を生成でき、食材にできるイシクラゲは最適です。つまり、宇宙農業の立役者としてこれ以上ない生物なのです。 イシクラゲが含まれるシアノバクテリアは、30億年前に酸素を作り出した地球の開拓生物として重要な役割を果たしました。そして今度は地球を飛び出して、新天地ならぬ新天星で大活躍するかもしれません。実際に、2006年、イシクラゲは国際宇宙ステーションに持ち込まれています。 今回は地球を飛び出し、宇宙レベルで藻類のお話をしました。私たちにとっては非常に遠い未来の話だと思いますが、藻類の活躍の場が無限に広がっていることを知っていただけると嬉しいです! 掌のイシクラゲに宇宙を感じる筆者 参考資料Katoh, H., Furukawa, J., Tomita-Yokotani, K., & Nishi, Y. (2012). Isolation and purification of an axenic diazotrophic drought-tolerant cyanobacterium,...

米国の藻類燃料研究の変遷 part. 2 (2015-2017年度)
前回 part. 1では、米国の藻類燃料研究の流れと、2009~2014年度に開始されたプロジェクトを紹介した。 Modia[藻ディア] 米国の藻類燃料研究の変遷 part. 1 (2009~2014年度) https://modia.chitose-bio.com/articles/67 先日、3回に渡り2009年度から現在までの『日本の藻類燃料研究の変遷』についてまとめた。2010年、2016年の微細藻類研究ロードマップに基づき、米国の予算下で進められた(現在進行中も含む)主だったプロジェクトは全41にのぼる。各プロジェクトの概要を以下に紹介していく。微細藻類燃料に関する米国グラント一覧表(2009〜2018)/筆者作成今回 part.1では2009年度~2014年度に開始されたプロジェクトNo.1〜21の詳細を記す。2009年度採択の助成金1)Demonstrate the technical and economic feasibility of an algae-to-drop-in green ... 今回 part. 2では2015年度から開始されたプロジェクトNo.22〜41の詳細を記す。 微細藻類燃料に関する米国グラント一覧表(2009〜2018)/筆者作成 2015年度採択の助成金 22)Microalgae Commodities from...

中国でスピルリナ火鍋が起こす緑の革命
台湾出身の私は、冬はもちろんのこと夏でも一時帰国をする時には、どんなに暑くとも毎回必ず麻辣火鍋(中華圏全体で広く食される辛味の強い鍋料理の一つ)を食べる。 台湾の麻辣火鍋は、中央を太極の陰陽に見立てて仕切った金属製の丸鍋に、辛い紅湯スープとマイルドな白湯スープの2種類を別々に入れて煮立て、好みのスープの方に好きな食材を入れて食べる「鴛鴦火鍋(おしどりひなべ)」と呼ばれる形式が特徴的だ。一度に味の違う2種類のスープを楽しむことが出来るのが、鴛鴦火鍋の醍醐味である。 台湾に行かずとも、日本で台湾と同じ味を楽しみたい方におすすめしたいのが、日本に直営店舗がある天香回味[テンシャンフェイウェイ]という薬膳火鍋専門店である。60種類以上の漢方薬と香辛料で作った秘伝のスープの深み、優しさと複雑さを是非一度味わってみてほしい。 さて、鴛鴦火鍋といえば一般的には赤白の2色鍋をイメージするものだが、なんと、近年中国では常識の枠を超える緑白の2色鍋が出現したそうだ。そして、その緑色のスープの正体こそがスピルリナである。 緑色の火鍋を最初に開発したのは、四川に本店がある魚游天下というスピルリナの火鍋専門店のようだ(中国の発明特許番号:200810093149.3)。魚游天下はスピルリナを健康のテーマとし、魚を中心とした栄養バランスの良い健康的な食事を提供する飲食チェーン店である。中国雲南省で生産したスピルリナを使用し、中国人に馴染みの深い火鍋に取り入れることでスピルリナを食文化として普及させようとしている。 新たな食材を普及させるための戦略として、全く新しい食習慣を身につけさせる方法もあれば、地域ならではの食文化に合わせ、日々の食生活に徐々に浸透させていく方法もある。スピルリナを火鍋に取り入れて美味しく食べる方法は、世界最大のスピルリナ生産国でもあり、火鍋という食文化が広く浸透している中国ならではのアイデアだと思う。 私自身はこのスピルリナ火鍋をまだ食べたことはないのだが、美味しいと評判は上々らしい。魚游天下以外の飲食店でも今後続々と提供されるであろうスピルリナ火鍋によって、火鍋業界に緑の革命が起こることを期待している。 参考資料http://www.cy8.com.cn/pinpai/589http://news.21food.cn/6/925741.html
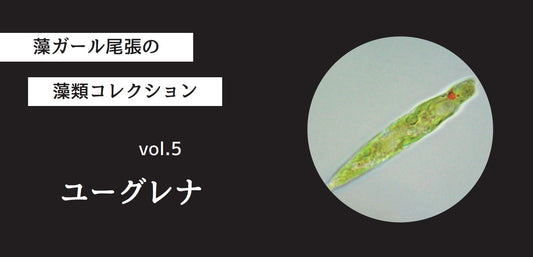
藻ガール尾張の藻類コレクション vol.5「ユーグレナ」
Euglena gracilisは、近年日本で『ユーグレナ』と呼ばれている話題の健康素材ですが、育て方ひとつで姿形が全く異なる生き物になることをご存じでしょうか? ●学名:Euglena gracilis●分類:真核生物>エクスカバータ>ユーグレナ藻綱>ユーグレナ目>ユーグレナ属●生息:日本を含めアジア、ヨーロッパ、アメリカなど世界中に生息。●体長/形態:約50 µmの緑色の細長い細胞。細胞内には、貯蔵物質のパラミロンと言われる無色の顆粒が複数存在している。一本の鞭毛をもち、細長い形態のまま遊泳する他に、「ユーグレナ運動」もしくは「すじりもじり運動」という変形運動を行う。●レア度:★★☆☆☆ ユーグレナ(Euglena gracilis)は緑色の小さな葉緑体を複数もち、光と二酸化炭素、水を利用して、無機培地(主に無機化合物が溶け込んでいて、エサとなるような有機物が入っていない培地)で光合成をする独立栄養生物です(詳しくはModia記事の『藻はどうやって生きているのか?-独立栄養と従属栄養の違い-』をご覧ください)。 ユーグレナの緑色は、主に葉緑体に含まれる葉緑素(クロロフィル)によるものです。その緑色のユーグレナを、暗所で有機培地(無機化合物の他に、多量のブドウ糖、酢酸などエサとなる有機物が多量に溶け込んでいる培地)を使って培養すると、光合成をせずに従属栄養生物として生活し始めます。 このように、ユーグレナは光合成をしなくても生きることができますが、3週間ほどで葉緑体は退化してしまい、プロプラスチド(proplastid)という無色の色素体を含む葉緑体になってしまいます。しかし、この無色のユーグレナを、明所で無機培養に戻して培養すると、プロプラスチドは再びクロロフィルを合成して緑色の葉緑体に戻ります(Schiff & Schwartzbach,1982)。 また、緑色のユーグレナを32~35℃の高温条件下、あるいはストレプトマイシンなどの抗生物質を含む培地で培養しても、葉緑体をもたないユーグレナが得られます。しかし、暗所での培養の時とは異なり、この無色のユーグレナでは細胞中の葉緑体退色型のプロプラスチドが消失しています。 葉緑体はとても複雑な機構をもっていて、真核生物の藻類は自力では復元できない細胞内小器官です(詳しくはModia記事の『一次共生とは? -藻類の起源-』『二次共生とは?-藻類多様性の謎-』をご覧ください)。そのため、細胞中の葉緑体退色型のプロプラスチドが消失してしまった無色ユーグレナは、もとの培養条件に移しても葉緑体を再生することができず、緑色ユーグレナには戻りません(Leedale 1967)。 このようにユーグレナ目の葉緑体は繊細なため、進化の過程で自然に葉緑体が消失した無色ユーグレナも存在します。それがユーグレナ目アスタシア属(Astashia)です(下記写真)。 姿形はユーグレナに似ていますが、葉緑体を持たないため無色透明です。アスタシアの遺伝子の組成を調べた結果から、かつてアスタシアは葉緑体を持っていたと考えられていますが、現在のアスタシアにはプロプラスチドは存在していません。 健康食品として売られているユーグレナ(Euglena gracilis)も、緑色ユーグレナ(株式会社ユーグレナ製造)と無色ユーグレナ(株式会社神鋼環境ソリューション製造)の二種類があります。このように藻の様々な特徴を活かした商品が世に出ることを、藻ガール尾張は心から嬉しく思います! 雨ニモマケズ。風ニモマケズ。サンプリングを楽しむ筆者。 参考資料Schiff, J. A., & Schwartzbach, S. D. (1982). Photocontrol of...

米国の藻類燃料研究の変遷 part. 1 (2009~2014年度)
先日、3回に渡り2009年度から現在までの『日本の藻類燃料研究の変遷』についてまとめた。 Modia[藻ディア] 日本の藻類燃料研究の変遷 part.1 (2009~2010年度) https://modia.chitose-bio.com/articles/58 先日、2018年3月時点で国の予算を受けて進行中の藻類研究を記事にまとめた。この記事では、2018年3月時点で走っている藻類研究を大小全て並べてみたが、今回は過去も含めて「藻類燃料」に関連する予算で動いているプロジェクトに焦点を当てて調べてみた。 米国での藻類研究への注目が集まった2008年前後から、国内の主だったプロジェクトを調べてみたところ、燃料関連ではこれまでに60以上のプロジェクトが行われていることがわかった(現在進行中も含む)。 今回から3回に渡り、2009年度から現在までの『日本の藻類燃料研究の変遷』... Modia[藻ディア] 日本の藻類燃料研究の変遷 part.2 (2011年度) https://modia.chitose-bio.com/articles/60 前回 part. 1では、日本の藻類燃料研究の流れと、2009~2010年度に開始されたプロジェクトを紹介した。今回 part. 2では2011年度に開始されたプロジェクトNo.23〜39の詳細を記す。なお、一覧表および次項にある各プロジェクトの説明に記載した金額は、各事業の募集時点の予算規模(最大額)を記している。微細藻類燃料に関する国内助成金一覧表/筆者作成2011年度当時は、藻類が急速に注目を集める中、最終目標に燃料を設定しながら、多様な研究が行われていた。多様な藻類脂質原料の燃料化研究、バイオ燃料化プロセスの中の特定プロセ... Modia[藻ディア] 日本の藻類燃料研究の変遷 part.3 (2012~2017年度) https://modia.chitose-bio.com/articles/61 part.1、 part.2では、2009~2011年度採択の藻類燃料研究分野助成金プロジェクトを紹介した。最終回 part.3では2012年度から2017年度に開始されたプロジェクトNo.40〜62の詳細を記す。なお、一覧表および次項にある各プロジェクトの説明に記載した金額は、各事業の募集時点の予算規模(最大額)を記している。微細藻類燃料に関する国内助成金一覧表/筆者作成2012年度以降の藻類燃料研究分野助成金プロジェクトの件数は減少しているものの、1件当たりの助成金額は大きく、プレイヤーが集約傾向にあるといえる。研究内容としては、低コス... 2010年、2016年の微細藻類研究ロードマップに基づき、米国の予算下で進められた(現在進行中も含む)主だったプロジェクトは全41にのぼる。各プロジェクトの概要を以下に紹介していく。 微細藻類燃料に関する米国グラント一覧表(2009〜2018)/筆者作成 今回 part.1では2009年度~2014年度に開始されたプロジェクトNo.1〜21の詳細を記す。...

藻が彩る光の森
2018年5月25日から6月16日までの23日間、オーストラリアのシドニーで「ビビッド・シドニー(Vivid Sydney)」という祭典が開催された。今年で10年目を迎えたビビッド・シドニーは、毎年5月に南半球の冬の到来と共に始まる世界最大級の光と音楽とアイデアの祭典であり、光の「ビビッド・ライト」、音楽の「ビビッド・ミュージック」、アイデアの「ビビッド・アイデア」の3つのセクションから成る。今年はこれまで以上に充実したプログラムで、開催期間中はシドニーの街全体が華やかに彩られた。 光の「ビビッド・ライト」では、LEDライトやプロジェクションマッピングなどでオペラハウスやハーバーブリッジなどをメインに、街中の様々な場所がカラフルにライトアップされる。今回、リビングライトというテーマの作品で初めて藻類が取り入れられ、ビビッド・ライト展示の一環として中心的な役割を果たしていた。 リビングライトは最大2.5mまでの高さが異なる18基のリアクターから構成されており、各リアクターの中ではそれぞれ異なる藻類が培養されていた。そのリアクターを明るいLEDライトで下から照らし、藻類の赤色や金色、蛍光緑色などの色合いを強調させることで、生き生きと呼吸する藻類で作られた光の森が訪れる人々を歓迎するという概念を表現した。また、リビングライトには”The Nucleus”という特別な装置があり、来場した参観者が 装置の中に手を入れ、その手を振ることで光の色や強度をコントロールすることができるインタラクティブな仕掛けもあった。 Living Lights Artists:University of Technology, Sydney: Peter Ralph (Australia) / Lochlan de Beyer (Australia) / Leo Hardtke (Australia) Living Lights is a 'forest' made...

米国の藻類研究から見えてきた課題
先日こちらの記事でも触れたが、米国で2010年から2016年までに行われた藻類研究の結果から明らかとなった各要素技術に対する課題が『National Algal Biofuel Technology Review』にまとめられている。このレビューでは研究課題を3つの大きな分野(原料生産、変換、社会基盤)に分類し、各分野の中で工程順に区切って課題を整理している。 米国はこのような体系立った課題の整理と共有の仕組みが非常にうまい。この整理と共有によって、多くの藻類研究者が各工程に現在どういった課題があるのかが把握でき、新しいアイデアや技術をもっている研究者が参入できるようになるのだ。このような仕組みについては日本も積極的に見習いたいところである。 今回は米国でまとめられた課題について、各分野の工程ごとに紹介していきたい。 原料生産分野(バイオマス生産) 藻類生物学 ・藻類基礎生物学のさらなる理解。・全既知種における藻類データベースの構築(種、タンパク質、遺伝子、発現遺伝子)。・データベースのオープンアクセス化、研究者間のデータ共有化、研究トレンドの共有化。・有望生産株への外来遺伝子発現のための分子生物学的手法の開発。・屋外池生産管理に関する理解(生態系構築、捕食者把握、クラッシュ現象解明など)。・遺伝子組み換えに対する安全性対策、管理体制のさらなる理解。 微細藻類培養 ・培養動態、培養安定性のさらなる理解(作物保護、栄養添加、栄養制限など)。・ベンチスケールから実証へのスケールアップ化時のデータ相関性についての改良。・生産性解析における測定基準の統一。・藻体生産にかかる持続性及び資源経済性の理解(水資源、栄養素、各再利用など)。・工業レベルでの二酸化炭素利用するためのさらなる理解。 収穫・脱水 ・工業レベルでの収穫、脱水、乾燥技術の開発。・工業レベルでの収穫、脱水技術の経済合理性、必要エネルギー量、環境持続性の確認。・長期間稼働を踏まえた上でのパフォーマンスの有効性の確認。・収穫、脱水の影響について種特異的な効果のさらなる理解。 変換分野(燃料化) 抽出・分離 ・抽出技術を工業スケールにした時の経済性とシステムに与えるインパクトの調査。・最終生産物に対する原料組成の影響の調査。・工業スケールにおける既存及び新抽出技術の比較試験。・大規模スケールアップした時の水管理、副次反応、作業温度、圧力などの影響チェック。 燃料変換 ・工業スケールでの最適変換効率の探索。・工業スケールでの燃料回収率の最適化。・すべてのスケール段階における燃料会得率の確認。・工業スケールにおける既存及び新抽出技術の比較試験。・工業スケールでの全行程の変換エネルギー、排ガス量、夾雑物の最小化に関する試験。・種特異的な変換技術、変換制限に対するさらなる理解。 残渣 ・残渣からの高付加価値物質の同定と評価(飼料、肥料、バイオプラ、界面活性剤など)。・残渣からの有価物の抽出と回収技術の最適化。・応用開発を進めるための、質と安全面からの試験を含んだ市場調査。 社会基盤分野(インフラ整備) 物流と燃料利用 ・藻類バイオマス、中間物質、燃料、派生商品に対する貯蔵や運搬方法。安定性などの把握。・工場設置場所に合わせた物流エネルギーやコストの最適化・規制及び消費者からの利用条件の遵守(例:エンジンパオーマンスや燃料適合性など) 資源と場所 ・資源循環性を含む、藻類バイオマス生産に影響する種々の要因を統合させたモデルの作成。・資源の特徴及び要求性をシュミレーションするための手段と解析技術の標準化。・二酸化炭素固定と微細藻類バイオマス生産に関する調査。・塩濃度バランス、エネルギーバランス、水、栄養素のリサイクル、温度管理に関する調査。・二酸化炭素排出及び排水処理プラントと微細藻類生産施設の併設に関するさらなる理解。 これら課題の抽出と整理に合わせて、得られた知見を踏まえた新しい工程モデルとロードマップが作成されている。2010年ロードマップと比較して、乾燥工程が簡略化され、各項目で目指すべき目標数値が具体的に設定されているのが特徴である。 新しいモデル工程と要素技術(National Algal...
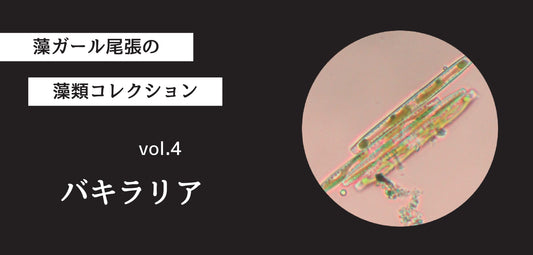
藻ガール尾張の藻類コレクション vol.4「バキラリア」
藻ガール尾張は池や沼があると、炎天下であっても暴風雨であっても、藻採取サンプリングせずにはいられません。今回は、少し前のお話しになりますがゴールデンウィークに見つけた、藻類界のスーパースター『バキラリア』を紹介します! ●学名:Bacillaria sp.●分類:真核生物>SAR>ストラメノパイル>ケイ藻●生息:日本を含め、世界中に分布。●体長/形態:長辺約100 µm の細長い四角形をしている細胞が、群体に連なっている。長軸方向に滑る滑走運動をすることが特徴。●レア度:★☆☆☆☆ ケイ藻は、「珪藻土」で知られるようにガラス質の殻をもっている藻類です。顕微鏡で観察すると、とても細かい模様が刻まれていて、まるでガラスの芸術品です。 バキラリアは、藻類の中でもとてもユニークな動きをします。下記の連続写真からわかるように、「南京玉すだれ」のようです。この動きは、「バキラリア・ダンス」と藻類マニアの中では言われていて、藻類屋さんの中では不朽の一発芸となっています。 尾張のフェイスブックでは、その動きを動画でもご紹介しています。是非一度ご覧ください! (動画が再生されない場合は、下記URLよりご覧ください↓)https://www.facebook.com/satomi.owari/posts/1792537824136734 ケイ藻は細胞内のアクチン、ミオシン、そして細胞外の粘液繊維(多糖)により1細胞で滑走運動をすることは知られています。しかし、バキラリアのこの連携された動きの生物学的な制御機構(細胞間の連携など)はわかっていません。また、この動きに数学的に解析を試みた研究も行われていますが、”カオス(chaotic、Ussing et al.2005)”と最後にまとめられているように、難解なようです。 採取サンプルにバキラリアがいると、誰しも思わず見惚れてしまいます。筆者も発見した時はバキラリアに夢中でした。 お気に入りスポット(千葉県手賀沼)で春のサンプリングを楽しむ筆者。(2018年5月。ここでバキラリアを見つけました) 晴れて気温も上がり過ごしやすかった今年のゴールデンウィーク。当時、池の水をすくって顕微鏡で観てみると冬から春への変化を垣間見ることが出来ました。藻類の密度は少ない中、バキラリアといったケイ藻の割合が多いのが春の特徴です。 冬は、池の底と表層の水温差がなくなるため対流が起こり、底に溜まっていた栄養塩は表層へと自然に舞い上がります。しかし、冬は水温が低いため藻類の増殖は抑制されており、種類も量も多くはありません。春になると気温も水温も上昇するため、比較的低温でも増殖できる藻類から増殖を開始します。そのトップバッターがケイ藻なのです。 今は夏真っ盛りです。暑さに強い藻類相に変化しています。みなさまも藻採取サンプリングに繰り出してみてはいかがでしょう?くれぐれも、熱中症にはご注意下さいね。 参考資料Ussing, A. P., Gordon, R., Ector, L., Buczkó, K., & VanLandingham, S. L....

藻類と時間
最近は日本や世界のグラント情報など、少し堅い記事ばかりなので、たまにはコラム的なところを書きたいと思う。最近、循環の時間について思うことがあったので、今回は時間軸でみた藻類について考察してみたい。 以下の図は人類が食べてる農作物であったり、使ったりしているエネルギーの循環サイクルを時間軸ごとに大まかに分類したものである。例えば、葉物野菜は定植されてから出荷されるまで早い物では1ヶ月単位で回っている。米のような穀物は日本だと1毛作なので、1年に1回転としよう。一方、樹木だと芽生えてから成木になって利用されるまで10年はかかるだろう。そして我々が日頃使っているエネルギーは、化石資源からきているので、億年単位のサイクルでまわっているものと言えよう。なお、全ての循環の源は太陽エネルギーであることは言うまでもない。 このように我々が日々利用している食料やエネルギーというのは、それぞれ異なる時間軸の循環に乗っている、ということがわかっていただけると思う。人類はこれらの循環時間をうまくミックスをしながら生活を、さらには文化を作り上げてきたわけである。 食料源・エネルギー源の時間サイクルの違い(筆者作成) さて、上の循環時間の分類図の中に、日単位の循環がないことにお気づきだろうか。私も整理してて驚いたのだが、意外にも人類は『日単位の循環』というのをこれまで持っていなかったのだ。牛乳とか卵とかあるじゃん、という意見もあるかと思うが、これらは鶏や牛を介して餌が変換されているものなので、ちょっと違う。餌まで遡って見れば野菜(月)や穀物(年)の時間軸に依存しているものといえよう。 そこでジャーン、我らの藻類の登場である。藻は早いものだと1日単位で倍に増えていくため、日単位の循環を作ることができるのだ。先ほどの図でいくと以下の様な位置にスポッとハマるのである。 藻類の時間サイクル(筆者作成) この話だけ聞くと『ふ〜ん、そうなんだ』で終わられてしまいそうだが、これって結構革命的な話なのではないかと私は考えている。 大昔、狩猟が生活の基盤であたっとき、人類は森や平原、海などに生息する動物や魚を狩り、生活の糧を得てきたとされている。この場合、一つの地に定住せずに、小集団で移動しながら偶然性に依存する暮らし方をしていたわけだ。そんな中、1万5,000年ぐらい前に農業が発生したと言われているが、そこから人類は月、年、10年という単位の循環を計画的に組み合わせながら、定住生活を生み出してきたわけだ。農業の発生により人類の生活様式や文化が大きく変わったことに異論を唱える人はいないだろう。 また、人類は200年ほど前の産業革命によって、今度は化石資源という億年単位のとんでもなく大きな循環を使うようになった。この産業革命によって、また人類の生活は大きく変わったわけであり、この変化に対しても異議を唱える人は少ないかと思う。 こうして振り返ってみると、新しい時間軸の循環の登場のたびに人類の生活様式や文化が劇的に変化しているように見えてこないだろうか。そういった視点から見たときに、今生まれつつある『日単位の藻類』という新しい循環は、人類の生活様式を大きく変えていく潜在力があるんじゃないかと思うのだ。 そんな風に循環の時間のことを考えると、そもそも生まれて死ぬまでが100年程度の人類が扱っていいのは、100年未満の循環なのかもな、なんてことをふと思ったりもする。億年単位の大きな循環がどんな動きをするか想像すらできない中で、寿命100年の生物がそれをうまく使いこなせる気がしないというか。。ただ、そんな大きな循環を使って生きている現代人だからこそ、藻類を使った新しい循環系を見出すことができたのかも、とも思う。考えてみれば億年単位の循環を作ってきたのは藻類なんだなぁ、、なんて思うと、この繋がりになんとも言えない妙を感じるのである。

スピルリナワクチンの可能性
大人も子供も関係なく、予防接種と聞くと鋭い注射針を思い出し、嫌がる人も多いのではないだろうか。園芸学科出身の私は、バナナなどを食べるだけで免疫を獲得できるようになることを大学時代からずっと期待してきた。 こうした夢のような期待に応えてくれるかもしれない研究が、健康食品でお馴染みの藻類「スピルリナ」で行われていることをご存知だろうか? ワクチンによる予防接種 ワクチンは感染症の原因となる細菌やウイルスを弱毒化させたもの、あるいは病原性を無毒化させ抗原性だけを残した特殊な薬液である。この薬液に含まれる抗原と呼ばれる生体に免疫応答を引き起こす物質に対して体内の免疫細胞が反応して抗体を産生する。抗体は抗原と特異的に結合することで抗原を体内から排除する免疫応答を起こし、私たちの体を感染症から守る。ワクチンを事前に接種することで、免疫細胞に投与した抗原分子の特徴を一度記憶させ、実際に病原体が生体内に入ってきた時には速やかに抗体が産生されて生体を防御するため、発症が抑えられるという仕組みである。 ワクチンの接種方法は、ほとんどが皮下注射や筋肉内注射だが、ポリオウイルスに対する経口ワクチンや、結核に対するBCG(Bacillus Calmette-Guerin)のようなスタンプ式で行うものもある。1990年代からは新しい経口型ワクチンとして、食べるワクチン(edible vaccine)が注目されてきた。これは、野菜や果物などの植物に遺伝子組み換え技術を応用することにより製造したワクチンである。植物は、種類によっては安価に栽培することができるため、ワクチンの製造コストを下げることができる。また、そのままの形で投与することができるため、痛い注射をする必要もなくなる。 食べるワクチンの研究開発 2017年にアリゾナ州立大学(Arizona State University)を退官したチャールズ・アーンツゼン(Charles Arntzen)教授は、食べるワクチン研究の第一人者として知られている。アーンツゼン教授の研究にインスパイアを与えたのは、1986年にアメリカで組み換DNAによるB型肝炎ワクチンが承認されたことだった。このワクチンは遺伝子組み換え技術を利用して、B型肝炎ウィルスの抗原遺伝子を酵母に組み込み、ウイルスに特異的な抗原性を示すタンパク分子だけをつくらせる方法で製造したものである。アーツゼン教授は酵母の代わりに植物に遺伝子組み換え技術を応用することで、安価な経口型ワクチンを作ることができるのではないかと考え、複数の作物種に抗原の発現を試みようとした。 1992年、タイのバンコクを訪れたアーンツゼン教授は、泣きやまない我が子にバナナを与えてなだめる母親の姿を見て、加熱が不要で生食可能なバナナワクチンを思いついた。実用化を目指すため、当時バナナの遺伝子組み換え技術でリードしていた台湾大学園芸学科の教授のもとを訪れたと聞いている。しかし、遺伝子組み換えの果実植物を作るには最低3年間のサイクルが必要だった上に、バナナにおける抗原の発現レベルは低かった。そのため、残念ながら夢のバナナワクチンの開発は中止されたが、当時大きな話題となった。 食べる「スピルリナワクチン」の可能性 ヒト用の安全なワクチンを製造する場合、厳しい品質管理のもと、安定的に製品を供給することが第一要件である。組み換え植物を用いて食べるワクチンを製造する利点は、植物が安価に栽培できること、地産地消によって長距離の低温保存・輸送が不要であること、抽出・精製が不要であること、経口投与が可能であることなどが挙げられる。一方で、組み換えによる植物個体間の抗原発現量のばらつきや、抗原の安定性および免疫原性の変動が非常に大きいことが問題となる。何より、精製されていない場合、抗原の正確な投与量をどのように決めるのかが大きな課題となっている。 ここで登場するのが、健康食品でお馴染みの藻類「スピルリナ」である。原核単細胞生物であるスピルリナは増殖が速いため、研究に要する時間が果実食物(年単位)と比べて比較的短時間(日単位)で行えるので、遺伝子組み換え生物の作成を短時間で成功させられる可能性がある。さらに長年食用されてきた経験があるため、食べるワクチンの利点を保ちつつ遺伝子組換え植物を用いたワクチン開発におけるボトルネックを解消できるのではないだろうか? 2017年に米国ワシントン州シアトルに創立されたルーメン・バイオサイエンス社(Lumen Bioscience Inc.)は、スピルリナから医療、食品、化粧品など様々な分野で利用できるような産業付加価値の高いタンパク質分子などを工業生産する研究開発に注力している。2018年5月21日に同社は、独自のスピルリナベースのタンパク質発現プラットフォームを用いた超低コストの経口投与化型遺伝子組み換えマラリアワクチンの研究開発が、米国国立衛生研究所NIH(National Institute of Health)の助成金に採択されたことを発表した。 マラリアワクチンの実用化への課題 世界保健機関(WHO)の世界マラリアレポート2016によると、マラリアは結核、エイズと並ぶ世界三大感染症のひとつであり、2015年には全世界で2億1200万人が感染し、そのうち42万9000人が死亡している。感染者の90%がアフリカ大陸に集中しており、全死亡者数の70%は5才以下の子どもと推定されているが、有効なワクチンの開発は未だ成功してない。現時点では唯一、英製薬大手のグラクソ・スミスクラインが30年間に渡る研究の末に開発したワクチン「Mosquirix™」が臨床試験段階にある。2017年4月24日、WHOは世界初のマラリアワクチンの実用化に向け、2018年からアフリカ3カ国(ガーナ、ケニア、マラウイ)で本格的なMosquirix™の試験投与を始めると発表した。 しかし、Mosquirix™は従来型のワクチンと同様に、製造段階から使用時まで低温で保存・輸送をしなければならず、製造コストが高いという課題が残っていた。また、医師や看護師など医療従事者による注射が必要となる。それに対し、ルーメン・バイオサイエンス社が開発したスピルリナをプラットフォームとした経口投与型遺伝子組み換えワクチンは室温での保存・輸送が可能であるため、用量当たりの製造コストを大幅に削減することができる。また、注射が不要なため医療従事者の動員も不要である。そのため、医療レベルの低い貧困地域へのワクチンの拡大普及を図ることができる。 ルーメン・バイオサイエンス社のスピルリナ研究への期待 2018年1月5日ルーメン・バイオサイエンス社は、発展途上国の子供達の命を奪っている下痢性疾患に対し、スピルリナプラットフォームを用いた経口投与型抗体を開発するため、ビル&メリンダ・ゲイツ財団(Bill & Melinda Gates...

米国における藻類研究の動向
先日、こちらの記事で国内の微細藻類研究動向について国家予算の視点からまとめてみた。国内を俯瞰した記事の後は、海外の動向も知りたい、ということで、今回から数回に分けて世界の微細藻類研究動向をまとめていきたい。 まず第1回目は米国の微細藻類研究の動向について過去の変遷も踏まえて書いていく。米国の場合は、「自国での燃料生産」に焦点を当てているのが特徴であり、微細藻類研究も燃料生産が軸となっている。 米国における微細藻類燃料研究開発の歴史 米国では1978年から1996年にエネルギー省が資金を出したプロジェクトAquatic Species Program-Biodiesel from Algae(ASP)で微細藻類からのバイオディーゼル(BDF)を生産する取り組みが大々的に進められたが、当時の原油価格と比較して経済的な優位性が認められないため中断された。 ASPの約20年間にわたる取り組みをまとめた報告書。300ページを超える報告書であり、こちらからダウンロードが可能。 一度は下火になった微細藻類由来の燃料開発であったが、2004年頃からの世界的な原油価格の高騰に加え、2007年に『エネルギー独立安全保障法 (EISA:Energy Independence and Security Act法)』が制定されたことをきっかけに、「微細藻類からの燃料生産構想」を掲げる複数のベンチャー企業が立ち上がった。 また、トウモロコシに代表される食用作物の燃料化に対する世間からの風当たりが強まっていた中、食料と競合せずに陸上植物よりも効率よくエネルギーを生産できるという新しいバイオマスエネルギーの話に多くの投資家やベンチャーキャピタル、事業会社からの資金が集まり、微細藻類研究は一躍脚光を浴びることとなった。 しかし、微細藻類燃料開発への活発な投資の背景にあった原油価格が急落。2014年前半まで1バレル=100ドルとなっていた原油価格が、2016年2月には一時26.05ドルまでに低下する展開になった。この原油価格の急落は、米国で起こった『シェール革命』が主な原因と言われている。このシェール革命による原油価格の低下にあわせるようにバイオマスエネルギーへの期待値も下がり、バブルのような状態にあった微細藻類燃料の研究開発に関しても熱気が冷めていった。かつてのような狂騒状態は落ち着き、米国での微細藻類燃料研究は終焉した、というような見方もあるようだが、決してそうではない。投資を集めるために目立つが勝ち、といった表面的な研究開発を行っていたプレイヤーは淘汰され、官主導のもとで本当に力のある大学、機関、企業が地に足を付けた研究開発を粛々と進めている。 米国の微細藻類燃料研究の体制 米国の微細藻類燃料研究は、官が主導で行われているのが特徴である。EISA法によってバイオ燃料使用が義務化された後、米国環境保護局(EPA: Environmental Protection Agency)が具体的な混合義務量の数値を2022年まで各年で設定したロードマップを作成している。この目標値は再生可能燃料基準 (RFS: Renewable Fuel Standards)として毎年更新された後、提示される。 2007年に設定されたRFS当初案 *バイオディーゼルのみ (ガロン ディーゼル相当/年)...
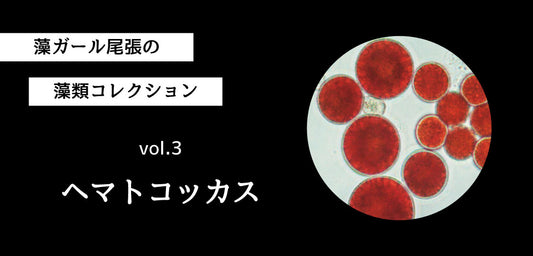
藻ガール尾張の藻類コレクション vol.3「ヘマトコッカス」
藻ガール尾張の藻類トリビア第3弾は、ヘマトコッカスのご紹介です。ヘマトコッカスという藻類は、アスタキサンチンを産生することでとても有名ですが、実は藻類の正式な名前(学名)がいまだに決まっていないという点においてはとても珍しい藻類です。 ●学名:Haematococcus lacustris (Gir.-Chantr.) Rostaf. (=Haematococcus pluvialis Flot.)●分類:真核生物>アーケプラスチダ>緑藻綱●生息:日本を含めアジア、ヨーロッパ、アフリカ、北アメリカなど世界中に生息●体長/形態:通常は約20 µmの緑色の卵型細胞で2本の鞭毛で動き回る。細胞の外側は寒天質に覆われている。細胞がストレスを感じると、アスタキサンチンを蓄積し、鞭毛消失し、形態は球状に変わる。●レア度:★☆☆☆☆ Modiaでも度々取り上げられている『ヘマトコッカス』。アスタキサンチンを産生することが知られています。 Modia[藻ディア] アスタキサンチンとは? -健康機能と市場の動向- https://modia.chitose-bio.com/articles/characteristics_of_astaxanthin 前回の記事では、ヘマトコッカスという藻類が赤色の抗酸化色素「アスタキサンチン」を蓄える特徴があることをお伝えしました。今回はそのアスタキサンチンを掘り下げていきます。アスタキサンチンは藻類の抽出物として国内外で産業化が進み、いま多くの注目を集めている物質です。1.アスタキサンチン(Astaxanthin)とは アスタキサンチンの骨格イソプレン(a)とアスタキサンチン(b)の構造式 / 筆者作成アスタキサンチンは、カロテノイドの一種キサントフィル類の脂溶性物質の赤橙色の色素で、化学式 はC40H52O4です。カロテノイドと... 2018年1月初出の記事『ヘマトコッカスとは?』では、ヘマトコッカスの名前について、「生物分類の学名はHaematococcus lacustris (Gir.-Chantr.) Rostaf. ですが、Haematococcus pluvialis Flot.として広く知られています」と、曖昧な表現をしてしまいました。 Modia[藻ディア] ヘマトコッカスとは? -生物学的特徴とアスタキサンチンの生産- https://modia.chitose-bio.com/articles/characteristics_of_haematococcus アスタキサンチンという赤色の抗酸化色素を蓄えることで有名な藻類「ヘマトコッカス」。数ある藻類種の中でも特に産業化が進んでいる、認知度の高い種です。本記事ではこのヘマトコッカスという藻について、紹介していきたいと思います。1.ヘマトコッカスとは? -生物学的特徴を中心に- 左図:藻類の系統樹、右上写真:ヘマトコッカスの通常時の様子、右下写真:ストレス下の様子 /...

日本の藻類燃料研究の変遷 part.3 (2012~2017年度)
part.1、 part.2では、2009~2011年度採択の藻類燃料研究分野助成金プロジェクトを紹介した。 Modia[藻ディア] 日本の藻類燃料研究の変遷 part.1 (2009~2010年度) https://modia.chitose-bio.com/articles/58 先日、2018年3月時点で国の予算を受けて進行中の藻類研究を記事にまとめた。この記事では、2018年3月時点で走っている藻類研究を大小全て並べてみたが、今回は過去も含めて「藻類燃料」に関連する予算で動いているプロジェクトに焦点を当てて調べてみた。 米国での藻類研究への注目が集まった2008年前後から、国内の主だったプロジェクトを調べてみたところ、燃料関連ではこれまでに60以上のプロジェクトが行われていることがわかった(現在進行中も含む)。 今回から3回に渡り、2009年度から現在までの『日本の藻類燃料研究の変遷』... Modia[藻ディア] 日本の藻類燃料研究の変遷 part.2 (2011年度) https://modia.chitose-bio.com/articles/60 前回 part. 1では、日本の藻類燃料研究の流れと、2009~2010年度に開始されたプロジェクトを紹介した。今回 part. 2では2011年度に開始されたプロジェクトNo.23〜39の詳細を記す。なお、一覧表および次項にある各プロジェクトの説明に記載した金額は、各事業の募集時点の予算規模(最大額)を記している。微細藻類燃料に関する国内助成金一覧表/筆者作成2011年度当時は、藻類が急速に注目を集める中、最終目標に燃料を設定しながら、多様な研究が行われていた。多様な藻類脂質原料の燃料化研究、バイオ燃料化プロセスの中の特定プロセ... 最終回 part.3では2012年度から2017年度に開始されたプロジェクトNo.40〜62の詳細を記す。なお、一覧表および次項にある各プロジェクトの説明に記載した金額は、各事業の募集時点の予算規模(最大額)を記している。 微細藻類燃料に関する国内助成金一覧表/筆者作成 2012年度以降の藻類燃料研究分野助成金プロジェクトの件数は減少しているものの、1件当たりの助成金額は大きく、プレイヤーが集約傾向にあるといえる。 研究内容としては、低コスト化の屋外培養試験研究に大きめの予算がついている。一方で、品種改良による機能向上藻類の作成に関する研究も目立ってきている。また、復興予算や海外支援予算からの藻類燃料研究も見られるようになった。 2012年度採択の助成金 40)微細藻類を利用した石油代替燃料等の製造技術の開発 【概要】農山漁村地域において燃料および飼料の製造が可能となるような技術を開発することを目指す。開発項目は以下の5項目。1.微細藻類の分離と品種改良 2.大量培養システムの開発 3.藻体回収技術の開発 4.油脂抽出技術の開発 5.抽出残渣の飼料としての利用(このうち、品種改良、大量培養、回収技術、燃料化技術については2012年度からNEDOの『油脂生産性の優れた微細藻類の育種・改良技術の研究開発』へと引き継がれた)。...
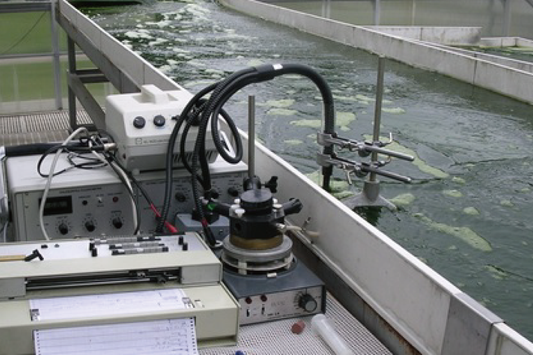
藻類クロロフィル蛍光を利用した光合成活性測定法 -生物学と物理学の融合:生物物理学(Biophysics)-
今月から新たに、Jose RomelがModia執筆者に加わりました!おしゃべり好きでアニメオタクのおじさんですが、世界の名だたる藻類研究室を渡り歩いてきた正真正銘の「藻類界のエリート」です。これまで抱いてきた藻類への熱い情熱を今後は社会に実装しようと思い、アカデミックから企業に場を移して、ちとせ研究所に入社しました。ちとせ研究所では約3年間マレーシアの藻類培養の最前線で活躍しています。今後のJoseの記事にもご期待ください! 写真:左;チェコ共和国の藻類研究室にて(Jose RomelとProf. Jiri Masojidek)。右;マレーシアのちとせ研究所・技術コンサルタント先(Sarawak Biodiversity Center)にて。 光合成とは、光エネルギー(例えば日光)と水を利用して、無機栄養分(例えば肥料)と二酸化炭素を、炭水化物(バイオマス量)と酸素へ変えるプロセスです。地球上の全ての生き物は、この光合成から得られる代謝産物に、直接または間接的に依存しています。 光合成による二酸化炭素や酸素の増減を測定する方法が、光合成活性の測定法として、古くから用いられています。この測定方法は高額な機器が必要な上、扱いが難しいことから、主に研究目的での利用に限定されます。 こうした中、近年、光学的な光合成活性の測定法が急速に発展しています。細胞が吸収した光エネルギーのうち、光合成に使われなかったエネルギーをクロロフィル蛍光として検出する方法です。現在では、安価とは言わないまでも手に届いやすい価格の、簡便なクロロフィル蛍光測定機器が開発されています。この光学的な測定方法は光合成活性の絶対量の測定には向いていませんが、モニタリングに適しており、植物生理学・生態学分野などで広く応用されています。 このクロロフィル蛍光による光合成活性測定方法について私が学んだのは修士課程を過ごしたイスラエルのネゲヴ・ベン=グリオン大学(Ben-Gurion University)でした。そしてイスラエルで学んだ技術を活かして、チェコ共和国のチェコ科学アカデミー・微生物学研究所(Institute of Microbiology of the Czech Academy of Sciences)では様々な藻類を用いて、また様々なフォトバイオリアクター(PBR)を用いてクロロフィル蛍光測定を行いました。 本記事では、光合成の仕組みと、クロロフィル蛍光でなぜ光合成活性が測定できるのかを説明します。 光合成の仕組み 光合成は、原核生物であるシアノバクテリアでは、細胞内のチラコイド膜上で、また真核生物の藻類と植物では葉緑体(チラコイドの集合体)内で行われます。以降は、真核生物における葉緑体での光合成について説明します。 光合成は、大きく2つの反応;光に依存する「明反応」と、光に依存しない生化学反応である「暗反応」に分けられます。これらの2つの反応は、一般的に空間的・時間的に切り離されています。 図1 葉緑体の光合成模式図 (Buchanan et al. 2000)...
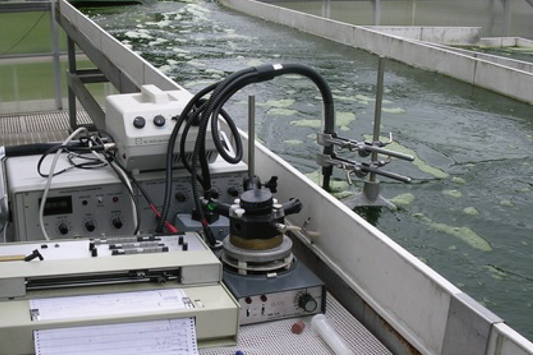
Biophysical Measurement of Algal Photosynthesis Utilizing Chlorophyll Fluorescence
※本記事の日本語訳記事もご覧ください!わかりやすい解説と筆者の紹介付きです。 Modia[藻ディア] 藻類クロロフィル蛍光を利用した光合成活性測定法 -生物学と物理学の融合:生物物... https://modia.chitose-bio.com/articles/biophysics_jap 今月から新たに、Jose RomelがModia執筆者に加わりました!おしゃべり好きでアニメオタクのおじさんですが、世界の名だたる藻類研究室を渡り歩いてきた正真正銘の「藻類界のエリート」です。これまで抱いてきた藻類への熱い情熱を今後は社会に実装しようと思い、アカデミックから企業に場を移して、ちとせ研究所に入社しました。ちとせ研究所では約3年間マレーシアの藻類培養の最前線で活躍しています。今後のJoseの記事にもご期待ください!写真:左;チェコ共和国の藻類研究室にて(Jose RomelとProf. Jiri Masojidek)。右;マレー... Keywords: photosynthesis, chlorophyll fluorescence, mass algal culture monitoring Photosynthesis is the process where light energy (e.g. sunlight) and water is...
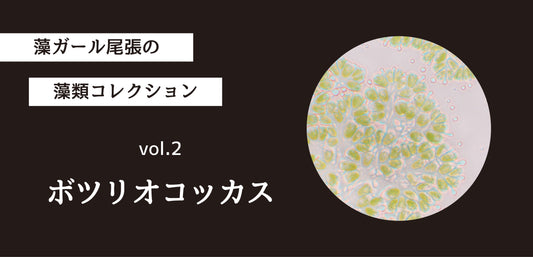
藻ガール尾張の藻類コレクション vol.2「ボツリオコッカス」
現在、様々なバイオマスを使ったバイオ燃料の研究が進められています。その中でも、石油を作る藻類と云われ、幅広く研究されている『ボツリオコッカス』は、藻類燃料研究の代表種です。 ●学名:Botryococcus braunii●分類:真核生物>アーケプラスチダ>緑藻・トレボキシア藻網●生息:日本を含めアジア、ヨーロッパ、アメリカなど世界中に生息。時折大量繁殖を起こすが、通常の水中密度は極めて低い。●体長/形態:単細胞は約10 µmの緑色の卵型細胞。数十個から数万個の細胞がブドウの房のように連なり、外側は細胞外マトリクスに包まれている。細胞内に油滴(重油相当の炭化水素)を作り分泌し、細胞外マトリクスに蓄積する性質がある。●レア度:★★★★☆ 現在使用されている天然資源の石油や天然ガスが、元々何から作られているかご存知ですか? 大昔に藻類や動物プランクトンの死骸が堆積したことが始まりです。この堆積層が長い年月をかけて熱や圧力を加えられ、地中深くで石油や天然ガスが含まれるオイルシェール層(油質頁岩層)へと変化しました。オイルシェール層の割れ目を通って、石油や天然ガスが溜まったところが、現在の油田やガス田となっています。 もちろん、石油や天然ガスとして出来上がったものは生物の形は残っていません。しかし、オイルシェール層には石油や天然ガスになる前の、プランクトンの状態が残っていることがあります。左の走査型電子顕微鏡写真は、オイルシェール中に含まれたボツリオコッカスです。ブドウの房状の構造がよく保存されています。全世界で発見されるオイルシェールの中にボツリオコッカスが主成分として含まれているかまでは研究は進んでいませんが、多くのオイルシェールはボツリオコッカスと主とする緑藻が起源であるという見解がなされています(写真:Derenne et al. (2000)より)。 太古の湖でボツリオコッカスが大量増殖している情景、そして風に流されて湖岸へと吹き寄せられるボツリオコッカスとそれが分泌する油膜のきれいなグラデーションが想像されます。この堆積物が地中に埋もれて、悠久の時を経て現代のオイルシェールや石油や天然ガスとなって我々人類を支えていると思うと、藻って偉大だなと思わずにいられません。 世界有数の石油・天然ガス産出地域にある池で、ボツリオコッカスの大量増殖に出会いはしゃぐ筆者。 参考資料Derenne, S., Largeau, C., Brukner-Wein, A., Hetenyi, M., Bardoux, G., & Mariotti, A. (2000). Origin of variations in...

日本の藻類燃料研究の変遷 part.2 (2011年度)
前回 part. 1では、日本の藻類燃料研究の流れと、2009~2010年度に開始されたプロジェクトを紹介した。 Modia[藻ディア] 日本の藻類燃料研究の変遷 part.1 (2009~2010年度) https://modia.chitose-bio.com/articles/58 先日、2018年3月時点で国の予算を受けて進行中の藻類研究を記事にまとめた。この記事では、2018年3月時点で走っている藻類研究を大小全て並べてみたが、今回は過去も含めて「藻類燃料」に関連する予算で動いているプロジェクトに焦点を当てて調べてみた。 米国での藻類研究への注目が集まった2008年前後から、国内の主だったプロジェクトを調べてみたところ、燃料関連ではこれまでに60以上のプロジェクトが行われていることがわかった(現在進行中も含む)。 今回から3回に渡り、2009年度から現在までの『日本の藻類燃料研究の変遷』... 今回 part. 2では2011年度に開始されたプロジェクトNo.23〜39の詳細を記す。なお、一覧表および次項にある各プロジェクトの説明に記載した金額は、各事業の募集時点の予算規模(最大額)を記している。 微細藻類燃料に関する国内助成金一覧表/筆者作成 2011年度当時は、藻類が急速に注目を集める中、最終目標に燃料を設定しながら、多様な研究が行われていた。多様な藻類脂質原料の燃料化研究、バイオ燃料化プロセスの中の特定プロセスに特化した研究、藻類培養をコントロールする研究、燃料と燃料以外の機能とを合わせた研究などがあげられる。 2011年度採択の助成金 23)油分生産性の優れた微細藻類の育種・改良技術の研究開発 【概要】コンタミネーションの発生し難い酸性環境で増殖し、高い油分蓄積能力を有する微細藻株Pseudochoricystis(シュードコリシスティス)を用いて、レースウェイポンドにおける油分生産能力の評価、および、コスト低減と安定生産を目指した培養システムの開発を行う。【委託先】<大学>中央大学*(中核機関) <企業>株式会社デンソー【期間】2011~2014年度【予算】240百万円 (60百万円/年)【事業名】NEDO「戦略的次世代バイオマスエネルギー利用技術開発事業」 24)炭化水素系オイル産生微細藻類からのDrop-in Fuel製造技術に関する研究開発 【概要】微細藻類由来のバイオ燃料製造技術開発の一環として,炭化水素系バイオオイルを産する微細藻類(ボトリオコッカス並びにオーランチオキトリウム)に着目し、これらの藻類が作る油脂(バイオクルード)を軽質燃料(ガソリン、ジェット燃料,軽油)へ改質する研究開発を実施する。また、微細藻類油脂から作られるバイオ燃料が、既存石油精製装置並びに物流システムへ適用可能な“Drop-in fuel※”となることを示す(※石油系燃料にそのまま混合可能な高品質な燃料)。【委託先】<企業>出光興産株式会社【期間】2011〜2012年度【予算】120百万円 (60百万円/年)【事業名】NEDO「戦略的次世代バイオマスエネルギー利用技術開発事業」 25)循環型エネルギーを利用した硫酸性温泉紅藻によるレアメタル回収システムの開発 【概要】硫酸性温泉紅藻の金属回収機構の解明により、循環型エネルギーを利用したレアメタルリサイクルシステムの開発を行う。このシステムでは、金属精製や金属廃棄物処理から生じるレアメタルの回収と水質浄化の工程で生じるCO2を固定してバイオ燃料を生産することで、カーボンニュートラルな金属リサイクルの達成を目指す。【委託先】<大学>筑波大学【期間】2011〜2014年度【予算】40百万円 (10百万円/年)【事業名】JST さきがけ「藻類・水圏微生物の機能解明と制御によるバイオエネルギー創成のための基盤技術の創出」 26)多様な光スイッチの開発による細胞外多糖生産の光制御 【概要】光合成生物は光合成を効率よく行うために、さまざまな光センサーを駆使し、変動する光環境に馴れている。一方、近年、光合成を利用したバイオエネルギー生産が注目されているが、実際的な産業利用のためには、生産効率の向上が必須課題となっている。本研究では、光センサーとその制御系の新たな組み合わせを創出することで、多様な光スイッチを開発し、効率的な細胞外多糖生産系の確立を目指す。【委託先】<大学>東京大学【期間】2011〜2014年度【予算】40百万円 (10百万円/年)【事業名】JST...

藻業は農業となれるのか? -米国「藻類農業法案」提出をうけて-
藻類生産を工業として扱うか、農業として扱うか。世界で決まりが整備されない中、アメリカが農業として扱う整備を進めようとしている。 Algae Agriculture Act of 2018とは 2018年3月23日、米国連邦下院にAlgae Agriculture Act of 2018 (H.R.5373) が提出された。 www.congress.gov H.R.5373 - 115th Congress (2017-2018): Algae Agriculture Act of 2018 https://www.congress.gov/bill/115th-congress/house-bill/5373?r=6 Summary of H.R.5373 - 115th...

「植物肉」が注目され資金が集まる本当の理由 -2050年の「タンパク質危機」を藻類培養が救う-
[初出:JBPress] 2017年末、生産能力を3倍に拡大する目的で5500万ドルの資金調達を発表した、とある「肉」のスタートアップがある。総調達額は公表額だけで7200万ドル、出資者にはマイクロソフト社の創設者であるビル・ゲイツやレオナルド・ディカプリオなどの著名人も並ぶ、その会社の名は「ビヨンド・ミート(Beyond Meat)」。 名前からして、今までの肉製品を超える、何か凄いモノを想像させられる。 公式WEBサイトでは、食欲を刺激される写真が並ぶばかりでなく、牛肉のパテと比較して、より多くのタンパク質を含みながらもコレステロールはほとんど含まない、「Beyond」の名に相応しい品質の説明が分かりやすく記載されている。また、米大手スーパーマーケットや大手ファストフードチェーンへ導入されるなど、米国にて実に1万9000以上の店舗でビヨンド・ミートの製品が取り扱われているという、優秀な導入実績も目を引く。 しかし、ビヨンド・ミートの最も重要な特徴は、この「肉」らしきものが、実は植物由来の原料から作られているという点にある。ビヨンド・ミート以外に、インポッシブル・フーズ(Impossible Foods)も植物由来の原料から作った肉を販売しており、同社の総調達額は3億ドル近くにのぼる。焼くと滴る肉汁が特徴で、その様子は公式WEBサイトなどで見ることができるが、空腹時に見る際は十分にご注意いただきたい。 これらの「肉」は「植物肉」「人工肉」「擬似肉」などと呼ばれる新しい食品素材として、健康志向の強い消費者やベジタリアン、ビーガンを中心に注目されている。 日本においても、一時期「謎肉」なるものが話題を集めた。謎肉はその一部に豚肉を利用している点において、完全な植物由来の原料から作られた肉とは言えないが、動物由来の原料を植物由来の原料に置き換えるというコンセプトは同じである。 実は、植物由来の原料からこうした肉代替品が作られる背景には、「消費者の健康志向」以上の、より現実的に逼迫した動機が存在するという事実をご存知だろうか。 それは、世界的なタンパク質不足問題(=タンパク質危機)だ。 「日本では少子高齢化が進んでいるし、そもそも飽食社会の現代においてタンパク質が不足するなんて全く想像つかないぞ」と切り捨てられてしまいがちな話題ではあるが、話を続ける。 現行の食習慣が続く場合、人口増加および経済成長により、2050年には世界のタンパク質需要が、対2005年比で約2倍になると試算されている。特に、新興国の多いアジア域におけるタンパク質需要の増加は著しい。 しかし、詳しくは後述するが、この急激な需要を賄えるほどのタンパク質生産を2050年までに達成することは難しいとされている。結果として、早ければ2030年前後に、タンパク質の需要・供給のバランスが崩れる「タンパク質危機」が顕著になると言われている。 この問題へは大きく2つの解決策が考えられる。 1つ目は、食習慣を肉食から菜食へと改めること。 2つ目は、大幅なタンパク質の増産を行うこと。 食習慣を肉食から菜食へと改める 実は、肉食は菜食と比べてタンパク質の摂取効率が悪い。果たしてどういうことか。 それは、飼料変換効率、つまり畜産物1kgを生産するために、どれだけの飼料が必要なのかを考えてみると見えてくる。 例えば、牛肉生産では、生産される牛肉の約10倍量の飼料用穀物が必要だと言われている。この時、飼料中の(植物性の)タンパク質含有率を約10%、牛肉中のタンパク質含有率を約25%と仮定すると、牛肉生産とはつまり、1kgの植物性タンパク質を0.25kgの動物性タンパク質へと変換する作業であることが分かる。つまり、総量として4分の1に減少しているのだ。 タンパク質供給という観点からは、0.25kgの動物性タンパク質ではなく、1kgの植物性タンパク質を摂取する方が効率的であることは明白である。 こうした理由が、冒頭に挙げたビヨンド・ミートやインポッシブル・フーズのような、「植物性のタンパク質を、動物性のものに変換することなく直接加工することで、擬似動物性タンパク質製品を作る」という取り組みの動機となっている。また、飼料変換効率が比較的高い、養鶏や水産養殖が世界中で大きな伸びを見せていることも、このような背景を踏まえている。 こうした近年の動きは、近い将来におけるタンパク質需給バランスの改善には効果的であることが認められているが、一方でタンパク質需要の増加がタンパク質供給の増加を上回り続ける限り、いずれは需要が供給を上回る事態が生じることは避けられないと予想される。 そのため、2050年以降の将来も見越したタンパク質供給の安定化を考える上で、2つ目の解決策である「タンパク質の増産」が根本的に必要となる。 大幅なタンパク質の増産を行う タンパク質危機という問題は、穀物の生産量を増やせば解決しそうに見えるが、実際はそれが非常に難しい。どういうことか、ここから少し丁寧に考えてみる。 急激なタンパク質需要を賄うには、2050年にかけて、世界全体の穀物生産量を毎年約2.4%ずつ増やし続ける必要があると試算されている。穀物生産量を増やすには「農地面積を増やす」もしくは「単収*1を増やす」の2つの方法がある。*1=単位農地面積あたりの収穫量。 しかし、2005~2050年の間で合計しても、農地面積は最大でも1桁%程度しか増加しないと見積もられている。森林を切り開くことで、大幅な農地面積拡大の可能性なども議論はされているが、その場合、拡大した広大な農地へ十分に供給できるほど淡水資源を確保できないと言われている。 また、「緑の革命」と呼ばれる穀物の大量増産を達成した時期を含め、過去60年間での平均年間生産量増加は、もっとも高い値を記録した大豆やトウモロコシですら、それぞれ年あたり1.3%および1.6%程度であり、今後2050年までにそれを大幅に上回る単収の増加は難しい。...

脂質分野における藻類の利用 -バイオ燃料への可能性-
一般的に植物性脂質といえばパーム油や大豆油が広く知られていますが、植物の祖先に当たる藻類も細胞内に脂質をため込む性質をもっています。藻類から作られる脂質は、大きく油脂、糖脂質、リン脂質および炭化水素に分けられます。今回は藻類全体が脂質分野で注目される理由についてまとめていきます。 ※脂質、油、脂肪といった言葉の定義について詳しく知りたい方は、下記連載をご覧ください。 Modia[藻ディア] 油にまつわる言葉の整理 第1回 -油、脂質、脂肪とは- https://modia.chitose-bio.com/articles/definition_of_oil 「藻類バイオ燃料」「DHAやEPAに代表されるオメガ3脂肪酸」「βカロテンやアスタキサンチンといった抗酸化物質・色素・カロテノイド」「パームオイルや菜種油に対応するような、藻から取れる油脂」これらの話をする場合、藻類に含まれる「あぶら」が議論の対象となります。オイル、油、脂、脂質、脂肪等、人によって様々な言葉が使われますが、意図的であろうとなかろうと、言葉の誤用・勘違いによる誤解が後を絶たないように感じます。そこで、人々が言う「あぶら」とは一体何なのか、数回に分けて簡単に整理していければと思います。... Modia[藻ディア] 油にまつわる言葉の整理 第2回 -脂肪酸、油脂とは- https://modia.chitose-bio.com/articles/definition_of_oil-2 前回の記事では「油」、「脂質」、「脂肪」といった言葉を整理していきましたが、今回は「脂質」に含まれる「脂肪酸」、「油脂」といった少し範囲の狭まった言葉について紹介していきます。前回の記事はこちらよりご覧ください。「脂質 (lipid)」に含まれるあれこれ藻類バイオ燃料を語る際に議論の対象となるのは、藻類に含まれる「脂質」になります。では、「脂質=燃料なのか?」と聞かれれば、当然そうではありません。次に、前述の「油脂」を含め、藻類に含まれる様々な「脂質」について、もう少し掘り下げてみたいと思います。「... 藻類は脂質生産性が高い とりわけ注目を集めている藻類の脂質は油脂です。藻類の油脂蓄積量は、平均的には10~30%程度、多い種では50%以上にも上ります。主な藻類種における脂質の割合は、『食品分野における藻類の利用』に示されているので、併せてご覧ください。 単細胞の藻類では、藻全体が油脂源となり、数時間~数日で分裂・増殖をします。藻類に寿命はありません。比較としてパームオイルの原料植物のパームヤシを挙げると、定植からオイルの含まれる果実が収穫できるまでに約3年かかり、数カ月~1年に一度の収穫しかできません。また、パームヤシは25~30年で植え替えなければなりません。 藻類と高等植物の油脂生産性の比較/中原(ちとせ研究所)作成 上記のグラフは、藻類と植物の年間の油脂生産性の比較のグラフです。成長速度や油脂含有率を考慮した実質の生産性を表しています。油脂含有率の低い藻類(油脂含量10%)でもパームと同等、油脂含有率が平均から高い藻類(油脂含量30%、50%)なら3~5倍にものぼります。このように藻類の油脂生産性は、現在地球上に存在する全ての生物の中で最も高いため、油脂を含む脂質原料として有望視されているのです。 藻類は脂質の種類が豊富 脂質生産性の高さに加え、藻類は生成できる脂質の種類が豊富であることが特徴です。藻類の種類、同一種内の株ごと、また培養方法によっても、藻類の作る脂質の組成や含有率は様々に変化します。これは逆に考えると、藻類種や培養方法を選択することで、自由自在に目的の脂質を生産することが可能だという事です。 様々な藻類の脂質(脂肪酸)組成(%)/筆者作成 ※脂肪酸の表記は炭素数と二重結合の数で特徴を表します。例えば、「22:6(DHA)」は、22個の炭素が直鎖状に結合し、また炭素間の結合には二重結合が6個含まれて、名称はDHAという脂肪酸という事を表現しています。二重結合がない脂肪酸を飽和脂肪酸、二重結合(場合によっては三重結合)をもつ脂肪酸を不飽和脂肪酸といいます。 上記の表は、脂質の一例として、様々な脂肪酸の組成を示しています。植物と藻類の脂肪酸組成の共通点は、炭素数16の脂肪酸を多く含んでいることが挙げられます。植物と藻類の違いは、藻類の脂肪酸は多様性に富んでいることです(炭素数の種類が多いこと、二重結合をもつ不飽和脂肪酸が多いこと)。各々の藻類には各々に特徴的な脂肪酸組成をもっています。脂肪酸に関わらず、脂質全体をみても藻類の脂質には多様性があります。 油脂 上:油脂原料として利用される藻類/筆者撮影、下:藻類に含まれる脂肪酸の構造式 /筆者作成...
![ちとせの藻ヂカラ[中編] -ちとせの藻類プロジェクト-](http://matsuri.chitose-bio.com/cdn/shop/articles/098720ff09672cc2474b29e6e50ead70-1024x501_02c75421-9fcc-461e-9495-17eefc10f16e.jpg?v=1718796484&width=533)
ちとせの藻ヂカラ[中編] -ちとせの藻類プロジェクト-
前編では、我々がなぜ藻類プロジェクトに取り組むのかを紹介した。 前編を簡単にまとめると、・近い将来、食料や燃料が足りなくなる、・その解決のためには光合成量を増やす必要がある、・光合成量を増やすには藻が最適であるという内容だった。 では、具体的にどのような取り組みを行っているのか?本稿では現在進行しているプロジェクトの中から、主に3つのプロジェクトを紹介する。 ●前編:ちとせはなぜ藻類プロジェクトに取り組むのか●中編:ちとせの藻類プロジェクト(←本記事)●後編:ちとせの武器、3つの藻ヂカラ 藻類ジェット燃料プロジェクト 目的:エネルギー枯渇問題を解決する具体的には?:藻で代替ジェット燃料を作る藻の種類:ボツリオコッカス事業体:株式会社ちとせ研究所パートナー:NEDO、株式会社IHI、神戸大学場所:鹿児島、タイ 株式会社IHIへ企画を持ち込み、2011年よりスタートした藻類ジェット燃料プロジェクト。2012年からは、 “国家プロジェクト”として、新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)の委託事業としての開発を進めており、2013年にはIHI横浜事業所の屋上にて100㎡の屋外培養、2015年には鹿児島にて1,500㎡スケールの屋外培養池での大規模培養を成功させた。 2015年に公開したバイオ燃料用微細藻類(ボツリオコッカス)の屋外大規模培養の様子 現在は、開発してきた生産プロセスを用いて商用候補地タイでの10,000㎡のパイロットスケール実証試験設備を整備し、本格運転を開始している。 本プロジェクトに使用している藻は、「ボツリオコッカス」という緑藻類の一種。燃料に近い性質を持つ油を乾燥重量の半分程度蓄積することから、古くから燃料代替として期待されてきたが、「増殖スピードが非常に遅いこと」そして「大量培養技術が確立されていないこと」が大きな懸念点であった。 そこで本プロジェクトでは、神戸大学が開発した「高速増殖型ボツリオコッカス」という、通常のボツリオコッカスに比べて増殖スピードの速い藻をベースに、低コスト・大量培養を実現するための品種改良を行なうと同時に、大量培養技術の確立を目指している。 藻類自体の生産性の向上を目指したラボでの研究開発も継続しているが、各地の屋外で行なう試験の比率が年々増えているためなかなかプロジェクトメンバーが一同に集まることがない。メンバー全員が集まる写真を探したところ、2017年6月のちとせグループキックオフミーティング時の写真しか手元になかった。一部メンバー入れ替えはあるが、だいたいこんなメンバーだ。 現在の課題は製造コスト。まだまだ「燃料」として手の届く価格ではないのが現実だ。だが、技術開発を進め、課題をひとつひとつクリアし、着実に目標に近づいている。 今後も太陽光のみで育てるというポリシーを決して曲げること無く、果敢に挑み続けてゆく。 タベルモプロジェクト 目的:食糧問題(タンパク質クライシス)を解決する具体的には?:藻を、大豆や肉の代わりとなるタンパク質源として供給する藻の種類:スピルリナ事業体:株式会社タベルモ(メイン)、株式会社ちとせ研究所パートナー:株式会社産業革新機構(現INCJ)、三菱商事株式会社場所:静岡県掛川市、ブルネイ 栄養の種類・バランス・消化吸収効率が高く、タンパク質が豊富なスピルリナ。一般的には粉末や錠剤などのサプリメントとして販売されているが、豊富な栄養をそのまま摂れる「食材」として普及させることを目的に「生」での製品化に2013年より着手した。 一般的なスピルリナの培養方法では生食に適さないため、ハウスなどの環境づくりと同時に、独自の培地を開発し工夫を重ねることで生食に適した培養方法を構築。静岡県掛川市で培養したスピルリナを2015年より生スピルリナ「タベルモ」というブランドで販売している。 新商品のフローズンデザートを販売したり、各種イベントへ出展したりと、メンバー総出で認知を広めるために活動してきた。商品開発にイベントの運営、POPやチラシやイベントブースのデザインにWEBサイトづくり、メディアの運営など、スキルが増えて成長してゆくメンバーが実にたくましい。 スピルリナをタンパク質源として広く活用していくことを考えると、現時点では生産コストがまだまだ高い。そのため、さらなる技術開発を行いつつより太陽光の多い場所にて培養することで生産性を上げて製造コストを下げ、来たるタンパク質危機(タンパク質クライシス)に備えた商品展開を進めてゆく。 [2018.8.27追記]2018年5月22日、本プロジェクトの事業体である株式会社タベルモは、株式会社産業革新機構(現INCJ)と三菱商事株式会社より17億円の資金調達実施の発表をした。調達資金でブルネイに工場を建設し、タンパク質危機の解決に向けた事業展開を加速してゆく。より詳しくは以下の記事を御覧ください。◯17億円の資金調達を実施したタベルモ社の目指す未来とは?◯Hottopics vol.51(7月号) ←「●タベルモ増資の発表を行いました」参照 [2019.6.28追記]2019年6月28日、タベルモはブランドを全面的にリニューアルした。英語表記をTavelmoutからTabérumoに変更、ロゴマークをしずくから地球上の全ての生き物との健康・調和・希望を表現したマークに変更した。これまで以上に魅力のあるブランドに、そしてさらなる広い顧客層にアピールしていく。 [2019.10.24追記]2019年10月22日、ブルネイに新工場が竣工した。新工場で生産した製品は、2020年4月に日本市場で販売開始予定である。詳しくは以下の記事を御覧ください。〇世界初新鮮な生スピルリナを生産・販売するタベルモ ブルネイの新工場が竣工 -スピルリナで将来のたんぱく質需要増大へ対応、生産能力10倍へ-〇株式会社タベルモ及び現地子会社がブルネイに建設した新工場の竣工式を執り行いました [参考]◯タンパク質危機(タンパク質クライシス)について詳しく知りたい方はこちらの記事をどうぞタンパク質生産の未来について -タンパク質危機(タンパク質クライシス)を解決する?藻とメタン資化菌-◯藻の食品利用について詳しく知りたい方はこちらの記事をどうぞ食品分野における藻類の利用 -可能性と課題-...

日本の藻類燃料研究の変遷 part.1 (2009~2010年度)
先日、2018年3月時点で国の予算を受けて進行中の藻類研究を記事にまとめた。 Modia[藻ディア] 国内における藻類研究の動向(2018年3月現在) https://modia.chitose-bio.com/articles/56 最近は藻ガール尾張のマニアックな紀行記事に押され気味で、私の記事の存在感低下が著しい。それはそれでいいことなのだが、そもそも私の記事と藻ガールの記事の何が違うのだろうか、ってところを色々な角度から考えた結果、『藻に対する愛の差』ってことに行き着いた。よっしゃ、じゃあ俺も負けずに藻への愛に溢れる記事を書いたろうじゃないの!ということで、緊急企画『現時点で国からの研究予算の交付を受けて進めらている藻類関連の研究についてのまとめ』をお届けしたい。すいません、やっぱ愛より金っすわ。国内の藻類研究予算... この記事では、2018年3月時点で走っている藻類研究を大小全て並べてみたが、今回は過去も含めて「藻類燃料」に関連する予算で動いているプロジェクトに焦点を当てて調べてみた。 米国での藻類研究への注目が集まった2008年前後から、国内の主だったプロジェクトを調べてみたところ、燃料関連ではこれまでに60以上のプロジェクトが行われていることがわかった(現在進行中も含む)。 今回から3回に渡り、2009年度から現在までの『日本の藻類燃料研究の変遷』についてまとめる。この変遷を見ることで、テーマの移り変わりと主要プレイヤーがどこなのかが見えて来る。 藻類燃料研究に助成金を出している配分省庁と事業名 複数の省庁から予算が出ているので、先記事でも紹介した下記の図を踏まえた上でご参照いただければと思う。 藻類研究に予算をつけている各省庁の関係図/筆者作成 2008年から現在までの、助成金配分省庁と事業は以下の通りである。 【経済産業省系】資源エネルギー庁管轄・2016〜2018年度「微細藻類を活用したバイオ燃料生産のための実証事業」NEDO管轄・2010〜2016年度「戦略的次世代バイオマスエネルギー利用技術開発事業」・2015〜2017年度「微細藻類を活用したバイオ燃料生産のための実証事業費補助金」・2017〜2020年度 「バイオジェット燃料生産開発事業/一貫製造プロセスに関するパイロットスケール試験」 【文部科学省系】JST管轄・ 2008~2016年度 CREST「二酸化炭素排出抑制に資する革新的技術の創出」・ 2010〜2018年度 CREST/さきがけ「藻類・水圏微生物の機能解明と制御によるバイオエネルギー創生のための基盤技術の創出」・2012〜2016年度「東北復興次世代エネルギー研究開発プログラム」・ 2015〜2020年度 SATREPS「環境・エネルギー(低炭素社会)」(JST/JICA/AMEDでのジョイントプログラム)・ 2017〜2021年度 未来創造事業「「ゲームチェンジングテクノロジー」による低炭素社会の実現」 【農林水産省系】・2012〜2015年度「農山漁村におけるバイオ燃料生産基地創造のための技術開発」 【復興庁系】・2013〜2015年度「福島県再生エネルギー次世代技術開発」 上述した各予算枠組みのもとで行われた、全62のプロジェクトをまとめた一覧表を作成したので是非見ていただければと思う(下記)。中原渾身の力作である。どのような予算の下で、どんなプレイヤーたちが、どんな研究をしてきたのかが俯瞰できるように作ったつもりだ。なお、一覧表および次項にある各プロジェクトの説明に記載した金額は、各事業の募集時点の予算規模(最大額)を記している。 微細藻類燃料に関する国内助成金一覧表/筆者作成 今回 part.1では2009年度及び2010年度に開始されたプロジェクトNo.1〜22の詳細を記す。 2009年度採択の助成金...
![ちとせの藻ヂカラ[後編] -ちとせの武器、3つの藻ヂカラ-](http://matsuri.chitose-bio.com/cdn/shop/articles/098720ff09672cc2474b29e6e50ead70-1024x501_5ded66ea-57b3-402b-a7e5-db0c0bc02852.jpg?v=1718797169&width=533)
ちとせの藻ヂカラ[後編] -ちとせの武器、3つの藻ヂカラ-
前編では我々がなぜ藻類プロジェクトに取り組むのかを、中編ではちとせの取り組む藻類プロジェクトを具体的に紹介してきた。 今回は、「ちとせの藻ヂカラ」最終回として、我々が藻類プロジェクトに取り組む上で武器としている、『ちとせの3つの藻ヂカラ』について紹介する。 ●前編:ちとせはなぜ藻類プロジェクトに取り組むのか●中編:ちとせの藻類プロジェクト●後編:ちとせの武器、3つの藻ヂカラ(←本記事) ①目的に合う藻をつくる、『藻・育成力』 私たちに得意なことと不得意なことがあるように、藻にも得意不得意がある。つまり、藻ならなんでもOKというわけではない。 そのため、藻類プロジェクトに取り組む際は、まず目的に合う藻を見極め、その藻の能力を伸ばすことが必要なのだ。スポーツ選手の卵を選び、その後さらに育成するイメージだ。 これを「藻・育成力」と本稿では整理する。 藻の育成にあたっては、「不均衡変異導入法」を活用する。これはちとせ研究所が15年の年月を掛けて技術強化を続けている独自の育種技術である。生き物自体が可能性として持っていた変異を誘発するため多様性を有する変異効果が期待できること、そしていわゆる遺伝子組み換えには値しないため産業用途にも広く活用できる点が強みだ。 この技術を活かし、実際に藻を育成(品種改良)した例をあげる。 ●藻類ジェット燃料PJ このPJで使用している藻は、「ボツリオコッカス」という緑藻類の一種。燃料に近い性質を持つ油を乾燥重量の半分程度蓄積することから、古くから燃料代替として期待されてきたが、増殖スピードが非常に遅いことが大きな懸念点であった。 そこで、神戸大学が開発した「高速増殖型ボツリオコッカス」という、通常のボツリオコッカスに比べて増殖スピードの速い藻をベースに、低コスト・大量培養を実現するための品種改良を行った。 A.藻体のサイズUP 目的:サイズを大きくすることで培養液からの藻体の回収を容易にし、回収コストを下げる(藻体のサイズが小さいと、分離のために遠心分離機などの機器を使用しなければならないため回収にエネルギーコストがかかってしまう) 獲得した粒径拡大株(左が元株) B.多糖の分泌を抑える 目的:粘性を持つ多糖の分泌を抑えることで培養液のねばつきを抑え、藻体の回収を容易にし、回収コストを下げる 多糖分泌低減株の培養試験中の様子 C.藻が水面に浮くように 目的:培養池の水面に藻体が浮くことで回収を容易にし、回収コストを下げる 獲得した浮上特性株(左が元株) このように、複数の能力を付加した株で、2015年鹿児島で1500㎡の規模での屋外培養を行った。タイで準備中の10,000㎡規模の生産試験でもこのように改良した株を使用する予定だ。 ここまでで、ジェット燃料向きの油をつくる藻「ボツリオコッカス」の中で増殖スピードの速いポテンシャルの高い系統に、「不均衡変異導入法」というちとせ独自の育種技術で低コスト・大量培養に必要な能力を付加した例を紹介した。 ②産業規模に藻を増やす、『藻・培養力』 ①で紹介したように、得意不得意を見極めて育成しただけでは、藻類プロジェクトは成り立たない。産業として大きく育てるために必要なのは、大量培養する技術だ。 これを、「藻・培養力」と整理する。 藻類の大量培養法としては、『池を使った開放系培養法[オープンポンド]』と『バイオリアクターを使った閉鎖系培養法[フォトバイオリアクター(PBR)]』の大きく2種類存在する。 前者は50年前に確立された浅い池を用いた培養方法で、水車や空気などで水を攪拌させながら藻類を培養する。後者は近年開発が進んでいるもので、チューブやフィルム、膜などを用いて立体的に藻類を培養する。 農業にも各作物に合わせた様々な農法があるのと同じように、藻類も諸条件によって最適な培養法は違う。ちとせでは、「藻類の種類」×「生産物の単価」×「生産地の気候」に合わせた培養環境をその都度作りあげ、実際に事業規模で運営している。 池を使った開放系培養法[オープンポンド培養]...
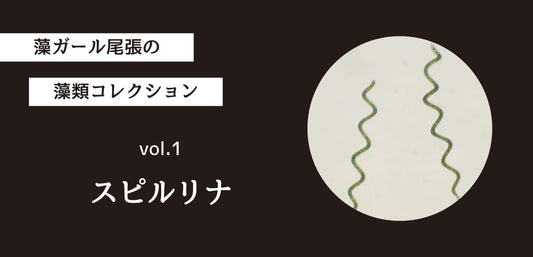
藻ガール尾張の藻類コレクション vol.1「スピルリナ」
Modiaはこれまで数多くの藻類に言及してきました。このコーナー『藻ガール尾張の藻類コレクション』では、それぞれの藻類にまつわるちょっとしたエピソードを紹介していきたいと思います。 記念すべき第1回は、Modiaでも度々取り上げられている『スピルリナ』です。この『スピルリナ』、実は誤ってつけられた名前だったことをご存知でしょうか? ・学名:Arthrospira platensis・分類:原核生物 > 真正細菌 > シアノバクテリア ※下図の系統樹もご覧ください!・生息:アフリカ中部、中央・南アメリカのアルカリ性湖沼・体長/形態:直径5~8µmの小さな円筒状の細胞が螺旋状に連なった形態で、全長は300µm以上にもなる。・レア度:★★★☆☆ 『スピルリナ』と皆さんが言っている藻の現在の学名は、アルソスピラ属の Arthrospira platensis です。どこにも『スピルリナ』とは入っていません。かつてはスピルリナ属の Spirulina platensis という学名だと考えられていて、属の名前を取って『スピルリナ』という名称で人々の社会に健康食品等として浸透していきました。 しかしその後、スピルリナ属に属するとみなされていた一群の藻類の中には、別系統のアルソスピラ属が紛れ込んでいることが分かったのです。紛れ込んでいた中に、『スピルリナ』も含まれていたのです。 少し学術的な話ですが、藻類における属の定義は、最初にその属が定義された藻類種に基づきます。そのため、スピルリナ属の中では新参者だった Spirulina platensis は、アルソスピラ属という別の属に移され、その学名は Arthrospira platensis と変更されたのです。 スピルリナとシアノバクテリアの系統樹/筆者作成 学名が Arthrospira platensis に変更された後、藻類学者の間ではもはや『スピルリナ』という呼称は使用されませんが、昔から広く人々に親しまれてきた『スピルリナ』という呼び名は、今後も長く愛され続けるでしょう。 プランクトンネットを使って藻を採取する筆者 参考資料Vonshak, A. (Ed.). (1997). Spirulina platensis arthrospira: physiology, cell-biology and biotechnology. CRC Press.Ballot, A.,...

藻類の光感受性タンパク質が、視力を失われた患者の視機能を回復する希望!
先月末に放送された「生きるを伝える」という番組で、全盲のプロドラマーである佐藤尋宣さんのドキュメンタリーが紹介された。子供の頃から目に異常を感じた佐藤さんは、網膜色素変性症と診断されていた。高校生の時にドラムとの運命的出会いが訪れたが、21歳で完全に失明になった。それでも23歳でプロのドラマーになる夢を果たせた。 難病といわれる「網膜色素変性症」という目の病気に明確な効果を示す治療法は確立されていない。その中で、藻類タンパク質を利用した画期的な遺伝子療法の臨床試験が今年(2018年)始まろうとしている。 藻類で本当に目の病気が治すことができるのかと疑問に思う人も多いだろう。今回は、正常な人の視覚と網膜色素変性症の原因、そしてなぜ藻類のタンパク質が人の治療に役立つ事ができるのかを紹介する。 人が物を見る仕組み そもそも、「物を見る」とは、眼の網膜で受けた光刺激を信号に変えて、網膜神経節細胞という神経細胞を介して情報が脳へと送られ、大脳皮質の視覚野で形や色、明るさ、動き、位置などが分析されることを意味する。神経細胞の細胞内の素早い伝播には、細胞内外の「膜電位」の差を利用した電気信号が用いられている。 網膜についてもう少し詳しく見ていくことにする。眼球の内側、一番奥にある網膜という薄い膜状の部分には光や色を感じるのに重要な視細胞(桿体細胞と錐体細胞)がたくさん存在している。桿体細胞は高感度で弱い光を感じ取る細胞であり、眼球1つに1億個以上も存在し、中心窩を除く網膜全体に分布している。一方、錐体細胞は強い光と色を検知する細胞であり、網膜の中心部である黄斑部に600万個ほど高密度に存在している。 網膜の構造/”Retina“よりModia編集部が作成 網膜色素変性症とはどんな病気だろう? 網膜色素変性症は遺伝要因が大きいとされ、3000~4000人に1人の割合で発症する難病であり、世界で約150万人の人が罹患していると推定されている。網膜色素変性症は先進国における遺伝性失明症の主因であり、日本では、緑内障、糖尿病網膜症に続き、中途失明の原因となっている。病原となる遺伝子変異は60種類以上が同定されているものの、常染色体優性遺伝、常染色体劣性遺伝、X連鎖劣性遺伝と様々な遺伝形式によるため、治療において原因遺伝子の特定が困難である。 網膜色素変性症という疾患は、初期段階では桿体細胞の機能が失われ、夜盲症や視野狭窄が現れる。錐体細胞の機能は網膜色素変性症に関連する遺伝子の変異には影響されないが、発症すると徐々に色覚異常や中心視力の低下が進行し、最終的には失明に至る。現時点で、臨床的に明確な効果を示す治療法は確立されておらず、世界中で様々な治療法の研究が行われている。 藻類の光受容性タンパク質の本来の機能 藻類は光合成をして生きているため、光は必要不可欠である。光合成を効率よく行うため、多くの藻類は鞭毛を動かして最適な光環境へと自ら移動できる運動機構をもつ。眼点という部位で光の方向性や強さを感知して、弱光下では光に寄ってくる正の走行性を、強光下では光を回避するため負の走行性を示す。眼点には光受容性タンパク質が存在している。 藻類の中でモデル生物といわれている緑藻綱クラミドモナス(Chlamydomonas reinhardii)では、光受容性タンパク質の研究が進んでいる。クラミドモナスの光感受性タンパク質のうち、チャネルロドプシンⅡ(ChR2)は、光を感じると陽イオン(Na+やCa2+)を細胞外から細胞内に流入する光受容イオンチャネルである。チャネルロドプシンⅡはタンパク質分子単独で光を感受すると膜電位を変化させることができる。クラミドモナスは光を受容すると、眼点のチャネルロドプシンが膜電位差を生じさせ、それが鞭毛に伝わり、鞭毛を動かして目的の方向へと細胞が進んでいく。 藻類の光感受性タンパク質の治療への応用 藻類タンパク質を利用した治療法の臨床試験を行う企業は、フランスを拠点とする、2013年に創立されたGenSight Biologics社というバイオファーマである。同社は既にヒトの遺伝子を用いた様々な網膜神経変性疾患や中枢神経系疾患の新規治療法の開発を進めている(詳細は末章「希少疾病用医薬品の開発に期待」に記載)。 今年1月、GenSight Biologics社は、藻類光受容性タンパク質による網膜色素変性症 (retinitis pigmentosa) への遺伝子治療の第I相/第II相臨床試験開始の申請がイギリスの医薬品・医療製品規制庁に承認されたことを発表した。試験は2018年の第1四半期に開始される予定である。 www.gensight-biologics.com GenSight Biologics receives MHRA approval to initiate...

そのバイオ燃料、エネルギー量が減っていないか?-「エネルギー収支比」で考える藻類バイオマス燃料-
2012年の環太平洋合同演習(RIMPAC)で公開演習を行った「グリーンエネルギー大艦隊(Great Green Fleet)」 Photo by U.S. Navy. [初出:JBPress] 東京など世界各都市で開かれるモータショー。そこでは各メーカーが力作のコンセプトカーを展示する。ビジョンやデザイン、新たな技術など、コンセプトカーは自動車の未来を魅せてくれる存在だ。自動走行する車や、電気や水素の力で走行する車など、コンセプトカーが体現する未来に共感し、その研究開発を応援する人々も多いことだろう。 我々が研究している藻類バイオ燃料の分野においても、バスを走らせたり飛行機を飛ばしたりなど、未来を魅せるパフォーマンスは度々行われている。 2012年7月、藻類バイオ燃料における世界最大級のパフォーマンスがハワイ沖で実施された。米軍が日本など21カ国と共に実施した合同軍事演習「環太平洋合同演習(RIMPAC:リムパック)」において、バイオ燃料を使った「グリーンエネルギー大艦隊(Great Green Fleet)」の初の公開演習を行ったのだ。巨大な空母を利用した大掛かりなパフォーマンスである。 ここでは、米国のバイオ燃料ベンチャー旧ソラザイム(現コービオン) 製の「従属栄養方式」で生産された藻類バイオマス由来のバイオ燃料が、化石燃料と共に利用された。 このパフォーマンスには、その後さまざまな批判が上がったが、それらの批判を含め包括的な議論をまとめた米国エネルギー省(DOE)による「National Algal Biofuels Technology Review」などの文献の刊行は、「夢」の主導者としての米国の矜持であると感じる。 光で育てる「光合成方式」と、エサを与えて育てる「従属栄養方式」 RIMPACでのグリーン艦隊のパフォーマンスはなぜ批判されたのか。その原因の1つが、使用されたバイオ燃料が「従属栄養方式」で生産されたという点である。 バイオ燃料の生産には、原料としてさまざまな種類のバイオマスが利用される。微細藻類(以下、藻類)由来のバイオ燃料であれば、その原料は「藻類バイオマス」となる。 藻類バイオマス生産には、大きく分けて、光合成独立栄養方式(以下、光合成方式)と化学合成従属栄養方式(以下、従属栄養方式)、の2つの方式が存在する(下の図)。 図:従属栄養方式と独立栄養方式 前者は、光(多くの場合、太陽光)をエネルギー源として、かつ、二酸化炭素を炭素源として、バイオマスを生産する方式であり、一般にいう農業生産の大部分はこれにあたる。一方、後者は、有機化合物(多くの場合、糖類など)をエネルギーと炭素の両源としてバイオマスを生産する方式であり、ヒトを含めた多くの動物の成長はこれにあたる。(詳しくはこちらをご覧ください) 産業利用されている藻類バイオマスの大半は「従属栄養方式」 現在、燃料に限らず、藻類バイオマスがさまざまな産業分野で利用されているが、その多くは従属栄養方式で生産されたものである。 例えば、オランダの総合化学メーカーDSMが生産するDHA(ドコサヘキサエン酸)製品はCrypthecodinium(クリプテコディニウム)やSchizochytrium(シゾキトリウム)といった藻類を、コービオン(旧テラビア)が生産する食用油脂やタンパク質粉末はChlorella(クロレラ)という藻類を、従属栄養方式で生産したバイオマスから生産している。最近話題になった、神鋼環境ソリューション製の「神戸ユーグレナ」も、従属栄養方式で生産されたミドリムシの乾燥粉末である。 従属栄養方式での培養の様子 「従属栄養方式」は、燃料「生産」ではなく物質「変換」 「従属栄養方式」は、燃料「生産」ではなく物質「変換」藻類バイオ燃料開発・研究においても、従属栄養方式で生産された藻類バイオマスが度々利用されてきた。冒頭で記載した、RIMPACでのパフォーマンスに使用された藻類バイオ燃料も「従属栄養方式」で生産されたものである。...

食品分野における藻類の利用 -栄養組成から免疫効果まで-
今年に入って特定の藻類に注目した記事を書く機会が多かったのですが(Modiaが発行しているニュースレターでも、毎月一種の藻類を特集しています!)、今回は対象を広げて、藻類全体が食品分野で注目される理由と直面している課題についてまとめていきます。 そもそも藻類は、光合成によって光エネルギーを取り込み、それを細胞が利用できる形に変換してエネルギーを蓄えます。窒素、リン、カリウム、ミネラルといった無機物を取り込み、タンパク質等を生成しながら成長し、分裂して、増殖していきます。取り込み過ぎたエネルギーは脂質で貯蔵することもあります*。光合成も、物質の生成反応も、すべて1つの細胞で行うことができるため、藻類は様々な物質を生産できる「生体装置」ということができます。*脂質については『油にまつわる言葉の整理 第1回 -油、脂質、脂肪とは-』こちらの連載もご覧ください。 免疫促進など機能性が認められている藻類食品 藻類全体の栄養素組成を見てみると、まず第一に、生体装置の本質である「タンパク質」の含有量が高いことが挙げられます。また、光合成によって得られたエネルギーの貯蔵や、細胞を支える繊維構造として「炭水化物」も重要な役割を果たしています。藻類の種類や培養条件によっては、不飽和脂肪酸などの「脂質」も蓄積することが可能です。さらに、こうした栄養素に加え、人体にとって必要な「ビタミン」や「ミネラル」も含まれているため、藻類は古くから健康食品として世界中で利用されています。 動物実験や臨床試験では、藻類の健康への効果が幅広く検証されています。例えば、ガン細胞の増殖抑制効果、アレルギー反応の抑制効果、免疫機能の促進、抗ウイルス作用、肝臓機能の向上などです。日常的に藻類を摂取することで、腸内環境の改善や生活習慣病の改善も期待できるといわれています。 上記のように様々な効果が検証される中、近年では健康志向の高まりもあり、『藻活』と呼ばれる藻類を積極的に食べる習慣も広がってきています。 藻類の栄養素組成 食用として利用されている、または研究開発が進行中の藻類の栄養素組成 / 筆者作成 上図は、現在食用として利用されている、もしくは食用として研究開発が進んでいる藻類とその組成を示しています。 食品として現在利用されている藻類は、スピルリナ、クロレラを筆頭に、ドナリエラ、ユーグレナ、アファニゾメノン(ブルーグリーンアルジ)等があります。これらの藻類はタンパク質源とミネラル・ビタミンが豊富であるという観点から、藻類をそのまま乾燥粉末にして利用されています。 また脂質組成が特徴的なナンノクロロプシスは、不飽和脂肪酸EPA含有率の高いことを売りに同じく乾燥粉末にして利用されています。この他にもヘマトコッカスは抗酸化作用の強い赤色色素アスタキサンチンを抽出して健康食品の材料として利用されています(詳しくは下記ページをご覧ください)。 Modia[藻ディア] ヘマトコッカスとは? -生物学的特徴とアスタキサンチンの生産- https://modia.chitose-bio.com/articles/characteristics_of_haematococcus アスタキサンチンという赤色の抗酸化色素を蓄えることで有名な藻類「ヘマトコッカス」。数ある藻類種の中でも特に産業化が進んでいる、認知度の高い種です。本記事ではこのヘマトコッカスという藻について、紹介していきたいと思います。1.ヘマトコッカスとは? -生物学的特徴を中心に- 左図:藻類の系統樹、右上写真:ヘマトコッカスの通常時の様子、右下写真:ストレス下の様子 / 筆者作成ヘマトコッカスとして一般的に知られる藻類は、Haematococcus pluvialis(※)という、真核生物>アーケプラスチダ>緑藻綱>ボルボックス目>ヘ... Modia[藻ディア] アスタキサンチンとは? -健康機能と市場の動向- https://modia.chitose-bio.com/articles/characteristics_of_astaxanthin 前回の記事では、ヘマトコッカスという藻類が赤色の抗酸化色素「アスタキサンチン」を蓄える特徴があることをお伝えしました。今回はそのアスタキサンチンを掘り下げていきます。アスタキサンチンは藻類の抽出物として国内外で産業化が進み、いま多くの注目を集めている物質です。1.アスタキサンチン(Astaxanthin)とは アスタキサンチンの骨格イソプレン(a)とアスタキサンチン(b)の構造式 /...
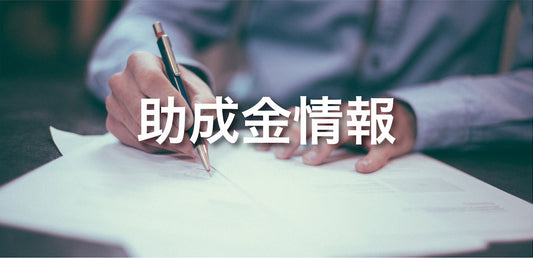
国内藻類関連の助成金一覧 (2018年3月時点)
国内の藻類関係の助成金に関して、予算元の各省庁の組織図と進行中のプロジェクトを下記にまとめております。(2018年3月時点) 2017年度時点で藻類研究に予算をつけている各省庁の関係図 / 筆者作成 Contents [非表示] 経済産業省 資源エネルギー庁 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO) 中小企業庁 内閣府 日本医療研究開発機構(AMED) 農林水産省 農林水産技術会議事務局 農研機構生研支援センター 環境省 地球環境局 文部科学省 科学技術振興機構(JST) 日本学術振興会(JSPS) 経済産業省 資源エネルギー庁 【微細藻類を活用したバイオ燃料生産のための実証事業費補助金】 ●バイオ燃料用藻類生産実証プロジェクト 推定予算(千円):150,000 期間:H27-29年対象者:株式会社ユーグレナ、株式会社中部プラントサービス、三重県、多気町 ●土着藻類によるバイオマス生産技術の開発 推定予算(千円):150,000 期間:H27-29年対象者:一般財団法人藻類コンソーシアム、株式会社熊谷組、株式会社相双環境整備センター、藻バイオテクノロジーズ株式会社、高砂熱学工業株株式会社、筑波大学、株式会社日水コン、富士通株式会社、ヴェオリア・ジェネッツ株式会社、三菱化工機株式会社 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO) 【バイオジェット燃料生産技術開発事業/一貫製造プロセスに関するパイロットスケール試験】 ●高速増殖型ボツリオコッカスを使ったバイオジェット燃料生産一貫プロセスの開発推定予算(千円):660,000 期間:H29-32年対象者:株式会社IHI、神戸大学...

国内における藻類研究の動向(2018年3月現在)
最近は藻ガール尾張のマニアックな紀行記事に押され気味で、私の記事の存在感低下が著しい。それはそれでいいことなのだが、そもそも私の記事と藻ガールの記事の何が違うのだろうか、ってところを色々な角度から考えた結果、『藻に対する愛の差』ってことに行き着いた。よっしゃ、じゃあ俺も負けずに藻への愛に溢れる記事を書いたろうじゃないの! ということで、緊急企画『現時点で国からの研究予算の交付を受けて進めらている藻類関連の研究についてのまとめ』をお届けしたい。すいません、やっぱ愛より金っすわ。 国内の藻類研究予算の出所 まずは日本国内の藻類研究予算がどのような省庁から出ているかの概要図をまとめてみたのでご覧頂きたい。 藻類はその特性上、研究対象が幅広い。このため、特定の省庁に固まることなく、色々なテーマで研究予算がついて、その管轄省庁がどこなのか混乱することも多い。このため、まずは省庁、外局・内局、独立行政法人、大学、民間など、私なりに研究資金が降りてくる階層順に整理してみたのが下の図となる(今回は藻類研究に予算を出している機関だけをピックアップしている)。 例えば内閣府の立ち位置や、独立行政法人と省庁との関係性とか、これまではぼんやりと捉えていたところがあったが、図に落とし込むことで整理できたように思う。 2017年度時点で藻類研究に予算をつけている各省庁の関係図 / 筆者作成 日本の行政システムによる研究推進体制を俯瞰してみると、まずは文科省下のJSPS(日本学術振興会)が管轄している『科研費』を中心に基礎的な研究開発が数多く進められている。科研費の多くは大学がメインであるが、これらの基礎研究の中から、大きな成果が出たものや時流に乗ったものが育ち、次のプログラム(他省庁も含む)としてサポートされていく流れとなっている。 続いて、実際に現在進められている藻類研究を見ていく。 現在進行している藻類研究の一覧 上記ページに、現在進行中の藻類関連研究の一覧をまとめたので是非ご覧頂きたい。管轄している省庁、部局、プログラム名、研究テーマ名、予算規模、対象者で区別している。 研究テーマ数でみると、圧倒的に数が多いのはやはり科研費である。現時点で大小合わせて90近いテーマの藻類研究が進められている。これらの中から未来の大型プログラムへと育つシーズがでてくることを期待したい。また逆に言えば、これら科研費で動いている小型の研究開発テーマ群を眺めることで、研究者たちが次の時代の藻類研究として何に興味を持っているかのトレンドを見ることができるだろう。 ちなみにこういった研究予算の流れ方は、藻類研究に限らず他の研究分野でも似た構造をとっているため、興味のある対象分野でどのような研究がトレンドとなるかを予測する際に科研費のテーマを眺めるのはおすすめの方法である。 次に、動いている研究テーマを『アカデミア系(学問的な興味)』と『ビジネス系(実用化を意識)』に大きく分けてみる。このうちのアカデミア系テーマは、共生、進化、分類といった『進化分類系』、赤潮、アオコ、海中塩分測定といった『環境系』、光ストレス耐性、光エネルギー散逸といった『光合成系』、というような幾つかのカテゴリーに分けられる。 ビジネス系のテーマでは『生産系』『リサイクル系』『CO2利用系』に分けられる。このうち生産系ではやはり燃料生産関連のテーマが多いが、それ以外にも機能性物質(ポリアミン、多糖類、プラスティック、デンプン、脂質)なども出てきている。リサイクル系では排水処理、下水利用、焼却灰利用、リン回収といったものが多い。 CO2利用系はどのテーマに対してもアドオンできるので、メインのテーマ+α的な位置づけで使われている。 今回、こうして藻類研究だけをまとめてみたわけだが、想像していた以上に幅広く、かつ多くの藻類研究に予算がついていることがわかった。まだまだ私が把握しきれていない藻類研究もあることだろう。さらには過去に行われたものの、そのまま日の目を見ずにお蔵入りしているテーマも数多くあるはずだ。日本の藻類産業を創り上げていくためにも、このような藻類研究の全体像を俯瞰しながら、どういった知見や技術が日本にあるのか、もしくはあったのか。それらを整理し、アウトプットすることが大事だ。 バラバラに行われている藻類研究を体系化してまとめ、理解しやすい形で情報発信していくことは優秀な人材の業界への流入にもつながっていくことだろう。そのためにも、藻類に興味を持った誰もがすぐにアクセスできて、国内外の藻類研究の全体像や情報、最新動向がわかる『場』を作ることが重要だ。Modiaが目指すべきは藻類に関する最初の場になることだ。そして、そういった場に命を吹き込む、もっとも大事なピースが『藻に対する愛』なのだろうなぁ。
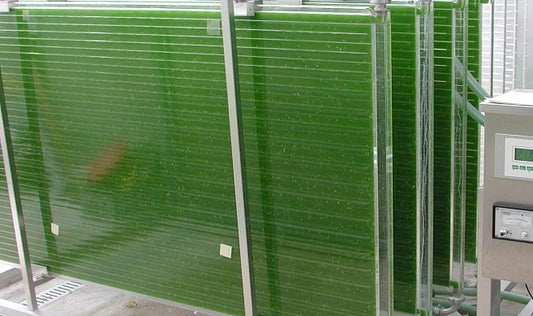
藻類培養の変遷 -円形ポンドから担持体培養まで-
これまで微細藻類(以下、藻類)を培養する方法として、円形ポンド、レースウェイポンド、フラットパネル型培養槽、チューブ型培養槽など様々な方法が考案・実証されてきた。先日Modiaで担持体培養や従来の培養方法との比較に言及した記事が公開されたが、今回は改めてポンド培養から担持体培養に至るまで、藻類培養の変遷を時間軸に沿う形で整理していきたい。 Modia[藻ディア] 大きな可能性を秘める、微細藻類の「担持体培養」とは https://modia.chitose-bio.com/articles/53 これまでModiaでは微細藻類の培養として、主にオープンポンドやフォトバイオリアクターを用いた生産を取り上げてきた。今回は、藻類培養の手法として今後広く普及する可能性のある「担持体培養」を従来の方法と比較しながら紹介していく。微細藻類の培養法の分類まず微細藻類の培養法は、液体培養(懸濁培養)と固体培養に大きく分けられる。従来のオープンポンドシステムやソフトプラスチック(LDPE)を利用したフォトバイオリアクター*は液体培養に分類される。*フォトバイオリアクターについてはこれまでも下記の通り特集してきた一方、... 藻類培養の一次世代「円形ポンド、レースウェイポンド」 藻類培養の歴史を遡ると、まず初めに円形ポンドやレースウェイポンドを用いたシステムが1960年代から1980年代にかけて商業利用され始めた。これらのシステムは、「シンプルで大型化が容易、初期投資が比較的少なく済む」等の理由から、現在でもクロレラやスピルリナの商業生産において広く利用されている。ただ、大きな問題も抱えており、その最たるものが低い光合成効率(光エネルギーからバイオマスへの変換効率)である。水面付近では、日中の非常に強い日射によって「光阻害 (photoinhibition)」と呼ばれる成長阻害を藻類に引き起こしてしまう。一方で、水面から入射する日光は培養液中を数センチしか透過できないため、水面から数センチ以上の水深では光合成によるバイオマス生産がほとんど期待できない。結果として、水面から大きな光エネルギーを得ているにも関わらず、その光合成効率は非常に低い。 こうした理由から、円形ポンドやレースウェイシステムでは水深を最大で30cm程度に限定することが多いが、水深が浅くなることで、天候の変化による水温・水質の急激な変化、バブリングによる水底から供給されるCO2利用効率の低下等の問題が生じてしまう。これらの副次的な問題については、コストを掛けることで一定の改善が可能ではあるが、光合成効率の根本的な改善には繋がらない。 光合成効率を改善させる培養システム「フォトバイオリアクター」 こうした問題を解決するべく、フラットパネル型培養槽やチューブ型培養槽などの新しい培養システムがこれまで考案されてきた。これらの異なる形状の多様な培養システムにおいて、その研究・開発の背景にある哲学は根本的に同じで、光合成効率の改善を目的としている。多くの場合、受光面積/培養容積比の改善がその対処法として検討される。培養容積に対して大きな受光面積を確保し、より多くの細胞に適量(高過ぎも低過ぎもしない量)の光エネルギーを分配することで、光合成効率の改善が試みられてきた。結果として、技術的な側面からのみ論じれば、フラットパネル型培養槽やチューブ型培養槽を始めとした「閉鎖型フォトバイオリアクター(以下、PBR)」では、従来のポンドやレースウェイと比較して高い光合成効率が報告されている。 しかし、商業的な側面では、「PBRが抱える複雑な構造やそれに伴う初期投資の増大、そして大規模化が困難であること」が大きな課題となっている。事実、2016年に刊行されたNational Biofuels Technology Reviewでは、PBR利用の今後における大きな課題として、バイオフィルム除去の必要性や水温管理の難しさと共に、「設備投資の高さ」や「低拡張性」が挙げられている。 簡単にまとめると、これまでの藻類培養システムの歴史は「安いが低効率のポンド vs 高効率だが高いPBR」とのせめぎ合いであるといえる。 次世代の培養法として注目される「担持体培養」 そんな状況の中、コンセプトとしては古くからあるが、昨今その研究・開発が盛んになりつつある新しい培養方法の一つとして「担持体培養」が注目されている。担持体培養とは、何かしらの担持体表面に藻類のバイオフィルムを形成させ、そこに吸水性の担持体もしくは担持体上部からの給水により培地を供給することで藻類バイオマスの生産を試みた方法である。このシステムでは、先に挙げた「受光面積/培養容積比」はこれまで考案されている多様なシステムの中で最も高い値を示している。つまり、理論的には最も高い光合成効率を達成する可能性がある。その上、1) 培養に必要な水分量が非常に小さく、2) ガス交換(CO2供給およびO2除去)効率が非常に高く、さらに3) 既存のPBRと比較して大規模化が容易である と論じられている。 事実、小規模実証試験の結果では、既に50g/㎡/dを超える非常に高いバイオマス生産性が報告されていたり、前述したNational Biofuels Technology Reviewでも、今後検討の余地がある新たな培養システムの一つとして注目されている。また、この担持体培養の概念をポンドやレースウェイシステムに応用した研究(下記記事参照)や、将来的な宇宙開発への応用を期待したNASAの研究等がある。 Researchers...
![ちとせの藻ヂカラ[前編] -ちとせはなぜ藻類プロジェクトに取り組むのか?-](http://matsuri.chitose-bio.com/cdn/shop/articles/098720ff09672cc2474b29e6e50ead70-1024x501.jpg?v=1718795812&width=533)
ちとせの藻ヂカラ[前編] -ちとせはなぜ藻類プロジェクトに取り組むのか?-
世の中には様々な課題に対して様々な技術で挑む人達がいる。センサー技術や今流行りのAI技術、デザインの技術等など色々あるが、わたしたちちとせグループは、生き物を「育種・培養」する技術をベースに様々な課題に取組んでいる。今回は、2000年代半ばから着目し、研究開発のみならず事業化を進めてきた「藻」の話をしようと思う。 「藻」と言われても正直興味ないよと思うかもしれない。ちなみに私も元々「藻」にはさして興味はなかった。 しかし、小さな緑の生き物たちの秘めるポテンシャルや、藻で課題を解決しようと奮闘するちとせのメンバーを見ているうちに「藻」が興味うんぬんではなくもはや当たり前に必要な存在になったように思う。ふと気づいたら、藻の情報サイト『Modia[藻ディア]』を立ち上げて編集長を務めてしまっていたほどで、「藻」という言葉を見ない日はもはやほとんどないに等しい。 マニアック過ぎる情報は『Modia』におまかせするとして・・・、 CHITOSE JOURNALでは、●前編:ちとせはなぜ藻類プロジェクトに取り組むのか(←本記事)●中編:ちとせの藻類プロジェクト●後編:ちとせの武器、3つの藻ヂカラと3回に分けて藻の話をしていくことにする。 ※補足:各プロジェクトは日々動いているため、あくまで現時点(2018.3時点)での情報となります。 千年先まで豊かに暮らすために ちとせグループは、生き物の力を活用することで、千年先まで人類が豊かに暮らせるようにするための技術の開発と展開に取り組む企業群だ。 そう、「ちとせ」とは「千年」の意味からきている。▷社名・ロゴマークに込めた想い 千年先まで人類が豊かに暮らすためには、「食料」と「燃料」は絶対に欠かすことが出来ない資源であり、これらが保証されていることは豊かな生活を送るために絶対不可欠だ。 全ての有機物は太陽エネルギーから ところで、我々は何のために食料や燃料を利用するのか?それは、「エネルギー」を得るためである。食料や燃料に含まれる「有機物」から「エネルギー」を取り出して使っているのだ。 この有機物に含まれるエネルギー、実は全て太陽エネルギーから由来している。「光合成」という植物の営みが玄関口となり、太陽エネルギーを有機物の形に変えて地球上に取り込んでいるのだ。 ※石油や天然ガスなどの化石燃料は、遥か昔、光合成によって生み出された有機物が何百万年もかけて姿を変えたもの 「光合成」の量を増やさねばならない 昨今、世界的な人口増加や生活水準の向上により、食料(特にタンパク質)・燃料需要ともに大幅に増加することが予測されており、このままでは両者とも不足すると言われている。 この問題を解決するためには、これまでよりも効率的に、そして持続可能な形で食料・燃料となる有機物(バイオマス)を生み出す必要がある。 有機物は太陽エネルギーが姿を変えたものなので、まず前提として太陽エネルギーが十二分に存在する必要があるが、この点については心配ない。 つまり、地球に降り注ぐ太陽エネルギーを有機物に変換する「光合成」の量を、利用可能な形でいかに増やすかが人類の持続可能な繁栄に必要なことなのだ。 しかし、慣行農業ベースのバイオマス生産(陸上農業)を拡大することだけでは、この食料・燃料の増加に対応することができない。なぜならば、基本的に農業は土壌を必要とするため土地に制限があり、また、生産性を向上させる技術の目処も立っていないためだ。 そこで、注目すべきが「藻」である。 なぜ光合成の量を増やすのに「藻」が最適なのか 利用可能な光合成量を増やすにあたり、なぜ「藻」に注目すべきなのか。その理由は大きく3つある。 ①生産性が極めて高い 植物は陸上で体を保つため、根、茎、葉といった骨格部分に光合成で取り込んだ多くのエネルギーを割く必要がある。それに対し、藻類は水中生物なので、骨格を多く作る必要がなく、その分のエネルギーは人が活用できるタンパク質や油の合成に使われるのだ。この結果、植物と比べて生産性が大幅に高くなる。 ②土地を選ばない 藻類は水と光さえあれば基本どこでも培養することができる。このため、砂漠や荒地のような、植物が育たず現在利用されていない土地を有効活用することができるのだ。つまり、農業と住み分けが出来るということである。実際、現在実用化されている藻類の多くは農地として使えない土地が利用されている。 ③水資源を有効活用できる 藻類は大量の水を使うようにイメージされがちだが、実は農業よりずっと少ない水資源で培養することができる。農業では畑に散布される水のほとんどが蒸発、もしくは地下に浸透してしまうのに対し、藻類では水面からの蒸発分のみで済むためだ。また、種を選べば汽水・海水を使うこともできるため、淡水資源以外の水資源を利用することも可能なのだ。...

地衣類とは? -藻ガール尾張の博物館紀行-
現在、国立科学博物館では、企画展「地衣類 ー藻類と共生した菌類たちー」が開催中です。 企画展「地衣類―藻類と共生した菌類たち―」(2017年12月19日(火)~2018年3月4日(日))- 国立科学博物館 今回は、簡単に地衣類について整理した後、この企画展の紹介をしたいと思います。 地衣類とは 地衣(ちい)、聞きなれない言葉だと思いますが、私たちの身近なところにいる生物です。例えば、こんなところにいます。 (左)木肌についた黄緑や青緑の地衣類、(中央)木肌についた薄青緑の地衣類、(右)コンクリートについた緑の地衣類 樹木の木肌また岩肌に、まるで黄緑、青緑、薄青緑のペンキが塗られているような光景を見かけたことがありませんか?実はその正体は地衣類なのです。 地衣類は、光合成ができる藻類(緑藻と藍藻(シアノバクテリア))と、光合成ができない全く別の生き物・菌類(酵母、カビ、キノコが含まれる子嚢菌と担子菌)が共生している複合体生物です。地衣類の本体は菌類であり、藻類と共生している生活スタイルを「地衣化」といいます。 地衣類は実に様々な環境に生育できます。極地などの寒冷地域や、有毒ガスが存在する地域など、藻類や菌類が単独では生活できない厳しい環境にも分布しています。 地衣類の共生関係 通常、藻類は水中で光合成をして自力でエネルギーを獲得できる独立栄養生物です。一方で、菌類は私たちと同じ従属栄養生物であり、どこからかエネルギーをもらってこなければ生きていけません。 地衣類横断模式図a:上皮層、b:藻類層、c:髄層、d:下皮層、e:偽根 上図は典型的な地衣類(異層状地衣類)の断面図です。本体である菌類の中の、上図b層に藻類が共生していて、光合成をしています。菌類側にとっては、光合成ができる藻類を体内で飼うことでエネルギーを獲得できるので、好都合であることはすぐに理解できると思います。 では、独立栄養生物の藻類があえて菌類に収まっているのはなぜでしょうか? 藻類側にも様々なメリットがあると考えられています。菌類に入ることで、乾きに弱く水中生活に適している藻類は、乾燥から守られます。それと同時に、光合成に使う光量の調節や紫外線からも守られます。また、外敵からの忌避作用もあるのです。 この様に、地衣類は菌類側にも藻類側にも利点があるため、共生関係が成り立っているのです。そして、共生関係が成り立っているからこそ、極限環境でもお互いに助け合って生活ができて、分布域を広げているのです。 国立科学博物館・企画展「地衣類 ―藻類と共生した菌類たち― 」に行ってきました! 2017年12月19日~2018年3月4日、国立科学博物館では企画展「地衣類 ―藻類と共生した菌類たち― 」が開催中です。終了間近ですが、筆者から展示の様子を少しだけ報告いたします! ※撮影協力:国立科学博物館 展示は1部屋にコンパクトにまとめられていました。ここに、地衣類の説明、標本、化学物質の利用、人々との関わり、アート、マント?!と、1部屋では収めるのが大変だっただろうというほどの充実した展示が行われていました。 主な展示内容は以下の通りでした。・地衣類の生物学的な特徴の説明・高山から街中、はたまた極地から熱帯まで、多種多様な実際の地衣類の標本・地衣類から取れる特殊な化学物質の説明・地衣類色素による染色物の実物・地衣類による環境モニタリングの説明・地衣類食品の実物紹介・地衣類蛍光色素を使ったアート・地衣類マントで地衣類体験 衝撃ナンバーワン 私たちが見かける地衣類といえば、先の写真のような、何かの基質(木や岩など)の側面に添って付着し、一体化している物ばかりと思っていました。しかし、もっと大きくてつるのような地衣類も日本でごく普通にみられることを、藻好きとして恥ずかしながら、この展示で初めて知りました。...

大きな可能性を秘める、微細藻類の「担持体培養」とは
これまでModiaでは微細藻類の培養として、主にオープンポンドやフォトバイオリアクターを用いた生産を取り上げてきた。今回は、藻類培養の手法として今後広く普及する可能性のある「担持体培養」を従来の方法と比較しながら紹介していく。 微細藻類の培養法の分類 まず微細藻類の培養法は、液体培養(懸濁培養)と固体培養に大きく分けられる。従来のオープンポンドシステムやソフトプラスチック(LDPE)を利用したフォトバイオリアクター*は液体培養に分類される。*フォトバイオリアクターについてはこれまでも下記の通り特集してきた Modia[藻ディア] フォトバイオリアクターを用いた微細藻類バイオマスの生産コスト https://modia.chitose-bio.com/articles/18 イタリアのTredici教授の研究グループより、安価なソフトプラスチック(LDPE)を利用した微細藻類屋外培養設備(=フォトバイオリアクター)の技術経済試算に関する論文が発表された。Techno-economic analysis of microalgal biomass production in a 1-ha Green Wall Panel (GWP®) plantフォトバイオリアクターとは Photobioreactor PBR 4000 G IGV Biotech微細藻類を含む光合成を行う生物を、光エネルギーを利用して培養する装置であり、広義には商業用に広くに用いられているオープンポンド・レースウェイもフォトバイオリアクターに含... Modia[藻ディア] バイオリアクター型の藻類生産施設"Algae Dome" https://modia.chitose-bio.com/articles/36...

アスタキサンチンとは? -健康機能と市場の動向-
前回の記事では、ヘマトコッカスという藻類が赤色の抗酸化色素「アスタキサンチン」を蓄える特徴があることをお伝えしました。 Modia[藻ディア] ヘマトコッカスとは? -生物学的特徴とアスタキサンチンの生産- https://modia.chitose-bio.com/articles/characteristics_of_haematococcus アスタキサンチンという赤色の抗酸化色素を蓄えることで有名な藻類「ヘマトコッカス」。数ある藻類種の中でも特に産業化が進んでいる、認知度の高い種です。本記事ではこのヘマトコッカスという藻について、紹介していきたいと思います。1.ヘマトコッカスとは? -生物学的特徴を中心に- 左図:藻類の系統樹、右上写真:ヘマトコッカスの通常時の様子、右下写真:ストレス下の様子 / 筆者作成ヘマトコッカスとして一般的に知られる藻類は、Haematococcus pluvialis(※)という、真核生物>アーケプラスチダ>緑藻綱>ボルボックス目>ヘ... 今回はそのアスタキサンチンを掘り下げていきます。アスタキサンチンは藻類の抽出物として国内外で産業化が進み、いま多くの注目を集めている物質です。 1.アスタキサンチン(Astaxanthin)とは アスタキサンチンの骨格イソプレン(a)とアスタキサンチン(b)の構造式 / 筆者作成 アスタキサンチンは、カロテノイドの一種キサントフィル類の脂溶性物質の赤橙色の色素で、化学式 はC40H52O4です。 カロテノイドとは、イソプレン骨格の炭素数が40個まで連なった共役二重結合を持つ長鎖の一群の色素の総称です。このカロテノイドの中で、炭化水素のみを持つものをカロテン、酸素を含む官能基(ヒドロキシ基[-OH]、ケト基[=O]、カルボニル基[−C(=O)−]など)を含むものをキサントフィルといいます。今回取り上げたアスタキサンチンは共役二重結合の数がカロテノイドの中で最多の13個あり、両末端環にケト基とヒドロキシ基を持つ構造(上図参照)をしています。 また、カロテノイドは抗酸化機能に重要な役割を果たすことが知られています。その中でもアスタキサンチンは、抗酸化機能を持つ部位が他のカロテノイドよりも多いことが報告されています。後ほどお話しますが、この抗酸化機能を利用した健康に関する研究も進められています。 2.様々な動物に含まれているアスタキサンチン 海釣りの餌に使われるオキアミ、サーモン、茹でたエビ、カニといった、魚介類の赤い部分の多くは、アスタキサンチンの赤色です。また、フラミンゴ*のピンク色も、アスタキサンチンによるものです。しかし、動物はアスタキサンチンを自分で作り出すことはできません。では、これらの生き物はどこからアスタキサンチンを手に入れているのでしょう?*ケニアのコフラミンゴの様子を特集したこちらの記事も併せて参照ください アスタキサンチンを持つ動物たち (a)オキアミ、(b)サーモン、(c)カニ、(d)フラミンゴ 自然界でアスタキサンチンを生成できる生物はヘマトコッカスなどの微生物だけです。つまり、アスタキサンチンの赤色を持つ動物には、アスタキサンチン(もしくはその元となるカロテノイド)を持つ藻類を直接または間接的に摂取しているのです。例えば、アスタキサンチンを持つ藻はオキアミといった小型の動物に食べられ、そのオキアミはエビやサーモンといった中型の動物に食べられ、これら中型の動物はフラミンゴといった大型の動物に食べられるのです。 ちなみに、エビやカニといえば、青みがかった色を思い浮かべる人も多いのではないでしょうか。実はエビやカニは、生きている間は体内のアスタキサンチンがタンパク質(オボルビン、クラスタシアニン)と結合するために黒っぽい青灰色をしているのです。そして、茹でる・炒めるなど熱を加える過程でタンパク質が変性し、アスタキサンチンが遊離されて本来の赤い色が出てくるのです。 3.アスタキサンチンの健康機能 アスタキサンチンの抗酸化作用はビタミンEの約550倍から約1,000倍、βカロテンの約40倍という報告もあり、「自然界最強の抗酸化成分」といわれ、近年注目が集まっています。またその抗酸化力の強さから「老化抑制、免疫機能の促進、筋肉疲労の改善」といった、アスタキサンチンの健康への効果に着目した研究も進められています。 アスタキサンチンがもたらす健康への効果 / Yamashita ,E...

日本発!下水を利用した珪藻培養のパイロットプラントの完成 -兵庫県立大学チームの取り組み-
これまでトレンド記事は海外のものを紹介することが多かったが、今回は日本からのニュースをお伝えしたい。 珪藻培養のパイロットプラントの完成 共同発表:珪藻のフィジオロミクスに基づく褐色のエネルギー革命のためのパイロットプラントの完成~培養コストの大幅低減による低炭素社会実現と有用物質の生産~ 共同発表:珪藻のフィジオロミクスに基づく褐色のエネルギー革命のためのパイロットプラントの完成~培養コストの大幅低減による低炭素社会実現と有用物質の生産~ 先月1月25日(木)に兵庫県立大学で記者発表があり、菓子野准教授らの研究グループが珪藻の一種であるCheatoceros gracilisを培養するためのパイロットプラントを完成させたことが報告された。C. gracilisは珪藻の一種であり、エビの初期餌料や二枚貝の餌として利用されている海産性の藻類だ。 今回のパイロットプラントには、ハウス内に約3.5x6メートルのプール型培養槽、約2x10メートルのレースウェイ型培養槽の2タイプの培養槽が設置されており、5〜8トンの培養が可能とのことだ。 このパイロットプラントは下水処理場の隣に隣接しており、処理場に流入する汚水、および汚水処理により発生するCO2を用いた培養試験ができることが特徴だ。下水中に含まれる窒素やリン酸を栄養塩として使って培養することで、培養成分のコストを抑えた培養が可能となる。 珪藻培養のパイロットプラントの外観図 / 兵庫県立大学提供 下水で藻類を培養する、という試みは特段珍しい話ではない。海外でも国内でも下水中に含まれている栄養源を利用して大量培養系の構築を試みる取り組みは以前から行われている。実際、下水を用いた培養というのは絵としては美しいが、現実的にはなかなか難しい。下水中には確かに栄養源はあるのだが、その濃度というのは藻類の培養に最適化されているわけではないので、高い生産性を出すにはある程度の濃度調整をする必要が出てくる。今回用いる下水自体の水質がどれだけ安定しているかも一つポイントになるだろう。 また、下水には多くの他の微生物が混じっているので、それらが混在する中で狙った種を優先種としてキープさせるには、高い培養技術が求められる。ただ、今回は海産性のC. gracilisを用いているので、海水と混ぜる事によって下水(=淡水)由来の微生物の繁殖はある程度抑制できる可能性がある。この際、塩濃度の条件設定もキーとなってくるだろう。今回のパイロットプラントを使った実証で最適化条件を見つけられる事を期待したい。 同大学におけるその他の取り組み -C. gracilisの遺伝子組換え技術の確立とマイクロバブルを用いた抽出プロセスの開発- なお、菓子野准教授のグループは、パイロットプラントを設置する前から、C.gracilisの基礎研究を体系的に進めている。2015年にはエレクトロポレーションを用いたC. gracilisの遺伝子組換え技術の確立に世界で初めて成功し、汎用的な形質転換ベクターも開発している。 遺伝子組換えのターゲットとしては、リシノール酸(C18H34O3)を生産させている。 リシノール酸(C18H34O3)の骨格 リシノール酸はω-9型の非飽和脂肪酸で、天然ではトウゴマの種子に存在する。ひまし油の構成脂肪酸の約90%はリシノール酸のトリグリセリドである。工業的にはひまし油の加水分解または鹸化によって作られている。鎮痛剤や抗炎症剤としての効果があり、薬としても用いられる。 左写真:ひまし油 中央写真:トウゴマ 右写真:トウゴマの種子 さらに同研究グループは、マイクロバブルを用いた新規な抽出プロセスも開発している。これは培養液内でマイクロバブルを発生させ、細胞を破壊し、発泡した泡画分に成分(油脂)が濃縮される、という仕組みとなっている。通常、マイクロバブルは藻体の浮上や光合成効率の活性化に用いられていたが、このように細胞破砕と濃縮に用いた例はなく、昨年特許*も出願されている。*特願2017-038278:有用物質回収方法及び有用物質回収装置 今回は下水と組み合わせた大量培養のためのパイロットプラントに関する記者発表であったが、培養から出口となる高付加価値なターゲット、さらに低コストな回収プロセスまで一貫して開発を進めているところも把握しておきたい。点ではなく、それぞれの技術が線としてちゃんと繋がっているのは、目標としている構想がしっかりしているからだろう。 珪藻を軸にした再生可能物質生産に基づく低炭素社会 / 兵庫県立大学提供 日本にはこのような優れた研究をしているチームが複数あるが、これらの優れた知見や工夫が他のチームにも共有されるような場を作っていくことが、国として藻類研究の底力を強化することに繋がるはずだ。Modiaもその一端となれるよう、海外動向だけじゃなく、国内の優れた技術の把握と共有にさらに力を入れていきたい。 参考画像・”Castor...
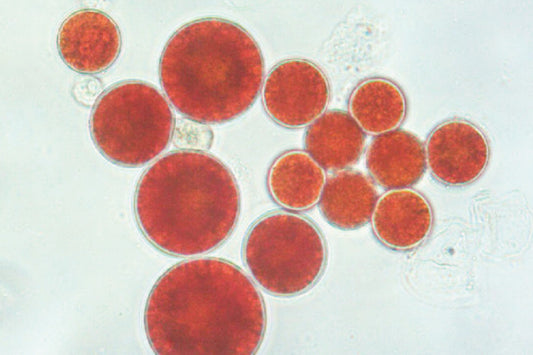
ヘマトコッカスとは? -生物学的特徴とアスタキサンチンの生産-
アスタキサンチンという赤色の抗酸化色素を蓄えることで有名な藻類「ヘマトコッカス」。数ある藻類種の中でも特に産業化が進んでいる、認知度の高い種です。本記事ではこのヘマトコッカスという藻について、紹介していきたいと思います。 1.ヘマトコッカスとは? -生物学的特徴を中心に- 左図:藻類の系統樹、右上写真:ヘマトコッカスの通常時の様子、右下写真:ストレス下の様子 / 筆者作成 ヘマトコッカスとして一般的に知られる藻類は、Haematococcus pluvialis(※)という、真核生物>アーケプラスチダ>緑藻綱>ボルボックス目>ヘマトコッカス属の藻類です。 ※生物分類の学名はHaematococcus lacustris (Gir.-Chantr.) Rostaf. ですが、Haematococcus pluvialis Flot.として広く知られています。 通常の形態は緑色をした少し縦長の細胞で、そこから生えた2本の鞭毛で動き回ります。そして、細胞の外側には寒天質の透明な膜がうっすらと覆っています(右上写真を参照)。この寒天質がヘマトコッカスの形態学的特徴の一つです。 ヘマトコッカスの最大の特徴は、細胞がストレスを感じるとアスタキサンチンという赤色のカロテノイド色素を蓄積することです。ストレス初期は鞭毛の生えた状態で緑色から徐々に赤色に変化していき、ストレスが一定以上続くと鞭毛のない球状の細胞に成長していきます。通常時とストレス下での違いについては、写真で見るのが最も分かりやすいと思うのでぜひ下記よりご覧ください。 www.photomacrography.net :: View topic - Haematococcus pluvialis, astaxanthin, cysts www.photomacrography.net :: View topic - Haematococcus...

微細藻類が薬剤耐性の救世主に!? -NoMorFilmプロジェクトの取り組み-
現在、世界各地で薬剤耐性(AMR)の予防が叫ばれ、抗菌薬の過度な使用についての喚起が広がっている。 国連広報センター 薬剤耐性は「無視できない危機」と国連が警告 抗生物質の責任ある使用を呼びかけ |... http://www.unic.or.jp/news_press/features_backgrounders/26692/ 薬剤耐性感染症への抗生物質の効果をテストする研究所職員©Photo: PAHO/Joshua Cogan2017年11月13日 – 国連は11月13日に始まった... 歴史を遡ってみると、1928年に世界で初めての抗生物質としてペニシリンがイギリスの医学者アレクサンダー・フレミング(Alexander Fleming)によって発見されて以来、各地で抗菌薬の開発が進み、無数の命が救われてきた。その後、最初の数十年間に年間約15~20種の新たな抗菌薬が開発・承認されたが、直近十年で上市された新たな抗菌薬はわずか6種しかない。抗菌薬を使い続けると耐性菌が現れ常に新たな抗菌薬が必要とされる中、国連をはじめ世界各地で薬剤耐性に対して警鐘が鳴らされている。 薬剤耐性の要因の一つであるバイオフィルムとは こうした薬剤耐性を引き起こす原因の一つが、バイオフィルム(菌膜、Biofilm)だ。バイオフィルムとは、細菌が菌体外に分泌する多糖類などのマトリクスと菌の集合体により形成される構造体を指す。我々の生活に身近なところでは洗面台や浴槽のヌメリや歯垢などがバイオフィルムの一種である。 このバイオフィルムは医療現場において治療を大変難しくしている。というのも、細菌が付着・増殖してマトリクスに覆われたバリアを張った状態(=バイオフィルムを形成した状態)になると、薬剤に抵抗性を示すだけでなく、生体の防御機構から逃れやすくなるからだ。アメリカ国立衛生研究所(National Institutes of Health;NIH)の報告によれば、細菌感染症の80%以上はバイオフィルムが関与していると推定されている。近年、インプラントやカテーテル、人工関節などの人工医療材料を用いた治療に伴い、バイオフィルムに関連した感染症(バイオフィルム感染症)が増加している。一旦バイオフィルム感染症が起これば、感染症のコントロールは困難となり、医療材料を摘出せざるを得ないのが現状である。この場合、抗菌薬使用の増加を伴い、再置換術のコストは一件当たり約60,000〜100,000ドルの増加が見込まれる。 微細藻類を使った抗菌成分の探索への期待 バイオフィルム等により薬剤耐性が拡大している一方で、新規抗菌薬の開発は停滞している。こうした困難な状況の中、スペインのバルセロナ国際保健研究センター(ISGlobal)が率いるNoMorFilmプロジェクト*は、抗菌薬の開発にあたり微細藻類の可能性に注目している。このプロジェクトは、大陸を超えて世界各地から収集した6,800種類もの微細藻類から、全く新しい構造を持つバイオフィルム系抗菌成分の探索を目的としており、来年3月まで研究が進められている。NoMorFilmの目的や研究開発の様子を知りたい方は、是非下記動画をご覧頂きたい。*本プロジェクトは、EUの研究助成プログラムである”Horizon 2020”に採択され、2015年4月1日~2019年3月31日の4年間、760万ユーロの研究助成金を受けて研究が進められている。 今回取り上げた薬剤耐性の問題については日本政府も対策を急いでおり、現に2016年4月には下記「薬剤耐性対策アクションプラン」が策定された。その中で、新規抗菌薬の研究開発も重点推進6分野の1つに含まれている。 https://cdn.shopify.com/s/files/1/0655/9730/9184/files/AMR.pdf?v=1718806494 微細藻類は未だに多くの謎を持っており、藻ディアでも注目し続けてきた。しかし、未知な部分が多いからこそ、微細藻類が人々の健康に脅威を与える薬剤耐性や感染症を克服する抗菌薬の画期的な突破口になり得るのではないかと強く期待している。まずは、今回取り上げたNoMorFilmプロジェクトの行方を注視していきたい。 参考資料・薬剤耐性(AMR)対策アクションプラン -厚生労働省http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10900000-Kenkoukyoku/0000120769.pdf・森川...

藻類という思想
毎年、年末年始は引きこもって時間ができるので、自分の興味の源泉は何かというところについて考える。特に昨年はModia[藻ディア]で記事を書き始めたこともあり、自分が藻類のどの辺に惹かれているのか、ということを改めて考えてみた。 私はアカデミックな研究対象として藻類に惹かれているわけではない。藻ディアで共に記事を執筆している尾張のように顕微鏡を覗いて藻類の姿形に興奮することもなければ、種を分類したり、進化の過程を知ったり、新しい代謝経路の発見にテンションが上がるタイプではない。また、星野のように藻類培養装置の設計、培養技術の開発、大規模生産システムの構築、というような生産工学的な方面に興味があるわけでもない。ならば、生産された藻類の製品化や商品設計、それらを販売するためのマーケティングがやりたいのか、と聞かれればそれも違う。 それでは、なぜ私は藻類に惹かれているのか。 光合成を起点とした藻類の持つ意志 思考を整理するにあたって最初に振り返ったのは、「藻類が持つ、太陽光から生命*を生み出す機能」に興味があるという自分の感覚だ。*ここでは”生命=自ら増えるもの”と定義しておく。 例えば、太陽光を浴びた石は熱くなるが、石自体はその熱によって増えようとするわけではない。一方、太陽光を浴びた藻類は分裂し、自ら増えようとする。石には増える意志がないが、藻類には増える意志がある。端的に言えば、生命と非生命を分ける意志の発生こそが自分の興味の原点ともいえよう。 生命には意志がある 生命について食物連鎖的な観点から見ると、光合成が最初の反応となる。光合成によって有機物が合成され、そこに意志が宿ることで生命が誕生しているわけである。つまりは、光合成の反応を突き詰めていけば、意志が発生する瞬間が見えるかもしれない。そんな背景から、私は光合成を研究してきた経緯を持つ。ただ、残念ながら、光合成の反応を細かく調べたところで、酵素の活性を見ることはできたが、そこに意志の発生を感じることはできなかった。 一方、研究をしながらふと思ったこともあった。それは光合成というシステムで有機物が合成されたから意志が発生したのではなく、最初に意志があったから光合成が物質合成するようになったのではないか、ということだ。逆説的な話であるが、研究を進めるまでは『最初に物質があって、そこに意志が吹きこまれて生命が生まれる』と考えていた。しかし、実はそうではなくて、『最初に意志があって、そこに必要な物質が集まると生命という形をとる』という順番である気がしたのだ。 非科学的な話であることは自覚しているのだが、私にはこの考え方が妙にしっくりきたのだった。仮にそうだとした場合、最初から存在している意志というものは何か、いつどこにいるのか、という話になる。人によってはそれを気と言ったり、魂と呼んだり、マザーネイチャーとか名付けたり・・となるのかもしれないが(こうした類の話も個人的には好きであるが)、私がたどり着いた答えは「循環」であった。 生命系の循環における藻類の役割 地球上では水、炭素、窒素を始め、様々な物質がそれぞれのスケールで循環しているが、この循環する力=意志であると考えたのだ。というのも、循環は一方向に回転する力であり、その方向に従って全物質が動いている以上、循環こそが生命を支配している意志と言えるんじゃないかと思ったからだ(そもそもこのエントロピー増大則はどこから来ているのだろう・・とかなると議論がまとまらなくなるのでひとまず置いておく)。いずれにしても、大前提として常にどこにでも循環が発生している世の中で、光合成のシステムも生物も、循環することを正とし、それに最適化するように発生し、進化してきたのではないか。 炭素循環の絵。炭素に限らず様々な物質が循環しており、世界は循環に支配されているとも言える。 この物質循環という流れの中の、我々が属する生命系の循環について考えた時に、藻類というのは循環の動力となる太陽エネルギーを取り込むポジションに位置することとなる。そう考えると、私は循環のエンジンとしての役割を持つ藻類に惹かれていたのであり、興味の本体は循環思想にあることに改めて気づいた次第である。 藻類を起点とした新循環の絵 / 筆者作成 このような自身の興味の本体を踏まえた上で、人類が新しく手に入れた「藻類」というエンジンを使ってどんな循環を生み出していけるのか。そして、その新しい循環を作った先に人類がどんな文化を生み出していくのか。それが見たくて、知りたくてずっと藻類と関わってきているんだな、という結論に至った。 ・・と新年早々、とてもパーソナルな話にお付き合い頂きありがとうございます。今年もどうぞよろしくお願いします。 参考画像・”Beech seedling“© 2010 The Cookiemonster / CC BY 2.0・”Bufo boreas“© 2011...

一生に一度は見てみたい! -藻が作り出す絶景7選-
昨今、藻といえばタンパク質等の栄養面や燃料利用に注目が集まりがちだが、藻の持つ色素も同様に重要な特性だ。藻ディアでも、藻の色素を上手く活用した商品を紹介してきた。 Modia[藻ディア] 藻の口紅 https://modia.chitose-bio.com/articles/10 先日の7月6日は「国際キスの日」だったらしい。(ただ、日本では5月23日が「キスの日」とされているし、更には国によって日が異なるようだ。)そんなキスの日にちなんで、藻類由来の成分が入った口紅「Skinicer Ocean Kiss」を紹介する。引用元:https://aesthetikonzept.com/product/skinicer-ocean-kiss-lipstick-classic-red/入っているのはスピルリナ(Spirulina platensis)由来の抽出物で、成分名はSpiralinと命名されている。Ocean-Pharmaというドイツの会社が製造しているようだ。スピルリナはスピルラン(Spirulan)と呼ばれる... Modia[藻ディア] 生きてるインク https://modia.chitose-bio.com/articles/15 藻類の『色』と『増殖の速さ』をうまく利用した生きているインクの紹介をしたい。このユニークなアイデアを形にしているのはLiving Ink社。コロラドに拠点をおくコロラド州立大発のベンチャー企業だ。https://www.instagram.com/p/-welbJnjkj/?taken-by=livinginktech世界で最もサステイナブルなインクを、藻類でCEOのScottとCTOのSteveの2人は、コロラド州立大学でPh.Dとして分子生物学の研究をしていた時に出会った。2人とも藻類からのバイオ燃料とバイオプロダクトの研究をしていたという。藻類を使ったプロダクトアイデアを考え... 今回は少し視野を広げて、色素を始めとする藻の特性が生み出した幻想的な景観を紹介していきたい。奥地にあることや絶景が見られる期間が限定されていることから、実際に訪れるのが困難な場所もあるが、絶景の写真とその成り立ちだけでもご覧頂きたい。 1.クリミア半島の赤く染まる海(ウクライナ) まず紹介したいのは、ジブリ作品「風の谷のナウシカ」に登場する「腐海」のモデルとなった、ウクライナのアゾフ海の西岸に広がる干潟だ。これは、微細藻類ドナリエラ(Dunaliella)が増殖することによって、海が赤く染まって見えるのだそうだ。ちなみに、以前藻ディアでは、ドナリエラが繁殖した中国の塩湖を特集しているので、未読の方は併せて参照頂きたい。 Modia[藻ディア] 彩りの塩湖。その彩りの正体は? https://modia.chitose-bio.com/articles/6 中国山西省にある「中国の死海」として知られる運城塩湖は、毎年春になり気温が上昇すると湖の色がカラフルに変わる、人気の観光スポットである。色が異なる複数の小さな湖で構成される運城塩湖を上空から眺めると、まるでカラーパレットのように鮮やかな彩りである。是非、下記のリンク先の写真を見ていただきたい。China's 'Dead Sea' Transforms Into A Rainbow-Here's WhyA salt lake...
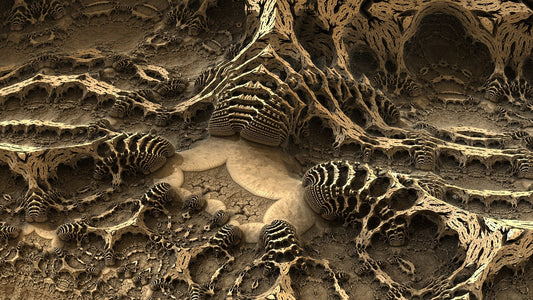
マダガスカルで7,000万年前に起こった動物の大量死の原因とは!?
先日Modia[藻ディア]で公開された『海洋無酸素事変 -藻が動物の絶滅に関わっていた!?- 』の記事内に、「藻の大繁殖が、地球規模での動物の大繁殖や大絶滅の引き金になっていた可能性がある」という記述があったが、その一例と考えられる記事があったので今回紹介したい。 Modia[藻ディア] 海洋無酸素事変 -藻が動物の絶滅に関わっていた!?- https://modia.chitose-bio.com/articles/30 先日公開された藻ディアの記事で、「太古の海洋における藻の大繁殖と動物の進化・繁栄の関連性」について紹介された記事があった。その中で取り上げられた論文について、海外のニュース記事では「Algae paved way for animal evolution(藻類が動物の進化の道を作った)」という大層なタイトルを付けて紹介されていた。今回は、このタイトルとは180度異なる、藻の話を紹介していく。藻が持つ負のイメージインターネットのニュースサイトで、「藻」や「Algae」を検索してみると、藻類が持つタンパク質(当記事を参照)やジェット燃料(当記事... 記事によると、アフリカ大陸マダガスカル島のマジュンガ盆地に存在する、白亜紀後期に堆積した地層マエバラノ層(Maevarano Formation)において、約7,000万年前に生息していた恐竜、ワニ、トカゲ、鳥など約1,200種の動物の化石が見つかったという。同一種ではなく多様な種の動物の化石が、堆積岩層のほんの一部(テニスコートの3分の1の面積)からまとまって見つかるのは異例なことだ。一体、この原因は何であろう? Did tiny algae fell mighty dinosaurs? Seventy million years ago, they all came to...
![[訪問記]伝統的な智慧と、最新の科学が融合!?マレーシアで出会ったHighly educated farmerの哲学](http://matsuri.chitose-bio.com/cdn/shop/articles/2_7eafa780-95f2-419d-9094-0d01c59f9859.jpg?v=1718782584&width=533)
[訪問記]伝統的な智慧と、最新の科学が融合!?マレーシアで出会ったHighly educated farmerの哲学
先日、マレーシアのとあるファームを視察させてもらう機会があったのだが、そこで出会った人々やシステムに多くの刺激を受けたので紹介したい。 自然の力を効率的に活かした次世代型ファーム マレーシアのサラワク州の州都クチンから車で1時間ちょっとに位置するこのファームでは、平飼いの鶏を行っている。設立は2年ほど前で、現在飼っている鶏の数は約5,000羽ほど。「平飼い」「完全有機」「抗生物質フリー」を売りに市場価格の3倍程度の値段で市場に卸しているが、消費者の反応は上々だそうだ。テストマーケティングを終えて、これから生産の拡大を考えているとのこと。オーナーは複数の事業体を経営し、すでに一財を成している華僑の方だ。 このファームの特徴は、鶏を核とした地産地消の循環型システムが形成されていることだ。同様のコンセプトを持つファームというのは日本でもよく聞く話ではあるが、それがちゃんと機能しているファームを私自身は初めて見たように思う。 当初は雛を外部から購入し育てて出荷していたが、現在は自分達で採卵から孵化まで行っているとのこと。また、いくつかの系統の親鶏を購入し、掛け合わせながらオリジナル種の作成にもトライしている。もともと経験はなかったようだが、試行錯誤して系を立ち上げたと話していた。とりあえず自分たちでなんでもやってやろうのDo It Yourself の姿勢はこのファームのポリシーとして一貫している印象を受けた。 孵化装置。下の段には生まれたばかりの雛がいた。中には卵の殻を破ることができずに息絶えるものもいる。 孵化後の幼鳥たち。羽数の割には静かであった。掛け合わせを行っているため、羽の色は様々。 効率的な餌の生産システム ちなみに、餌も彼らが独自に調合したものを使っている。近くに生えている竹から始まり、バナナ工場から捨てられる廃棄物、ホテルや飲食店から出る食品残渣で育てたブラックソルジャーフライ(アフリカミズアブ)と呼ばれるハエの幼虫などなど。基本的に、野生に生えているものか廃棄されているもので作られている。 その中でも興味深かったのはブラックソルジャーフライの幼虫、要はウジ虫の生産システムだ。私も文献や映像では人工生産の様子を見たことはあったが、実際に組織的に生産されている現場を初めて見たので、少し詳細に説明したい。 まず、30×80cmほどの大きさの船型の容器に食品残渣を入れ、そこに卵から孵化させた幼虫を入れる。幼虫は残渣を食べて大きくなり、2週間弱で2kgほどの量になるという。1gの卵が2週間で2,000倍になるのだからなかなかの効率だ。この育った幼虫はある程度まで育つと蛹になるため乾いた環境を求める習性をもつ。このため、残渣で湿った餌場から離れたところを目指して壁を登っていくのだが、壁の途中に穴が空いており、登ってきた幼虫がその穴から下の収穫コンテナに落ちていく仕組みになっているのだ。まるまる太った幼虫が自動的に収穫機の中に落ちていく姿は、登って火に入る何とやらである。こうして収穫された幼虫は、乾燥させると40%タンパク質、30%脂肪という高栄養価の粉末となり、これが鶏の餌として使われるわけである。 飼育容器は船型になっていて、餌となる食品残渣が入れられている。前後の斜めになっている壁を幼虫が登っていく仕組み。 斜めの壁に空いている穴。蛹になろうとする幼虫が登ってきてこの穴から落ちる。 自動的に落ちてきた幼虫たち。人の手を全く介さずに収穫できる。 入れる餌の量は深さで決まっていて、6cmほどだと言っていた。というのも、それ以上深く入れると残渣自身が自己発酵によって温度を持ち、高温度に弱い幼虫が死んでしまうのだそう。自然の動きや虫の特性をしっかり理解して、それを効率的な生産システムとしてワークさせていることに感心しきりであった。 自然の摂理を積極的に活用 また、タンパク質源としてはウジ虫以外に池に生えているアカウキクサも利用していた。このウキクサは根の部分に窒素固定できる藍藻が共生しており、窒素肥料を入れなくても育つことができる。大豆でいう根粒菌のようなものだ。その窒素固定量については様々な報告があるが、日本の水田で約1年間で総計ha当り450kgの窒素を貯えることができたとの報告がある(1978 渡辺)。通常、水田への窒素肥料投入量は50kg程度とされるので、その固定能の高さがわかるだろう。この窒素固定力は熱帯マメ科牧草の窒素固定量年間最高値に近いものであり、熱帯などで緑肥として利用していることも理にかなっている。ここの池では2週に1度の頻度で収穫して餌として与えているとのこと。 池に生えているアカウキクサ。強い光が当たるとアントシアニンをためて赤くなる。根に窒素固定ができる藍藻が共生しており、窒素肥料がなくても生育できる。 アカウキクサの近影写真。茎は短く、羽状に分枝して、長さ約2mmほどの葉を密生する。 上葉には、粘液質の液体で満たされた小孔があり、そこにラン藻(シアノバクテリア)の仲間であるアナベナの1種(Anabaena azollae)が共生している。アナベナは大気中の窒素をアンモニアに還元して、栄養素として利用可能とする能力をもっており、それによってアカウキクサの繁殖を助けている。 その他にもアレロパシー*を利用した農作物の栽培などを行っている。例えばマリーゴールドの隣に唐辛子系の作物を植えると虫や病気になりにくい、とかそういうものだ。*ある植物が他の植物の生長を抑える物質を放出したり、またある動物、微生物を防いだり引き寄せたりする効果の総称 ファーム内には様々な植物がアレロパシーの配置を考えられて植えられている。一つ一つの植物に学名・特性・用途等の解説がある。 他に、飼育段階で印象に残ったのは、パイロンという蛇を雛のいるケージで飼っていることだ。パイロンは木製の箱に入っていてるだけなのだが、こいつが置いてあると、雛を食べてしまう野生の鳥が近づかないそうだ。箱の中にいるので姿は見えないのだが、臭いなのか第6感なのか、野生の鳥はパイロンがいることに気づいて近寄らないという。パイロンは3匹いて、1ヶ月ごとに交代させているということだった。さながら用心棒といったところだろうか。 用心棒として飼われているパイロン。この箱を置いているだけで外敵が寄ってこないとのこと。ただ、1ヶ月ぐらいで効果が切れるので交代させるそうだ。 現場で貫かれていた哲学...
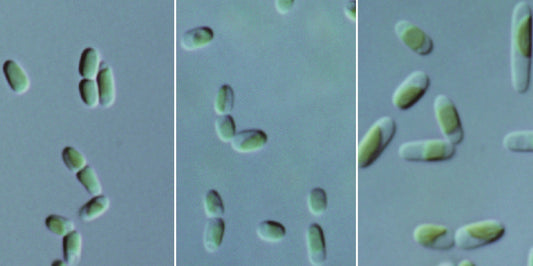
藻はどうやって生きているのか?-独立栄養と従属栄養の違い-
中学や高校の生物の授業で、「植物は光合成をするので、生きるのにエサを必要としない『独立栄養生物』である」、「動物は生きるのにエサを必要とする『従属栄養生物』である」と習ったことがある方も多いと思います。 それでは、藻はどうやって生きているのでしょう?「光合成するから、もちろん『独立栄養生物』でしょ!」と考える方が多いでしょう。実は、その考え方は合っているとも、間違っているとも言えるのです。 そもそも、生物界全体を見回してみると、光合成をする従属栄養生物もいますし、光合成しなくても生きられる独立栄養生物もいます。つまり、各生物は一つの分類に当てはまるものでもないのです。 今回は、藻類を含めた生物界の栄養的分類の整理と藻類の栄養的分類のお話をしたいと思います。独立栄養と従属栄養の違いは何なのか。これを理解しないと、藻類ビジネスにおける藻類バイオマスの生産性とコストを正しく試算することはできません。 栄養的分類とは Wikipediaでは、栄養的分類に関して以下のように説明されています。 『栄養的分類とは、生物の増殖、生育条件による分類法であり、厳密な種の分類等にはあまり用いられないものの、網羅的な性質を簡易に理解するために用いられる。』 引用元:Wikipedia 言い換えると、栄養的分類とは、生きるために必要な栄養を得る方法を整理した生物の性質を示す分類を指します。つまり、生物種の分類のように、一種に対して一つに決まる分類ではなく生物一種に対して複数の分類が当てはまることもあります。 実際に栄養的分類を見てみましょう。下記の通り、8つの分類に分かれています。 『栄養的分類』/Wikipediaより引用 後ほど詳しく説明しますが、栄養的分類は3つの構成要素(エネルギー源、還元当量源、炭素源)から成り立ちます。3つの構成要素がそれぞれ2種に分かれるため計8つの分類になっていますが、中には該当する生物がいない分類もあります。 一般的に使われる「独立栄養生物」、「従属栄養生物」とは? 上記表からも分かる通り、正しい栄養的分類における「独立栄養生物」と「従属栄養生物」の違いは、『炭素源』が「二酸化炭素」か「有機物」かに依るだけで、両者はそれぞれ4つもの異なる分類に細分化されます。 皆さんが普段目にする生物について言えば、植物は「光合成無機独立栄養生物」、動物や菌類(キノコ)は「化学合成有機従属栄養生物」に当てはまります。これを略して、植物は「独立栄養生物」、動物・菌類は「従属栄養生物」と言っているのです。 栄養的分類の構成要素 生物が生きるということは、”生体で「何か」と「何か」を混合して、新しい有機物をつくる” という反応を常に繰り返すことです。この反応を起こすためには、駆動する「力」が必要です。栄養的分類とは、この生きるための根本的な反応を分類したものです。上記の説明では「力」が『エネルギー源』、「何か」が『還元当量源』と『炭素源』に当ります。 以下、それぞれについて簡単に説明していきます。 (1)エネルギー源(光合成 / 化学合成) 反応を起こすためのエネルギー源を示します。「光合成」とは、文字通り光を利用してエネルギーを得ることです。光リン酸化と呼ばれる反応からエネルギーを得ています。「化学合成」とは、還元型化合物の酸化によってエネルギーを得ることです。酸化的リン酸化と呼ばれる反応からエネルギーを得ています。 (2)還元当量源(無機物 / 有機物) 光合成でも化学合成でも、共通して言えることは、何かを酸化してエネルギーを得ているということです。酸化させられる物質、つまり還元する物質を「還元当量源」といいます。これは、電子提供する物質ともいえます。還元当量源は、「無機物」か「有機物」に分かれます。「無機物」は、主にH2Oですが、H2S、H2などがあります。「有機物」は、段階的に反応する系(回路)なので、様々な物質や反応があります。 (3)炭素源(CO2 / 有機物) 生物に必須の有機物が、何の炭素源から作られるかを示しています。炭素源はCO2と有機物に分かれ、CO2を利用する生物を「独立栄養生物」といい、有機物を利用する生物を「従属栄養生物」といいます。その中でも一番有名な有機物は、炭水化物の単糖・グルコース(ブドウ糖)ですが、様々な糖、脂肪やタンパク質も利用されます。 ここまで、栄養的分類の要素について見てきました。そして、先に植物は「光合成無機独立栄養生物」とお伝えしましたが、同じく光合成をする藻類はどこに分類されるでしょうか?...

藻の「光る」特性を活かした神秘的な置物
冬になり、街のあちこちに美しく輝くイルミネーションが見られるようになったが、冬だけではなく年中イルミネーションを楽しめる神秘的な置物について今回は紹介したい。 以前、藻ディアではオーストラリアの夜光虫の記事を取り上げたが、夜光虫は今回取り上げる渦鞭毛藻の一種で、夜に波しぶきなどの物理的刺激を受けると、「光る」性質を持っている。 Modia[藻ディア] 南オーストラリアの夜光虫 https://modia.chitose-bio.com/articles/1 南オーストラリアのポートリンカーンの近くのTulka beachで、暗闇に光る藻が発生している。光の正体はNoctiluca scintillansと呼ばれる渦鞭毛藻の一種で、日本では『夜光虫』と呼ばれている。「虫」という言葉がつくが虫ではないというややこしさは、あの有名な「ミドリムシ」と同じだ。今年のGW、湘南の海で大量発生した夜光虫の幻想的に光り輝く姿がニュースでも取り上げられたことは記憶に新しい。その幻想的な姿を一目見ようと多くの人が夜の海に訪れ、Twitter上には多くの写真がアップされていた。「夜光虫ファン」と呼ばれる人... 今回紹介する商品は、渦鞭毛藻Pyrocystis fusiformisの「光る」特性を活かした米BioPop社のDino Sphereである。この商品の扱い方はとてもシンプルであり、購入後届いた容器に、栄養と渦鞭毛藻が入った溶液を入れるだけ。そのまま放置した状態でも1~3ヶ月は持つが、定期的に肥料を与えることで、それ以上長持ちさせることができる。ちなみに、Amazonでの価格は、容器、藻、肥料併せて90ドル程度。クリスマスプレゼントとしても素敵ではないだろうか。 渦鞭毛藻の発光メカニズムは、通常の生物発光と同様に、ルシフェラーゼ(酵素)の触媒によりルシフェリン(基質)の一部が酸化され、酸化型ルシフェリンが生じるときに青色光が放出されるというものだ。実際には、渦鞭毛藻に外的刺激が加わると反応が進行し、0.1秒以下の速いフラッシュとして青色の光が観察される。ちなみに、渦鞭毛藻は、約24時間の「概日性リズム」を持ち、夜のみ発光するような仕組みになっている。そのため、昼間に暗い場所に渦鞭毛藻を置いても光ることはない。藻類の概日リズムについては、下記ページも参照頂きたい。 Modia[藻ディア] 藻類の概日リズム -2017年ノーベル賞を祝し- https://modia.chitose-bio.com/articles/39 先月、2017年度のノーベル生理学・医学賞が発表されました。今年の同賞は、概日リズム(Circadian rhythms;サーカディアン・リズム)を生み出す遺伝子とそのメカニズムを発見した米ブランダイス大学のホール(Jeffrey C. Hall)博士とロスバシュ(Michael Rosbash)博士,ロックフェラー大学のヤング(Michael W. Young)博士の3氏に授与されました。Nobel prize for medicine awarded for insights...

藻入りのタピオカ
1990年代後半に大流行したタピオカドリンクが、近年再び脚光を浴びている。東京では、台湾におけるタピオカミルクティー発祥の店”春水堂“が2013年に進出したことを皮切りに、ここ数年で幾つもの台湾カフェのお店が誕生した。また、日本同様アメリカでも人気のようで、中国系アメリカ人達がニューヨークに立ち上げたTea and Milkというショップは、Vendy AwardやTaste Asiaなど多くの賞を受賞しており、現地の人気店になっている。 www.hamlethub.com Astoria’s “Tea and Milk” Top Contender for Best Street Beverage in NYC http://news.hamlethub.com/astoria/places/61-astoria-s-tea-and-milk-top-contender-for-best-street-beverage-in-nyc #Astoria 's own @teaandmilk competes for @vendyawards "Best Street Drink." Stop in...

光合成から始まるドラマ
私が人生をかけるテーマとして選んだ『光合成』であるが、この複雑な仕組みがどのようにして生まれたかは未だに明らかとなっていない。 光合成という言葉はよく知られているが、それがどんな反応から起こっているかは知らない人の方が多いだろう。光合成は大きく分けて、『明反応』と『暗反応』とから成り立っている。 光合成の全体図(Photosynthesis Overview ©2008 Daniel Mayer CC BY-SA 4.0) 光合成の仕組み -『明反応』と『暗反応』- 明反応は、太陽エネルギーを使ってH2O(水)から電子を引き抜いてH+を生じ、化学エネルギー分子NADPHとATPを生産する反応をいう。 明反応の概要(Thylakoid membrane ©2008 Akane700 CC BY 3.0) 一方の暗反応は、明反応によって生産されたNADPHとATPという物質を使って、CO2から糖C6H12O6を合成する反応である。ちなみに私は暗反応を構成するカルビン回路(Calvin cycle)と呼ばれる代謝回路を構成する酵素の1つを調べて博士号を取得したので、まさにこの分野が専門になる。明反応が電子伝達という機械的でドライな反応なのに対し、暗反応は酵素が組み合わさったウェットな反応、というイメージで覚えてるのは当時も今も変わらない。 暗反応の概要(Calvin-cycle3 ©2006 Mike Jones CC BY 2.5) 暗と明、この2つの反応が組み合わさることで、以下の有名な光合成の式が成立することになる。 H2O + CO2 → 1/6(C6H12O6) +...
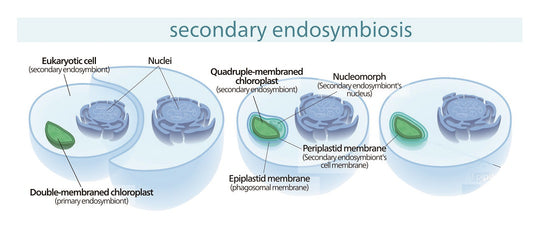
二次共生とは?-藻類多様性の謎-
以前の記事、『一次共生とは?-藻類の起源-』では、シアノバクテリアが真核生物に取り込まれて光合成能を獲得し、その生物が進化と分岐をすることで、スーパーグループ「アーケプラスチダ界」の藻類(灰色藻、紅藻、緑藻)が生まれたことを説明しました。一次共生について詳しく復習したい方は、下記記事をご覧ください。 Modia[藻ディア] 一次共生とは? -藻類の起源- https://modia.chitose-bio.com/articles/origin_of_algae 先月公開した記事では、藻類は「酸素発生型光合成を行う生物のうち、陸上植物を除いたもの」と曖昧な定義がされていて、進化を示す分子系統樹上では原核生物にも真核生物にも点在することをお話ししました。たしかに、多くの真核藻類(ユーグレナ藻、珪藻、褐藻、渦鞭毛藻、クロララクニオン藻、ハプト藻、クリプト藻等)は系統樹上では点在しています。しかし、灰色藻・紅藻・緑藻だけが、藻類としてまとまったグループ「アーケプラスチダ(別名:プランテ)」で固まっています。そもそも、なぜアーケプラスチダ界は酸素発生型光合成を... この記事内で、「アーケプラスチダ界以外の真核藻類は、異なる生い立ちで光合成能を獲得した」とお話ししました。この「異なる生い立ち」というのが「二次共生」です。今回の記事では、この「二次共生」について説明したいと思います。二次共生によって、形態や色、代謝系までもが異なる「藻類の多様性」が生じたのです。 一次共生のおさらい 光合成の仕組みを生み出した原核藻類「シアノバクテリア」を、真核生物が丸ごと細胞内に取り込んで、自分の一部として共生させてしまった現象を「一次共生(primary endosymbiosis)」という事をお話ししました。 ここで取り込まれたシアノバクテリアは、「葉緑体」として細胞内の光合成器官として働いています。一次共生で生まれ、分岐・進化した藻類を「一次植物」と言い、緑藻、紅藻、灰色藻が含まれます。我々が普段目にする植物も、緑藻から分岐しているので一次植物です。 藻類の「葉緑体の共生」を考えるとき、葉緑体の膜の枚数を見てみると、とても面白いことがわかります。シアノバクテリアの細胞膜の枚数は外膜と内膜の2枚です。シアノバクテリアを共生してできた、つまり一次共生でできた葉緑体も、シアノバクテリアを丸ごと取り込んだので、膜の枚数は同じく2枚です。 一次共生の藻類の光合成色素 二次共生をお話しする前に、「藻類の光合成色素」について説明します。 原核生物のシアノバクテリアも、真核生物の藻類も、共通して青みを帯びた緑色のクロロフィルaを持っています。さらに、一次共生で生まれた灰色藻、紅藻、緑藻は、それぞれ特有の光合成色素を進化させました。進化した光合成色素と、クロロフィルaの含有量を変化させることで、藻類の名前に示す色が現れてきたのです。 順に見ていくと、「灰色藻*」は青緑色の藻類です。光合成色素はクロロフィルaと青色のフィコビリンが含まれています。灰色藻の光合成色素は、シアノバクテリアの光合成色素と極めて似ています。*日本語では「灰色」藻という名称ですが、英語では Glaucophyta(glaucus :地中海の色(sea-green))と訳されます。つまり、英語では「海の緑色」という意味になります。 「紅藻」は赤色の藻類です(一部、青緑色の藻類もあります)。光合成色素は、クロロフィルaと赤色や紫色のフィコビリン、カロテノイドが含まれます。紅藻の葉緑体の色はフィコビリンとカロテノイドが特徴づけています。 「緑藻」は緑色の藻類です。健康食品として人気のクロレラや、ミカヅキモ、ボルボックスなどです。緑藻の葉緑体に含まれる光合成色素には、クロロフィルaとクロロフィルbが含まれています。クロロフィルbは、深い緑色をしています。 二次共生とは 全生物の系統樹では、5つのスーパーグループの「界」と所属不明の生物に分類されていて、藻類は多くの界に点在しています。詳しくは『藻類とは?-実は曖昧な藻類の定義。その理由に迫る-』をご覧ください。 Modia[藻ディア] 藻類とは? -実は曖昧な藻類の定義。その理由に迫る- https://modia.chitose-bio.com/articles/what_are_algae 皆さん、「藻類(そうるい)」「藻(も)」と聞くと何を想像されますか?池に漂っている緑色の生物を想像される方、クロレラやスピルリナ、ユーグレナといった健康食品を想像される方、海苔やわかめ、昆布といった海藻を想像される方、赤潮やアオコの原因を想像される方。当サイトで最新ニュース紹介している通り、独立栄養で有用物質を生産できる今ホットな生物と想像される方。どれも正解です。わかめや昆布といった体長数十メートルの「大型海藻」も、クロレラやミカヅキモといった顕微鏡でなければ観察できない数マイクロメートル... 一次共生で生まれた灰色藻、紅藻、緑藻は、上記記事でも紹介したスーパーグループ「アーケプラスチダ」にまとめられる藻類です。アーケプラスチダ界以外の藻類はどうやって葉緑体を獲得したのでしょうか? 答えは、一次共生で生まれた藻類を、今度はまた別の真核生物が丸ごと細胞内に取り込んで、自分の一部として共生させてしまったのです。この現象を、「二次共生(secondary endosymbiosis)」といいます。二次共生で生まれ、分岐・進化した藻類を「二次植物」と言います。シアノバクテリアと緑藻、紅藻、灰色藻以外の、すべての藻類が二次植物に含まれます。 二次共生で生まれた藻類であることは、どのようにして分かるの?と思われる方も多いでしょう。ここで、葉緑体の膜の枚数と光合成色素を見てみると、なるほど!と驚くのです。 二次共生の成立過程ークロララクニオン藻ー...

藻の怖い話 -赤潮-
今年の夏、長崎県で赤潮が大量発生し、トラフグやハマチなどの養殖魚52万匹以上が死に、被害額が5億円を超えたというニュースがあった。 産経ニュース 伊万里湾の赤潮被害5億円超 長崎県に支援要請 http://www.sankei.com/region/news/170825/rgn1708250004-n1.html 長崎県松浦市沖の伊万里湾の赤潮被害が長期化している問題で、同市の友広郁洋市長は24日、長崎県庁を訪れ、養殖魚の被害総額が5億円超となるとの見通しを伝え、死んだ魚… また2010年には、鹿児島、熊本、長崎の3県で計54億円の赤潮被害が発生している。 赤潮被害は日本に限ったものではなく、2016年にチリの養殖場では、2,300万匹ものサケが死に、損害額は1,000億円に達した。また、お隣の韓国でも、2013年に養殖場にて1,310万匹が命を落とし、9億円近く損失が出ている。 今回は世界で大きな被害をもたらしている赤潮について、取り上げていきたい。 赤潮とは 赤潮とは、水中で藻類などの微小な生物が異常に増殖し、藻の色により海水の色が変わる現象である。藻が産生するカロテノイドなどの色素によって海が赤く染まることが多いため、一般的に「赤潮」と呼ばれているが、地域によって呼び名はさまざまである。赤潮発生のメカニズムは完全に解明されていないが、主な要因として、生活排水や工業排水から、窒素やリンなどの栄養素が湖や海などに供給されることで、藻が増殖するとされている。 赤潮の原因となる生物としては多くの種が知られており、シアノバクテリア、珪藻、夜光虫*も入る渦鞭毛藻、ラフィド藻、ハプト藻などが含まれる。こうした藻の中には、毒を産生するものがあり、それにより魚介類や水生生物、人が死滅することがある。また、藻の死骸の分解時に、バクテリア等が酸素を大量消費し、酸素濃度が低下することによる魚の窒息死や藻がエラに詰まることによる窒息死も発生している。*夜光虫については下記記事も参照ください Modia[藻ディア] 南オーストラリアの夜光虫 https://modia.chitose-bio.com/articles/1 南オーストラリアのポートリンカーンの近くのTulka beachで、暗闇に光る藻が発生している。光の正体はNoctiluca scintillansと呼ばれる渦鞭毛藻の一種で、日本では『夜光虫』と呼ばれている。「虫」という言葉がつくが虫ではないというややこしさは、あの有名な「ミドリムシ」と同じだ。今年のGW、湘南の海で大量発生した夜光虫の幻想的に光り輝く姿がニュースでも取り上げられたことは記憶に新しい。その幻想的な姿を一目見ようと多くの人が夜の海に訪れ、Twitter上には多くの写真がアップされていた。「夜光虫ファン」と呼ばれる人... 人への影響 赤潮が人の健康へ与える影響は、大きく分けて以下の2種類がある。 ①藻が産生する毒を、水道水を通して摂取する場合 1996年ブラジルで、アオコが発生する水源を水道水に利用していた病院で、患者60名以上が死亡する事故が発生した。このような事件の発生もあり、WHO(世界保健機関)は、ミクロシスチンの暫定基準値を1 μg*/L程度とした。*1mgの1,000分の1 上の写真は、2014年に米五大湖の1つであるエリー湖にて藻が大量発生した様子だが、水道水に藻が産生する毒素 ミクロシスチン(フグ毒に匹敵)が検出されたため、エリー湖の水を水道水として利用していた40万人が一時的に水道水を利用できなくなった。 www.afpbb.com 米都市で水道水が飲用禁止に、40万人以上に影響 http://www.afpbb.com/articles/-/3022251 【8月4日 AFP】米オハイオ(Ohio)州トレド(Toledo)の当局は2日、同市と郊外の住民少なくとも40万人に対し、藻の繁殖によって発生したとみられる毒素「ミクロシスチン」が水道水から検出されたため、飲料用として水道水を利用しないよう警告した。 ②貝等が蓄積した毒素を食べる場合...

タンパク質生産の未来について -タンパク質危機(タンパク質クライシス)を解決する?藻とメタン資化菌-
ここ数年、私が注目しているのが世界のタンパク質生産の動向である。というのも、人の体は水分を除外すると60%がタンパク質でつくられており、もっとも基盤となる栄養素だからである。 我々のカラダは60兆もの細胞から成り立っているが、日々億単位以上の細胞が新たに生まれ変わりながら生命を維持している。このため、これらの細胞の主要構成要素となるタンパク質は常に外部から一定量を補給しなければならない。 人が1日に必要なタンパク質は、ざっくりいうと体重の1/1000といわれている。例えば体重が50kgであれば50gとなる。タンパク質は脂肪と異なり、体内に蓄積しておくことができないため、毎日新たに取り続けなければならない。現在の世界の人口を70億人として、1人当たりの平均体重を50kgと仮定した場合、年間約1.3億トン(1日あたり36万トン)のタンパク質の供給が最低でも必要な計算となる。 現在の人口増加ペースが続くと、全世界の人口は2050年に90億人を突破すると予想されている。この人口の増加に加え、新興国のGDP増加による食生活の向上(肉食化)によって、2050年には2005年時のタンパク質の2倍の供給量が必要になる。これまでは農業の生産性の向上によって年々増大するタンパク質需要に対応できてきたが、今後はその伸びだけでは吸収できなくなり、早ければ2030年頃には需要と供給のバランスが崩れ始めると予測されている。この予測は『タンパク質危機(protein crisis)』と呼ばれ、最近欧米を中心に注目され始めてきている。すでに欧州では[Protein challenge 2040]* というテーマでコンソーシアムができ始め、その中から幾つものプロジェクトが動き始めている。 タンパク質の需要と供給 / 筆者作成 さて、人類にとってのタンパク質の重要性について理解していただけたと思うが、現在の人類は年間1億トンを超える大量のタンパク質をどこから得ているのだろうか。魚や肉と考えるのが一般的だと思うが、さらに思考を一歩進めてそれら魚や肉を生産するための餌の段階にまで遡ると、『魚粉(動物性タンパク質)』と『大豆(植物性タンパク質)』が世界の2大タンパク質源となっていることが見えてくる。次にこの2大タンパク質源について少し説明したい。 魚粉 -世界の2大タンパク質源①- 魚粉というのは、海で捕られるカタクチイワシなどの小魚を乾燥して粉末にしたものである。魚粉はタンパク質含有量が60%以上と高く、アミノ酸組成に優れていることから、主に養殖用の飼料として重宝されてきた。しかし、2000年に700万トンあった魚粉生産量は、2010年に入ってからは450万トン前後で推移している。また、世界第1位の魚粉生産量を誇るペルーでは、資源保護と価格安定を目的に漁獲調整をしており、これ以上の魚粉の増産は期待できないというのが現実である。つまり、これ以上自然界からの漁獲高を増やすと自然の回復力では回復できないレベルになってしまうため、漁獲量を制限している状態なのである。その一方で、世界の魚需要は年々増加しており、その増加分は水産養殖の拡大によって賄われている。この水産養殖の拡大に伴って、魚粉に対する世界的需要も年々増加しているのが現状である。 世界漁業・養殖業白書2016より抜粋 より詳しく世界の漁業・養殖業の現状を把握したい場合は、以下のFAOがまとめているレポートの要約版を参考にしていただきたい。『世界漁業・養殖業白書2016』 養殖飼料としての魚粉需要高まりに対し、上述した背景からこれ以上の増産が期待できず、魚粉代替タンパク質源が今後求められていくことをまとめたレポートが、三井戦略研究所からも出ている。興味のある方は参考にして頂きたい。魚粉代替となる新タンパク源には大きな事業機会が眠っていることもよくわかる。『養魚飼料原料の多様化が創出する新たな事業機会と課題』 ちなみに「魚粉のもとになっている小魚の餌ってなんだ?」 と遡っていくと、最後は植物プランクトン(=藻)にたどり着く。光合成で増えた藻を動物性プランクトンが捕食し、動物性プランクトンを小魚が食べ、人間が捕まえるという食物連鎖となっている。 大豆 -世界の2大タンパク質源②- もう一方のタンパク質源である大豆は、日本人には食品として馴染み深い食材だ。世界的にみると1960年代3,000万トンにも満たなかった大豆の生産量は、2015年には3.2億トンと10.7倍と大きく増加している。この増加率は他の穀物(小麦3.1倍、米3.2倍、とうもろこし4.9倍)の増加率と比較しても圧倒的に高い。 この大豆の驚異的な増加率は、コメや小麦が「主食用」として人に直接摂取されることが多いのに対して、大豆が家畜の「餌」として「飼料用」に用いられることが多いことに由来している。実に大豆の7割は飼料用途で利用されていると言われている(食利用は1割程度)。世界中で生産された大豆の大部分は、牛乳、卵、チーズ、フライドチキン、ハム、ステーキ、アイスクリーム、、といった製品に姿を変え、間接的に我々の体に取り込まれていると言えよう。そんな世界の大豆生産と消費の現状については、以下の農水省の特集ページにわかりやすく記載されているので参考にしていただきたい。 農林水産省/特集1 大豆(1) ...

藻類の概日リズム -2017年ノーベル賞を祝し-
先月、2017年度のノーベル生理学・医学賞が発表されました。今年の同賞は、概日リズム(Circadian rhythms;サーカディアン・リズム)を生み出す遺伝子とそのメカニズムを発見した米ブランダイス大学のホール(Jeffrey C. Hall)博士とロスバシュ(Michael Rosbash)博士,ロックフェラー大学のヤング(Michael W. Young)博士の3氏に授与されました。 Nobel prize for medicine awarded for insights into internal biological clock 3氏のお祝いに、今回は藻類の概日リズムについて紹介します。 動物の概日リズムと生物時計 まず、概日リズムの解明が、ノーベル生理学・医学賞に値する成果である理由をお話しします。 そもそも、概日リズムとは、恒常環境下でその存在が確かめられる、約24時間周期で変動する生理現象です。この3氏は、ショウジョウバエを使って、「概日リズムが、per(period)遺伝子とtim(timeless)遺伝子の転写制御と、この2つの遺伝子が作り出すタンパク質発現量により、自律的に作られる時間制御機構である」ことを明らかにしました。これは、タンパク質量が「振子」の役割をしていて、ほぼ24時間を刻む自律的な「振動」の仕組みを生物の細胞が内在的に持っているということです。per遺伝子とtim遺伝子を「時計遺伝子」と呼ぶこともあります。 概日リズムと似た言葉に、「体内時計」、「生物時計」という言葉があります。どちらも、biological clockの和訳で同義です。生物時計とは、自律的に動く概日リズムが基本となって、光や温度、食事など外部刺激によって補正・同調される、生物が生まれつき備わっている時間測定機構です。生物時計が働くことで、生物は環境変化に応じて生活ができるのです。 3氏の概日リズムの解明により、生物時計の研究が急速に発展していき、「時間生物学」という学問分野が確立しました。そして、その発展の一つが、医学分野です。実は哺乳類にも、ショウジョウバエで解明された概日リズムのメカニズムとほぼ同じものを有しています。生物時計は睡眠パターン、摂食行動、ホルモン放出、血圧、体温調節などに必要なシステムであることがわかってきました。また、細胞が無限に増殖してしまうガン細胞も、生物時計の異常と考えられていて、生物時計のメカニズムに基づいた新薬の開発が進められています。 生物時計の仕組み ここで、ショウジョウバエの生物時計を説明します。 (2017年ノーベル生理学・医学賞受賞解説より引用)...
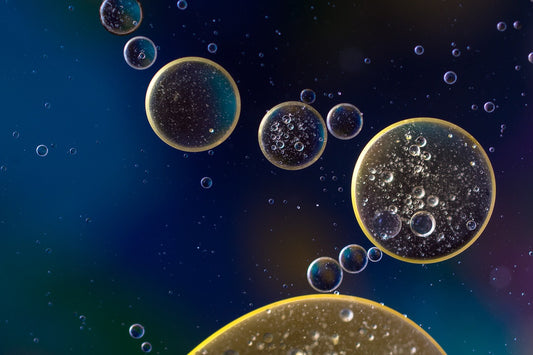
油にまつわる言葉の整理 第2回 -脂肪酸、油脂とは-
前回の記事では「油」、「脂質」、「脂肪」といった言葉を整理していきましたが、今回は「脂質」に含まれる「脂肪酸」、「油脂」といった少し範囲の狭まった言葉について紹介していきます。前回の記事はこちらよりご覧ください。 Modia[藻ディア] 油にまつわる言葉の整理 第1回 -油、脂質、脂肪とは- https://modia.chitose-bio.com/articles/definition_of_oil 「藻類バイオ燃料」「DHAやEPAに代表されるオメガ3脂肪酸」「βカロテンやアスタキサンチンといった抗酸化物質・色素・カロテノイド」「パームオイルや菜種油に対応するような、藻から取れる油脂」これらの話をする場合、藻類に含まれる「あぶら」が議論の対象となります。オイル、油、脂、脂質、脂肪等、人によって様々な言葉が使われますが、意図的であろうとなかろうと、言葉の誤用・勘違いによる誤解が後を絶たないように感じます。そこで、人々が言う「あぶら」とは一体何なのか、数回に分けて簡単に整理していければと思います。... 「脂質 (lipid)」に含まれるあれこれ 藻類バイオ燃料を語る際に議論の対象となるのは、藻類に含まれる「脂質」になります。では、「脂質=燃料なのか?」と聞かれれば、当然そうではありません。次に、前述の「油脂」を含め、藻類に含まれる様々な「脂質」について、もう少し掘り下げてみたいと思います。 「脂質」の分類法はいくつか存在しますが、その内、極性の有無(親水性基を持つか否か、つまり水に馴染む部分を持つか否か)で2種類に大別する方法をもとに話を進めます。 まず、無極性脂質または中性脂質と呼ばれるものから取り上げていきます。これらは、極性を持たない (親水性基を持たない)、もしくは持っていても疎水性基と比較して非常に小さいため、基本的に水に馴染まない脂質です。具体的には、油脂 (fat, triacylglycerides, TAGs, etc)、蠟 (Wax esters)、長鎖脂肪酸 (fatty acids)、ステロール (sterols)、カロテノイド (carotenoids)等があります。今回の記事では、その中でも頻繁に話題に上る「脂肪酸」と「油脂」の2種類について紹介します。 脂肪酸 (fatty acids) 脂肪酸は、化学的には一般式 CnHmCOOHで表される化合物になります。そして、生体内で生成される脂肪酸は、反応上、一般的に炭素(C)の総数は偶数になります。 脂肪酸を簡単に言えば、「基本は偶数個の炭素の鎖。一端の形状がちょっと特殊」、「脂質の内、一番基本的な形のもの」くらいに覚えておけば良いかと思います。 下図は、代表的な脂肪酸で、最近は巷でも話題のDHA (ドコサヘキサエン酸)の構造を表した図になります。22個の炭素原子(黒球)で構成される鎖の一端に、カルボキシ基(赤球で表された酸素分子がくっ付いている部分)が繋がった構造であることがわかります。 少し詳しく見ていくと、2つの炭素原子が1本の腕で繋がっている部分と、2本の腕で繋がっている部分があることがわかります。1本の腕で繋がっている部分を飽和結合、2本の腕で繋がっている部分を不飽和結合と呼び、不飽和結合が少なくとも1つ以上ある脂肪酸のことを不飽和脂肪酸と呼びます。EPA...

スピルリナの持つ7つの効能
2010年から現在に至るまで、私の所属する(株)ちとせ研究所ではスピルリナの研究開発を継続し、国内唯一の生食タイプのスピルリナを生産してきた。 私自身も静岡県の掛川市でスピルリナの培養に携わり、生スピルリナの生産に向けて注力してきた。今では、掛川でのスピルリナ生産が学生時代のバドミントンに次いで私の第二の青春になっている。 真夏の強い紫外線を物ともせず、たくましく増え続けるスピルリナ。その強さのもととなるのは、高い抗酸化力や生理活性物質などスピルリナ自身が産生する有効成分である、と私は考えている。 これまでにも、藻ディアでは度々スピルリナの話題を取り上げてきた。 Modia[藻ディア] 中国最大のゴーストタウンがあるオルドス市には、世界最大規模のスピルリナ生産地... https://modia.chitose-bio.com/articles/13 中国北部の広大な内モンゴル自治区、南西部に位置する「オルドス市(鄂尔多斯/Ordos)」をご存知だろうか?引用元:https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%AA%E3%83%AB%E3%83%89%E3%82%B9%E5%B8%82オルドス市には、2003年頃から100万人規模の都市として開発された「康巴什(カンバシ)新区」がある。しかし、現在は6万人ほどしか住んでおらず、入居者のないマンションやオフィスビル、人も車もほとんどいない整備された大きな道路の広がるその街並みから「中国最大のゴーストタウン」と呼ばれ、世界中から注目されている。中国の砂漠に... Modia[藻ディア] 食品業界で使用が広がるスピルリナの幻想的な青色 https://modia.chitose-bio.com/articles/23 世界中で若者を中心にInstagramに代表される写真をメインとしたSNSが広まる中、見た目が印象的な商品が多くの話題を集めている。特徴的な青色とピンク色によるパステルカラーもトレンドの一つだ。今回、スピルリナの色素を原料としたパステルカラーのドリンクがアメリカで話題となり、訴訟問題にまで発展しているので、その記事を紹介したい。Brooklyn cafe claims Starbucks stole their 'unicorn' drink米コーヒーチェーンのスターバックスが、アメリカ・カナダ・メキシコの3ヶ国で今年の4月19日から23日までの5日間限定で... Modia[藻ディア] ロケットに乗った藻 -藻、宇宙へゆく- https://modia.chitose-bio.com/articles/24 今年の8月14日、SpaceX社のCSR-12ロケットが米国のケネディー宇宙センターから打ち上げられた。民間のロケットが商業ベースで日常的に打ち上げられていることも驚きだが、藻ディアとして注目すべき点は他にもある。このロケットには、なんと『藻』が乗っているのだ。CSR-12ロケットでは、学生宇宙実験プログラムStudent Spaceflight Experiments Programに採択された米国及びカナダの計21の学校のプロジェクトを行うことになっている。その中の1つとして、NYのイースト高校のチームによる「植物プランクトンを用いた微小重力空間におけ... 上記記事と重複するところもあるが、改めて、スピルリナとは何かを簡単に紹介する。 スピルリナは、藍藻類に属する全長0.3-0.5mmの螺旋状の微細藻類で、35 億年前に地球上に誕生し、マヤ文明の時代から人々の貴重な栄養源の1つとして世界中で食されてきたという長い歴史を持つ。また、ビタミン・ミネラル・タンパク質などの...

珪藻の殻を利用したソーラーパネル
3.11以降、身近なところでも太陽光発電のソーラーパネルをよく見かけるようになった。 ソーラーパネルには様々なタイプがあるが、現在最も普及しているのは結晶シリコンを用いたタイプである。シリコンは日本語ではケイ素と呼ばれている。ケイ素の原料は珪石(SiO2)で、地球の表面上では酸素の次に多い化合物であり、珪藻(ケイソウ)・放散虫・シダ植物・イネ科植物などといった一部の生物でも骨格として利用されている。栄養素としての必要性はあまり判っていない。 多方面から注目を集める珪藻 このうち、藻類の一種である珪藻はケイ素を利用している生物としては最もメジャーな生物であり、最近では『珪藻土のお風呂マット』などで、珪藻の名前を目にされたことがある方も増えたのではないだろうか。このお風呂マットに使われている珪藻土は珪藻の殻の化石にあたる。 また、藻ディア内でも珪藻にまつわる記事があるので、ぜひ参考にして頂きたい。 Modia[藻ディア] 海洋の一次生産者の主役、珪藻の重要な遺伝子の発見 https://modia.chitose-bio.com/articles/19 「珪藻」は、食物連鎖の基盤となる単細胞の小さな藻類だ。食物連鎖における一次生産者として全体の20%を占めており、海洋の一次生産者としては実に45%を占めている。また、珪藻は大量の二酸化炭素を取り込み、酸素を排出している。その光合成量は、なんと世界の全熱帯雨林に相当するほどだ。ガラスと同じ、二酸化ケイ素でできた被殻があるのが特徴で、顕微鏡で観察すると冒頭の写真のように、様々な美しい形状を観察することが出来る。「珪藻」にはピンとこない方も、「珪藻土」という言葉は聞いたことがあるのではないだろうか?珪藻... 海や湖沼などで大量に繁殖した珪藻は、死ぬとその死骸が水底に沈殿していく。死骸の中身の有機物は徐々に分解されていくが、二酸化ケイ素を主成分とする殻は分解されずに蓄積していく。このようにしてできた珪藻の化石からなる岩石が、珪藻土と呼ばれているのだ。 珪藻の殻には小孔が多数開いているため、水分や油分を大量に保持することができる。お風呂マットなどはこの性質を応用して作られた製品となる。ちなみに、珪藻土の最大の用途は濾過助剤である。吸着能力が低く、溶液中に溶解している成分はそのまま通し、不溶物だけを捕捉する性質を利用したものだ。余談だが、私が以前勤めていたワイナリーでも、ワインを瓶詰めする前に、珪藻土フィルターを使って不純物を取り除いていたことを思い出した。 この珪藻の殻は、弁当箱のように、大きい外殻の内側に小さめの内殻(それぞれ半被殻; theca と呼ばれる)が組み合わされた構造となっている。これを顕微鏡で覗いてみると驚くほど美しい形をしている。 顕微鏡でしか見えない数μm(ミクロン)の世界に、こうした幾何学的で美しいデザインが生み出されている時点で、私なんかは自然の中に人智の及ばぬ存在を感じてしまう。アートと称して人が作り出した物よりもアートっぽく、意志を感じるデザインに見えるからだ。 ちなみに、この珪藻の美しさに魅せられている人は世界中に数多くいて、その名も「珪藻美術館 (Diatoms Art Museum)」という写真集が出ているので、興味ある方はぜひご覧頂きたい。 珪藻の殻にビジネスチャンスを見出したベンチャー企業 さて、前置きが長くなったが、この珪藻の殻をソーラーパネルの素材として利用しているベンチャーを紹介したい。2014年に設立されたスウェーデンの藻類工場は持続可能な考え方をもったスタートアップ企業である。 This Swedish startup found the answer to more efficient...

藻ガール尾張のわくわく藻探し -道端で発見!つかめる微細藻類「イシクラゲ」-
先日、「藻類農業」について藻ディアで紹介がありました。記事内では、将来のタンパク質危機に備えて、藻類を培養する取り組みが紹介されていましたが、何も手入れをしなくても、藻類が生える。そんな夢みたいな「藻類農業」が、実は道端にあるかもしれません。 Modia[藻ディア] タンパク質危機(タンパク質クライシス)に備え、老舗農業企業が藻類農業へ参入 https://modia.chitose-bio.com/articles/7 タンパク質危機 / タンパク質クライシス(Protein Crisis)という言葉をご存知だろうか。人口の増加と新興国の経済発展による生活レベルの向上により、人類が必要とするタンパク質の需要に、供給が追いつかなくなることを予測した警鐘である。我々の試算だと早ければ2025年ごろからその傾向が顕在化し、世界的な問題になっていくと予測している。※以下の記事では、より詳しくタンパク質危機に関して紹介していますhttps://modia.chitose-bio.com/articles/40/こうした、近い将来訪れるであろうタンパク質危機に備えた動きが活発化して... 散歩で「イシクラゲ」発見 藻類好きの私にとって、散歩とは「藻探し」です。とはいっても、藻(ここでは微細藻類を指します)は、なかなか目で見ることはできません。水にも、土にも、空気中にも、木肌にも、コンクリート壁にも、雪にも、どこにでも藻はいます。しかし、それがどんな藻なのかは、顕微鏡で観察しなければわかりません。ですから、私の散歩のお土産は、いつも野外の水や土です。わくわくしながら採取しています。 某日、久しぶりの晴れ間に散歩に出かけると、微細藻類なのに、手でつかめるほどの塊になっている藻がいました。その名は、「Nostoc commune」。和名は「イシクラゲ」といいます。 「イシクラゲ」とは イシクラゲは藍藻(シアノバクテリア)のネンジュモ(Nostoc)の仲間です。 このイシクラゲを顕微鏡で見ると、球状の細胞が数珠状に繋がっている細胞群で構成されています。この一本一本の細胞群をトリコームといいます。イシクラゲは、細くて長いトリコームがたくさん積み重なってバイオマット状になっています。イシクラゲは細胞外多糖を大量に細胞外に分泌していて、その細胞外多糖が糊(のり)の役目となり、トリコーム一本一本がお互いに付着して大きな塊になっているのです。 イシクラゲの顕微鏡写真(筆者撮影) 私たちに身近な「イシクラゲ」 イシクラゲは私たちの身近な場所で見かけることができます。というのも、窒素固定能を持つため、公園や駐車場、荒れ地など、他の植物や藻類が育たないところでも生息することがでるのです。ただ、生息場所には迷惑になるほどたくさん生える傾向があり、藻好きの私にはちょっと悲しいですが、専用の駆除剤まで売られてます。 イシクラゲを見つけた日の風景と、その3日後の風景の写真を示します。同じイシクラゲとは思えないほどに様子は変わっていました。初めて見つけた時のイシクラゲは、黒みがかった緑色で、全体がぶよぶよで見るからに水分をたっぷり含んでいる様子でした。一方で、晴れの日が続いた3日後に観察すると、イシクラゲは黒色になり、全体がかちかちに乾いていました。 乾燥耐性がある「イシクラゲ」 イシクラゲは、水分をたっぷり含んだ「膨潤状態」において、細胞が光合成をして細胞増殖をします。一方で、水分を失った「乾燥状態」では、細胞は生命活動は停止して休眠状態になることがわかっています。「乾燥状態」のイシクラゲは、水を約30倍吸収して「膨潤状態」になります。本来、細胞は極度の乾燥状態になると、生命状態が停止して死んでしまいます。ところが、イシクラゲは乾燥しても水を与えると復活するのです。文献によると、博物館に所蔵されていたイシクラゲの乾燥標本が、87年後に膨潤させてみると増殖を始めたという報告があります(Lipman 1941)。 このイシクラゲの乾燥耐性の理由は、イシクラゲが分泌する細胞外多糖にあります。この細胞外多糖は、保水能力はもちろん、強光阻害から細胞を守る抗酸化機能(Li et al. 2011)や日焼け止め機能(Bohm et al. 1995)があることが明らかにされています。 「イシクラゲ」は食べられます イシクラゲの生息域は、日本国内にとどまらず、暑いところは亜熱帯から、寒いところは南極まで、世界中にいます。実はイシクラゲ、日本や中国、台湾などでは古くから食べられています。イシクラゲ(乾燥)は、粗タンパク質30%、脂質0.5%、炭水化物60%、無機質10%の栄養構造をしており、こうした多くの炭水化物を占める細胞外多糖は新しい食物繊維になりうると言われています(hori...
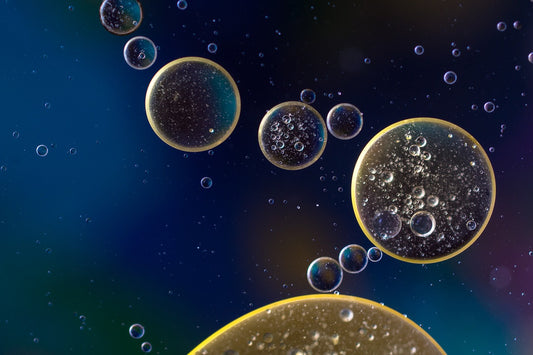
油にまつわる言葉の整理 第1回 -油、脂質、脂肪とは-
「藻類バイオ燃料」「DHAやEPAに代表されるオメガ3脂肪酸」「βカロテンやアスタキサンチンといった抗酸化物質・色素・カロテノイド」「パームオイルや菜種油に対応するような、藻から取れる油脂」 これらの話をする場合、藻類に含まれる「あぶら」が議論の対象となります。オイル、油、脂、脂質、脂肪等、人によって様々な言葉が使われますが、意図的であろうとなかろうと、言葉の誤用・勘違いによる誤解が後を絶たないように感じます。そこで、人々が言う「あぶら」とは一体何なのか、数回に分けて簡単に整理していければと思います。 「油」とは まず、これらの言葉の中で最も大きな範囲を定義する言葉が「油」です。三省堂大辞林によると、「油」とは、 動物の組織や植物の種子あるいは石油・石炭などの鉱物から抽出される、水に溶けにくく燃えやすい物質。食用・灯火、減摩剤・燃料など多くの用途がある。 とあります。一方、英辞典ではどう記載されているでしょうか。一般に、日本語の「油」に相当する英単語として「oil」が使われます。Oxford English Dictionaryによると、「oil」とは、 A viscous liquid derived from petroleum, especially for use as a fuel or lubricant. (石油から得られる粘性の高い液体、特に燃料や潤滑油として利用される) (With modifier) Any of various viscous liquids...

バイオリアクター型の藻類生産施設”Algae Dome”
先月デンマークで開催された現代アートの祭典CHART Art Fairにおいて、人気家具メーカーIKEAのラボSpace10がデザインした藻類生産施設”Algae Dome”が、コンテストの建築部門で受賞した。 IKEA's Space10 creates algae-producing pavilion in Copenhagen このSpace 10は、一昨年の11月にIKEAがデンマークの首都コペンハーゲンに設立した研究所で、デザイナーから研究者まで多様な人材が集まっている。これまで、持続可能な暮らしの実現を目的として、都市型農業・環境保全・ヘルスケアなど幅広い分野の研究開発を行い、未来の都市生活の形を探求してきた。その中でも代表的な作品が、高さ2.8メートル、幅2.5メートルの球状菜園”The Growroom“である。空間を有効活用した球形のデザインが特徴的なこの菜園は、スペースに制限のある都市を対象とした食料生産のソリューションの一つとして注目を集めている。 SPACE10 open sources The Growroom | SPACE10 今回受賞した”Algae Dome”も、同様に空間を最大限に活用した設備になっている。高さ4メートルの木材で作られた枠組みに約300メートルの透明なチューブを張り巡らせて微細藻類を培養する設備は、藻ディアでも度々取り上げているフォトバイオリアクターの構造である。 Modia[藻ディア] フォトバイオリアクターを用いた微細藻類バイオマスの生産コスト https://modia.chitose-bio.com/articles/18 イタリアのTredici教授の研究グループより、安価なソフトプラスチック(LDPE)を利用した微細藻類屋外培養設備(=フォトバイオリアクター)の技術経済試算に関する論文が発表された。Techno-economic...

広大な砂漠を利用した藻類生産
先日藻ディアで公開された記事に、内モンゴルの砂漠地帯「オルドス市」のスピルリナ生産に関するものがあった。記事内では、砂漠に位置するにも関わらず、スピルリナの生産・商品開発・販売すべてを同地で行うことで、オルドス市が”世界の藻都”として注目されていることが紹介されていた。 Modia[藻ディア] 中国最大のゴーストタウンがあるオルドス市には、世界最大規模のスピルリナ生産地... https://modia.chitose-bio.com/articles/13 中国北部の広大な内モンゴル自治区、南西部に位置する「オルドス市(鄂尔多斯/Ordos)」をご存知だろうか?引用元:https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%AA%E3%83%AB%E3%83%89%E3%82%B9%E5%B8%82オルドス市には、2003年頃から100万人規模の都市として開発された「康巴什(カンバシ)新区」がある。しかし、現在は6万人ほどしか住んでおらず、入居者のないマンションやオフィスビル、人も車もほとんどいない整備された大きな道路の広がるその街並みから「中国最大のゴーストタウン」と呼ばれ、世界中から注目されている。中国の砂漠に... 一方、同じ砂漠地域とはいえ、オルドス市と緯度や経度のまったく異なるイスラエルにおいても、藻類生産が進んでいる。 Is 2016 the year of algae? 今回は、同国における藻類生産について考察していきたい。 過酷な環境であったからこそ、築かれた農業技術 イスラエルは、国土の60%が乾燥・半乾燥地域でありながら、食糧自給率は90%を上回っている。その高い食糧自給率の背景には、水の有効活用がある。例えば、下水処理水のリサイクル率は、2位のスペインが12%(日本は2%)である中で、イスラエルは83%であり世界1位を誇っている。また、同国で普及している点滴灌漑は、プラスチック製のパイプを通して必要な場所だけに水を届けることで、蒸発を抑制し利用効率を倍増させている。さらに、この水に肥料や農薬を入れることで、散布をより効率的に行っている。近年では、最先端のIoTやクラウド技術を導入し、あらゆる場所からの管理を可能とする農地も増えている。 WIRED.jp 水がないから、ここまでこれた: イスラエルのウォーターテックが世界を救う | WIR... https://wired.jp/special/2016/israel/water-tech/ いま、2,000年前から水不足に立ち向かってきたイスラエルが世界を救おうとしている。過酷な環境での血がにじむような努力の結果、点滴灌漑、淡水化施設、再生水など驚くべきテクノロジーを手にした彼らに世界が求める未来の水の探し方を訊ねてみた。 このように技術を結集させて過酷な砂漠地帯で農業生産を行う同国だが、藻類産業にも力を入れている。 砂漠地帯における藻類生産 1988年に設立されたAlgatechnologies社は、微細藻類を商業的に培養することを専門とするイスラエルのバイオテクノロジー企業だ。同社は、微細藻類の中でも、Haematococcus pluvialis由来のアスタキサンチンを生産している。このアスタキサンチンを商品化した AstaPure®は、栄養補助食品、化粧品、機能性食品/飲料として利用されている。こうした藻類生産を”持続的”に行うために同社は、使用した水の8割を再利用することや、太陽光発電により電気を生み出すことで、限りある資源を効率良く利用している。また、溶媒を使用しない超臨界を用いたアスタキサンチンの生産も行っている。https://www.youtube.com/watch?v=hcEjEztv11c また、日本企業も藻類生産を目的にイスラエルに進出している。岐阜県を拠点とする日健総本社はイスラエルに現地法人を立ち上げ、カロテノイドを豊富に含む藻類であるドナリエラ(Dunaliella...

遺伝子組み換え藻類を使った、次世代の水産餌料
今年はサンマが不漁のようで、サンマの水揚げ量が全国3位の気仙沼市では、サンマ祭り用の量が確保できず延期になったと、ニュースになっていた。毎年の漁獲状況は我々日本人の生活にも大きく関わり、新聞やニュースでも頻繁に取り上げられる。 河北新報オンラインニュース 不漁で確保できず…気仙沼「サンマまつり」初の延期 http://www.kahoku.co.jp/tohokunews/201709/20170908_13038.html 宮城県気仙沼市の気仙沼魚市場前にある海鮮市場「海の市」で10日に開催予定だった「海の市サンマまつり」が、サンマの不漁の影響で延期されることが7日、決まった。まつりの延期は初めてで、17日に先延ばしされ 今回は、こうした漁業大国である日本が見習うべき事例について見ていきたい。 Windfall for oral aquaculture vaccine development 2016年4月に米サンディエゴで設立したMicroSynbiotiX社は、遺伝子組み換え技術を用いて藻類に水産用の経口ワクチンを生産させる技術を持っている。この技術により養殖時の病気予防管理の手間が低減され、環境負荷の低減にも繋がることが期待されている。 有望なマーケットである水産養殖 日本の水産業は年々衰退しているが、世界的に見ると水産養殖業は年率5.1%の成長率で伸びている。この成長率は食料生産分野の中でも最も高い伸びであり、2019年には2,000億ドル(20兆円)に達すると予測されている。水産養殖は世界的に見て最も将来性のある有望なマーケットの一つなのだ。養殖量が増加する一方で、養殖最中に病気で失われる魚も年々増加し、その額は毎年100億ドル(1兆円)以上にのぼる。 MicroSynbiotiX社の共同設立者であるSimon Jegan Porphy氏は次のようにコメントしている。「当社の技術は、抗生物質の使用を削減または廃止し、細菌および致死性の病気を防いで水産養殖場での魚の死亡率を低減させます。近年、養殖された魚介類はタンパク質源としての価値が急速に上がってきていますが、いまだに毎年何百万トンもの魚介類が病気によって失われています。我々はそのロスをなくしていきたいのです。」 MicroSynbiotiX社はつい先日、シリーズA*の投資集めに成功したと報告した。集めた額はUSD1.2M(約1.3億円)。Alimentos Ventures* がリードを務め、それ以外ではSOSV*、 RebelBio* 、Yield Lab Ireland*、アイルランド商務庁が出資者として名を連ねている。また別途オーストラリア政府からの助成金もUSD 0.15M(約1,650万円)ほど入っており、まさに世界規模での資金集めに成功している。*シリーズA:スタートアップ段階でベンチャーキャピタル等が最初に出資するラウンドAlimentos Ventures:水産系の初期ステージ企業への投資を専門とするドイツ系のベンチャーキャピタルSOSV:米国系スタートアップ専用ベンチャーキャピタルRebelBio:アイルランドのバイオ企業スタートアップ専門のベンチャーキャピタルYield Lab Ireland:アイルランドの農業系スタートアップ専門のベンチャーキャピタル 水産養殖のニーズに応える、経口ワクチン入り藻類...

葉緑体の一次共生の謎がついに明らかに?!
藻類の「進化」、「多様性」を語るうえで、最も大きなイベントはなんといっても「共生」です。かく言う私も、藻類の「共生」の面白さに魅かれ続けています。 真核生物がシアノバクテリアを取り込み、葉緑体になった現象を「一次共生」といいます。そして、一次共生で誕生した藻類を「一次植物」といいます。このイベントは生命の進化の中でも、一度しか起こっていないと考えられています。詳しくは先日公開した下記記事をご覧ください。 一次共生とは? -藻類の起源- 一次共生という現象は、生物の教科書にも載っているほど広く知られています。しかしながら、どんなシアノバクテリアが、いつ、どこで共生したのかははっきりしていませんでした。 そんな中、新種のシアノバクテリアの発見により、謎が解明されつつあります。 (poncetoledo et al. 2017より引用) 新種のシアノバクテリアの特徴 今回見つかった新種のシアノバクテリアの名前はGloeomargarita lithophoraと言います。メキシコの湖から発見されました。この藻類は炭酸カルシウムのナノ粒子を細胞内で生成する点が、今までに知られていたシアノバクテリアとは違い注目を集めていました(Couradeau et al. 2012)。このGloeomargaritaとその他のシアノバクテリア、そして一次植物の葉緑体の遺伝子DNA配列を合わせて分子系統樹を描いたところ、なんと、シアノバクテリアの中でもGloeomargaritaが一次植物の葉緑体に一番似ていることが明らかになったのです(Ponce-Toledo et al. 2017, de Vries & 2017Archibald, )。つまり、Gloeomargarita似のシアノバクテリアが真核生物に取り込まれて一次共生が起こったということです。 どこで共生は起こったか? さらに、分子系統樹で用いたシアノバクテリア、灰色藻、紅藻、緑藻それぞれの生息域を調べました。「共生者*」であるシアノバクテリアは、淡水域に生息している種も海に生息している種もいますが、Gloeomargaritaとその近縁種の生息域は淡水域に限定されました。「宿主*」である一次をもつ藻類では、最も昔に進化したのは灰色藻と言われています。灰色藻は淡水域にしか見つかっていない藻類です。共生者も宿主も淡水域に生息する藻類であることから、一次共生は淡水域で起こったことが強く示唆されました。*共生関係が成り立つとき、共生する側を共生者、共生される側を宿主といいます。 いつ共生は起こったか? また、分子系統解樹と、化石から推定される地質年代を照合していくことで、何億年前に葉緑体の一次共生が起こったのかが類推できます。それによると、21億年前、シアノバクテリアのGloeomargaritaと一次植物群が分岐していました(Sánchez-Baracaldo...

“死の湖”ソルトン湖におけるバイオ燃料生産の取り組み
先月、米エネルギー省が管轄するサンディア国立研究所から、ユニークな方法によるバイオ燃料生産の実証試験の記事が出ていたので紹介したい。 The good, the bad and the algae カリフォルニア州最大で964㎢の湖水面積をもつソルトン湖(Salton sea)は、カリフォルニアで最も汚れた湖として知られている。ソルトン湖の周辺はもともと標高が海面下にあるほど低く、その湖水面でマイナス227フィート (-69 m) と、デス・ヴァレーに次ぐ全米二位の最低地点である。1905年に起こったコロラド川の氾濫によって、大量の水が流れ込み、現在のような大きな面積の湖となった。 溢れ出た水が流れ着いたことにより生じたソルトン湖には、水が入る入り口はあるが、循環させるための出口が無い。そのため、水は周りの土から塩分を吸い取りはじめ、流れ着いた農薬などを含みどんどん汚れていった。この汚染によって、1970年頃にはほとんどの生物が生存する事の出来ない、「死の湖」へと変わっていったのだ。現在のソルトン湖の塩分濃度(約4.4%)は太平洋の海水(約3.3%)よりも濃いほどに上昇しており、塩分に強い魚と知られるティラピアさえも死んでしまうような状態になっている。 そんな「死の湖」になるほど汚染されているソルトン湖であるが、サンディア国立研究所では藻類を利用してこの汚染を浄化し、それと同時に再生可能なバイオ燃料源を作り出すための研究を進めている。彼らのアイデアは、この汚染された湖の水を、藻類を培養するための培養液として使い、生産された藻類からバイオ燃料等を製造する、というものだ。 通常、藻類を大量培養する時は、人工的にプールを作って水を張り、そこに藻類の成長に必要な栄養素を溶かし込んで培養する。一方、今回サンディア国立研究所がとっている方法は、ソルトン湖の汚染された水(藻にとっては栄養源になる)をポンプで引き上げて、傾斜した雨どいのような水路に流す。そうすることで、水路の壁面に藻類を付着させることができ、藻類は汚染された水から栄養源を吸収してどんどん増えていく、というものだ。ちなみに、水を汲み上げるポンプは太陽電池を利用するため、電力をかけずに汲み上げ続けることができる。この仕組みによって、汚染された水からは塩類が抜けて浄化され、藻類はコストをかけずに増やすことができる。あとは定期的に増えた藻類を回収し、バイオ燃料に変換していけばよいだけだ。オペレーションコストとしては藻類の回収作業コストと変換コストだけで済む。 このシステムは『Algae Turf Scrubber(ATS)』 と呼ばれる方法がベースとなっている。ATSのコンセプト自体は1970年代から提唱されており、今は観賞魚の水槽などの水処理システム等の小さなタイプのものがDIYで作られていたりする。特徴としては、ある特定の藻類種を単一で培養するわけではなく、そこに流れる水の中で最も育つ藻を優先的に育てていく、ということが挙げられる。生えてくる藻類ならなんでもよし、ということで、農業でいうところの「自然栽培」に近い培養方法といえるかもしれない。米国の企業であるHydroMentia Technologies LLCでは、水処理にATSを使って実用化させている。今回の雨どい型の培養装置を開発したのも同社ということだ。現在は900フィート(270m)ほどの実証機での試験段階だが、既存の人工的な培養方法に引けを取らないレベルの生産性が出ているとのこと。近い将来、今は廃墟と化しているソルトン湖周辺が藻類燃料生産の一大生産地となり、浄化された水によって湖畔に再び人が賑わう時代が来ることを期待したい。 現在、世界では海や湖に農業肥料や工業廃水が流れ込んで富栄養化が進み、毒性を持った藻類が大発生(赤潮など)して人、魚、動物に被害を与えるという現象が頻発している。ある意味、これも自然界の浄化作用とも取れるものだが、それを人工的に発生させ、得られた産物を有効利用しようとするサンディア国立研究所の取り組みは、こういった現象の解決策に繋がる可能性がある。 昔、小学校の頃の漢字の試験で『自然』の反対語は『人工』という回答を見て、人類は自然に敵対する存在なのか、とショックを受けたことがあった。ただ、実際に科学に親しむことでより強く感じるのは、人類は自然の反対の立場になれるほど強くも賢くもない存在であるということだ。自然の営みをよく観察し、そこに流れる大きな力を上手に利用させてもらいながら、豊かな生活を築いていくことに人類は全ての知恵を注ぐべきだと感じている。 今回取り上げたサンディア国立研究所の取り組みは、自然の流れを理解した上に人の知恵を入れ込んで形にしようとしている点において、これからの生き方の一つの回答のような気がしている。こうした自然と共生する感性は、日本人が最も得意とする部分であって、本来は日本からもこういった自然との共生型技術がどんどん出せるはずだ。この日本人の感性にこそ、次の時代のビジネスチャンスが眠っていると感じるし、世界からも求められているところだと思うのだ。
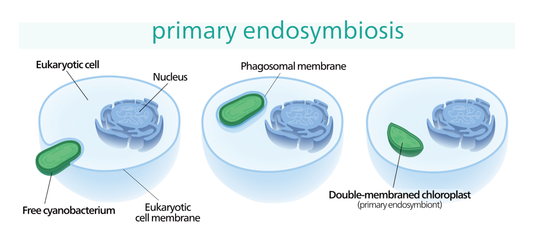
一次共生とは? -藻類の起源-
先月公開した記事では、藻類は「酸素発生型光合成を行う生物のうち、陸上植物を除いたもの」と曖昧な定義がされていて、進化を示す分子系統樹上では原核生物にも真核生物にも点在することをお話ししました。 Modia[藻ディア] 藻類とは? -実は曖昧な藻類の定義。その理由に迫る- https://modia.chitose-bio.com/articles/what_are_algae 皆さん、「藻類(そうるい)」「藻(も)」と聞くと何を想像されますか?池に漂っている緑色の生物を想像される方、クロレラやスピルリナ、ユーグレナといった健康食品を想像される方、海苔やわかめ、昆布といった海藻を想像される方、赤潮やアオコの原因を想像される方。当サイトで最新ニュース紹介している通り、独立栄養で有用物質を生産できる今ホットな生物と想像される方。どれも正解です。わかめや昆布といった体長数十メートルの「大型海藻」も、クロレラやミカヅキモといった顕微鏡でなければ観察できない数マイクロメートル... たしかに、多くの真核藻類(ユーグレナ藻、珪藻、褐藻、渦鞭毛藻、クロララクニオン藻、ハプト藻、クリプト藻等)は系統樹上では点在しています。しかし、灰色藻・紅藻・緑藻だけが、藻類としてまとまったグループ「アーケプラスチダ(別名:プランテ)」で固まっています。 そもそも、なぜアーケプラスチダ界は酸素発生型光合成を行う生物群だけで構成されているのでしょうか? その答えは、アーケプラスチダ界が、光合成を行う1つの真核藻類から分岐・進化した生物群だからです。では、アーケプラスチダ界以外の真核藻類も、酸素発生型光合成を行う生物から進化したのではないの?と疑問に思われますよね。実はアーケプラスチダ界以外の真核藻類は、アーケプラスチダ界とは異なる生い立ちで酸素発生型光合成の能力を獲得したのです。その真相はまたの機会にお話ししたいと思います。 今回は、アーケプラスチダ界がどのように酸素発生型光合成をするようになったのかをお話しします。 初めての酸素発生型光合成生物ーシアノバクテリアー 地球に生命が誕生してから、初めて光を利用し、酸素発生型光合成を行った生物は原核生物の「シアノバクテリア」です。シアノバクテリアの特徴は、細胞を包む膜が2枚あることです。細胞質と接している内側の細胞膜は「内膜」、リポ多糖類に覆われている外側の膜は「外膜」といいます(図:シアノバクテリアの外側2つの実線の円)。内膜と外膜の間には「ペプチドグリカン層」があります(図:シアノバクテリアの外側2つの実線の円に挟まれた点線の円)。内膜の内側には光化学反応が起こる「チラコイド膜」(図:細長い円)があり、そこで光合成をしています。また、チラコイド膜には、「フィコビリソーム」(図:チラコイド膜に付着する黒い丸)という大きなタンパク質複合体が結合しています。 (Keeling 2004をもとに作図) 光と二酸化炭素を使って糖を貯めて酸素を放出する「酸素発生型光合成」は、数億年とも数十億年ともいわれるくらい長い時間をかけて出来上がった仕組みと言われています。シアノバクテリアが単系統であることはつまり、原核生物の中で光合成の代謝系を作ることに成功した生物が1つしかいない可能性を示しています。生物の進化の中で、光合成の代謝系を作ることがいかに大変であるかを物語っていると言えるでしょう。 真核藻類の葉緑体はシアノバクテリアの細胞内共生により生まれた 生き物が様々な代謝系を作り、且つ連携させることは非常に長い時間が必要です。光合成の代謝系もまた然りです。真核生物は、ちょっと異なる性質を獲得した個体が生まれ、やがて元の生物とは異なる新たな生物種に分岐・進化してきましたが、多様化した生物種の代謝系は、どの種を取ってもほぼ同じなのです。 ところが、真核藻類の光合成の代謝系は、真核生物の進化の中で突然現れた代謝系です。どういうことでしょうか?この答えが、「一次共生」といわれる細胞内共生なのです。 長い期間をかけて作られたシアノバクテリアの光合成の代謝系は、光と二酸化炭素と水があればエネルギーが作り出せる素晴らしい仕組みです。この光合成の代謝系を自分のものにできたら、独立栄養で生きていけます。仮に、私たちが光合成をできたら、食事をしなくても生きていける、というようなイメージです。 この光合成の仕組みを丸ごと取り込んでしまった現象が「一次共生(primary endosymbiosis)」といわれるものです。言い換えると、真核生物がシアノバクテリアごと細胞内に取り込んで、自分の一部として共生させてしまったのです。そして、この共生したシアノバクテリアこそ、真核生物の光合成器官の「葉緑体」となったのです。 一次共生で生まれ、分岐・進化してきた一次植物 一次共生が確かに起こったという根拠は沢山あります。その中で今回は、「膜」の特徴について紹介します。下図をもとに、一次共生を説明します。 (Keeling 2004をもとに作図) 先述の通り、シアノバクテリアは外膜と内膜で包まれ、その膜の間にはペプチドグリカン層があります。そのシアノバクテリアを真核生物が取り込んで葉緑体として共生させました。一次共生で獲得された葉緑体は、シアノバクテリアの細胞膜(内膜)由来と、真核生物が取り込んだ時の膜(食胞膜)由来の二重の膜をもつ細胞小器官になったと考えられています。一次共生の細胞内共生によって獲得した葉緑体を持つ植物群は「一次植物」といいます。その一次植物は、葉緑体を保持したまま分岐・進化をしていきました。つまり、一次植物は単系統であり、アーケプラスチダ界というスーパーグループでまとめることができるのです。 一次植物のうち、藻類は灰色藻と紅藻と緑藻です。灰色藻は、二重膜に包まれた葉緑体があり、外膜と内膜の間にペプチドグリカン層が残っています。また、チラコイド膜にはフィコビリソームが着しています。紅藻は、二重膜に包まれた葉緑体がありますが、外膜と内膜の間のペプチドグリカン層は消失しています。チラコイド膜にはフィコビリソームが付着しているのは、灰色藻と同じです。緑藻は二重膜に包まれた葉緑体があります。葉緑体の外膜と内膜の間のペプチドグリカン層はなく、チラコイド膜にフィコビリソームが付着していません。 未だ謎だらけの一次共生 この3種類の中で、一次共生が起こってから、最初にできた藻類は何でしょうか? 膜の視点では、シアノバクテリアの特徴が灰色藻の葉緑体の特徴と一番似ていることから、灰色藻が一番先に分岐した藻類といわれています。しかし、DNA量の視点から、紅藻が一番先に分岐したという説もあり、灰色藻か紅藻かのどちらが先か、まだ決着がついていません。...

海洋無酸素事変 -藻が動物の絶滅に関わっていた!?-
先日公開された藻ディアの記事で、「太古の海洋における藻の大繁殖と動物の進化・繁栄の関連性」について紹介された記事があった。その中で取り上げられた論文について、海外のニュース記事では「Algae paved way for animal evolution(藻類が動物の進化の道を作った)」という大層なタイトルを付けて紹介されていた。 The New Daily Algae paved way for animal evolution: Australian study http://thenewdaily.com.au/life/tech/2017/08/17/algae-paved-way-animal-evolution/ Traces of algae found in ancient rocks from central Australia have helped...

欧州の動向から考える、バイオ燃料の行く末
今年6月、米トランプ大統領が地球温暖化対策の国際枠組み「パリ協定」からの離脱を発表したことが日本でも大きなニュースになった。一方欧州では、温暖化対策を推進するための具体的な政策が明らかとなったので紹介する。 欧州における温暖化対策を巡る動き 7月6日、フランスのマクロン政権は2050年までの低炭素化長期目標を発表し、排出権取引やCO2を吸収させる取り組みにより、CO2排出量を”ゼロ”にする「カーボンニュートラル」を達成すると宣言した。そして、この目標を達成するため、2040年までにガソリン車・ディーゼル車の販売を禁止することを宣言した。 さらに同月、イギリスも大気浄化計画の一環として、フランスと同様に2040年までにガソリン車・ディーゼル車の新規販売を全面禁止すると発表した。 欧州では英・仏だけでなく、ノルウェー、オランダやドイツも同様の政策を検討している。脱ガソリン・脱ディーゼル方針を打ち出す国が増える中、自動車業界はもちろん、バイオ燃料市場はどのように変化していくのであろうか?今後を予測する前に、まずはバイオ燃料利用の歴史を振り返りたい。 バイオ燃料利用のこれまで バイオ燃料の大規模な利用は1970年代まで遡る。まず、世界最大の砂糖の生産・輸出国であるブラジルが、1930年代よりサトウキビを原料としたエタノール生産を国家主導で開始した。その後、1973 年の第一次オイルショックを契機に同国は「国家アルコール計画(PRO-ALCOOL)」を策定し、エタノールの生産拡大が推進された。現在も、ブラジルはバイオエタノール大国として、燃料用エタノールの活用が進んでいる。ちなみに、同国では国内全てのガソリンスタンドにおいてエタノールの割合が25%以上とすることが義務付けられている。 近年、地球温暖化対策、エネルギー安全保障、循環型社会の形成などの観点から、バイオ燃料は再生可能エネルギーとして注目され、アメリカを始めとした世界各国において、研究開発及び実用化が活発になっている。その中でも、サトウキビやトウモロコシなどを原料にした「第一世代バイオ燃料」、セルロース系原料やエネルギー作物を使う「第二世代バイオ燃料」に続き、生産効率が高く、食料や土地利用との競合のない「第三世代バイオ燃料」と呼ばれる藻類燃料が大きく期待されている。 自動車業界の転換とバイオ燃料の行方 ガソリン車・ディーゼル車の生産が縮小に向かっている中、今後も持続可能な液体燃料の生産に注力するメリットがあるのかという疑問が湧いてくる。こうした疑問に対し、英Heriot-Watt大学のRaffaella Ocone教授は、次のように答えている。 持続可能な液体燃料の開発は継続すべきです。というのも、従来のガソリン車から電気自動車へと一気にシフトすることは不可能であり、ガソリンエンジンと電気モーターの両方を持つハイブリッド車が今後重要な役割を果たしていくからです。 また、航空、船舶、コンテナ輸送においては、車と異なり電気化が困難であるため、今後も液体燃料への依存は変わらないと考えられます。一例として、米海軍は、バイオ燃料を使った世界初の艦隊を立ち上げています。 そもそも、温室効果ガス排出の削減は世界共通の課題である。現在、EU 全体のCO2排出量のおよそ23%が輸送部門によるものであり、その約7割が道路輸送である。脱炭素社会に向けた戦略として、EUは温室効果ガス排出量を2050年までに1990年比で80~95%削減することを目指しているが、今回のガソリン車・ディーゼル車の販売禁止はその一翼を担うことになるであろう。 今後、従来のガソリンエンジンは減少の一途を辿っていくであろうが、バイオ燃料については引き続き需要が発生し続けるであろう。 参考資料・France to ban sales of petrol and diesel cars by 2040https://www.theguardian.com/business/2017/jul/06/france-ban-petrol-diesel-cars-2040-emmanuel-macron-volvo・Navy...

リフレッシュに最適な”クロレラカフェ”
先日、最近話題の”テレワーク”に絡めて、「なぜカフェでは仕事に集中できるのか?」という下記の記事が出ていた。 AERA dot. (アエラドット) なぜカフェだと仕事に集中できるのか? 温度だけでなく◯◯濃度が関係 〈dot.〉 https://dot.asahi.com/dot/2017072600075.html?page=1 7月24日に日本で初めて実施され話題となった「テレワーク・デイ」。始業から10時半までの間、出勤せずにどこで業務を行うという試みだ。果たして、この1日が日本人の働き方を変える第一歩となるのか。日本マ... 自宅、オフィス、カフェにおいて仕事をした時の集中度を比較する実験を行ったところ、カフェで仕事をすることが最も集中できることがわかった。この実験では、その理由の一つとして、「二酸化炭素濃度が低い」という点をあげている。 たしかに、窓を閉め切ったオフィスに長時間滞在していると、夕方には部屋の空気が淀んできて、頭が回らず集中できなくなることがある。単に疲れただけの気もするが、多少なりとも二酸化炭素濃度が影響しているのであろう。近年は、リフレッシュを目的とした酸素バーなるものが都内にも出てきているが、普段無意識に吸っている空気の「質」というのは想像以上に人の気持ちや体に影響を与えているのかもしれない。 そんな中、藻類の光合成を利用した酸素バーのアイデアを見つけたので紹介したい。『Chlorella Oxygen Pavilion』と題されたその施設は、Adam Miklosi 氏によってデザインされた、”藻類酸素バー”と名付けられるようなコンセプトの建物だ。小さな円形の小屋の外側にクロレラが培養されたチューブが張り巡らされており、クロレラが光合成することによって小屋の中に酸素が供給される、というものだ。 文章だけではなかなかイメージが湧かないと思うので、ぜひ下記ページをご覧頂きたい。 Portable Algae-Powered ‘Chlorella’ Pods Could Provide Fresh Air in Polluted Cities これは、まさに藻類版の森林浴と言えるのではないだろうか。施設に必要な面積も大きくないため、街の中にも設置可能だ。実際にこうした酸素カフェが街中にあれば、リフレッシュ目的に利用する人も多いのではと思う。...

藻を「釣る」チンパンジー
今回は、藻とチンパンジーの関係について、興味深く、かつ貴重な事例を発見したので紹介したい。 元々、野生のチンパンジーが様々な用途で道具を使用することはよく知られている。例えば、石を使ってアブラヤシの堅果を割ることや、樹の中のオオアリを枝で掘り出す事例が有名だ。 こうした中、昨年、ギニア北部の森林地帯Bakounに生息する野生のチンパンジーが、木の枝を使って渓流の底から藻類を釣って食べる様子が撮影された。この時収穫された藻は、Spyrogyra sp.と呼ばれる淡水性の微細藻類アオミドロの一種であった。アオミドロはタンパク質、淡水化物、ミネラル分を豊富に含むことから、チンパンジーはこれらの豊富な栄養分を得るために、繁殖する特定の期間に収穫したのだろうと推測されている。 まさに「百聞は一見にしかず」が文字通り当てはまるケースなので、ぜひ下記動画をご覧頂きたい。 この動画では収穫の動作の一部が切り取られているが、実際は短い場合では1分、長い場合は1時間以上も、チンパンジーは微細藻類の収穫に興じていたようだ。 これまで、水生植物を食する行動は5種類のチンパンジーでしか確認されておらず、その中でも「藻」の摂食行動に限ると、世界で2か所でしか確認されていない。ただ、それらはいずれも単独で収穫したものであり、今回のように「集団」で道具を用いて藻を収穫し、食す様子が確認されることは、非常に稀なケースであるようだ。 このような貴重な映像資料がクリック一つで見られることに感動を覚えるとともに、個人的には、動画を初見した際、原始人が登場する「even a caveman can do」シリーズの某CMを思い出した。 今回の場合は、「even Chimpanzees know!!」とでも言うのだろうか? 参考資料・Boesch,C. et al., Chimpanzees routinely fish for algae with tools during the dry season...

藻がいなければ、私たちは存在していなかった!? -地球の歴史と生命の関係-
「なぜ今ここに我々は存在するのか?」 みなさんも一度は興味を持つ問いだと思います。科学界でも、「地球上の動物出現」は最大の謎の一つです。そんな中、この謎の答えは、氷河期の「藻」の大発生だった、という論文が科学雑誌Natureに掲載されました。 www.nature.com The rise of algae in Cryogenian oceans and the emergence of animals : Nature... http://www.nature.com/nature/journal/vaop/ncurrent/full/nature23457.html The transition from dominant bacterial to eukaryotic marine primary productivity was...

牡蠣の養殖業界に吹く新しい風
老若男女問わず、日本人に大人気の牡蠣。1999年に全国初のオイスターバーが誕生して以来、オイスターバーは増加を辿り、牡蠣を楽しめる場所が広がっている。今回はそんな牡蠣と藻にまつわる話を紹介したい。 ベルギーのTomAlgae社がアジアの牡蠣養殖業者に向けた藻類生産を間もなく開始するようだ。当社のCEOであるWilliam van der Riet氏は、今はアジアのどの国かは明言できないが、9月には明らかになるだろう、と述べている。 TomAlgae社は2013年に設立された、藻類による水産飼料生産に特化したベルギー発の藻類ベンチャーだ。15年に英Benchmark Holdings社に買収された後、現在はその傘下で活動している。メインの事業は、フリーズドライを用いた水産餌量の開発であり、商品のラインナップも豊富である。その中でも、” Thalapure Mollusca”と呼ばれるフリーズドライで調整された藻類は、牡蠣の稚貝生産における藻類培養の手間を省くことができ、牡蠣産業への進出の大きな一歩になるかもしれない。 そもそも、甲殻類・貝類の幼生期は非常に小さく、餌として植物プランクトンしか食べることができない。そのため、稚貝生産において藻類培養は欠かせないが、安定した培養を実現するのは難しい。培養の安定性は稚貝生産に直接影響を与えるため、極めて重大だ。今回のテーマである牡蠣の稚貝生産においても、幼生期の最初の1-2ヶ月は藻類を食べて成長するため、生産者の多くは自前で藻類を培養し、生餌として与えている。当社はここにビジネスチャンスがあると注目しているのだ。 また、TomAlgae社はアジアとは別に、来年の秋にはアメリカでも上市を計画している。米国の東海岸ではこの5年で牡蠣の生産量が2倍に増えているとのことで、こうした需要を見越した上での計画であろう。加えて、ワシントンの牡蠣養殖の巨大企業であるTaylor Shellfish社への協業が狙いにあると推測される。同社がフリーズドライされた藻類の製品に関心を示すかは不明だが、広報部長であるBill Dewey氏は、確かに藻類供給が牡蠣生産の主要なテーマであることを認めている。 こうした中、フリーズドライ製品が生餌と同等の栄養をもたらすことができれば、生産者が藻類培養に関わる手間を減らすことにつながり、水産養殖業界において画期的な商品となる可能性がある。また、新規参入を目指す生産者にとっても、初期段階で本業に注力することができ、メリットが大きいと考えれられる。 ただ、フリーズドライでは製法にかかるコストが乗る分、生餌よりは原価が上がることが予測される。この原価の差を、保存性の向上・軽量化による利便性と輸送コストの低下で解消できるかどうか、まさにこの点のトレードオフが事業成立可否を決めるポイントになっていくであろう。 ちなみに日本では、「オイスターバー」を全国展開し2015年に上場したゼネラル・オイスター社の子会社であるジーオー・ファーム社が、昨年から沖縄の久米島にて海洋深層水を使用した陸上完全養殖に挑戦している。 国内外問わず、藻類が重要な役割を果たす甲殻類・貝類の養殖業界におけるトレンドを今後も引き続き注視していきたい。加えて、牡蠣の旬な時期まで後3か月近く、今年も首を長くして待ちたい。 画像引用オーイシ – 岩牡蠣の浜焼き今期初@MANDO(20 June 2012) / CC by 2.0

高温で生育する「温泉藻」の可能性
今年ももうすぐ夏が終わろうとしている。例年よりも雨の日が多い一方で、晴れの日には35℃以上の「猛暑日」になるまで気温が上がり、屋外で快適に過ごすことが難しかった夏であったように思える。 今回は、そんな猛暑日をはるかに超える高温の中でも生育する生物について紹介したい。 熱水泉から放たれる鮮やかな七色の正体 米イエローストーン国立公園の熱水泉(Grand Prismatic Spring)は、鮮やかな色彩により、観光客に人気の写真スポットである。 Photo by James St. John – Grand Prismatic Spring (5 June 2013) 17 / CC by 2.0 この泉の七色の正体はバクテリアや藻類が産生する色素によるもので、緑色はクロロフィル由来、黄色・オレンジ・赤色はカロテノイド由来の色だ。熱水泉の中心は87℃にも及び、こうした高温の中で生き延びる生物は熱安定性の高いタンパク質を持つ、という特徴がある。 また、温泉大国である日本では、こうした熱安定性の高い「温泉藻」を活用した商品が開発されている。 高校球児に使用された温泉藻 大分県別府市にある(株)サラヴィオ化粧品は、世界一の泉源数を誇る地元の温泉地を中心に、これまで多くの藻を発見してきた。そしてこの中で、新種の藻類である温泉藻類RG92が安全性と有効性に最も秀でており、痛み・かゆみの軽減や炎症の抑制、さらにアンチエイジング作用があることを特定した。 このRG92の特徴を活かし、日焼け止め、ヘアケア、スキンケアなどが商品化されている。その中でも、「RG92マルチアクティブローション」は、夏の甲子園でベスト8に進出した大分県明豊高校の野球部に寄贈され、プレー後の疲労回復や日焼けによる炎症の対策として使用されていた。 www.saravio.jp 明豊高校野球部(甲子園2017年夏ベスト8)にRG92マルチアクティブローションを寄贈 http://www.saravio.jp/ir/activity/activity62.html...

ロケットに乗った藻 -藻、宇宙へゆく-
今年の8月14日、SpaceX社のCSR-12ロケットが米国のケネディー宇宙センターから打ち上げられた。民間のロケットが商業ベースで日常的に打ち上げられていることも驚きだが、藻ディアとして注目すべき点は他にもある。このロケットには、なんと『藻』が乗っているのだ。 wxxinews.org East High student experiment blasts off into space http://wxxinews.org/post/east-high-student-experiment-blasts-space A group of students from East High got to watch live as their science experiment made it's way...

食品業界で使用が広がるスピルリナの幻想的な青色
世界中で若者を中心にInstagramに代表される写真をメインとしたSNSが広まる中、見た目が印象的な商品が多くの話題を集めている。特徴的な青色とピンク色によるパステルカラーもトレンドの一つだ。今回、スピルリナの色素を原料としたパステルカラーのドリンクがアメリカで話題となり、訴訟問題にまで発展しているので、その記事を紹介したい。 Brooklyn cafe claims Starbucks stole their 'unicorn' drink 米コーヒーチェーンのスターバックスが、アメリカ・カナダ・メキシコの3ヶ国で今年の4月19日から23日までの5日間限定で発売していた「ユニコーンフラペチーノ」は、インパクトの強いカラフルな見た目であることから若者を中心に大きな話題となった。 しかし、同様のパステルカラーのドリンクが、昨年既にブルックリンにあるカフェThe Endで販売されていたため、スターバックスは商標権侵害で訴えられ、1,000万ドルの損害賠償を請求されている。 The Endの「ユニコーンラテ」は2016年12月から販売されている。人気の秘密である美しく幻想的な青色は、ブルーマジックというスピルリナエキスによるものだ。このユニコーンラテは瞬く間にお店の看板メニューとなり、The Endのオーナーは今年1月に商品名の商標登録を申請していた。 商品の中身は、The Endの「ユニコーンラテ」がカシューナッツ、ショウガ、ナツメヤシなどをすり潰し、先述のブルーマジックを加えたものであるのに対し、スターバックスの「ユニコーンフラペチーノ」は牛乳やマンゴーシロップ、ブルーシロップ等で作られており、原材料と味は両者で異なる。ただ、商品名の類似に加え、ピンクとブルーを使用した特徴的な色合いも共通している。 スターバックスの「ユニコーンフラペチーノ」は5日間の期間限定販売であったが、先にパステルカラーのドリンクを販売していたThe Endがスターバックスの商品を模倣したように顧客に誤解されるケースもあったと、今回の訴訟にあたってThe Endのオーナーは主張した。 一方、スターバックス側はその訴えに対し、「当社の商品は、パステルカラーをテーマにした多くの食品やソーシャルメディアでのトレンドに影響されている」と語っている。 藻の持つ色素は近年様々な業界で注目され、商品化されているが、特にスピルリナの幻想的な青色は、食品業界において大きなインパクトを与え始めている。 欧米では数年前から食品に天然色素を用いる動きが加速し、スピルリナの青色色素の需要が急増しているが、日本においても、スピルリナ生産最大手DIC(株)が青色色素「リナブルー」の一般販売を開始し、SNSでは当商品がジュースや食品に用いられている様子をみてとることができる。また同社は、今後の更なる需要の拡大を視野に、生産設備への投資を進めており、来年にはアメリカにて新設備を稼働させる予定である。 今後、スピルリナを始めとする藻の持つ鮮やかな色が、食品業界にどのように浸透していくか、引き続き注目していきたい。 参考資料:Watch Chelsea White Introducing...

オーストラリアにおける長期的視野に立った藻類産業の育成
以前、オーストラリアのクイーンズランド州が藻類農場の建設をサポートする取り組みを紹介したが、今回も同国の藻類産業への取り組みを紹介したい。 オーストラリア東南部のニューサウスウェールズ州(NSW)は、2017年7月にUniversity of Technology Sydney(UTS)内にあるDeep Green Biotech Hub での取り組みに6百万豪ドル(約5.2億円:1豪ドル=87円換算)の追加投資をすることを決めた。 newsroom.uts.edu.au Bioeconomy boost with more money for Deep Green Biotech Hub http://newsroom.uts.edu.au/news/2017/07/bioeconomy-boost-more-money-deep-green-biotech-hub?adbsc=social_20170728_22863044&adbid=890808335838044160&adbpl=tw&adbpr=2904178699 A $6 million boost for business innovation in NSW...

米国における藻類バイオ燃料ベンチャーの今
2000年代の米国では、藻類バイオ燃料の商業化を掲げたベンチャー企業が数多く立ち上がった。 その中の一社、マサチューセッツ州に本拠を置くJoule Unlimited社がその活動を停止したことが、ワシントンDCで開催された米国エネルギー省(U.S. Department of Energy, DOE)の会議「Bioeconomy 2017」において確認された。 <Joule Unlimited社のこれまでの活躍の様子> ● 2012年に自動車会社Audiとの戦略的パートナーシップの締結● 2015年にEPAより、RINコード (D-code 5)(※) を取得● 同じく2015年に木質バイオマスからのバイオ燃料製造 (木質バイオマスをガス化し、FT法によって炭化水素を合成) を掲げたRed Rock Biofuels社の買収 ※RINコード (D-code 5)とは:バイオ燃料の生産法、使用法、輸送法をトラッキングするために、米国環境保護局(U.S. Environmental Protection Agency:EPA)の再生可能燃料基準(Renewable Fuel Standard : RFS)に基づいてつけられる再生可能識別番号(Renewable...

電気を使ったタンパク質生産
一部の生物は、二酸化炭素から様々な有機物を合成して生きている。二酸化炭素のような反応しにくい物質を基質にして合成を行うためには、なんらかのエネルギーが必要であり、藻類や植物はそのエネルギー源として太陽の「光」を利用する。「光」を利用して合成するので「光合成」と呼ばれている。 畑の肉とも呼ばれる大豆は、「光合成」で作るタンパク質だ。また、近い将来訪れると言われているタンパク質危機(Protein Crisis)に備えて注目が集まる藻類も、「光合成」でタンパク質を作る。 今回、エネルギー源として「光」ではなく「電気」を使い、微生物にタンパク質を合成させたという報告をしたのはフィンランドのLappeenranta University of Technology (LUT) とVTT Technical Research Centre of Finlandのチームだ。 「電気合成」でタンパク質生産 彼らのチームは電気と二酸化炭素を使って微生物を育て、その育てた微生物をタンパク質源として、食料や飼料に利用しようとしている。「光合成」ならぬ、「電気合成」によるタンパク質生産だ。このシステムを用いれば、電気さえあれば、世界のどこででもタンパク質を生産することができる。つまり、環境条件に依存しないで食料生産ができるようになるのだ。 VTTの主席研究員であるJuha-Pekka Pitkänenは「事実、すべての原料は空気中から取り出すことができるのです。将来この技術は、例えば飢餓に直面している地域や砂漠などで使うことができるようになるでしょう。一つの可能性として、消費者が必要なタンパク質を生産する家庭用の装置としての応用もあるでしょう。」と述べている。 光合成の10倍のエネルギー効率? この電気を利用したタンパク質生産の効率は、光合成と比べて10倍近くになるというが、現在は1gのタンパク質生産にコーヒーカップほどの実験設備を利用して約2週間かかるということなので、まだまだ発展途上ではありそうだ。研究者が目指している次のステップは、パイロット生産を開始し、食品や飼料の開発に十分な量の原料を製造することだという。 「我々は現在、リアクターの概念、技術、効率の向上、プロセスの制御といった技術の開発に注力しています。プロセスの制御には、微生物を可能な限り多く生育させるための再生可能エネルギーの調整や、モデリングが含まれています。このアイデアを大量生産に発展させ、技術がより一般化していくにつれて価格も下がっていきます。商業化のスケジュールは経済に依存します」とLUTのJero Ahola教授は述べている。 タンパク質量は50% この電気で育てた微生物には、50%のタンパク質と25%の炭水化物が含まれており、残りは脂質と核酸で、非常に栄養価が高いという。また、栄養価については生物種を変えることで変更できるという。 太陽光の代わりに電気を使う以外は、藻類と似たコンセプトを持った研究であり、とても興味深い。藻類の場合は、太陽光を使えることがメリットだが、デメリットとして太陽光が出ていないときは育てられないので、生育状況が天候に左右される。一方、電気微生物の場合は、太陽光がなくても電気さえ通電していれば育てることができるので、安定した生産ができるところがメリットとなる。太陽光が得られにくい地域などでの食料生産の手段としては面白そうだ。あとはどれくらいの効率まで持っていけるかの勝負であろう。 アカデミック寄りではあるが、日本でも同様の研究が行われている。 「電気で生きる微生物を初めて特定」理化学研究所・東京大学(2015年)http://www.riken.jp/pr/press/2015/20150925_1/ 電気が光と化学物質に続く地球上の食物連鎖を支える第3のエネルギーであることを示した、非常に意義のある研究成果であり、これからさらに注目されていくべき分野だと思う。 参考資料:Protein...
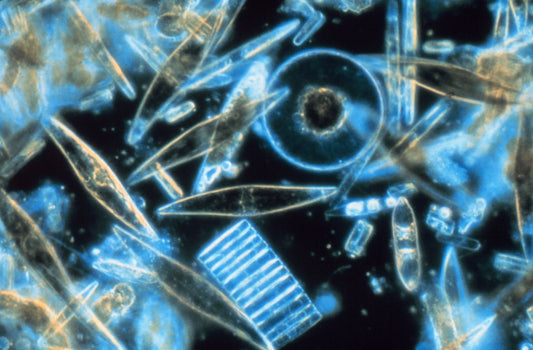
海洋の一次生産者の主役、珪藻の重要な遺伝子の発見
「珪藻」は、食物連鎖の基盤となる単細胞の小さな藻類だ。食物連鎖における一次生産者として全体の20%を占めており、海洋の一次生産者としては実に45%を占めている。また、珪藻は大量の二酸化炭素を取り込み、酸素を排出している。その光合成量は、なんと世界の全熱帯雨林に相当するほどだ。 ガラスと同じ、二酸化ケイ素でできた被殻があるのが特徴で、顕微鏡で観察すると冒頭の写真のように、様々な美しい形状を観察することが出来る。 「珪藻」にはピンとこない方も、「珪藻土」という言葉は聞いたことがあるのではないだろうか?珪藻土は、珪藻の被殻の化石が主成分の土のことであり、色々なものに活用されている。吸水性の高さを活かした、バスマットやコースターなどが最も身近かもしれない。他にも、醤油やビールのろ過助剤としての利用や、湿度調整と脱臭の目的で住宅用壁材としての利用など、実に幅広く活用されている。 このように、化石になってもなお私たちに多大な恩恵をもたらしてくれている珪藻は、食物連鎖と物質循環に大きな影響力を持つ。そして、それは珪藻の細胞サイズに依存することが知られている。 最近、英・イースト・アングリア大学(University of East Anglia)の科学者は、珪藻細胞の大きさを調節する遺伝子を同定した。研究結果は2017年7月21日、ISME Journalに公開された。https://www.nature.com/ismej/journal/vaop/ncurrent/full/ismej2017100a.html 珪藻類の細胞サイズは非常に多様であり、同じ種であっても環境や細胞周期によって変化する。珪藻細胞の大きさは、生理学と生態学の多くの面に影響を与える。例えば、大きい細胞ほど表面積/体積比が小さくなるため、効率よく栄養を取り込むことができない。その一方で、体積が大きいため、多くの栄養を細胞内の液胞に溜め込むことができる。また、大きな珪藻種は沈降速度が速いため、小さい珪藻種のように表層水で消費されることなく、深水層へ固定された炭素を運ぶことが出来る。このように珪藻類が食物連鎖と物質循環に果たす役割は細胞の大きさに強く依存するが、珪藻の細胞サイズを調節する遺伝子はこれまで解明されていなかった。 UEA大学.環境サイエンス.モック教授の研究チームは、珪藻の最も大きな特徴であり、珪酸質の被殻(frustule)と呼ばれる珪藻の細胞壁に当たる部分に注目した。珪藻の化石記録によると、被殻は1億8500万年以上前から出現していることから、研究チームは被殻が珪藻の進化過程において重要な役割を果たしていると仮定した。 被殻の中に存在し、被殻構築に関与すると思われるsilacidinと呼ばれるタンパク質の発現レベルを調節し、細胞の大きさへの影響を調べた結果、silacidinの発現レベルを低下させると珪藻細胞が大きくなることが分かった。また、silacidinをコードする遺伝子が、生態学的に重要ないくつかの他の珪藻類でも保存されていることが判明した。 この結果は、気候変動による食物連鎖に与える影響を理解する上で重要な意味を持つ。モック教授は『化石記録も、海水温度と珪藻の平均的な細胞サイズとの関係を示しているため、珪藻等の植物プランクトンの細胞サイズは、地球温暖化に応じて変化し続けると推測する。』と述べている。 参考資料:Scientists find secret to cell size in world’s biggest food producerhttps://phys.org/news/2017-07-scientists-secret-cell-size-world.html トップ画像Diatoms through the microscope.jpghttps://commons.wikimedia.org/wiki/File:Diatoms_through_the_microscope.jpg

フォトバイオリアクターを用いた微細藻類バイオマスの生産コスト
イタリアのTredici教授の研究グループより、安価なソフトプラスチック(LDPE)を利用した微細藻類屋外培養設備(=フォトバイオリアクター)の技術経済試算に関する論文が発表された。Techno-economic analysis of microalgal biomass production in a 1-ha Green Wall Panel (GWP®) plant フォトバイオリアクターとは Photobioreactor PBR 4000 G IGV Biotech 微細藻類を含む光合成を行う生物を、光エネルギーを利用して培養する装置であり、広義には商業用に広くに用いられているオープンポンド・レースウェイもフォトバイオリアクターに含まれる。しかし、一般には上述の開放系の培養システムを含まない、閉鎖系の培養システムを指すことが多い。 論文によると、今回試算のベースに利用されたフォトバイオリアクターは「Green Wall Panel (GWP®)」だ。 Products |...

藻類を利用した廃水処理システム
先月、米国ミズーリ州のClearas Water Recovery社は、廃液で藻類を培養することで水を浄化し、また増えた藻類を副産物として利用することを目的とした大規模施設の建設を発表した。 このシステムは、ABNR(Advanced Biological Nutrient Recovery)という名で、廃液に含まれる栄養成分(主に窒素とリン)を藻類が吸収して増えることで水を綺麗にする仕組み。大規模施設はユタ州の自治体に建設予定で、1日に4百万ガロン(15,200トン)の廃水を処理し、副産物として発生する藻類の生産量は1日あたり8,000ポンド(=3,629kg)になるとのこと。副産物として生産された藻類は、飼料利用をメインとした複数の用途展開が検討されている。 ABNRシステムについては、以下の説明動画をご覧いただきたい。 Clearas Water Recovery社は1日15,000ガロンの廃水を処理できる実証設備を保有しており、今回はそれを大幅にスケールアップさせたものとなる。 ABNRシステムは3つのステップから成り立っている。 ステップ1:廃液に二酸化炭素と種藻を混ぜる。二酸化炭素で藻類を活性化させ、pHレベルを管理する。 ステップ2:フォトバイオリアクターによる藻類の培養。この過程で二酸化炭素、窒素、リン、その他の栄養成分を藻類が吸収する。水流、pH、光強度が最適化されるように管理する。 ステップ3:育った藻を分離。増えた藻類の一部は種藻としてステップ1に送り、余った藻は収穫する。 これまでに3箇所の自治体と1つの工場に小スケールのプラントを導入しており、特にリンの回収能力に強みを持っているようだ。導入した小プラントから取れる藻類バイオマスについては、用途開発のための原料として利用しているとのこと。 廃液を綺麗にし、なおかつ、副産物として付加価値のあるものを取り出せるというシステムは、従来コストセンターであった廃水処理をプロフィットセンターに変えられるインパクトを持つ。ただ、コンセプトとしては優れている反面、生物を使った水処理には課題も多い。様々な廃水の多様性への対応、入ってくる水質の変動に対するロバスト性、廃水処理能力の安定性、副産物として得られた藻類の安全性や生産性…..など少し考えただけでも気になるポイントは多くある。Clearas Water Recovery社がこれらの技術的課題のハードルをどのように乗り越えながら大規模プラントを立ち上げていくか、続報を楽しみにしたい。
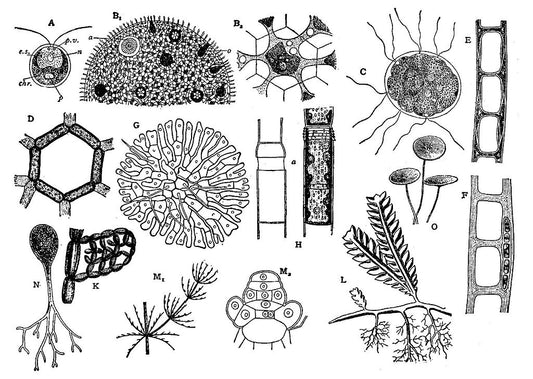
藻類とは? -実は曖昧な藻類の定義。その理由に迫る-
皆さん、「藻類(そうるい)」「藻(も)」と聞くと何を想像されますか? 池に漂っている緑色の生物を想像される方、クロレラやスピルリナ、ユーグレナといった健康食品を想像される方、海苔やわかめ、昆布といった海藻を想像される方、赤潮やアオコの原因を想像される方。当サイトで最新ニュース紹介している通り、独立栄養で有用物質を生産できる今ホットな生物と想像される方。 どれも正解です。 わかめや昆布といった体長数十メートルの「大型海藻」も、クロレラやミカヅキモといった顕微鏡でなければ観察できない数マイクロメートルの「微細藻類」も、みんな「藻類」です。 岩波生物学辞典で「藻類」を調べてみると、 『光合成の過程において酸素を放出する生物から有胚植物を除いたもの』 引用元:岩波生物学辞典 と書いてあります。つまり、酸素発生型光合成を行う生物のうち、コケ植物、シダ植物、種子植物を除いた生物の総称です。「藻類」の定義が、とても多様な生物の寄せ集めであり、曖昧なことがおわかりいただけると思います。 藻類の定義が曖昧なのはなぜか? なぜ、「藻類」の定義がとても曖昧なことになっているのでしょうか?それを知るために、生命の誕生までさかのぼります。 すべての生き物は一つの生命から 現在、地球上に存在する生き物も、過去に滅んでしまった生き物も、すべての生き物は元を辿ると1つの生命に行きつくといわれています。最初に誕生した1つの生物から、ちょっと異なる性質を獲得した個体が生まれ、やがて元の生物とは異なる新たな生物種に分岐しました。その新たな生物から、再びちょっと異なる性質を獲得した個体が生まれ、やがて元の生物とは異なる新たな生物種に分岐しました。その新たな生物から・・・・、 このようにして、最初に誕生した生物から、ちょっとずつ変化して、別々の生物種へ分岐を繰り返して、生命はずっと引き継がれていきながら今の生物が存在しています。もちろん、今いる生物も、新たな生物種に分岐する途中にいます。 この生物の分岐と進化の道筋をわかりやすく図にしたものが、「系統樹」です。 生命の進化を示す系統樹 上記図は、2012年にAdlらによって提案された全生物の系統樹です(わかりやすくするため、一部の生物群を省略しています。)。原核生物には単系統(同一共通祖先から進化した生物の集まり)が支持されている真正細菌と古細菌から構成されています。真核生物は単系統が支持されている5つのスーパーグループ(SAR〔ストラメノパイル界+アルベオラータ界+リザリア界〕、アーケプラスチダ界、エクスカバータ界、アメーボゾア界、オピストコンタ界)と、まとまりが未だに不明の生物群から構成されています。 38億年前に最初の生命は地球に誕生しました。これは「原核生物」といわれる、細胞内に細胞核を持たず、細胞内の構造がシンプルな生物でした。そして、光合成をする原核生物は30億年前に分岐したといわれています。原核生物は、約20億年かけて「真核生物」といわれる、細胞核を持ち、エネルギー供給器官であるミトコンドリアをもつ生物へと進化していきました。真核生物は、12億年前に多数の分類群に分化したと考えられています。これを真核生物のビッグバンといいます。あまりにも古く、また急激な進化だったので、このビッグバンの時の真核生物の分岐を辿ることは非常に困難ですが、真核生物の系統樹の根元のスーパーグループはこの時に分岐したと考えられています。 藻類は、進化を示す系統樹上で点在する 藻類の話に戻ります。 定義にある「藻類」を、系統樹の色付きの名前で示します。生命の進化を示す系統樹をみると、藻類は系統樹上に点在しており、ひとまとまりにはなっていないことがわかると思います。 まず、原核生物にも、真核生物にも藻類が存在することがわかります。次に真核生物を見てみると、アメーボゾア界とオピストコンタ界以外の、5つの界に藻類が存在していることがわかります。各々の界を見てみると、アーケプラスチダ界に所属する生物群(紅藻、陸上植物、緑藻、灰色藻)は全て光合成をする生物ですが、他の4つの界(ストラメノパイル界、アルベオラータ界、リザリア界、エクスカバータ界)はどれも光合成をする生物(=藻類)と、光合成をしない生物が混ざっていることがわかります。つまり光合成をする能力は、生物の分岐と関係がある部分と、関係がない部分があるということです。その理由は、生物光合成器官である葉緑体の獲得に深く関わっています。これはとても面白い話なので、またの機会にお話ししたいです。 「藻類」は30億年をかけて進化したてんでバラバラな生物群を、「光合成をする」というカテゴリーでくくったときの総称なのです。さらに、過去には光合成をしていたけれど、今はしなくなった藻類も多数知られていることが人々を混乱させています。例えば、2017年7月5日に中原氏が紹介した夜光虫は、光合成の機能を失った渦鞭毛「藻」です。 Modia[藻ディア] 南オーストラリアの夜光虫 https://modia.chitose-bio.com/articles/1 南オーストラリアのポートリンカーンの近くのTulka beachで、暗闇に光る藻が発生している。光の正体はNoctiluca scintillansと呼ばれる渦鞭毛藻の一種で、日本では『夜光虫』と呼ばれている。「虫」という言葉がつくが虫ではないというややこしさは、あの有名な「ミドリムシ」と同じだ。今年のGW、湘南の海で大量発生した夜光虫の幻想的に光り輝く姿がニュースでも取り上げられたことは記憶に新しい。その幻想的な姿を一目見ようと多くの人が夜の海に訪れ、Twitter上には多くの写真がアップされていた。「夜光虫ファン」と呼ばれる人... 「藻類」を知れば知るほど、「藻類」とは何かが分からなくなってしまいそうです。...

生きてるインク
藻類の『色』と『増殖の速さ』をうまく利用した生きているインクの紹介をしたい。 このユニークなアイデアを形にしているのはLiving Ink社。コロラドに拠点をおくコロラド州立大発のベンチャー企業だ。 https://www.instagram.com/p/-welbJnjkj/?taken-by=livinginktech 世界で最もサステイナブルなインクを、藻類で CEOのScottとCTOのSteveの2人は、コロラド州立大学でPh.Dとして分子生物学の研究をしていた時に出会った。2人とも藻類からのバイオ燃料とバイオプロダクトの研究をしていたという。藻類を使ったプロダクトアイデアを考えている時に、世界のインクの大半は石油由来で毒性の高いものが使われている、ということに気づき、藻類を使った世界で最もサステイナブルなインクを作れないか、というアイデアを思いついたそうだ。 2013年から活動を始め、2015年にはKick starterで製品化に成功。2016年にはTEDでのプレゼンに参加。 7:20あたりからご覧頂くと、Living Inkで描いたイラストが浮き出す様子を見ることが出来る そしてつい先日 Colorado’s Advanced Industries Accelerator (AIA),からの資金提供が決まり、製品の完成が見えてきたとのこと。今年の夏には製品がローンチされる予定のようだ。こうしてみると、まさにベンチャーのサクセスストーリーの王道をトントン拍子に進んでいるように見えるが、裏では技術的課題の解決含めて色々努力されたことだろう。 藻が育つことで浮き出すメッセージ さて、彼らのLiving Inkであるが、生きた藻体そのものを利用して作られている。このため、紙に絵を描いた直後は薄い状態で、色もついていない状態なのだが、部屋の光に当たるところに2,3日も置いておくと、藻が増えて緑色になっていく。それによって文字や絵が浮きだす、という仕組みだ。口で説明するのが難しいのだが、実際にどういう感じかをご覧になられたい方はTEDプレゼンテーションの7:20あたりからの動画を見ていただきたい。可愛いフクロウの絵が、時が経つにつれて増えて、文字も浮き出していく様子がわかる。 https://www.instagram.com/p/9aDcIxHjky/?taken-by=livinginktech ユニークなのは、時間とともにメッセージ性がやわらかく変化していくというところで、これは新しい発想ではないだろうか。植物が育っていくような感覚で、カードが育ってメッセージが浮きだす。時間軸が加わることで物語が生まれるところに、このアイデアの本質があるように感じた。 実際は育ちきった後はどうなるのか、とか、寒いところだと上手く育たないんじゃないか、とか、このペンの保存期間はどれくらいなんだろうか、とか。。細かいところを気にすれば色々ツッコミどころがないわけではないのだが、このインクに対してそんな小さなことを指摘するのは野暮だろう。この素敵なアイデアに乗って、時間とともに変化する様子を存分に楽しむのをマナーとしたい。 https://www.instagram.com/p/BTUDylClHEb/?taken-by=livinginktech このインクを使ったカードを小さな子供に送り、『光合成』や『藻類』の存在を身近に感じてもらうのも面白いかも。 購入は以下のサイトから。但し、注文から1ヶ月かかるそう。 Time 参考:Living Ink...

中国最大のゴーストタウンがあるオルドス市には、世界最大規模のスピルリナ生産地がある。
中国北部の広大な内モンゴル自治区、南西部に位置する「オルドス市(鄂尔多斯/Ordos)」をご存知だろうか? 引用元:https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%AA%E3%83%AB%E3%83%89%E3%82%B9%E5%B8%82 オルドス市には、2003年頃から100万人規模の都市として開発された「康巴什(カンバシ)新区」がある。しかし、現在は6万人ほどしか住んでおらず、入居者のないマンションやオフィスビル、人も車もほとんどいない整備された大きな道路の広がるその街並みから「中国最大のゴーストタウン」と呼ばれ、世界中から注目されている。 中国の砂漠には、豪華すぎるゴーストタウンがある(画像集) オルドス市のもう一つの顔は、世界最大規模のスピルリナ生産地 実は、「オルドス市」にはもうひとつ注目すべき話題がある。それは、DHAを含む好中温性スピルリナの発見により、世界最大規模のスピルリナ生産地となったことだ。 1996年、オルドスのアルカリ性湖にてDHAを含む好中温性スピルリナ発見 オルドス市が位置する海抜1500キロメートル前後のオルドス高原は、東・北・西3面を黄河に、南を万里の長城に囲まれ、砂漠が広がっている。オルドス高原北部にあるクブチ砂漠 (庫布其沙漠/ Kubuchi Desert)と南部にあるムウス砂漠(毛烏素沙漠/Mu-Us Desert)の間のオトク草原(鄂托克草原/Otog Glassland)には、アルカリ性湖と塩湖が多数分布しており、その中の1つのアルカリ性湖にて健康に良いことで注目されているオメガ3系多価不飽和脂肪酸であるDHA(ドコサヘキサエン酸、Docosahexaenoic acid)を含むスピルリナ、Arthrospira maxima NS-LC001株が1996年に発見された。 NS-LC001株は、東経108°04’、北緯39°14’にあり、モンゴル語で「白い湖」を意味するChahannaoer湖(察汗淖尔湖)で単離された。熱帯・亜熱帯湖で天然に存在する好熱性種のスピルリナと比較すると、この株は好中温性であり、最適温度が20℃前後。栄養成分のうち、タンパク質と脂質がそれぞれ67.6%と6.1%で、他にフィコシアニン(4.32%)、カロチノイド(0.29%)、とクロロフィル(0.76%)などの色素も豊富に含んでいる。そして何よりも、シアノバクテリアではめったに見られないDHAが含まれていることが一番の特徴だ(DHAの含量は総脂肪酸の2.2%)。 好中温性である点もDHAを含むという点もこれまでで唯一の報告であり、さらにスピルリナ従来の分布記録を大きく塗り替えた、最北端記録でもある。 生産から加工、商品開発、そして販売まで オルドス市に位置するオトク草原でのNS-LC001株の発見以来、中国政府は、2003年から13年間を通してオトク旗を「世界の藻都」として開発に力を入れてきた。その結果、オトク旗は今、スピルリナの生産から加工、商品開発、そして販売まで一体型産業構造である世界最大規模のスピルリナ産業園区となっている。園区面積は実に827ha(東京ドーム約176個に相当)、培養面積は267ha(東京ドーム約57個に相当)、年間生産量は3,500トンとのこと。さらに、2020年までに6,000トンまで生産量を増やす計画があるそうだ。園区には今現在26の企業が進駐している。 中国のスピルリナ生産量に関して正確な数字は分からないが、例えば以下の様な報告があるので紹介する。 現在、中国国内において、計750ha以上の生産設備で、年間9,600トンのスピルリナ粉末が生産されている 引用元:Chen, Jun, John Benemann, Jun...

藻類農業は、ビルの立ち並ぶ都会での地産地消を可能にする?
新しい農業の形として、藻類農業(Algae-culture)というものが世界各地で作られつつあるという報告をしたばかりだが、今日紹介するのは都市型の藻類農業の取り組みだ。 藻類は、NASAの宇宙ステーション滞在中の栄養源としても利用が検討されるなど、非常に高い栄養価を持った食物である。しかも、その生産能力は植物の数倍〜数十倍にのぼるため、農業に比べて生産面積も小さくて済む。さらに非常に小さく、どんな形の設備でも栽培できるという特徴がある。これらの特徴を生かして、都会の生活の中でも藻類農業を取り入れ行こう、というコンセプトの建築デザインが生まれつつある。 These Architects Want To Make Algae Farming Just Another Part Of Urban Infrastructure 先日カザフスタンで行われていた展示会にて、ロンドンをベースとするecoLogicStudioのデザイナーが海洋生物学者や藻類農家と協力し、都市建築の中に藻類農業を取り込んだ建築デザインを発表した。利用する藻類はスピルリナとのこと。スピルリナは牛乳よりカルシウムが多く、人参よりベータカロテンを含み、牛肉よりもタンパク質を含むパーフェクトフードだ。世界で最も食べられている藻類でもある。 BIO.tech HUTと呼ばれるプロトタイプでは、毎日平均612gのタンパク質を生産できる設定になっていて、これは大人12人の推奨摂取量を供給するのに十分な量である(もちろん、毎日大量のスピルリナを食べてることにはなるが。。)。なお、同じ量のタンパク質を供給するには牛だと8頭が必要な計算になるという。そして、これらの牛を育てるには660日の日数と日々70世帯分のエネルギー消費が必要になる。 このような食料供給という現実的な側面だけではなく、都市、特に公共の場で藻類農業を行うことのメリットは他にもあるという。ecoLogicStudioの共同創業者の一人であるClaudia Pasquero氏は『こうした統合されたデザインを都市の中で行うことで、エンドユーザーと今までとは異なる形態のコミュニケーションが確立し、それによって様々な消費方法が確立されていくことも目的としています。』と述べている。 日頃自分たちが使っている製品がどこから来ているかをわからないまま消費していくのではなく、目の前で成長していく様子が日々見れて、それを目の前で収穫し、その場で食べることができる。そんな一つの完結モデルが都市の中でも見ることができれば、確かにコミュニケーションが大きく変わるかもしれない。 地産地消を都会で、藻類を使えばそんなマイクロ自給自足ができるのだ。その存在は現代では切り離された『人』と『食』とのつながりをもう一度身近なものにしてくれるかもしれない。これまでは錠剤や緑の粉末、といった日常的な食物とはかけ離れたイメージの藻類だが、クリームやシナモン、ケーキ、パン、といったようなもっと食欲をそそり、美味しさを訴えられるレシピ開発ができれば、もっと身近な食材になっていくだろう。 オフィスビルの真ん中に緑に光る培養装置があって、その中で育っている藻類をその場で収穫して、その場で調理して食べる。そんな生産から消費まですべてが完結した藻類カフェを『都会』に作る、というコンセプトなどどうだろう。大規模で大きく育てる藻類農業もあれば、こうして小さく広げていく藻類農業もあるんだな。そしてその小さな農業を『都会』でやることにきっと大きな意味があるように思える。このアイデアいただき。 参考資料:FAST COMPANY「These Architects Want...

湖や池に大量発生した藻で作ったサンダルが登場。作れば作るほど水が綺麗に?
近年、ニュースなどで中国の湖や池で藻が異常なほど大量発生して、真緑になっている写真を見たことなどがないだろうか。これは多くの場合、湖や池に生活排水などが入り込んで富栄養化し、そこに藻が大繁殖したことによって引き起こされる。海で言えば赤潮なんかも同じ仕組みで起こっている。生物学の分野では『ブルーム(大発生)』と呼ばれている現象である。 ブルームを引き起こす藻類の中には、毒素を発生させ、他の水生生物や人類に被害をもたらす恐れがあるものも多い。藻類ブルームの発生は複雑で、そのメカニズムはまだ明らかになっておらず、正確な予測と予報を出すのが難しい。このため、藻類ブルームがもたらす危害を軽減するには、それをいかに処理するかが水環境保護における重要なテーマとなっている。 そんな中、この発生した藻類ブルームを何かに利用できないか、という取り組みを進め、見事素材として生かしたサンダルが商品化された記事が出ていたので紹介したい。 VivobarefootXbloom | May 2017 | Blog このサンダルを商品化したのは、イギリス発のシューズメーカーVivobarefoot社で、ミニマルランニングシューズのブランドで有名である。裸足に近い状態で歩いたり走ったりすることが足に最適な状態をもたらす、という哲学のもとで製品開発を進める、知る人ぞ知る、というようなブランドでもある Vivobarefoot社の主流ラインである、水陸両用の耐水性運動靴「ULTRA Ⅲ」シリーズ。通常、石油由来のエチレン酢酸ビニル(EVA)のポリマーから作られているが、2017年7月、EVA(60%)と藻類(40%)がブレンドされた新バージョンが登場した。ブルームになる前の藻類を収穫し、柔軟性のあるゴム状に加工し、EVAと混ぜる。このサンダル1対を作るために必要な量の藻類を収穫することによって、57ガロン(約216L)の水を浄化することにつながるわけである。 引用元:https://www.vivobarefoot.com/uk/blog/may-2017/vivobarefootxbloom# Vivobarefootの創設者Galahad Clark氏は次のように述べている。 『我々はEVAポリマーが基本的に石油化学由来の素材であり、持続可能な原料ではないことを知っていたので、EVAの代わりになるいい素材ががないか目を光らせていたのです。』 実際に藻類を素材にする際には様々な試行錯誤を重ねたようだ。彼らの靴はデザインがユニークで六角形の穴が多数空いているため、素材には素早い伸び縮みが求められる部分などに課題があったが、それらをクリアーし、今回の上市につながったとのこと。 また、Vivobarefootのクリエイティブディレクター、Asher Clark氏は次のように述べている。 『EVAの製品よりも少し気分が良い気がするよ。ちょっぴりスピルリナのようなにおいがするね。』 ぜひリンク先の製品写真も見ていただきたい。デザインが素敵でとてもクールだ。藻を素材にして環境に優しいから売れるというものではなく、その製品自体が魅力的で購入したいと思えるものである、ということがやはり大前提なのだと思う。その製品自体が十分魅力的な上に、それに加えて環境にも配慮しているストーリーもあるのだよ、という部分がクールであり、消費者の購入決断を一押ししてくれるのではないだろうか。
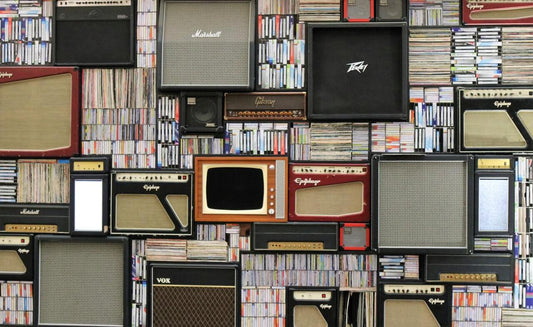
吟味されずに拡散する情報。その波紋は藻類研究の分野にも
今年5月、スタンフォード大学他の研究者・医者から一本の論文が報告された。Unexpected mutations after CRISPR–Cas9 editing in vivo 藻類の研究開発の分野でも話題のゲノム編集技術に関するものだ。 この論文は、ゲノム編集を貶める目的で書かれたものではない 論文の内容はこうだ。 – CRISPR-Cas9システム (以下、CRISPR) でゲノム編集を施した受精卵より誕生した2匹のネズミのゲノムを、ゲノム編集を施さなかった受精卵より誕生した一匹のネズミのゲノムと比較すると、ゲノム編集を施した部位以外の多くの部位で1塩基変異 (single nucleotide variants, SNVs) や挿入・欠損 (indels) が確認された。 – また、それらの予期せぬ変異が、ゲノム編集を受けた2匹のネズミのゲノム間で非常に共通していた。 – これら変異の多くが、CRISPRで使われたgRNAから想定しうる変異部位とは異なる場所で起こっていた。 この観察結果より、著者らはCRISPRによるゲノム編集によって予期せぬ変異が生じる可能性を報告した上で、いかにその可能性を減らし、ゲノム編集技術を改善し、臨床試験におけるリスクを減らすため、より一層の研究開発の必要性を報告内で提起している。 CRISPRによるゲノム編集が、予期せぬ変異を生じることは以前より議論されており、この報告が初めてのものではない。 また、この論文の著者であるMajahan医師はこう述べている。 「CRISPRシステムが悪いモノだとは思っておらず、それどころか素晴らしいモノだと考えている」 「私はCRISPRの技術と金銭的な関連はなく、単に患者がいるだけ」...

藻の口紅
先日の7月6日は「国際キスの日」だったらしい。(ただ、日本では5月23日が「キスの日」とされているし、更には国によって日が異なるようだ。)そんなキスの日にちなんで、藻類由来の成分が入った口紅「Skinicer Ocean Kiss」を紹介する。 引用元:https://aesthetikonzept.com/product/skinicer-ocean-kiss-lipstick-classic-red/ 入っているのはスピルリナ(Spirulina platensis)由来の抽出物で、成分名はSpiralinと命名されている。Ocean-Pharmaというドイツの会社が製造しているようだ。 スピルリナはスピルラン(Spirulan)と呼ばれる多糖類を作るが、この多糖類は抗ウィルス、抗真菌、抗菌、コラーゲン形成、細胞再生、紫外線防御といった特性を持つことが報告されている。今回の口紅はこのスピルランの特性を利用した製品となる。 考えてみれば、口紅というのは長期間、定期的に使われる割には、あまり衛生面を気にすることが少ないように思える。Spiralinはそういった口紅の衛生面を清潔に保てることも売りにしているようだ。また、冬場などにインフルエンザウィルスが流行する時の唇への習慣としても勧めている。 Skinicer Ocean Kissの 口紅はパラベンやシリコンが含まれていないとのこと。色は4色で、どの色も1本49ドル(約5,000円)。口紅以外にもSpiralin入りの製品ラインナップがあるので、気になる方はニュージーランドの販売会社Aesthetikonzept社のHPを参照いただきたい。 藻類には多糖類を生産するものが多く存在するが、その多くは機能性を有している。それらの特性を理解し、それらが生かされる形で身近な製品に利用されていくのは嬉しい。原料を作っているドイツの会社も、口紅を販売しているニュージーランドの会社も決して大きな企業ではないが、このようなユニークかつ身近な商品をつくり、一般に販売していくことは藻類への認知度向上につながる。こうした草の根で切り込んでいく取り組みこそが業界を作っていく、ということなのだと感じる。

遺伝子組換え微細藻類を、世界で初めて安全に屋外培養?
カリフォルニア大学サンディエゴ校の研究者と米国の藻類系ベンチャー企業サファイア・エナジー社(Sapphire Energy)は、米国環境保護庁(United States Environmental Protection Agency, EPA)の認可のもと、世界で初めて、遺伝子組み換え微細藻類の開放系利用における環境影響評価試験を行った。研究結果は2017年5月3日、ジャーナルAlgal Researchのオンライン版に公開された。 Scientists Complete First EPA-Approved Outdoor Field Trial for Genetically Engineered Algae 遺伝子組換微細藻類を、50日間屋外で培養 淡水に住む緑藻の一種、Acutodesmus dimorphusの遺伝子組み換え株を、50日間800Lスケールにて屋外培養することで評価試験が行われた。この藻類株は、脂肪酸生合成関連遺伝子と緑色蛍光タンパク質発現遺伝子が導入されたものだ。本試験は、米国エネルギー省の資金援助を受けている。 試験内容と結果 評価試験期間中、導入された遺伝子及びその遺伝子により得られた形質は、安定的に維持できた。遺伝子組み換え株を地元の五つの湖から採集した水のサンプルに接種し、サンプルにおける物種多様性、生物種構成、および生息する藻類のバイオマス量における影響は、野生株との間に差が見られなかった。また、遺伝子組み換え株の環境への拡散について調査したところ拡散が確認されたが、培養池から離れるほど拡散の検出は大きく減少した。 形質が維持でき、なおかつ在来種に悪影響を与えていないことから、研究者らは遺伝子組み換え株の屋外培養に成功したと結論づけている。 遺伝子組み換え藻類の活用に向けた第一歩? 共著者であるカリフォルニア大学サンディエゴ校・生物学部の生態学者ジョナサン シュリン(Jonathan Shurin)は次のように述べている。...
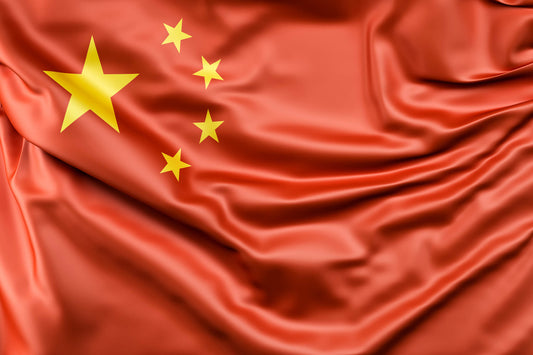
圧倒的な市場規模を誇る、中国の藻類産業
日本や欧米では、サプリメントや化粧品をはじめとした微細藻類由来の商品が市場を拡大し、様々な情報が日々飛び交っている。それに比べ、中国における藻類生産現場の情報を目にすることは非常に少ない。 そこで本日は、中国における藻類産業をまとめた報告を紹介する。 中国におけるスピルリナ生産(Chen et al. 2016) 中国におけるスピルリナの商業生産は1991年にShenzhen Lanzao Biotech Corporationによって初めて行われた。現在は、中国国内において、計750ha以上の生産設備で年間9,600トンのスピルリナ粉末が生産されていると見られている。また、これは年間売上6億5,000万USドル相当であると見積もられている。(つまり、中国の生産現場におけるスピルリナの年平均生産性は約13トン /haであり、生産されたスピルリナ粉末は1キロあたり約70 USドルで販売されていることになる。) また、この中国におけるスピルリナ生産量は世界総生産量の約3分の2にあたり、その大半が中国国内で消費されている。現在、中国におけるスピルリナの生産量は年間約10%の伸びを見せ続けている。 中国で生産されるスピルリナのほぼ全てが、パドルホイールを利用したレースウェイポンドを利用しているが、北部の内モンゴル地区では (ここでは年間約3,000トンのスピルリナが生産されている)、レースウェイポンドは屋外ではなく、温室内に設置されている。それでも北部の地方では、5~10月の期間にのみ生産が行われることが多い。 2004年のLiangらによる報告(Liang et al. 2004)によると、“中国におけるスピルリナ生産は1996年に1,000トンに達した”と、あることから、1996年から2012年の間に中国におけるスピルリナ生産量は約10倍に増加したことになる。また、2004年のPulzらの報告(Pulz and Gross 2004)によると、2004年時の “世界の微細藻類バイオマス生産量は約5,000トン、市場規模は年12.5億ドル程度” とあるので、それと比しても非常に大きな数字であることがわかる。 中国におけるクロレラ生産(Chen et al. 2016) クロレラの生産においても、中国は日本を抜き、世界最大の生産国になりつつある。しかし、その生産量はスピルリナの4分の1程度であると見積もられている。主な原因は、その培養の難しさにある。クロレラの培養はスピルリナの培養に比べて、コンタミネーションによる培養破綻の可能性がはるかに高いこと、および収穫に遠心分離を必要とするためである。そのため、通常クロレラの価格はスピルリナより高い。スピルリナ生産者が、その培養設備の一部を利用してクロレラを小規模に生産するケースが多い。 ドナリエラおよびヘマトコッカス等についても少し記述があるが、詳細についてほとんど触れられていないため、ここでは割愛する。 ...
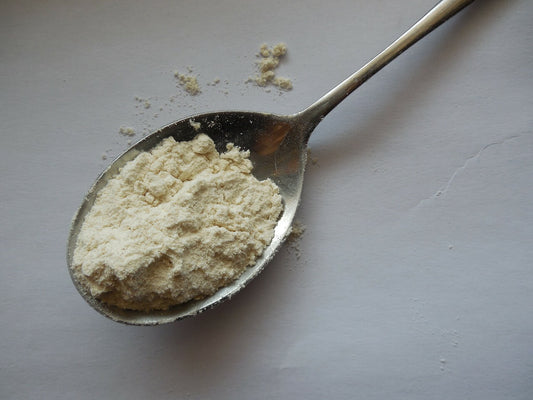
タンパク質危機(タンパク質クライシス)に備え、老舗農業企業が藻類農業へ参入
タンパク質危機 / タンパク質クライシス(Protein Crisis)という言葉をご存知だろうか。 人口の増加と新興国の経済発展による生活レベルの向上により、人類が必要とするタンパク質の需要に、供給が追いつかなくなることを予測した警鐘である。我々の試算だと早ければ2025年ごろからその傾向が顕在化し、世界的な問題になっていくと予測している。 こうした、近い将来訪れるであろうタンパク質危機に備えた動きが活発化している様子が分かる記事を一つ紹介する。 Woods Grain社がクイーンズランド州のサポート受け、新しい農業の取り組みとして藻類農場の建設を開始。ターゲット製品は『ω-3脂肪酸』と『タンパク質』。 Queensland Country Life Woods Grain to build algae farm http://www.queenslandcountrylife.com.au/story/4745927/woods-grain-to-build-algae-farm/ Why Goondiwindi's Woods Grain is diversifying into algae farming. オーストラリアのWoods Grain社は、Woods Groupというクイーンズランドで60年以上穀物生産を続けてきた老舗農業企業のグループ会社の一つ。タンパク質危機に備えて新しいタンパク質源を探していたところ、藻類に目をつけた形になる。 藻類栽培については、クイーンズランド大学のPeer...

彩りの塩湖。その彩りの正体は?
中国山西省にある「中国の死海」として知られる運城塩湖は、毎年春になり気温が上昇すると湖の色がカラフルに変わる、人気の観光スポットである。 色が異なる複数の小さな湖で構成される運城塩湖を上空から眺めると、まるでカラーパレットのように鮮やかな彩りである。是非、下記のリンク先の写真を見ていただきたい。 China's 'Dead Sea' Transforms Into A Rainbow-Here's Why A salt lake in Yuncheng, often called China's "Dead Sea," has tourists flocking to it for an unusual reason. Its...
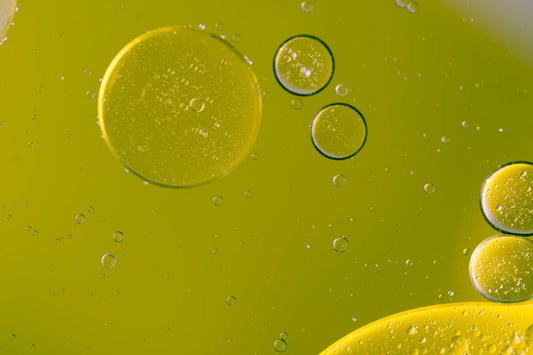
ゲノム編集で藻類オイルの生産量が2倍に!?エクソンモービル社とシンセティック・ジェノミクス社が注目の研究成果を発表
再生可能エネルギーとして有望視されている藻類バイオ燃料。安価に、そして大量にオイルを生産するために不可欠なのは、「高増殖性」と「高油脂生産性」の2つの要素を両立する藻類株の開発だ。 窒素などの栄養素が欠乏した条件下で藻類を培養すると、油脂生産量を増やすことができる。しかし、窒素欠乏下では光合成の阻害が起こり、藻類の成長が鈍化することで、最終的には油脂生産量が落ちてしまう。「高増殖性」を保ちながら「高油脂生産性」を達成する手法の開発は、長年の課題とされてきた。 そんな中、話題の「ゲノム編集」技術を用いた注目の研究成果が2017年6月19日に発表された。研究結果は同日にジャーナルNature Biotechnologyに掲載されている。 石油大手の米・エクソンモービル社(ExxonMobil Corporation)と米・シンセティック・ジェノミクス社 (Synthetic Genomics Inc.; SGI)が、藻類の増殖を著しく阻害することなく、油脂含有量を2倍以上に向上した news.exxonmobil.com ExxonMobil and Synthetic Genomics Report Breakthrough in Algae Biofuel Resear... http://news.exxonmobil.com/press-release/exxonmobil-and-synthetic-genomics-report-breakthrough-algae-biofuel-research IRVING, Texas & LA JOLLA, Calif.--(BUSINESS WIRE)--ExxonMobil...

「藻類バイオ燃料商業化」の御旗はどこへ?米国と米国企業に学ぶしたたかさ
本部を米国テキサス州に置くQualitas Health社(以下、QH社)が、Green Steam Farms社(以下、GSF社)と業務提携し、藻類の培養規模を3倍に拡大することを報告した記事がある。 Algae Industry Magazine Qualitas Health triples algae production | http://www.algaeindustrymagazine.com/qualitas-health-triples-algae-production/ Qualitas Health, an algae-based health and nutrition company headquartered in Texas, has announced a long term,...

南オーストラリアの夜光虫
南オーストラリアのポートリンカーンの近くのTulka beachで、暗闇に光る藻が発生している。 ABC News Glow-in-the-dark algae lights up Port Lincoln beach in SA http://www.abc.net.au/news/2017-06-19/luminescent-algae-in-port-lincoln/8630666?pfmredir=sm It was Kye Higgins' dog Miss Millie who discovered the bioluminescent bloom, known as sea...

藻類食品の大衆化に向けた動き
世界で藻類(微細藻類、大型藻類)を食品原料として利用する動きが広がっている。クロレラやスピルリナを始め、これまでは健康食品の一種、というカテゴリーで認知されてきた微細藻類であるが、近年では加工食品に使う原料としての利用が進んでいる。その動きをまとめた記事を今回は紹介したい。 www.nutritionaloutlook.com Algae Ingredients Turn Heads in Food and Drinks | Nutritional Outlook http://www.nutritionaloutlook.com/food-beverage/algae-ingredients-turn-heads-food-and-drinks Algae address today’s demands for plant-based, sustainable ingredients. 微細藻類の一般食品原料としての利用動向 現在、微細藻類食品原料として世の中に出回っている代表的な商品としては、DSM社のLife’s DHAの『ベジタリアンDHA』(微細藻類由来)、Terravia社の『藻類オイル』、『藻類タンパク質粉』、『藻類脂質粉』(全てクロレラ由来)などがある。これらは一般食品や飲料原料として製品に配合されながら市場で販売されており、すでに一定の成功を収めていると言えよう。 また日本ではサプリメントとして認知度が高いアスタキサンチンも、最近では一般食品原料としての応用展開が盛んだ。カロテノイド製品を取り扱う LycoRed社(Be’er Sheva、イスラエル)のGolan Raz副社長は、チュアブル菓子製品類での展開成長に期待している、と話す。 アスタキサンチンを生産しているAstaReal...

2018年度予算教書にみる、米国における藻類バイオ燃料研究開発の今後
今年の3月、Politicoから配信された以下のニュース記事をご存知だろうか。 POLITICO Energy Department climate office bans use of phrase ‘climate change’ http://www.politico.com/story/2017/03/energy-department-climate-change-phrases-banned-236655 The Office of International Climate and Clean Energy is the only office at DOE with the words...